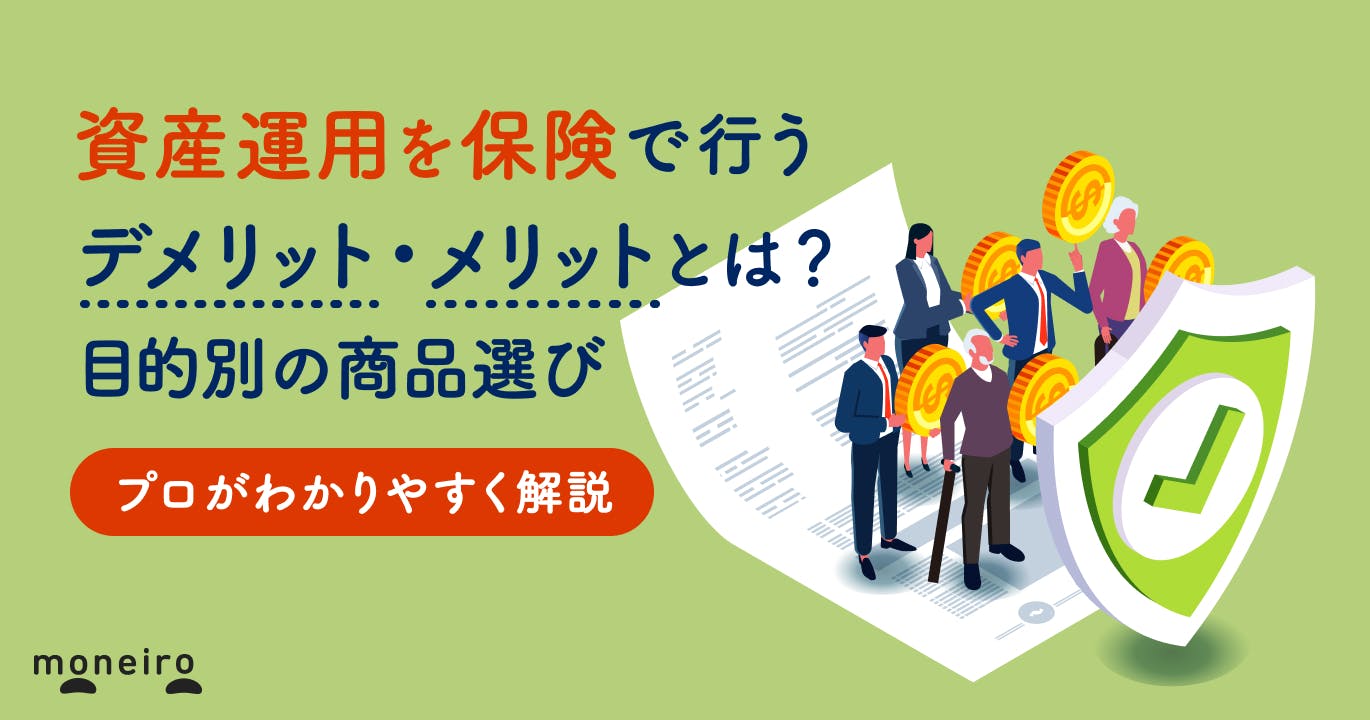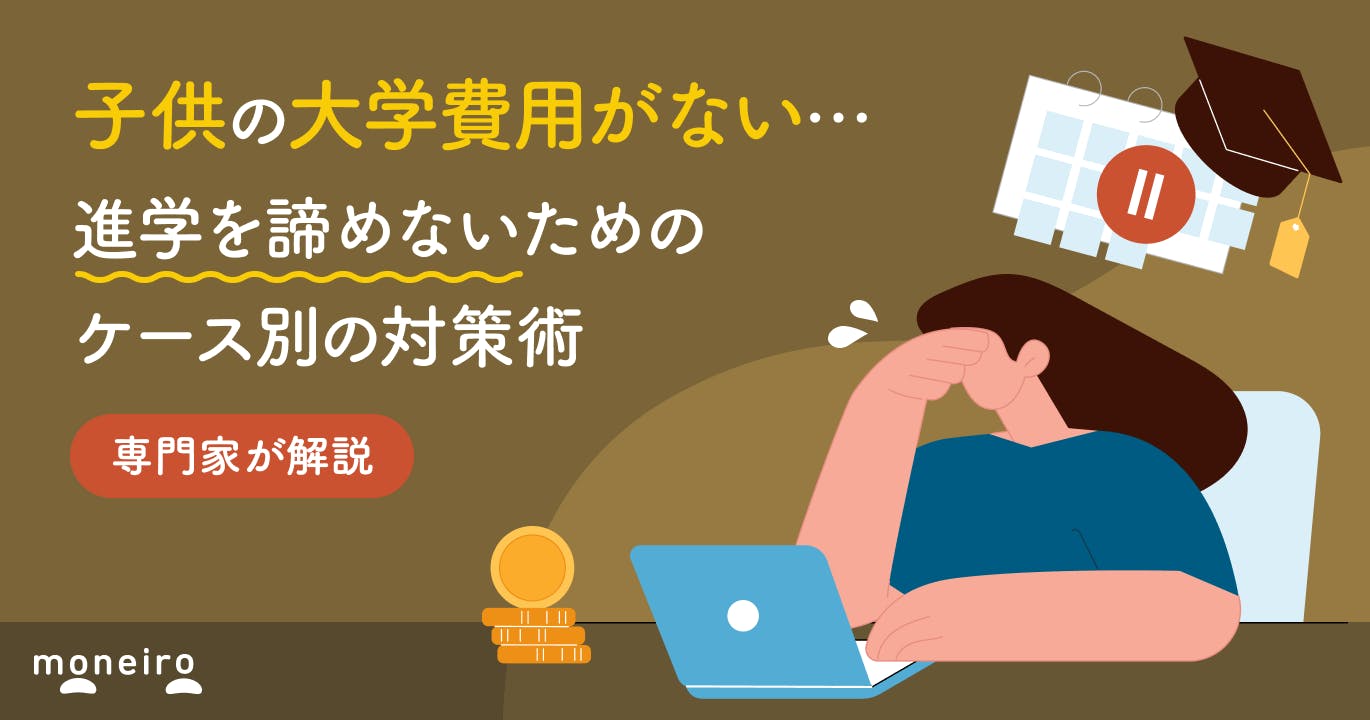
高校生等奨学給付金とは?母子家庭はいくらもらえる?条件・金額・申請方法を専門家が解説
»本当に必要な老後資金を把握していますか?|無料診断
高校生等奨学給付金は、主に住民税非課税世帯や母子家庭など、経済的に厳しい家庭の高校生を対象にした返済不要の給付制度です。
「自分の家庭も対象になるの?」「いくらもらえる?」「どうやって申請するの?」と疑問を抱く保護者は多いでしょう。
本記事では、母子家庭が知っておきたい給付金の基礎知識・支給金額・申請方法などを、詳しく解説します。経済的な不安を少しでも軽減できるよう、制度を正しく理解し、活用する一歩を踏み出しましょう。
- 高校生等奨学給付金とは授業料以外の教育費負担を軽減するための返済不要の給付⾦のこと
- 母子家庭が対象となるのは「生活保護世帯」「住民税所得割非課税の世帯」
- 母子家庭が利用できる教育支援制度は「母子父子寡婦福祉資金貸付金制度」「民間の奨学金制度」など
教育資金が気になるあなたへ
子育てや住宅ローンなど将来の負担はさまざまです。この先必要になる金額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶教育資金の準備方法をプロに無料相談:賢い将来資金づくりがわかる
高校生等奨学給付金とは
「高校生等奨学給付金」は、授業料以外の教育費負担を軽減するための返済不要の給付⾦です。特に経済的に困難な家庭(非課税世帯など)が対象となります。
制度の目的と概要
高校生等奨学給付金制度は家庭の経済状況にかかわらず、就学意志のある高校生等が安心して教育を受けられるように、教育費負担の軽減を図ることを目的としています。
高等学校等に通う生徒の授業料以外の教育費を支援するため、「高校生等奨学給付金」を支給し、家庭の教育費負担を軽減することで、教育の機会均等を図ります。
高等学校等就学支援金との違い
高校生等への修学支援制度には、「高校生等奨学給付金」と「高等学校等就学支援金」の二つがあります。
高等学校等就学支援金制度は高校等の授業料に充てるために支給されるものです 。学校設置者が生徒の代わりに国から支援金を代理受領します。
一方、高校生等奨学給付金は授業料以外の教育費(教科書費、教材費、学用品費、修学旅行費など)を支援する制度です。
両制度は目的が異なるため、それぞれ別々に申し込みが必要です。条件を満たせば併給も可能です。
(参考:みんなに知ってほしい 高校生等へのふたつの支援|文部科学省)
母子家庭が対象となる所得制限・条件
高校生等奨学給付金は、母子家庭(ひとり親家庭)など、経済的に困難な世帯を主な対象としています。具体的な所得制限や条件は以下の通りです。
対象となる世帯
高校生等奨学給付金の対象(※)となるのは、以下の世帯です。
- 生活保護世帯
- 住民税所得割非課税の世帯
生活保護受給世帯、または住民税所得割が非課税の世帯です 。家計が急変して非課税相当になった世帯も対象となります。
※高等学校、高等専門学校(1~3年生)などが対象
次の(1)~(3)の要件を基準日(令和7年7月1日)現在ですべて満たしている
必要があります。
(1)「高等学校等就学支援金(又は学び直しへの支援)」の支給を受ける資格を有
している生徒(以下「生徒」という。)がいる世帯
(2)生活保護を受給している世帯、又は市町村民税・道府県民税所得割額の合算
が0円(非課税)の世帯
(基準日にかかわらず、家計急変による経済的理由から、市町村民税・道府
県民税所得割額の合算が0円(非課税)に相当する世帯を含む。)
(3)保護者等(親権者)が埼玉県内に住所を有している世帯
(引用:奨学のための給付金(通常給付)申請のしおり)
母子家庭はいくらもらえる?給付金額を確認
高校生等奨学給付金の給付額は、世帯の状況や高校の種類によって異なります。
以下は、令和7年度(2025年度)の給付額の目安です。
(引用:令和7年度予算(高校生等への修学支援)|文部科学省)
※都道府県によって給付内容が異なります
【例:埼玉県国公立高等学校等】
(引用:奨学のための給付金(通常給付)申請のしおり)
高校生等奨学給付金の申請方法と必要書類
高校生等奨学給付金を受け取るためには、住んでいる都道府県への申請手続きが必要です。都道府県によっては学校経由で申請を行う場合もあるため、事前に確認をしましょう。
申請の流れと申請期間
①申請書等の入手…学校を通じて配布されることが多いですが、都道府県のウェブサイトからダウンロードも可能です。
②必要書類の準備…所得証明書、住民票など、世帯状況を証明する書類を準備します。
③申請書の提出:学校または都道府県の担当部署に提出します。
申請に必要な書類リスト
具体的な必要書類は都道府県によって異なります。一般的には、以下の書類が求められます。
- 高校生等奨学給付金支給申請書
- 住民税課税証明書または非課税証明書(世帯全員分)
- 世帯全員の住民票
- 在学証明書(学校が発行)
- 生活保護受給証明書(生活保護受給世帯の場合)
- 振込口座の情報がわかるもの
など
給付金の支給時期と受け取り方法
給付金の支給時期は、都道府県によって異なりますが、一般的には年に1回支給されます。申請が承認されると、指定された口座に直接振り込まれる形となります。
【例:埼玉県国公立高等学校等】
(引用:奨学のための給付金(通常給付)申請のしおり)
参考)公立高校の学費と私立高校の学費の比較
高校の学費は、公立と私立で大きく異なります。
令和5年度子どもの学習費(※)
※保護者が子どもの学校教育及び学校外活動のために支出した経費の総額
(参考:令和5年度子供の学習費調査の結果|文部科学省)
母子家庭が利用できる高校生等奨学給付金以外の教育支援制度
高校生等奨学給付金以外にも、母子家庭や経済的に困難な家庭が利用できる教育支援制度があります。複数の制度を組み合わせて活用することを検討しましょう。
母子父子寡婦福祉資金貸付金制度
母子父子寡婦福祉資金貸付金制度とは、母子家庭や父子家庭、寡婦の場合に利用できる制度です。
修学資金(高校、大学などに修学するための費用)や就学支度資金(入学費用)などを比較的低金利、または無利子で借り入れできます。
(参考:母子父子寡婦福祉資金貸付金制度 | 内閣府男女共同参画局)
生活福祉貸付金制度の「教育支援資金」
生活福祉資金貸付制度における「教育支援資金」は低所得世帯を対象とした生活福祉資金貸付制度の一つです。
高校や大学等への就学に必要な経費や、入学時に必要な経費を借り入れできます。
各自治体が設ける学費支援・貸付制度
多くの都道府県や市区町村が、国が定める制度以外に、独自の奨学金制度や、学費負担を軽減するための助成制度、貸付制度などを設けています。
住んでいる自治体のウェブサイトや教育委員会に問い合わせてみましょう。
まとめ
「高校生等奨学給付金」は、経済的に困難な家庭の高校生を対象とした、授業料以外の教育費を支援する返済不要の給付金です。
母子家庭(ひとり親家庭)も主な対象となり、住民税非課税世帯などが主な要件です。給付額は世帯の状況や高校の種類によって異なり、年額数万円から十数万円が目安となります。
申請は学校を経由するなどして都道府県教育委員会に、必要な書類を揃えて手続きをします。給付金は、授業料の実質無償化である高等学校等就学支援金制度とは別制度ですが、併給も可能です。
高校の学費が足りない場合でも、高校生等奨学給付金のほかに、母子父子寡婦福祉資金貸付金制度や教育支援資金、自治体独自の支援、国の教育ローンなど、さまざまな支援制度があります。
お子さまが安心して高校に行けるように検討しましょう。
教育資金が気になるあなたへ
子育てや住宅ローンなど将来の負担はさまざまです。この先必要になる金額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶教育資金の準備方法をプロに無料相談:賢い将来資金づくりがわかる
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。