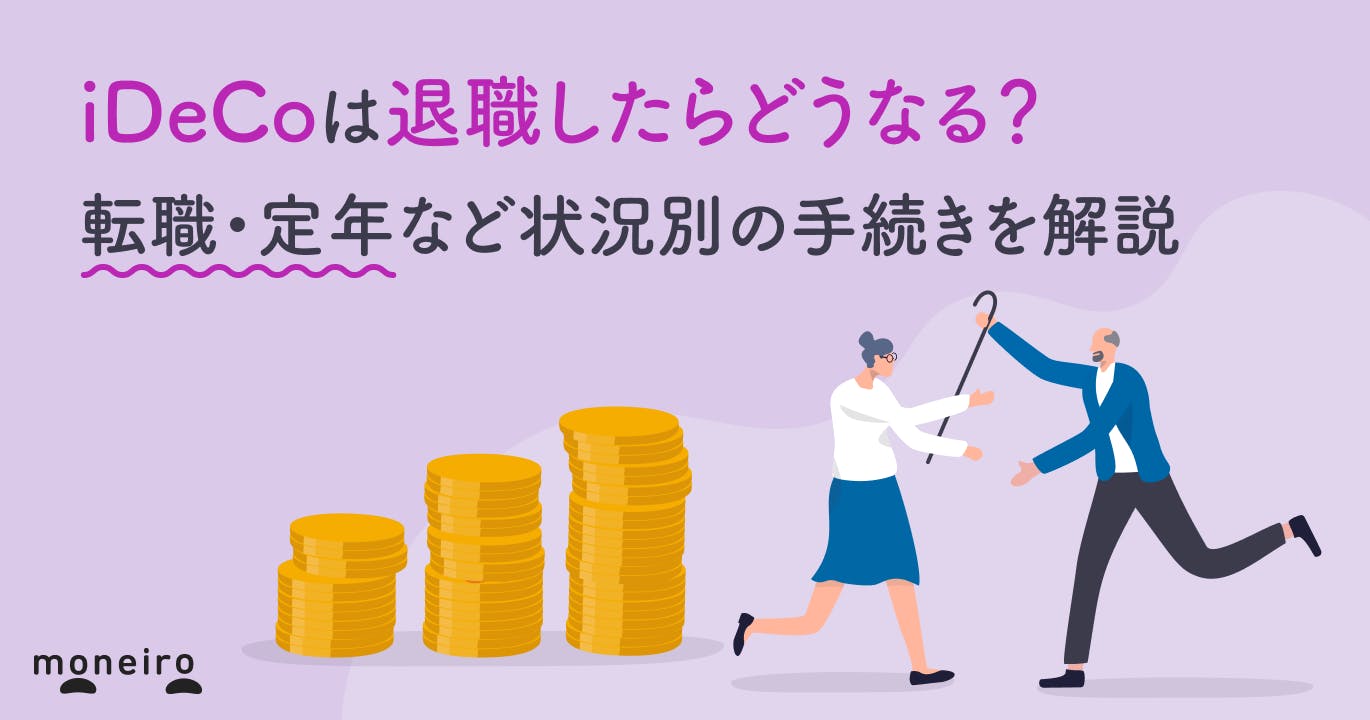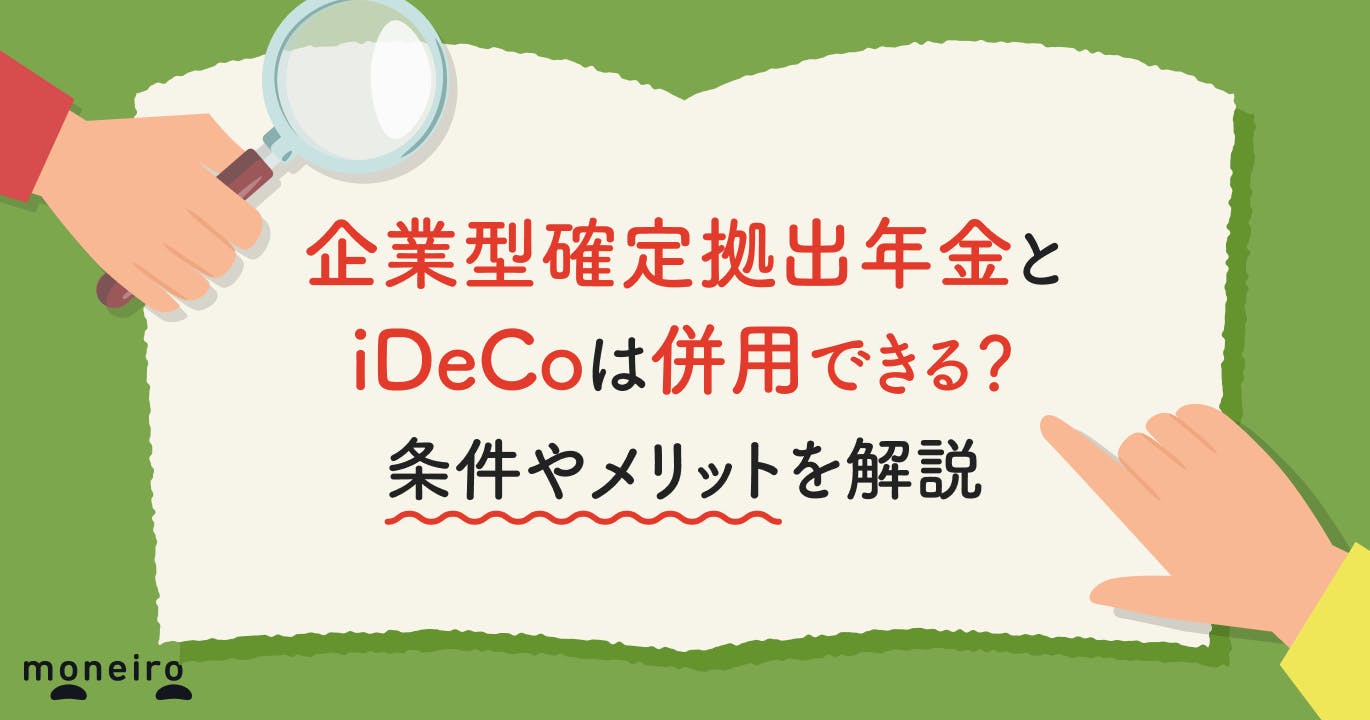iDeCoは退職したらどうなる?転職・定年など状況別の手続きを解説
≫iDeCoは続けるべき?あなたの最適解を3分で診断
会社を退職したら、iDeCoの資産はどうなるのでしょうか?実は、そのままにして「放置」するのは非常に危険です。適切な手続きを取らずにいると、資産が目減りするリスクがある「自動移換」に移行してしまうためです。
この記事では、転職、独立、定年など、あなたの状況に最適なiDeCoの手続きを、網羅的に解説します。企業型DCからの移換方法や掛金変更、退職後の節税戦略まで、大切な年金資産を損しないための知識を身につけましょう。
- iDeCo(個人型確定拠出年金)を退職後に放置した場合のリスク
- 転職、自営業、専業主婦など、状況別で取るべきiDeCoの手続きと掛金上限額
- 定年退職後のiDeCoの受け取り方における税制上の戦略
iDeCoの運用が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ

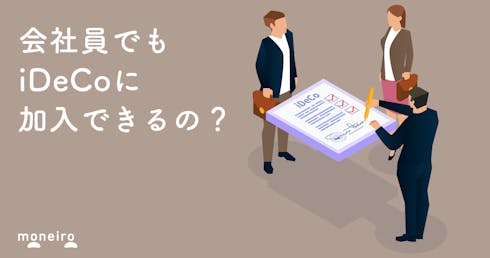
iDeCoを会社退職後に「放置」するとどうなる?
会社員が退職し、新しい勤務先が決まっていない場合や、手続きを失念した場合、iDeCoの資産は原則として、退職から6ヶ月後を目安に「自動移換」されてしまいます。この自動移換は、大切な年金資産を意図せず目減りさせてしまうリスクを伴うため、注意が必要です。
自動移換された資産は、国民年金基金連合会が指定した金融機関で管理されますが、資産運用は行われず、現金(預金)として管理されます。
資産が増える機会がなくなるだけでなく、移換時には移換手数料が発生し、その後も管理手数料が継続的に差し引かれていきます。その結果、運用益が得られない上に手数料だけが引かれ続けるという二重の損失が発生する可能性があるのです。この状態を避けるためには、退職後速やかに、自分の新しい状況に合わせた手続きを行うことが重要です。
【パターン別】退職したらやるべきiDeCoの手続きマニュアル
会社を退職した後の状況によって、iDeCoで取るべき手続きは異なります。
公的年金制度における被保険者種別が変わる場合が多いため、自身の新しい働き方(または働き方の変化)に合わせて、iDeCoの資産を適切に管理・運用していくための具体的な手続きを確認しましょう。
ケース1.転職先の企業型DCに資産を移す(移換)
転職先に企業型確定拠出年金(企業型DC)がある場合、原則として、これまでiDeCoで積み立ててきた資産(個人別管理資産)を、転職先の企業型DCに移換(積み替え)することになります。
手続きの流れ
- 転職先の担当部署に移換の意思を伝える:まずは転職先の企業の担当部署に対し、iDeCoの資産を企業型DCに移したい旨を伝えます。
- 運営管理機関から「個人別管理資産移換依頼書」等を取り寄せ、提出する:現在iDeCoを運用している運営管理機関(金融機関)に連絡し、「個人別管理資産移換依頼書」などの必要書類を取り寄せます。新しい勤務先が指定する手続きに従い、必要事項を記入し提出します。
- 資産の移換が完了するのを待つ:手続き完了後、数週間から数ヶ月で資産の移換が完了します。
移換時の商品選びの注意点
企業型DCへ資産を移換する際、iDeCoで積み立てていた運用商品は一度すべて売却され、現金化されてから新しい企業型DCに移されます。移換後、新しい企業型DCの運用商品を選択し直す必要があります。
移換前と後の商品ラインナップは異なるため、移換を機に、ポートフォリオを見直し、改めて運用方針に合わせて商品を選ぶ「配分指定」を検討することが大切です。
ケース2.転職先に企業型DCがない(iDeCoを継続)
転職先に企業型DCがない場合や、iDeCoをそのまま継続したい場合は、iDeCoの加入者資格を継続するための手続きが必要です。会社員として厚生年金に加入し続ける場合、被保険者種別は「第2号被保険者」のままですが、勤務先情報が変わるため届出が必要です。
手続きの流れ
- iDeCoの運営管理機関に連絡し「加入者登録情報変更届」などを取り寄せる:現在利用しているiDeCoの運営管理機関(金融機関)に連絡し、必要書類を取り寄せます。
- 必要事項を記入し提出する:「加入者登録情報変更届」に必要事項を記入して提出します(以前は、転職先の企業に「事業主の証明書」を記入してもらう必要がありましたが、制度改正により2024年12月から不要になっています)。
掛金上限額の確認
厚生年金に加入する会社員(第2号被保険者)としてiDeCoを継続する場合の掛金上限額は、転職先の企業年金(企業型DCや確定給付企業年金(DB)など)の加入状況によって、以下の通り異なります。
- 転職先に企業年金が全くない場合: 月額2万3000円(年額27万6000円)
- 転職先が企業型DCのみに加入している場合: 月額2万円(年額24万円)
- 転職先がDB等のみ、または企業型DCとDB等の両方に加入している場合: 月額2万円(年額24万円)
ケース3.自営業・フリーランスになる
会社を退職し、自営業者やフリーランスとして独立した場合、iDeCoの被保険者種別は「第1号被保険者」に変更になります。第1号被保険者は、掛金上限額が高く設定されており、iDeCoのメリットを最大限に享受できる可能性があります。
手続きの流れ
- iDeCoの運営管理機関に連絡し「加入者被保険者種別変更届(第1号被保険者用)」を取り寄せる:現在の運営管理機関に連絡し、被保険者種別を変更するための届出書を入手します。
- 必要事項を記入し、本人確認書類を添えて返送する:必要事項を記入し、本人確認書類や国民年金の保険料納付状況を確認できる書類などを添えて運営管理機関に返送することで、手続きは完了します。
掛金上限と節税効果
第1号被保険者になると、iDeCoの掛金上限が大幅に引き上げられ、年額81万6000円(月額6万8000円)まで拠出できるようになります。これは会社員の上限と比較して非常に大きなメリットです。
ただし、国民年金基金や国民年金付加保険料に加入している場合、それらの掛金とiDeCoの掛金を合わせて年額81万6000円が上限となります。
DeCoの掛金は全額が所得控除の対象となるため、所得税や住民税の節税効果が非常に大きく、所得が高い自営業者にとっては大きな魅力となります。
ケース4.専業主婦(夫)になる
会社を退職し、配偶者の扶養に入る専業主婦(夫)となった場合、iDeCoの被保険者種別は「第3号被保険者」に変更になります。
手続きの流れ
- 運営管理機関に連絡し「加入者被保険者種別変更届(第3号被保険者用)」を取り寄せる:iDeCoの運営管理機関に連絡し、第3号被保険者用の変更届を取り寄せます。
- 必要事項を記入し、返送する:必要事項、特に配偶者(扶養者)の情報を記入し、運営管理機関に返送します。
運用指図者になる選択肢
第3号被保険者としての掛金上限は月額2万3000円(年額27万6000円)です。掛金の拠出が難しい場合は、拠出を停止し、これまで積み立てた資産の運用のみを続ける「運用指図者」になる選択肢もあります。
運用指図者になることで、掛金を拠出する義務がなくなり、掛金拠出の都度かかる手数料(国民年金基金連合会への納付手数料等)が不要になるメリットがあります(ただし、運営管理機関の口座管理料は引き続き発生する場合があります)。
なお、パートなどで収入がある場合、年収が一定額を超えると第3号被保険者ではなくなり、国民年金や厚生年金に加入する第2号被保険者となる可能性があるため、収入状況を常に確認し、種別変更の手続き漏れがないように注意が必要です。
iDeCoの運用が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
ケース5.【番外編】公務員になる・海外移住するなど
公務員になった場合
公務員になった場合、被保険者種別は「第2号被保険者」(共済組合員)となります。手続きは、「ケース2」の一般の会社員が転職した場合と同様で、iDeCoの運営管理機関に「加入者登録情報変更届」を提出します。
退職し、海外に転居する場合
退職して海外に転居し、日本国内に居住しなくなった場合、原則としてiDeCoの掛金を拠出することはできなくなります。これは、iDeCoの加入資格が国民年金または厚生年金の被保険者であることを前提としているためです。
ただし、例外として、国民年金の任意加入者になる手続きを行った場合は、iDeCoの掛金拠出を継続できる可能性があります。任意加入しない場合は、速やかに掛金の拠出を停止し、運用だけを行う「運用指図者」になるための手続きを行う必要があります。手続きを怠ると、自動移換のリスクが発生します。
定年退職後のiDeCoの受け取り方戦略
iDeCoの資産は、原則60歳以降(加入期間による)に受け取りが可能になります。受け取り方には「一時金」として一括で受け取る方法と、「年金」として分割で受け取る方法があり、適用される税制優遇が大きく異なります。税負担を最小限に抑えるための戦略が重要です。
「一時金」受け取り:退職所得控除の活用
iDeCoの資産を一時金として受け取る場合、その税区分は「退職所得」となります。退職所得は、優遇された税制である「退職所得控除」を適用できる点が最大のメリットです。
退職所得控除は非常に強力であり、控除後の金額に対して1/2をかけたものが課税対象となるため、税負担が大幅に軽減されます。また、退職所得は分離課税であるため、他の所得(給与所得や公的年金など)と合算されずに課税計算が行われます。
控除額の計算方法
退職所得控除額は、iDeCoの掛金拠出期間(勤続年数に相当)によって計算されます。
- 拠出期間が20年以下の場合:40万円 × 拠出期間(※最低80万円)
- 拠出期間が20年超の場合:800万円 + 70万円 × (拠出期間 - 20年)
受け取り時期の調整戦略
会社の退職金とiDeCoの資産を同年に一時金として受け取ると、これらの金額に対して退職所得控除の枠を合算で使うことになり、控除枠を使い切ってしまい、税制上不利になる可能性が高まります。この不利を避けるため、iDeCoの受け取り時期を会社の退職金受け取りとはずらして(翌年以降に)受け取る戦略が重要です。
特に、税制上の優遇を最大限に享受するためには、退職所得控除の計算期間が重複しないように、「5年ルール」「19年ルール」といった複雑な税制上の規定を考慮に入れた計画が必要です。
iDeCoを先に、会社の退職金を後で受け取る場合のルールで、iDeCoの一時金を受け取ってから10年以内に会社の退職金を受け取ると、退職所得控除の枠が通算で計算されることになります。2025年までは「5年ルール」でしたが、2026年から「10年」に変わるため、受け取り方によっては老後の資金計画に大きな影響を及ぼす可能性があります。
会社の退職金を先に、iDeCoを後で受け取る場合のルールです。退職金の翌年1月1日から19年以内に、iDeCoの一時金を受け取ると、iDeCoの退職所得控除額から、会社の勤続期間と重複する加入期間分が減額調整されます。

「年金」受け取り:公的年金等控除の活用
iDeCoの資産を年金形式(分割)で受け取る場合、その税区分は「雑所得(公的年金等)」となります。
公的年金等控除のメリット
雑所得(公的年金等)として受け取る場合、「公的年金等控除」が適用されます。これは、一時金で退職所得控除枠を会社の退職金で使い切ってしまった場合に有効な選択肢となり得ます。控除額の計算方法は、受給者の年齢(65歳未満か65歳以上か)と、その年の公的年金等の収入額によって決定されます。
公的年金との合算
iDeCoを年金形式で受け取る場合、その収入は、老齢基礎年金や老齢厚生年金といった公的年金と合算されて公的年金等控除額が計算されます。年金収入の合計額が多くなると、税率が上がるだけでなく、国民健康保険料や介護保険料などの社会保険料の負担が増加する可能性があるため、総収入額のバランスを見ながら選択することが求められます。
「一時金」「年金」の併給
受け取り方には「一時金」「年金」に加え、一部を一時金で受け取り、残りを年金で受け取る「併給(へいきゅう)」という方法もあります。運営管理機関(金融機関)によって対応の可否が異なるため、対象の金融機関に事前に確認するとよいでしょう。
これにより、退職所得控除と公的年金等控除を組み合わせて活用し、税負担を最適化できる可能性があります。
結局どっちが得?状況別のおすすめ戦略
一時金と年金、どちらの受け取り方が有利かは、個人の退職金の額や公的年金の受給見込み額によって異なります。
一時金が有利な人
- 会社の退職金がない(または少ない)人:退職所得控除の枠をiDeCoの受け取りで最大限に使えます。
- 公的年金が多い人:年金で受け取ると公的年金と合算され、結果的に課税額や社会保険料が上がるリスクを回避できます。
年金が有利な人
- 会社の退職金が非常に多く、一時金で受け取ると退職所得控除枠を大幅に超えてしまう人:控除枠を超えた部分への課税が大きくなるため、年金に分けて控除を適用した方が有利になる可能性があります。
iDeCoに関するQ&A
退職した時のiDeCoの取り扱いに関するよくある質問にQ&A形式で回答します。
Q. 会社を退職したらiDeCoはどうなる?
会社を退職後、6ヶ月間手続きを行わなかった場合、iDeCoの資産は国民年金基金連合会が指定した金融機関に自動移換されます。自動移換されると、運用ができなくなり、手数料が引かれ続けることで資産が目減りするリスクがあります。
退職後は、転職先での企業型DCへの移換手続きや、新しい働き方に応じた被保険者種別の変更手続きを速やかに行う必要があります。
Q. iDeCoで会社を退職して無職になった場合の手続きは?
退職後に無職となり、国民年金の第1号被保険者になった場合でも、iDeCoの掛金拠出を継続できます。ただし、被保険者種別を「第1号被保険者」に変更するための手続きが必要です。手続きは、iDeCoの運営管理機関に連絡し、変更届を取り寄せて提出することで完了します。
なお、国民年金保険料の支払いを全額免除(産前産後期間の免除を除く)、一部免除、または納付猶予(学生納付特例など)されている期間は、iDeCoの掛金を拠出することができないため、その場合は運用指図者になる(または掛金の拠出を停止する)必要があります。
Q. 退職後の手続きはどこに問い合わせればいいですか?
iDeCoに関する手続きや問い合わせは、原則として現在ご自身がiDeCoの口座を開設している運営管理機関(金融機関)に対して行います。各種変更届や移換依頼書などは、すべてその運営管理機関から取り寄せ、提出することになります。
まとめ
iDeCoの資産は、退職後の放置が「自動移換」というリスクを生じさせるため、転職や独立など、状況が変化した際には、速やかに被保険者種別の変更手続きを行うことが不可欠です。
特に、定年退職後の資産の受け取りについては、一時金(退職所得控除)または年金(公的年金等控除)のいずれを選択するか、そして会社の退職金との受け取り時期の調整が、手取り額を最大化するための重要な戦略となります。
税制上のメリットを最大限に享受するため、まずは自分の退職金や公的年金の見込み額を把握し、計画的に受け取り戦略を実行しましょう。
≫あなたはiDeCoは続けるべき?今やるべき投資がわかる3分診断
iDeCoの運用が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
高橋 明香
- ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者
みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。