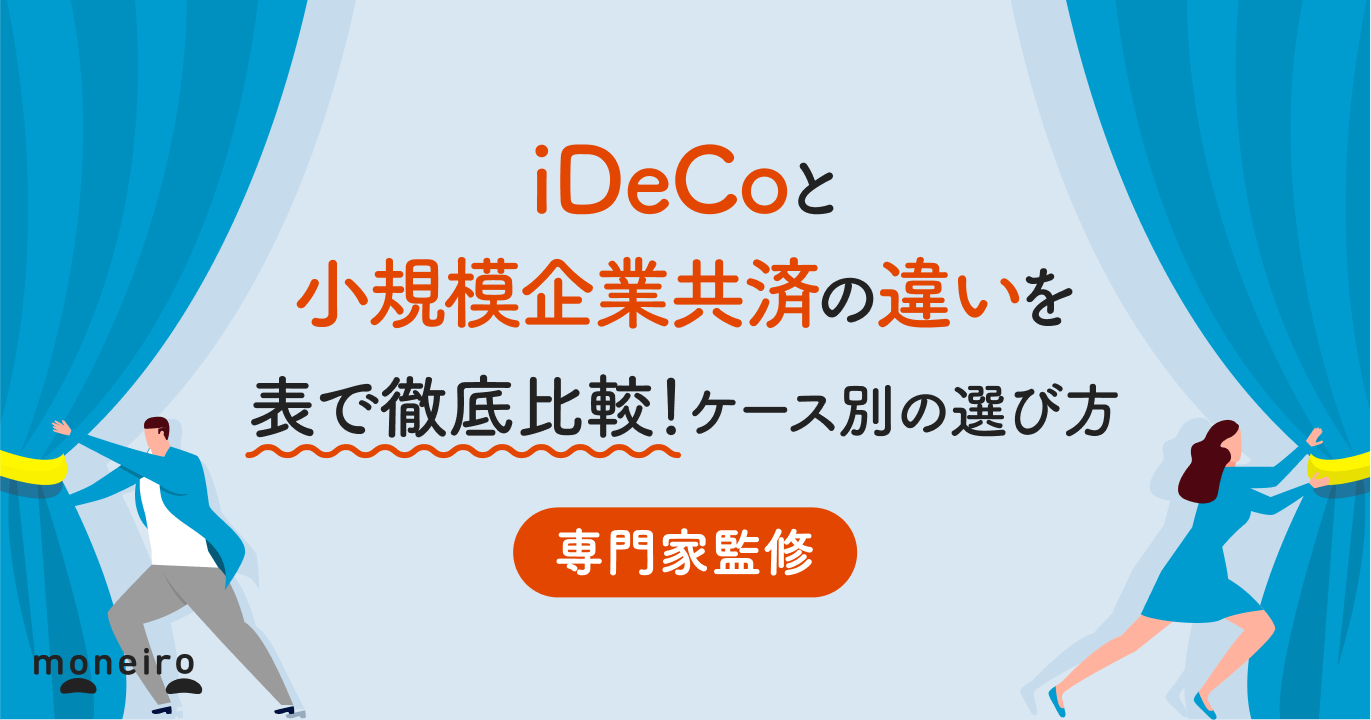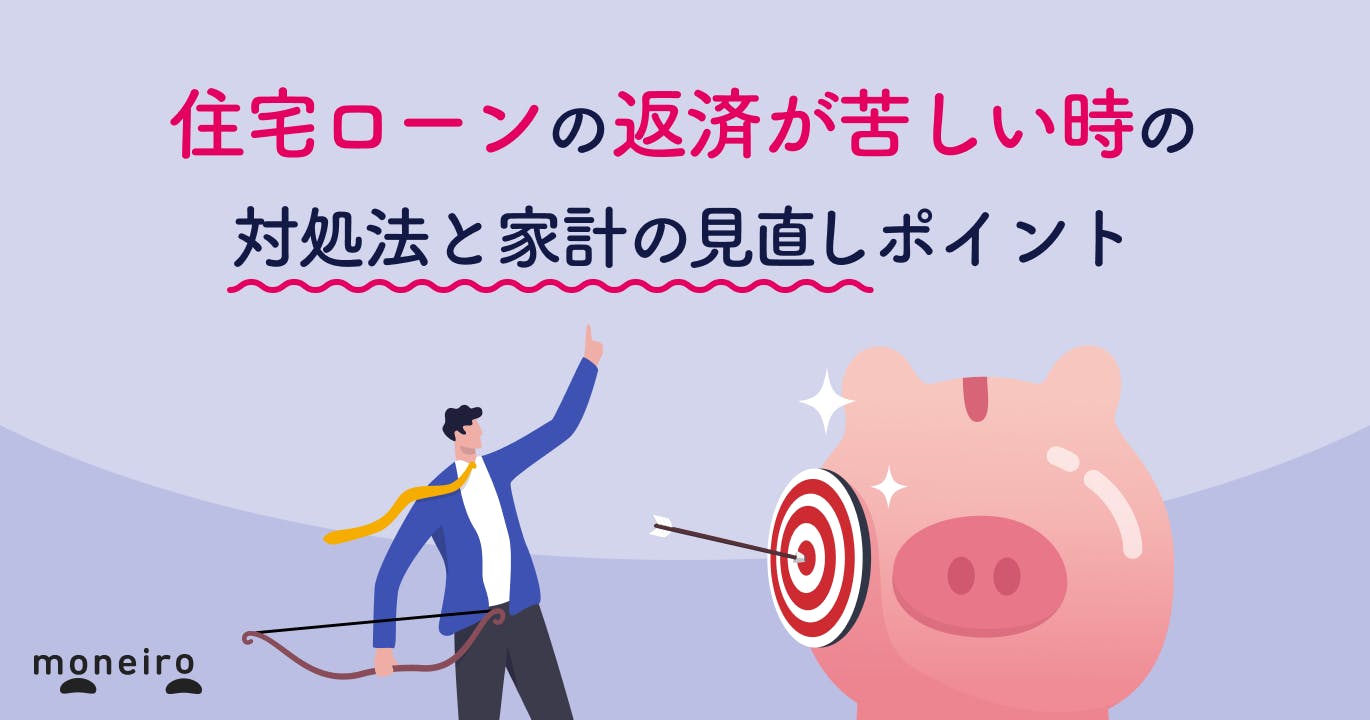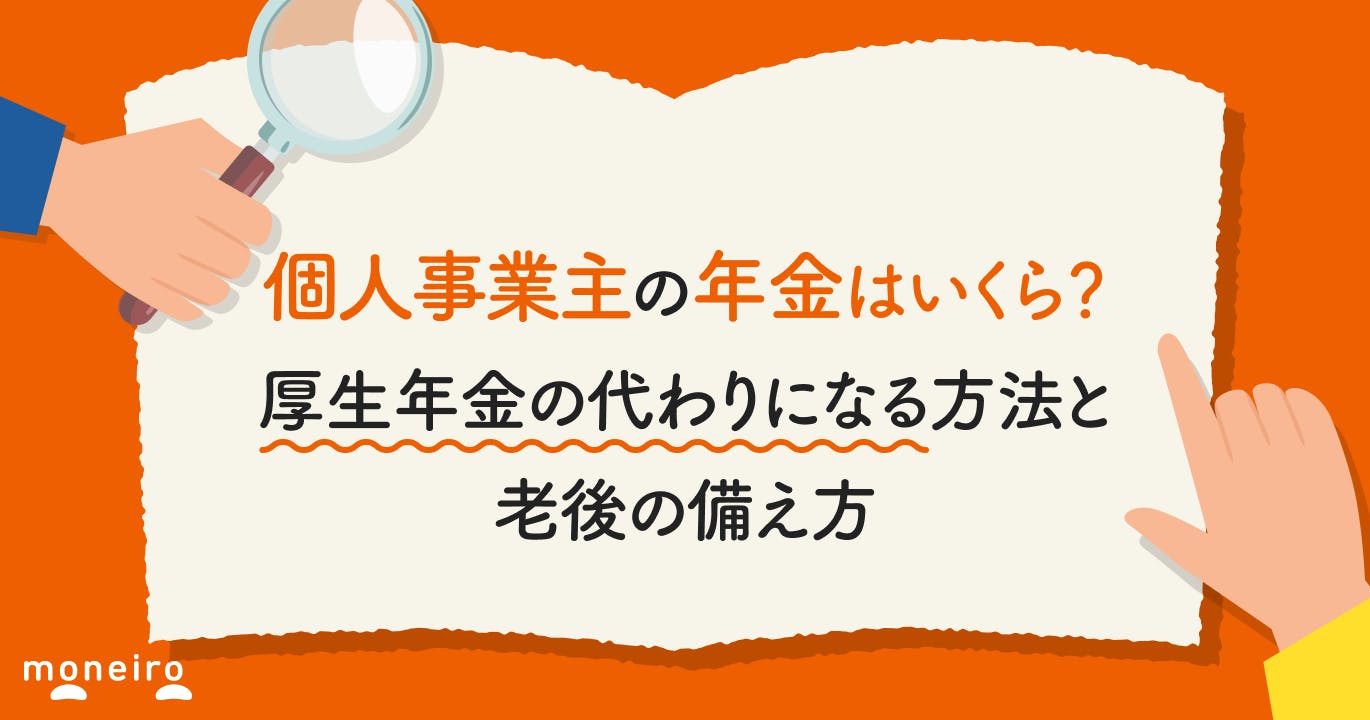
iDeCoと小規模企業共済の違いを表で徹底比較!ケース別の選び方と節税シミュレーション
将来資金づくりに迷ったら、3分診断でチェック
自営業者やフリーランス、中小企業経営者にとって、老後資金づくりと節税は大きなテーマです。老後資金を準備するうえで活用できる制度に「iDeCo(個人型確定拠出年金)」と「小規模企業共済」があります。どちらも掛金が全額所得控除になる制度ですが、仕組みやリスクはそれぞれ異なります。
記事では、両制度の違いをわかりやすく比較し、職業や目的別にどちらが向いているかを専門家がわかりやすく解説します。さらに、節税効果のシミュレーションや併用メリット・注意点も紹介します。自分に合った活用法を見つけ、将来の資産形成に役立てましょう。
- iDeCoと小規模企業共済の仕組み・税制面での違い
- あなたのタイプに合わせた制度の選び方
- 両制度を併用するメリットと注意点
老後資金が気になるあなたへ
老後にお金で困らないために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶40代からの老後資金作り:40代が目指すリスクとリターンのバランスとは?
▶50代からの老後資金作り:50代からでも間に合う?堅実な資産の増やし方
iDeCoと小規模企業共済の違い①仕組み
iDeCoと小規模企業共済は、どちらも節税しながら将来に備える制度ですが、その仕組みには違いがあります。
まずは仕組みの違いについて詳しく見ていきましょう。
制度の目的と位置づけ
iDeCo(個人型確定拠出年金)は公的年金に上乗せする形で、老後の資産を準備するための私的年金制度です。
加入者自身が掛金を拠出し、運用方法を選ぶことで、将来受け取る年金を形成していきます。
一方、小規模企業共済は、中小企業基盤整備機構が運営する制度で、個人事業主や小規模企業の経営者・役員のための退職金制度としての役割を担います。
会社員と異なり退職金がない事業主が、事業の廃止や退職後の生活資金を計画的に準備することを目的としています。
加入対象者と条件
iDeCoは、国民年金の被保険者であれば、自営業者、会社員、公務員、専業主婦(主夫)など、幅広い人が加入対象となります。
原則として20歳以上65歳未満の人が加入できます。
一方、小規模企業共済の加入対象は限定されており、個人事業主または小規模企業の経営者・役員が主な対象です。
小規模企業とは、常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下)の企業が該当します。
掛金の上限と拠出方法
掛金の上限額にも違いがあります。
小規模企業共済は月1000円〜7万円の範囲で、500円単位で自由に設定でき、年間の上限は84万円です。
一方、iDeCoは加入者の職業などによって上限額が異なります。
個人事業主(第1号被保険者)の場合、月額6.8万円(年額81.6万円)が上限となり、月々5000円から拠出が可能です。(※)
どちらの制度も、加入後に掛金額を変更することが可能で、家計や事業の状況に合わせて柔軟に対応できます。
※2027年から上限額が7.5万円に変更予定
解約条件と柔軟性の違い
iDeCoは老後資金の確保を目的としているため、原則として60歳になるまで資産を引き出すことはできません。
一方、小規模企業共済は、事業の廃止や役員の退任といった理由があれば、年齢に関わらず共済金を受け取れます。
ただし、自己都合による任意解約も可能ですが、その場合は元本割れのリスクが伴います。
特に、掛金の納付期間が20年未満で任意解約すると、受け取れる解約手当金が支払った掛金の総額を下回ってしまいます。
また、加入期間が12ヶ月未満の場合は、掛け捨てとなり一切受け取れません。
貸付制度の有無(小規模企業共済のみ)
小規模企業共済には、iDeCoにはない「契約者貸付制度」が用意されています。これは、納付した掛金の範囲内で、事業資金などを低金利で借り入れできる制度です。
急な資金需要が発生した際に、積み立てた資産を解約することなく活用できるため、事業のセーフティネットとしての役割も果たします。
資金が長期間拘束されるデメリットを、この貸付制度がある程度補っていると言えるでしょう。
iDeCoにはこのような貸付制度はありません。
iDeCoと小規模企業共済の違い②税制・運用・受け取り
iDeCoと小規模企業共済は、税制優遇や資産の増やし方、そして最終的な受け取り方においても違いがあります。お金に直接関わるこれらの違いを詳しく見ていきましょう。
掛金の税制優遇(全額所得控除など)
税制面での最大の共通点は、iDeCoと小規模企業共済のどちらも、支払った掛金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象になることです。
所得控除とは、所得税や住民税を計算する際に、所得金額から一定額を差し引くことができる仕組みです。
これにより、課税所得が圧縮され、結果として税負担が軽減されます。
例えば、課税所得500万円の人が年間60万円の掛金を支払った場合、約18万円もの税金が軽減される効果が期待できます。
一方、iDeCoの場合はさらに運用期間中に得た利益(運用益)がすべて非課税になります。
通常の金融商品で得た利益には約20%の税金がかかりますが、iDeCoではこれが免除されるため、複利効果を最大限に活かした効率的な資産形成が可能です。
運用方法とリスク(自分で運用するか、積立か)
iDeCoは、加入者自身が定期預金や投資信託などの金融商品を選んで運用します。
そのため、運用成果によっては資産を大きく増やせる可能性がある一方で、市場の変動などにより元本割れのリスクも伴います。
どのような商品を選ぶかによって、将来受け取る金額が変わってくるのが特徴です。
対照的に、小規模企業共済の掛金は、運営主体である中小企業基盤整備機構が一括して運用します。
加入者が個別の運用商品を選ぶ必要はありません。予定利率が定められており、事前に確定している共済金が支払われます。
ただし、20年未満の任意解約では元本割れする点に注意しましょう。
受け取り方法の違い(一時金・年金・併用)
iDeCoと小規模企業共済の資金の受け取り方法は以下の3つがあります。
- 一時金:積立額を一括で受け取る方法
- 分割(年金): 一定期間、分割して年金形式で受け取る方法
- 併用:一部を一時金で受け取り、残りを分割で受け取る方法
自身のライフプランや退職後の資金計画に合わせて、最適な受け取り方を選択することが可能です。
受け取り時の課税(退職所得控除、公的年金控除)
積み立てた資産を受け取る際には税金がかかりますが、iDeCoと小規模企業共済はどちらも大きな税制優遇が用意されています。
一時金として一括で受け取る場合は「退職所得」として扱われ、勤続年数(加入年数)に応じた「退職所得控除」が適用されます。
この控除額は非常に大きく、税負担を大幅に軽減できるのが特徴です。
分割して年金形式で受け取る場合は「公的年金等の雑所得」となり、「公的年金等控除」が適用されます。
こちらも一定額まで非課税で受け取れるため、税制上有利です。
注意点として、令和7年度の税制改正により、iDeCoや他の退職金を受け取る際のルールが変更されています。
異なる退職金を短い期間で受け取ると、退職所得控除を満額利用できない可能性があるため、受け取りのタイミング(出口戦略)は慎重に計画する必要があります。
老後資金が気になるあなたへ
老後にお金で困らないために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶40代からの老後資金作り:40代が目指すリスクとリターンのバランスとは?
▶50代からの老後資金作り:50代からでも間に合う?堅実な資産の増やし方
どちらが向いている?ケース別の選び方
iDeCoと小規模企業共済、それぞれの特徴を理解した上で、どちらが自分に向いているかを判断しましょう。
重要なのは自身の事業計画、資金状況、そしてリスクに対する考え方です。
ここでは、「安定志向」と「資産運用志向」という2つのタイプに分けて、それぞれにおすすめの制度を解説します。
安定志向なら小規模企業共済
将来の資産形成において、元本割れのリスクを避け、安定的に退職金を準備したいと考えたい場合は、小規模企業共済が適しています。
小規模企業共済は、iDeCoのように自分で運用商品を選ぶ必要がなく、運営主体が安定的に運用を行います。
そのため、市場の変動に一喜一憂することなく、計画的に資産を積み立てることが可能です。
さらに、契約者貸付制度がある点も大きな魅力です。
事業で急に資金が必要になった場合でも、積み立てた資産を担保に低金利で借り入れができるため、資金の流動性をある程度確保できます。
安全性とセーフティネット機能は、安定経営を目指す事業主にとって心強い味方となるでしょう。
資産運用志向ならiDeCo
節税メリットを享受しつつ、積極的に資産を増やしていきたいと考える場合は、iDeCoが向いています。
iDeCoの魅力は、運用して得た利益がすべて非課税になる点です。
通常の投資では利益に対して約20%の税金がかかりますが、iDeCoではその分を再投資に回せるため、複利効果を最大限に活かせます。
長期的に運用することで、小規模企業共済を上回るリターンが期待できます。
選んだ金融商品によって元本割れのリスクは伴いますが、リスク許容度の範囲内で商品ポートフォリオを組むことで、リスクをコントロールしながら長期的な資産形成を目指すことが可能です。
iDeCoと小規模企業共済は併用できる
iDeCoと小規模企業共済は、どちらか一方しか選べないわけではありません。
両方の制度に同時に加入し、併用することが可能です。
併用メリット(節税枠拡大・リスク分散)
iDeCoと小規模企業共済を併用する最大のメリットは、所得控除の枠を最大限に活用できる点です。
個人事業主の場合、小規模企業共済で年間最大84万円、iDeCoで年間最大81.6万円、合計で年間165.6万円もの金額を所得から控除できます。
これにより、単独で利用するよりも大きな節税効果が期待できます。
また、リスク分散の観点からも併用は有効です。
小規模企業共済は元本確保型の安定した「守りの資産」、iDeCoは運用次第でリターンを狙える「攻めの資産」と位置づけることができます。
性質の異なる2つの制度を組み合わせることで、資産全体のバランスを取りながら、安定的かつ効率的な資産形成を目指すことが可能になります。
併用に向いている人の特徴
iDeCoと小規模企業共済の併用は、資金に余裕があり、両方の掛金を無理なく継続して支払える個人事業主や経営者に向いています。
両制度を最大限活用すると、月々の掛金は合計で10万円を超えます。
この負担を長期にわたって続けられるかどうかが、併用を検討する上での重要な判断基準となります。
また、節税効果を最大化しつつ、資産運用にも挑戦したいという、安定性と収益性の両方を追求したい人にも併用は最適な選択肢と言えるでしょう。
まずは小規模企業共済で安定した基盤を築き、余裕資金でiDeCoの運用益非課税メリットを狙う、といった戦略的な活用が可能です。
併用時の注意点(掛金負担・受け取り時の課税)
iDeCoと小規模企業共済を併用する際には、いくつかの注意点があります。
第一に、掛金の負担が大きくなることです。両制度のメリットを最大限に享受しようとすると、月々の拠出額は高額になります。事業のキャッシュフローを圧迫しないよう、無理のない範囲で掛金額を設定することが重要です。
第二に、受け取り時の課税です。特に注意が必要なのが、両方の制度から一時金として受け取る場合です。
退職所得控除は、受け取る退職金の合算額に対して計算されます。もし、iDeCoと小規模企業共済の一時金を同じ年に受け取ると、控除枠を一度しか使えず、税負担が増える可能性があります。
税制改正により、退職所得控除のルールが厳格化されているため、受け取りのタイミングをずらすなど、計画的な「出口戦略」を立てることが必要になるでしょう。
節税効果をシミュレーション
iDeCoと小規模企業共済の所得控除による節税効果は、所得額によって変わります。
所得税は累進課税であり、所得が高いほど税率も高くなるため、高所得者ほど節税の恩恵は大きくなります。
所得控除による節税額は、その人の所得控除額に所得税と住民税の税率を掛けて算出されます。
住民税率は一律10%ですが、所得税率は課税所得に応じて変動します。
例えば、課税所得が500万円(年収600万〜700万円程度に相当)の個人事業主が、各制度を満額拠出した場合の節税額の目安は以下のようになります。
- 小規模企業共済(年84万円拠出): 約25万円の節税
- iDeCo(年81.6万円拠出):約24万円の節税
年収がこれより低い場合、所得税率が下がるため節税額は少し小さくなります。
一方、年収が高く課税所得が増えるほど、より高い所得税率が適用されるため、同じ掛金額でも節税効果はさらに大きくなります。
まとめ
iDeCoと小規模企業共済は、どちらも個人事業主や経営者にとって非常に有利な制度ですが、その特性は大きく異なります。
iDeCoは「運用益非課税」というメリットがあり、積極的に老後資金を増やしたい人に向いています。
一方、小規模企業共済は元本割れリスクはなく、貸付制度もあるため、安定的に退職金を準備したい安定志向の人に適しています。
両制度は併用が可能で、組み合わせることで節税効果を最大化し、リスクを分散させることができます。
ただし、併用する際は掛金の負担や、受け取り時の税金(出口戦略)について慎重に計画することが重要です。
ご自身の事業の状況、将来のライフプラン、そしてリスクに対する考え方を総合的に考慮し、最適な制度の活用法を見つけましょう。
»まずはライフプランに合わせて将来資金をシミュレーション
老後資金が気になるあなたへ
老後にお金で困らないために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶40代からの老後資金作り:40代が目指すリスクとリターンのバランスとは?
▶50代からの老後資金作り:50代からでも間に合う?堅実な資産の増やし方
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
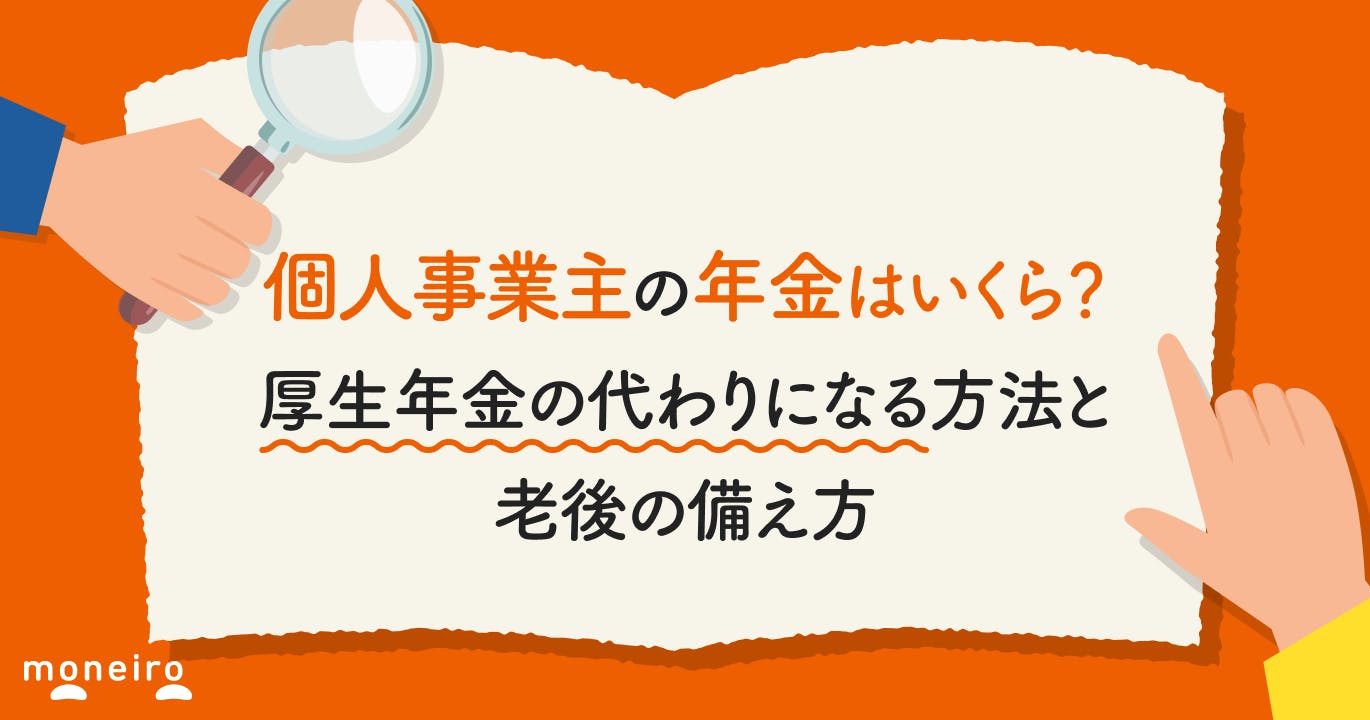

老後資金はどうやって準備する?必要資金の計算方法と準備方法を解説

小規模企業共済のデメリットとは?専門家が3つの注意点と活用法をわかりやすく解説
監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。