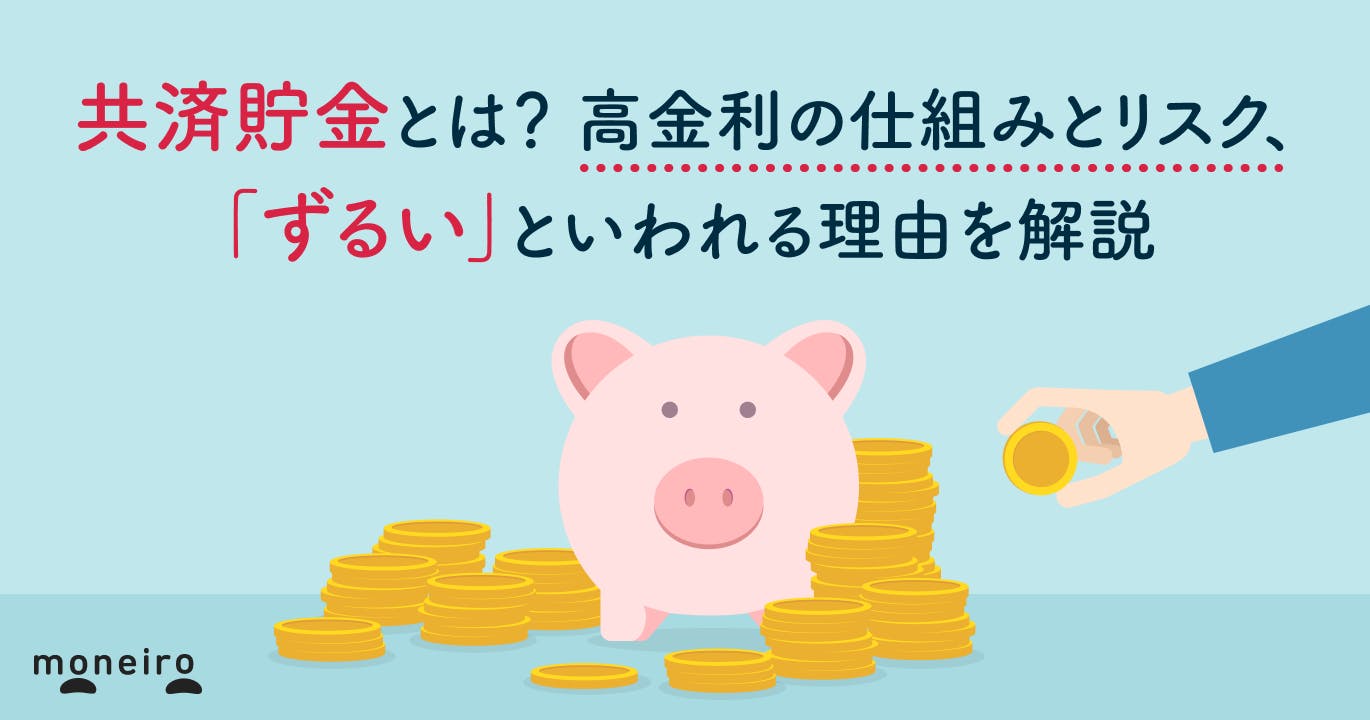共済貯金とは?高金利の仕組みとリスク、「ずるい」といわれる理由を解説
≫あなたは大丈夫?老後に不足する金額を3分で診断
高い金利が魅力の「共済貯金」は、公務員や特定の団体職員にのみ認められた福利厚生制度です。一般の銀行預金とは一線を画し、低金利時代においても高い利率が設定されているため、「ずるい」とまでいわれることもあります。
本記事では、共済貯金が高金利を実現できる仕組みや、給与天引きのメリット、そして退職時の取り扱いを含めたデメリットや注意点まで、詳細に解説します。
- 共済貯金が高い金利を実現できる仕組みと大きなメリット
- 共済貯金が抱えるインフレや利用制限といったデメリットやリスク
- 共済貯金の始め方や、退職時の取り扱い
将来資金が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
共済貯金とは?
共済貯金とは、特定の共済組合(例:公立学校共済組合、私立学校教職員共済など)の組合員を対象とした、福利厚生の一環として提供される貯蓄制度です。
これは、一般の金融機関が提供する預金とは異なり、組合員とその家族の生活の安定と経済的向上を目的として、組合が自主的に運営しています。組合員は給与や賞与からの天引きによって貯蓄ができ、高い利率で運用されることが最大の特徴です。
共済貯金が高金利を実現できる理由
共済貯金が、メガバンクなどの一般の金融機関の預金金利を大きく上回る高い金利(利率)を実現できるのには、その独自の運営形態に理由があります。
非営利目的の運営
共済貯金制度は、銀行のような営利企業とは異なり、組合員の福利厚生のために非営利目的で運営されています。
一般的な銀行は、株主への配当や人件費、広告宣伝費といった多岐にわたるコストを利益から捻出しなければなりませんが、共済組合は利益を追求しないため、運用で得た収益の多くを組合員に高金利として還元することが可能です。
限定された預金者と低コスト運用
共済貯金の利用者は、特定の共済組合の組合員に限定されています。一般の金融機関のように、全国に支店を配置したり、大規模な広告キャンペーンを展開したりする必要がありません。
これにより、運営に必要な人件費や管理コストを大幅に低く抑えることができます。この低コスト構造も、高金利を実現する重要な要因の一つです。
安定した資金運用
組合員から預けられた資金は、一般的に、安全性が高く安定した運用先へ投資されます。具体的には、国債や地方債、あるいは公的な融資制度への貸し付けなどに充当されることが多く、極端なリスクを取らずに安定的なリターンを確保しやすい環境にあります。
この安定した運用基盤があるため、共済組合は組合員に対して、長期にわたり比較的高い固定金利を提供できるようになっています。
共済貯金は「ずるい」といわれるほどの大きなメリット
共済貯金は、その高い金利や利便性から、公務員や特定の職員の「特権」のように見なされ、「ずるい」と表現されるほどの大きなメリットを享受できます。
銀行預金を大きく超える金利(利率)の高さ
共済貯金の最大のメリットは、何といっても一般の銀行預金を圧倒する金利の高さです。
近年の普通預金金利が年利0.2%程度であるのに対し、多くの共済貯金は年利0.5%以上で、中には1.5%を超えるような高い利率が設定されているケースもあります(具体的な利率は組合によって異なります)。
これは、銀行預金の数倍に相当し、単に貯金しておくだけでも効率的に利息を増やすことができます。
給与天引きで「先取り貯蓄」を自動化できる
共済貯金は、毎月の給与や賞与から天引き(控除)される形で積み立てが行われます。これにより、利用者は貯蓄のための手続きを意識することなく、「先取り貯蓄」を自動的に行うことができます。
手取り額から生活費を支払った後に残った分を貯蓄する「後取り貯蓄」よりも、着実に資金を積み上げていくことができ、貯蓄の意志力に頼る必要がない点が大きな強みです。
預入・払戻時の手数料が原則無料
多くの共済貯金制度では、預け入れ(積立)時や、必要な際の一部払い戻し時に、手数料が原則として無料です。
これは、一般の金融機関で時間外にATMを利用したり、振込を行ったりする際に手数料が発生する場合があるのと比較して、利用者にとって大きな利便性となります。
ただし、共済組合では、払戻し可能日が「毎月25日」など、あらかじめ決められています。一般的な普通預金と比べると資金の自由度では劣る点には注意が必要です。
将来資金が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
職場で完結する手続きの手軽さ
共済貯金の開始や積立額の変更、払戻しの手続きは、基本的に所属する職場の担当窓口を通じて行われるため、非常に手軽です。
煩雑な銀行の口座開設や、複雑な投資商品の購入手続きとは異なり、組合内で完結できるため、利用者にとって心理的なハードルが低いのもメリットです。
組合によっては独自の付加給付がある場合も
共済組合によっては、貯蓄機能だけでなく、独自の付加給付や福利厚生サービスが連動している場合があります。
例えば、病気や災害時の給付金、各種融資制度の利用など、組合員向けの優遇措置が受けられることがあります。これにより、共済貯金は単なる貯蓄手段としてだけでなく、組合員生活を総合的にサポートする役割を果たします。
共済貯金にはデメリットもある
高金利で魅力的な共済貯金ですが、利用にはデメリットや注意すべきリスクも存在します。
預金保険制度(ペイオフ)の対象外である
共済貯金は、銀行法や預金保険法に基づいた「預金」ではなく、共済組合法に基づく組合員向けの福利厚生制度であるため、預金保険制度(ペイオフ)の対象とはなりません。
共済組合は、主に安定性の高い国債や地方債などで資産を運用しており、健全な運営がされているため、破綻する可能性は低いと考えられますが、万が一の場合に銀行預金と同等の元本保護がない点は、リスクとして正しく認識しておく必要があります。
インフレで資産価値が目減りするリスク
共済貯金は高い金利を提供しますが、あくまで元本が保証された「貯金」であり、比較的低リスクに設定されています。
もしインフレ率(物価上昇率)が共済貯金の金利を上回った場合、購入できるモノの量が減少し、実質的な資産価値は目減りしてしまいます。
特に、長期的に見てインフレが進行した場合、高金利といえども資産形成の面では物価上昇に追いつけず、資産が目減りするリスクがある点には注意が必要です。
投資のような大きなリターンは期待できない
共済貯金は安全性を重視した運用であるため、株式投資や投資信託(NISA・iDeCoで活用されるものなど)といったリスク資産運用と比較すると、期待できるリターンは限定的です。
インフレに負けない積極的な資産形成を目指す場合、共済貯金のみに頼るのではなく、他の投資手段とのバランスも考える必要があります。
退職すると原則利用できない(出口戦略の重要性)
共済貯金は、共済組合の組合員資格を有していることが利用の前提条件です。
そのため、定年退職や自己都合退職によって組合員資格を失うと、原則として共済貯金は解約となり、貯蓄していた全額を一括で引き出すことになります。
退職時にまとまった資金が手に入りますが、その後の生活費や税金の取り扱い(出口戦略)を事前に計画しておかないと、資金使途を誤ったり、インフレや低金利によって資産が目減りしてしまうリスクがあります。
組合によっては預入限度額が設定されている
組合によっては預入限度額が設定されている 多くの共済組合では、組合員一人あたりの預入限度額が設けられています。
その上限額は元本と利息の合計で3000万円と定められているのが一般的ですが、組合によっては上限が異なる、あるいは設定されていない場合もあります。
共済貯金の始め方3ステップ
共済貯金は、一般的な金融商品の購入と比較して、非常にシンプルな手続きで始めることができます。
1.所属の共済組合の窓口に相談・書類を入手
共済貯金を利用するには、まず所属する共済組合の担当課(または職場の事務担当部署)に問い合わせ、共済貯金の利用を希望する旨を伝えます。
そこで、「共済貯金利用申込書」などの必要書類を入手します。各組合によって制度の詳細や提出書類が異なるため、必ず所属の組合に確認しましょう。
2.必要書類の記入・提出
入手した申込書に、毎月の積立希望額や積立開始を希望する月、引き落としに関する情報などを記入します。
積立額は、多くの場合、月々数千円から設定できます。必要事項を記入した後、指定された期日までに職場の担当窓口に提出します。
3.積立開始
提出が完了し、審査を経た後、指定した開始月以降の給与から積立額が自動的に天引きされる形で、共済貯金の積立が始まります。
積立額が変更になったり、利息が加算されたりする情報は、定期的に組合から送付される「貯金現在高通知書」などで確認できます。
共済貯金に関するQ&A
ここでは、共済貯金に関するよくある質問にQ&A形式で回答します。
Q. 途中で積立額を変更したり、一時的に止めたりはできる?
ほとんどの共済貯金制度では、途中で積立額の変更や一時的な積立の中断(停止)が可能です。
ただし、変更や停止には所定の手続きが必要で、通常は担当窓口へ「積立額変更届」などの書類を提出する必要があります。手続きの締め切り日によっては、希望する月からの変更に間に合わない場合もあるため、余裕をもって申請することが重要です。
Q. 共済貯金の利息に税金はかかる?
共済貯金で得られた利息(配当金)は、所得税法上の課税対象となります。一般的に、銀行預金の利息と同様に、源泉分離課税(20.315%)が適用され、利息が支払われる際にすでに税金が差し引かれています。
ただし、制度の運営主体や利息の性格によって税法上の取り扱いが異なる場合もあるため、詳しくは所属する組合の規定を確認するとよいでしょう。
Q. 共済貯金が3000万円を超えるとどうなる?
多くの共済組合で設定されている預入限度額(元利合計3000万円など)を超えた場合、原則として、超えた分の新規の積立は停止されます。金利は継続して付きますが、組合は超過した資金に対して高い金利を保証する必要がなくなります。
そのため、上限に達した資金については、税制優遇を受けられるNISAやiDeCo、あるいは普通預金や定期預金など、他の資産運用先に振り分ける計画を立てたほうがよいでしょう。
まとめ
共済貯金は、特定の組合員に限定された、高い金利と給与天引きによる強制的な貯蓄が魅力の福利厚生制度です。銀行預金を圧倒する利率は大きなメリットであり、資産形成の初期段階や、緊急時のための安全資産を積み立てる上で非常に有効な手段といえます。
しかし、インフレによる実質価値の目減りリスクや、預入限度額、そして退職時に原則解約となる「出口戦略」の必要性など、いくつかのデメリットも存在します。
共済貯金を活用する際は、この制度を資産形成の「土台」と位置づけ、上限に近づいた段階や、インフレ対策として、iDeCoやNISAといった他の投資手段とも組み合わせながら、分散投資を行うことが賢明な利用方法といえるでしょう。
≫あなたは大丈夫?老後に不足する金額を3分で診断
将来資金が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事


老後資金はどうやって準備する?必要資金の計算方法と準備方法を解説
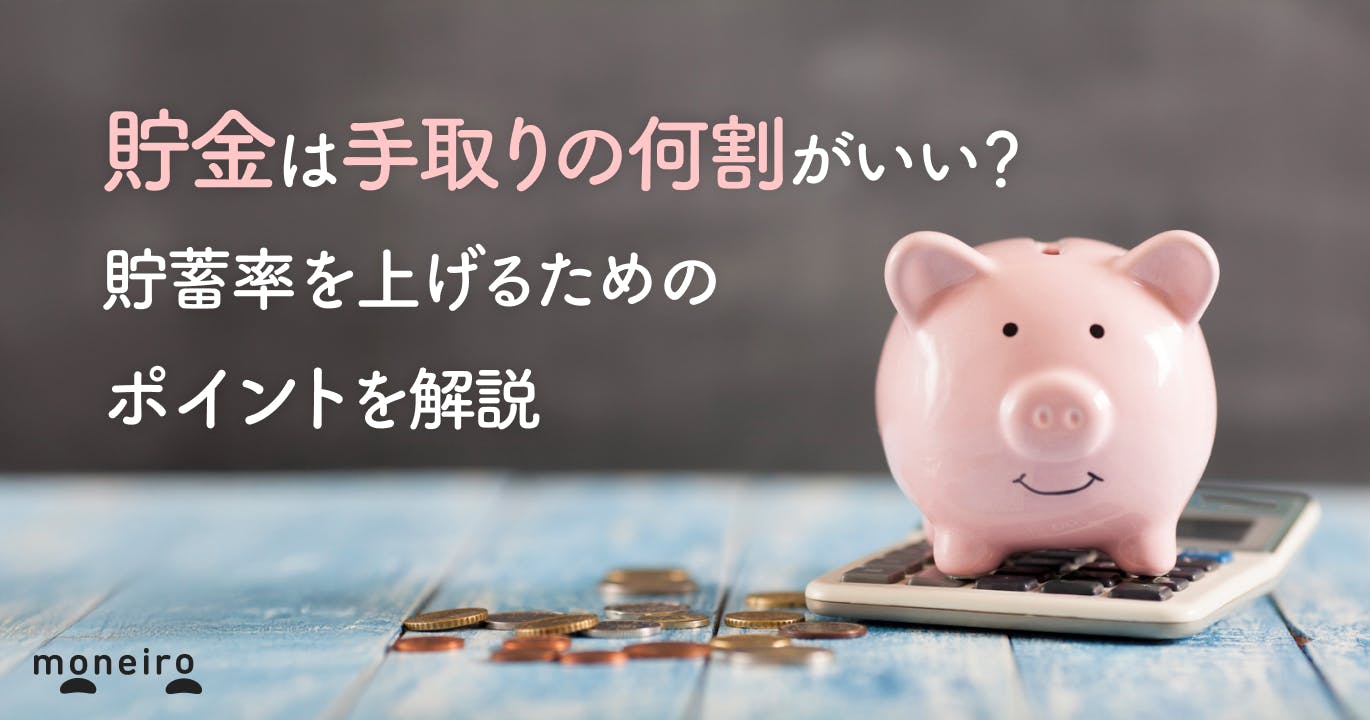
貯金は手取りの何割がいい?平均貯蓄率&貯蓄率を上げるコツを解説

財形貯蓄はやめたほうがいい?後悔しないための判断基準と代替案を解説
監修
高橋 明香
- ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者
みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。