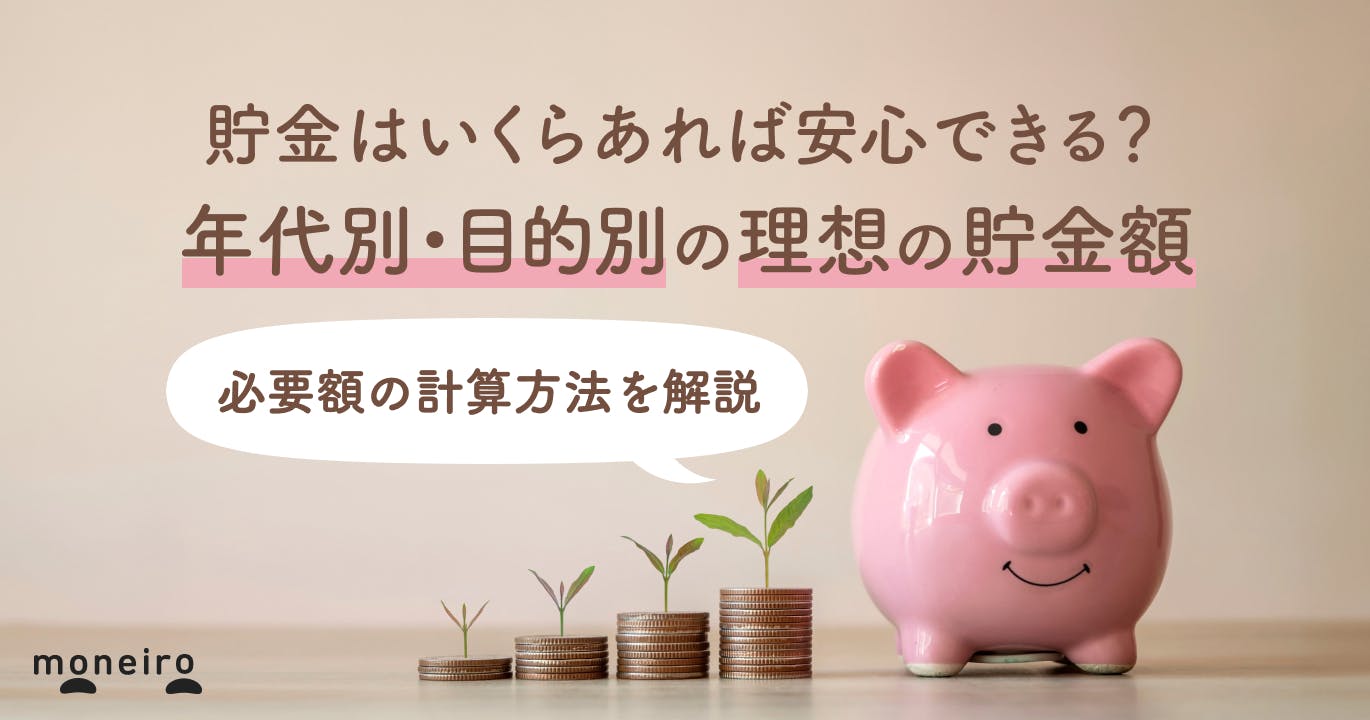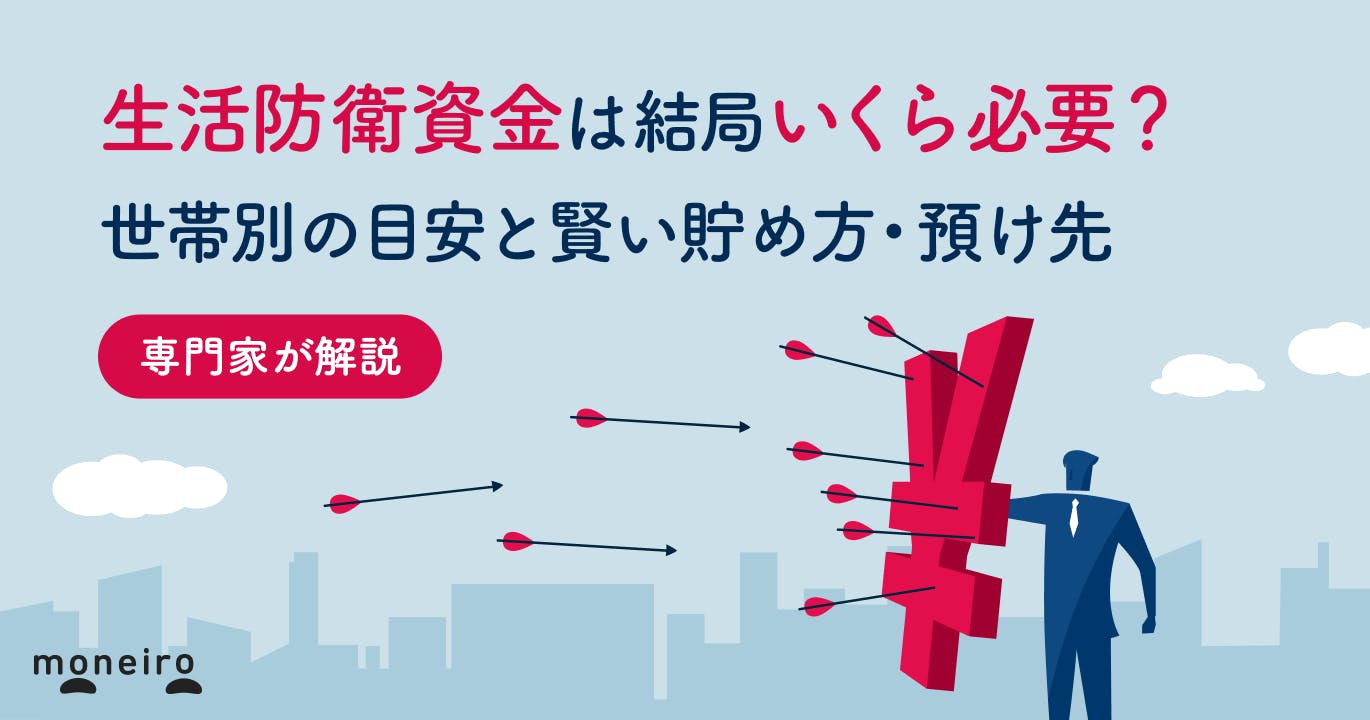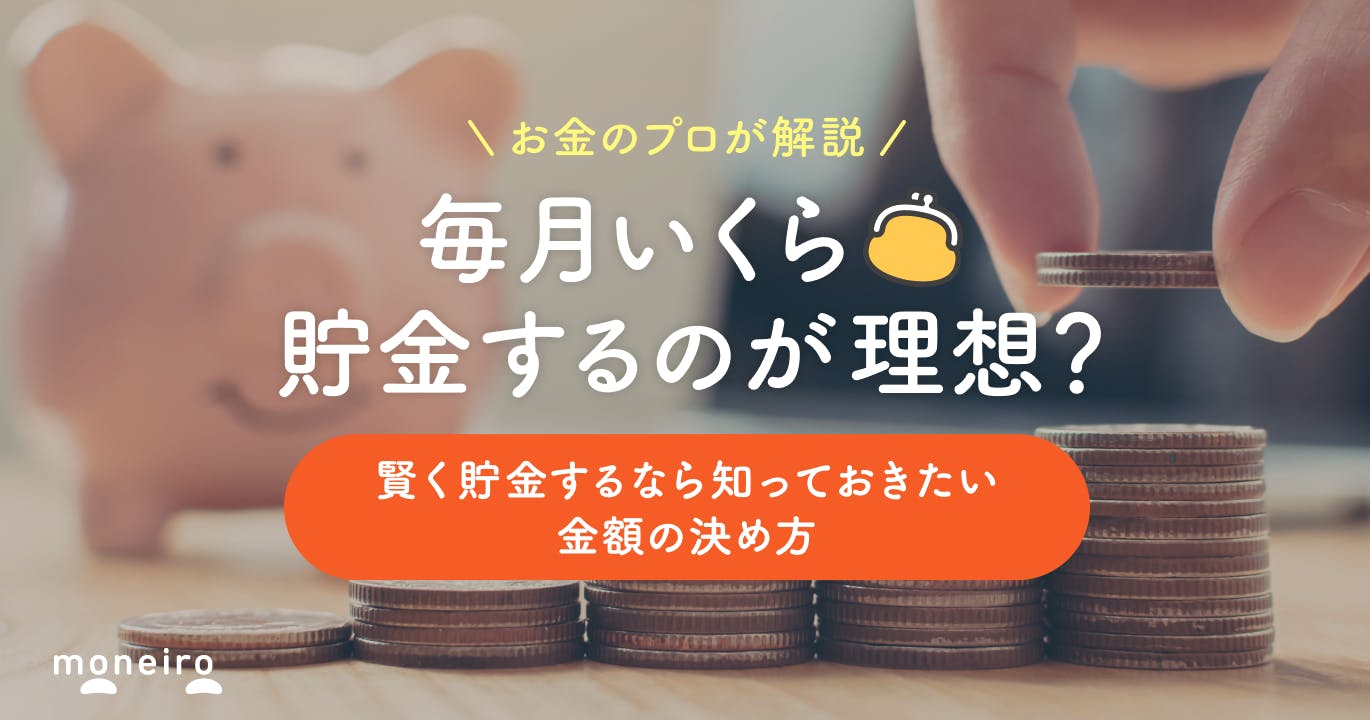財形貯蓄はやめたほうがいい?後悔しないための判断基準と代替案を解説
【無料】老後資金は大丈夫?将来の必要額を年収・資産から3分で診断
財形貯蓄をやめたほうがいいか悩んでいませんか?本記事では、そんな方に向けて、財形貯蓄のデメリットや、向いている人・向いていない人の特徴をわかりやすく解説します。
後悔しないための判断基準と、財形貯蓄を利用しない場合の代替案も併せて紹介しますので、ぜひ自分の状況と照らし合わせて最適な選択を見つける参考にしてみてください。
- 財形貯蓄制度の基本的な種類と仕組み
- 財形貯蓄を「やめたほうがいい人」と「続けるべき人」の特徴
- 財形貯蓄に代わる、より有利な資産形成の方法
将来のお金が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
そもそも財形貯蓄制度とは?3つの種類と基本をおさらい
財形貯蓄制度とは、勤労者の財産形成を促進するため、会社が給与からの天引きによって貯蓄を支援する制度です。財形貯蓄には、以下の3つの種類があります。
一般財形貯蓄
一般財形貯蓄は、毎月の給料やボーナスから自動的に天引きされて積み立てていく貯金制度で、会社を通じて金融機関と契約します。
この制度の特徴は、使い道に制限がないことです。例えば、旅行や趣味、家電の購入など、自由に使うことができます。また、契約時の年齢制限はなく、複数契約も可能なため、ライフスタイルに合わせて柔軟に利用できます。
財形住宅貯蓄
財形住宅貯蓄は、契約締結時に55歳未満の就労者が利用できる制度で、給料やボーナスから天引きされる形で、原則5年以上積み立てる貯蓄です。
この制度は、マイホームの購入や建て替え、リフォームといった住宅取得を目的としており、利子が非課税(元利合計550万円まで、一定の条件を満たした場合)になるメリットがあります。
ただし、住宅取得以外の目的で引き出すと、過去5年間分の利子が課税措置の対象となるため注意が必要です。また、財形住宅貯蓄は1人につき1契約に限定されます。
財形年金貯蓄
財形年金貯蓄も、55歳未満の勤労者が契約し、5年以上の期間にわたって賃金からの控除(天引き)で積み立てる貯蓄です。目的は、60歳以降に5年以上の期間にわたって年金として支払いを受けることです。
財形住宅貯蓄と同様に、元利合計550万円まで、利子等に対する非課税措置が適用されます。原則として60歳まで引き出せない制限があり、目的外の引き出しは非課税の対象外となります。こちらも1人1契約が原則です。
非課税限度額は、「財形住宅貯蓄」と合計で550万円までとなります。また、保険型商品の場合の非課税限度額は、財形年金貯蓄のみなら385万円、財形住宅貯蓄のみなら550万円、双方を併せる場合は、合計で550万円となります。
財形貯蓄はやめたほうがいい?3つのデメリット
財形貯蓄を利用する上では、いくつかのデメリットが存在します。これらを理解した上で、利用をを判断することが重要です。
金利が低い
財形貯蓄の金利は、一般的に普通預金と同程度か、わずかに高い程度であることが多いです。そのため、効率的に資産を増やしたいと考えている人にとっては、物足りなく感じる可能性があります。
低金利の状況下では、預貯金だけでは資産が大きく増えることは期待しにくいといえるでしょう。
資金の引き出しに制限がある
財形貯蓄は、資金の引き出しにある程度の制限があります。
一般財形貯蓄の場合
一般財形貯蓄は使途に制限がないため、比較的自由に引き出しが可能です。とはいえ、引き出すには会社や取扱金融機関への手続きが必要です。手軽にATMから引き出せる普通預金などと比較すると、引き出しの自由度が低いと感じるかもしれません。
財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄の場合
財形住宅貯蓄や財形年金貯蓄の場合、原則として、決められた目的外で引き出すと利子が課税対象になります。特に財形年金貯蓄は、原則60歳まで引き出せないという大きな制限があります。
ただし、災害による被害、年間200万円を超える医療費、寡婦・寡夫になった場合、特別障害者に該当した場合、特定受給資格者または特定理由離職者に該当した場合など、特定の理由による払い出しであれば、税務署の確認を受けることで非課税で引き出すことが可能です。
勤務先の制度に依存する
財形貯蓄は、勤務先の給与天引き制度を利用して積み立てる仕組みであるため、会社に制度が導入されていないと利用できません。また、導入されていても、取り扱う金融機関や利用可能な財形の種類が限られている場合があります。
さらに、転職や退職をすると積立が終了したり、口座の扱いが変わったりするため、継続利用が難しくなるケースもあります。このように、制度の利用や継続が勤務先に左右される点は大きなデメリットといえます。
財形貯蓄のメリットも確認しておこう
デメリットがある一方で、財形貯蓄には見逃せないメリットも存在します。これらのメリットが自身のライフプランと合致するかどうかを検討することが大切です。
手間なく、着実に貯蓄できる
財形貯蓄は、給与からの天引き(控除)で行われるため、手間なく自動的に貯蓄が進みます。
自分で意識して銀行に預け入れに行く必要がないため、「貯蓄が苦手」「ついつい使いすぎてしまう」という人でも、無理なく計画的に財産を形成できます。
利子等の非課税措置を受けられる
財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄には、利子が非課税となる優遇措置があります。
通常、預貯金の利子には20.315%(所得税、復興特別所得税、住民税の合計)の税金がかかりますが、財形制度を利用することでこの税金が免除され、効率的にお金を増やせます。
財形年金貯蓄は、60歳以降に5年以上かけて年金形式で受け取る場合、積立期間中および受取期間中の利子が非課税となります。ただし、年金形式ではなく一括で払い出す場合や、事前に設定した受取期間中に解約すると、解約利子に対し20.315%の税金がかかることがあります。
住宅ローンがお得になる
財形貯蓄をしている勤労者は、一定の条件を満たせば「財形持家転貸融資」を利用できることがあります。
この制度は、マイホームの購入や増改築(リフォーム)に利用できる住宅ローンで、一般の住宅ローンよりも金利が低めに設定されるのが特徴です。また、勤務先を通じた制度であることから、審査が比較的スムーズに進むこともあります。
低金利かつ柔軟な条件で資金を借りられるため、マイホームの取得やリフォームを計画している人にとって、大きなメリットのある制度です。
将来のお金が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
財形貯蓄をやらないほうがいい人
財形貯蓄のメリット・デメリットを踏まえ、財形貯蓄が向かない人もいます。以下に該当する人は、他の資産形成方法を検討したほうがよいかもしれません。
積極的にお金を増やしたい人
財形貯蓄は金利が低いため、預貯金に近い性質を持ちます。積極的にリスクを取りながら、より高いリターンを目指して資産を増やしたいと考えている人には、不向きといえるでしょう。
効率的な資産形成を目指すのであれば、他の運用商品を検討する必要があります。
引き出しの自由度を重視する人
急な出費に備えてすぐに資金を引き出せる自由度を重視する人には、財形貯蓄は不便に感じられるかもしれません。特に財形住宅貯蓄や財形年金貯蓄は、目的外の引き出しに制限があり、利子への課税リスクや、年金貯蓄の場合は原則60歳まで引き出せないといった制約があります。
必要な時にすぐ使える資金を確保したいのであれば、普通預金など流動性の高い金融商品のほうが適しています。
より有利な税制優遇制度を自分で活用できる人
財形貯蓄には非課税の優遇措置がありますが、NISAやiDeCoといった、これよりもさらに有利な税制優遇制度が他にも存在します。自分で積極的に情報収集し、これらの制度を活用できる知識や意欲がある人は、財形貯蓄にこだわる必要はないかもしれません。
例えば、iDeCoやNISAといった制度は、投資を通じて資産形成をしながら、税制上の大きなメリットを享受できます。
財形貯蓄とともに活用を検討したい2つの制度
ある程度リスクを取りながら積極的にお金を増やしたい人には、財形貯蓄よりもさらに有利な税制優遇制度があります。これらを財形貯蓄と組み合わせて利用したり、財形貯蓄に代わる選択肢として検討したりするのがおすすめです。
NISA(少額投資非課税制度)
NISAは、投資した株式や投資信託などから得られる売却益や配当金が非課税になる制度です。
NISAには、長期目線での積立投資に向いている「つみたて投資枠(年間120万円)」と、より多彩な選択肢から投資先を選べる「成長投資枠(年間240万円)」の2種類の投資枠があります。
投資した資産は原則いつでも資金を引き出すことができ、目的も自由であるため、将来のライフイベントに向けた資産形成に向いています。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCoは、自分で掛金を拠出し、自分で選んだ運用商品で資産を運用し、その成果を年金として受け取る私的年金制度です。大きな特徴は、拠出した掛金が全額所得控除の対象となり、所得税や住民税を軽減できる点です。
また、運用益も非課税で再投資され、通常は課税される運用益にかかる税金がかかりません。さらに、年金として受け取る際も、公的年金等控除や退職所得控除の対象となるなど、複数の税制優遇が受けられます。原則60歳まで引き出しができないため、老後資金の準備に特化した制度といえます。
財形貯蓄に関するQ&A
財形貯蓄についてよくある質問とその回答をまとめました。
Q. 財形貯蓄で550万円貯まったらどうなる?
550万円は、財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄の合算での利子が非課税になる限度額です。
この金額を超えて積み立てた場合、その超えた部分から生じる利子については、通常の預貯金と同様に20.315%の税率で課税の対象となります。なお、一般財形貯蓄はすべて課税対象です。
Q. 転職や退職をした場合、財形貯蓄はどうなる?
転職や出向で勤務先が変わった場合、新しい勤務先に財形貯蓄制度があれば、契約更新や書類提出などの手続きにより積み立てを継続できます。
もし新しい勤務先に制度がない場合や、同じ金融機関の取り扱いがない場合でも、退職から2年以内に財形貯蓄を取り扱う別の金融機関に預け替えることで、財形住宅貯蓄や財形年金貯蓄の非課税措置を維持可能です。
一方、退職して勤労者でなくなった場合、新たな積み立てはできません。また、退職後2年以内に預け替えや住宅取得・年金受取などの目的に沿った引き出しを行わないと、非課税だった利子が20.315%の税率で課税対象となるため注意が必要です。
一般財形貯蓄には非課税の特典がないため、これらの制限は適用されません。
Q. 財形貯蓄は会社側にもメリットがある?
はい、財形貯蓄制度は会社側にもメリットがあります。
従業員の貯蓄意識を喚起し、勤労意欲を高める効果が期待できます。また、会社にとっては大きな負担を負うことなく、福利厚生制度の充実や社内融資制度の拡充を図れるため、従業員の定着性を高め、優秀な人材の確保にも効果的とされています。
まとめ
財形貯蓄制度は、給与天引きによる着実な貯蓄が可能で、特定の目的に対しては利子等の非課税措置や財形持家転貸融資といったメリットを享受できる、堅実な資産形成手段です。
しかし、金利の低さや資金引き出しの制限といったデメリットも存在します。そのため、積極的な資産運用を望む人や、資金の流動性を重視する人などにとっては、財形貯蓄だけでは物足りない可能性があります。
財形貯蓄を続けるべきか、見直すべきかは、自身のライフプランや資産形成の目標、リスク許容度によって異なります。現状を把握し、NISAやiDeCoといった他の税制優遇制度も視野に入れながら、最適な資産形成戦略を立てることが重要です。
将来のお金が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
高橋 明香
- ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者
みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。