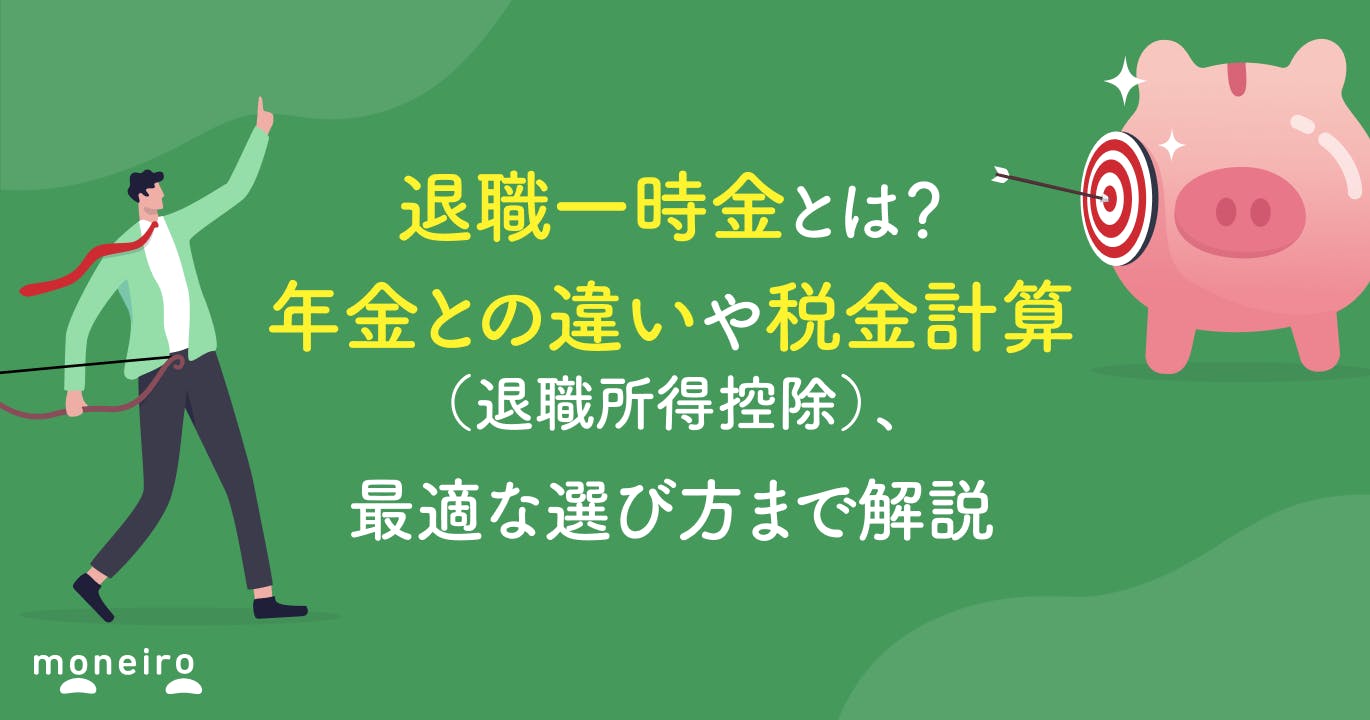退職一時金とは?年金との違いや税金計算(退職所得控除)、最適な選び方まで解説
≫老後の資金は足りる?あなたの必要額を診断
退職一時金とは、従業員が退職する際に会社から一括で支給される退職給付をいいます。退職後の重要な生活資金となるため、その仕組みや税制上の取り扱いを理解しておくことは非常に重要です。
本記事では、退職一時金の概要から、退職年金との違い、税制面で大きな優遇をもたらす退職所得控除の計算方法、さらには2026年に施行される税制改正の注意点まで、分かりやすく解説します。
- 退職一時金の基本的な定義、退職年金や企業型DCとの違い
- 退職一時金を受け取る際に適用される退職所得控除の計算方法
- 2026年以降、iDeCoなどの一時金受取で注意すべき「10年ルール」について
退職金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
退職一時金とは?3分で分かる基本と仕組み
退職一時金とは、退職給付の一種であり、従業員が退職する際に一時金の形で支給される会社の福利厚生の1つです。単に「退職金」と呼ばれる際、この退職一時金を指すのが一般的です。
退職一時金などの退職給付は、法律によって支給が義務付けられているものではありません。会社が制度を設けないことも可能であり、設ける場合でも、支給条件や支給額は会社が自由に設定できます。
3つの「退職一時金」
厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査」によると、退職給付制度を設けている企業は74.9%です。このうち、退職給付として退職一時金のみを支給している企業の割合は69.0%と、非常に多く採用されている制度であることが分かります。
退職一時金制度は、主に以下の3種類に大別されます。
- 社内準備(社内積立)型:会社内部に資金を積み立てて準備し、退職時に支給する形です。同調査時点では、この形態が56.5%と過半数を超える割合で採用されています。資金管理がしやすい反面、運用責任はすべて会社が負います。
- 中小企業退職金共済制度(中退共):中小企業が多く採用し、中小企業退職金共済が支払いを行うため、事務手続きが不要になります。
- 特定退職金共済制度:特定退職金共済団体と契約を締結し、管轄税務署の承認のもとで実施される制度です。
退職年金との違い
退職一時金が退職時に一括で1回のみ支給されるのに対し、退職年金(企業年金)は退職給付が年金の形で、終身または有期で定期的に一定額が支払われる点が大きな違いです。
退職給付全体で見ると、年金としてのみ支給する企業の割合は9.6%ですが、一時金と年金を併用している会社は21.4%です。受け取り方法の選択は、税制や社会保険料に影響を与えるため、慎重な検討が必要です。
脱退一時金との違い
「脱退一時金」は、名前は似ていますが「退職一時金(退職給付)」とはまったく別の制度です。
脱退一時金は、iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型DC(確定拠出年金)で、原則として60歳未満では受け取れない資産を、中途で引き出せる制度を指します。ただし、引き出しにはごく限定的な条件があり、例えば「拠出期間が5年以内かつ個人別管理資産額が25万円以下」といった法令で定められた要件を満たす場合に限られます。
最大の違いは税制面です。退職一時金は老後資金として「退職所得」として扱われ、退職所得控除が適用されますが、脱退一時金は「一時所得」として課税対象となります。
自分の退職金制度を確認する3ステップ
退職金の受け取りに関する最適な選択をするためには、まずご自身の会社の制度を正確に把握する必要があります。
STEP1.「就業規則」または「退職金規程」を入手する
基本的に、退職金制度の具体的な内容は、勤務先の「就業規則」または「退職金規程」に定められています。現在または過去の勤務先の人事部や総務部に問い合わせるか、イントラネット等を確認し、これらの規程を入手しましょう。
STEP2. 支給要件(勤続年数・事由)を確認する
規程から、退職一時金が支給されるための具体的な要件を確認します。「勤続何年から支給されるか」という勤続年数の条件のほか、「自己都合退職」と「会社都合退職」とで支給率が異なることが多いため、退職事由と支給率の関係をチェックしておくことが重要です。
STEP3. 受取方法(一時金/年金)の選択肢を確認する
退職金制度の中には、一時金のみ、年金も選択可能、あるいは一時金と年金の併用が可能など、複数の受け取り方法を用意している場合があります。年金を選択できる場合、その受取期間(例えば、10年確定年金や終身年金など)についても確認し、自分のライフプランに合った選択肢があるか把握しましょう。
退職金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
退職一時金(一括) vs 退職年金(分割)どっちが得?
退職金を一括で受け取るか、分割で受け取るかは、税制や社会保険料に大きく影響します。
税制面(退職所得控除 vs 雑所得)
一時金で受け取る最大のメリットは、退職所得控除という優遇措置が適用される点です。退職所得は、他の所得とは別々に税金が計算される分離課税であり、控除額を差し引いた後の金額にさらに2分の1を掛けたもののみが課税対象となるため、税負担が非常に軽くなります。
一方、年金形式で受け取る場合は、雑所得として扱われ、公的年金等控除の対象となりますが、一時金ほどの大きな税制優遇は適用されません。
社会保険料(国保・介護保険)への影響
一時金は、退職後の国民健康保険や介護保険の算定対象となる所得には原則として含まれません。そのため、高額な一時金を受け取っても、社会保険料が急激に上がることを避けられます。
しかし、年金形式で受け取る場合は、毎年受け取る年金が雑所得として社会保険料の算定対象に含まれます。これにより、保険料が増加し、退職後の手取り収入を圧迫する大きな要因となる可能性があります。
ライフプラン・運用面
一時金は、退職直後にまとまった資金が必要な人(例えば、住宅ローンの繰り上げ返済や、起業資金、旅行資金など)に向いています。また、受け取った資金を自分で積極的に運用したい人にも適しています。
年金形式での受け取りは、退職後も定期的な収入を確保して生活を安定させたい人や、自分で資産運用を行うことに不安を感じる人に向いています。
退職一時金の税金計算(退職所得控除)
退職一時金は退職所得として課税されますが、優遇された計算方法が適用されます。退職所得の金額は、以下の式で計算されます。
退職所得の金額 = (退職一時金の受取額 - 退職所得控除額) × 1/2
STEP1. 退職所得控除額の計算(勤続年数別)
退職所得控除額は、勤続年数(A)に応じて計算方法が異なります。勤続年数は、1年未満の端数があれば切り上げて1年として計算します。
例えば、勤続30年の場合、控除額は800万円 + 70万円 × (30年 - 20年) = 1500万円となります。
参考:No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁
STEP2. 課税退職所得金額の計算(1/2課税)
退職所得控除額を差し引いた金額のさらに2分の1のみが課税対象(課税退職所得金額)となるため、税負担が非常に軽くなります。もし退職一時金の収入金額が退職所得控除額を下回る場合、課税所得はゼロ円となり非課税です。
なお、源泉徴収されているため、原則として確定申告は不要ですが、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、確定申告で税金の還付を受ける必要があります。
STEP3. シミュレーション(勤続年数・金額別)
具体的な例で計算された退職所得(課税対象額)を見てみましょう。
勤続年数が長ければ長いほど、控除額が大きくなり退職者にとって有利になります。
退職一時金を受け取る手続きと注意点
次に退職一時金を受け取る際の手続きと注意点について詳しく解説してます。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出する
退職一時金の支給時に適切な退職所得控除を適用してもらうために、退職金を受け取るまでに「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出しなければなりません。この申告書を提出しないと、退職金から一律で20.42%の税金が源泉徴収されてしまい、後で確定申告が必要となります。
先にiDeCoなどDC一時金を受け取る場合
退職所得控除の適用に関して、iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型DC(確定拠出年金)の一時金など、複数の退職所得を一時金として受け取る場合のルールが、2026年1月1日から変更されます。
2026年1月1日施行:退職所得控除の「5年ルール」が「10年ルール」へ
従来は、DC一時金と企業の退職一時金を別々に満額の退職所得控除の対象とするためには、DC一時金を受け取った後、5年以上(前年以前4年以内ではない期間)空けて企業の退職一時金を受け取る必要がありました。これにより、税制優遇の「二重取り」が可能でした。
しかし、2026年1月1日以後にDC一時金を受け取る場合、この期間が10年(前年以前9年以内ではない期間)に延長されます。
しかし、2026年1月1日以後にDC一時金を受け取る場合、この期間が10年(前年以前9年以内ではない期間)に延長されます。
この改正は、退職所得控除を十分に活用できる期間を実質的に長く空ける必要が生じるため、退職金とDC一時金を近接して受け取ると、控除額が調整され、結果的に増税になる可能性が高まります。
退職一時金に関するQ&A
退職一時金に関するよくある質問にQ&A形式で回答します。
HQ. 退職一時金をもらうと、社会保険料は上がる?
退職一時金は原則として、退職後の国民健康保険や介護保険の算定対象となる所得には含まれないため、一時金の受取によって社会保険料が上がることはありません。
社会保険料が上がるのは、退職年金として分割で受け取る場合であり、これは雑所得として算定対象になるためです。
Q. パートやアルバイトでも退職一時金はもらえる?
会社の就業規則や退職金規程に支給の定めがあり、かつ支給要件(勤続年数など)を満たしている場合、パートやアルバイトの方も退職一時金を受け取ることができます。
社内準備型であれば、会社が支給事由を自由に決定できるため、勤続1年未満の退職でも支給される場合があります。
Q. 退職一時金と失業保険(基本手当)は同時に受け取れる?
はい、可能です。退職一時金の受け取り自体は、失業保険(雇用保険の基本手当)の受給資格に直接影響しません。
失業保険は、「働く意思と能力があるにもかかわらず、職に就けない状態」にある場合に支給されます。退職一時金を受け取った後でも、ハローワークで求職の申し込みを行い、受給資格が認定されれば基本手当を受け取ることが可能です。
ただし、退職理由によって給付制限期間(待機期間)が異なります。自己都合退職の場合は待機期間が長くなる一方、会社都合退職の場合は短縮されます。この点に注意が必要です。
Q. 死亡した場合、退職一時金はどうなる?
従業員が在職中または退職後に死亡し、未支給の退職一時金がある場合、通常は「死亡退職金」として遺族(原則として法定相続人)に支払われます。
この場合、故人の所得税(退職所得)ではなく、相続税の課税対象となります。ただし、相続税法上、死亡退職金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が設けられており、税制上非常に優遇されています。
まとめ
退職一時金は、退職後の生活設計において極めて重要な役割を果たすものであり、その最大の特長は、退職所得控除という大きな税制優遇を受けられる点です。一時金として受け取れば、社会保険料の算定対象外となり、手取りを最大化しやすいというメリットもあります。
しかし、2026年1月1日以降、iDeCoなどの一時金受取と企業の退職一時金の税制優遇の適用期間が「5年ルール」から「10年ルール」に延長されます。これにより、退職一時金の受け取り時期を把握することはこれまで以上に重要になります。時期を事前に確認した上、自分の場合はどの税制が適用されるのか、しっかり理解しておくようにしましょう。
まずは勤務先の退職金制度の内容(支給要件や選択肢)を就業規則等で確認するとともに、特にiDeCoなどの私的年金を利用されている方は、この税制改正を踏まえて、退職後の税負担が少なくなるよう、賢く受け取り戦略を立てましょう。
退職金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事

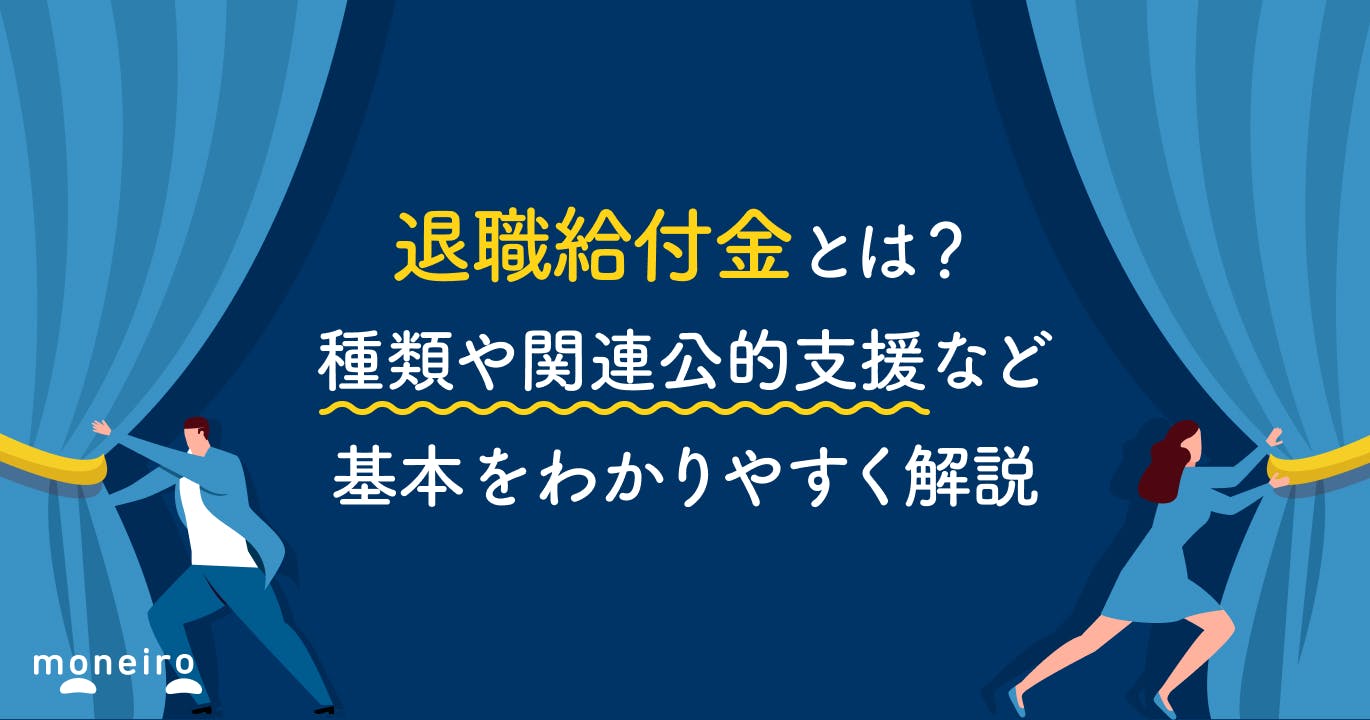
【社労士監修】退職給付金とは?種類や関連の公的支援など基本をわかりやすく解説
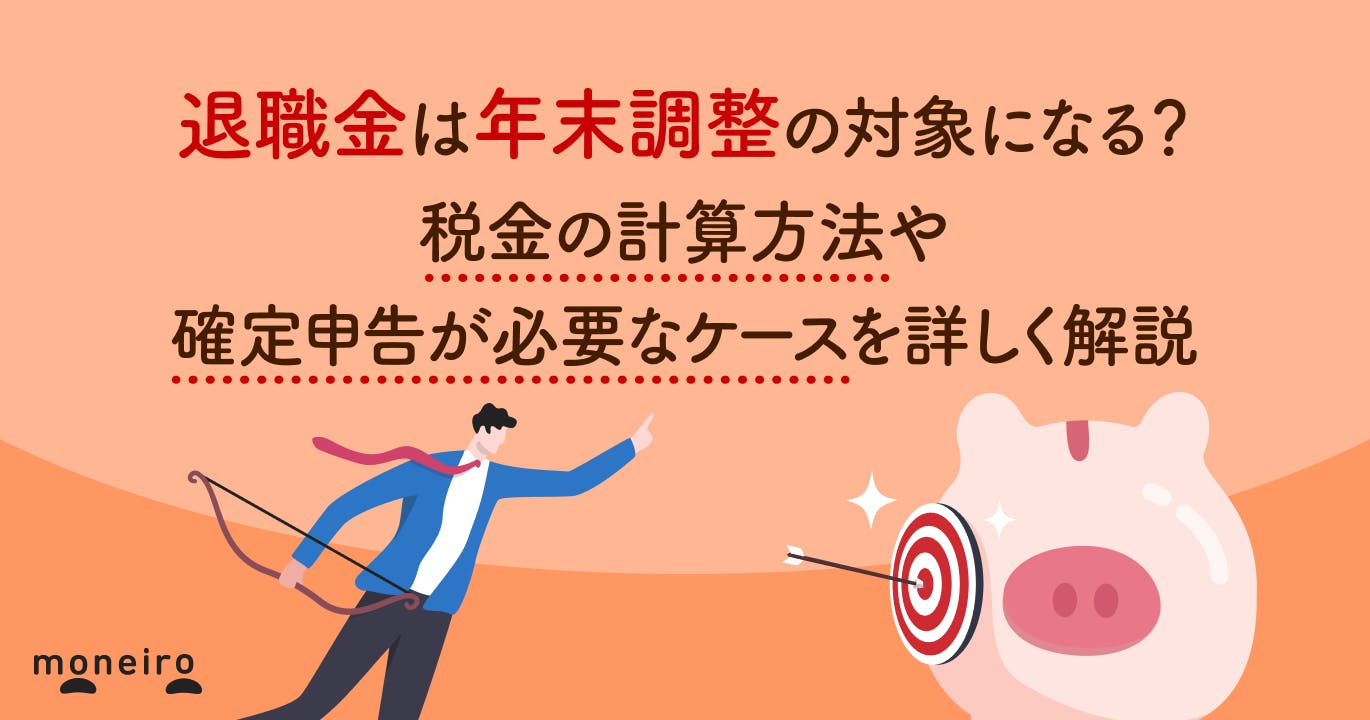
退職金は年末調整の対象になる?税金の計算方法や確定申告が必要なケースを詳しく解説
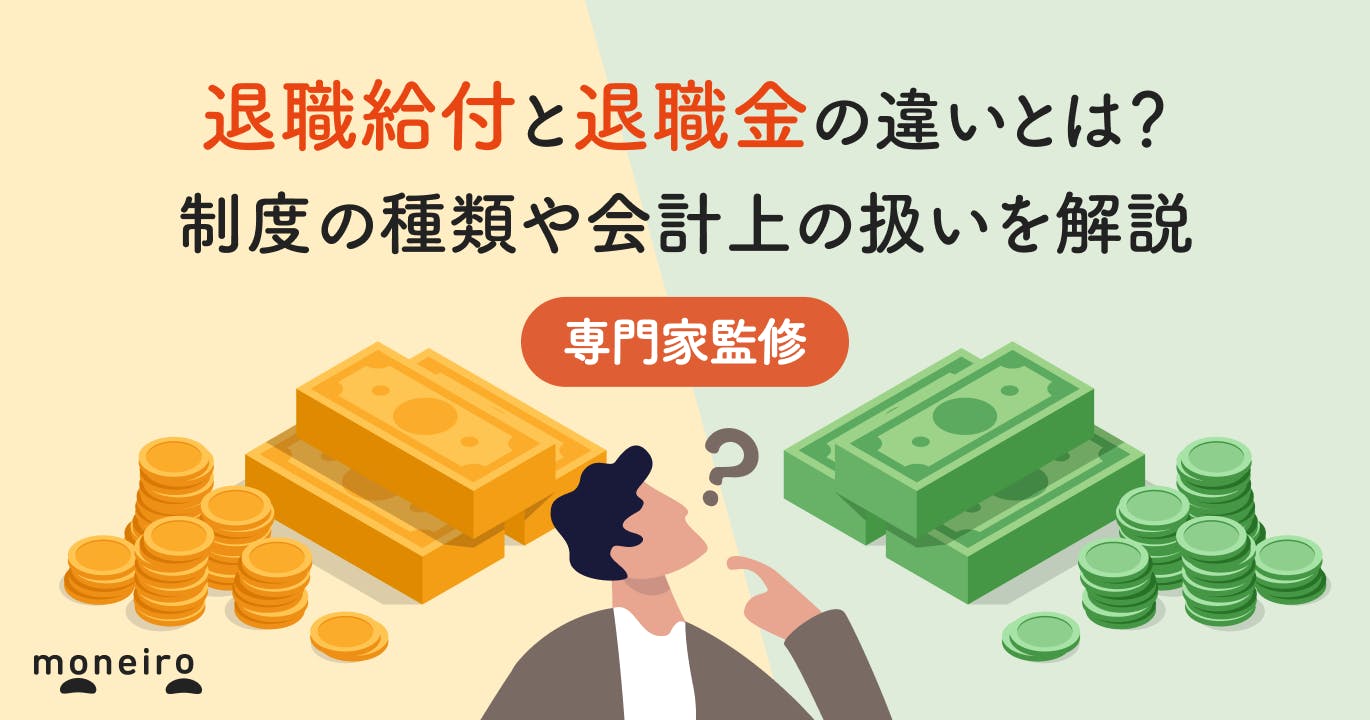
退職給付と退職金の違いとは?制度の種類や会計上の扱いを専門家が解説
監修
高橋 明香
- ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者
みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。