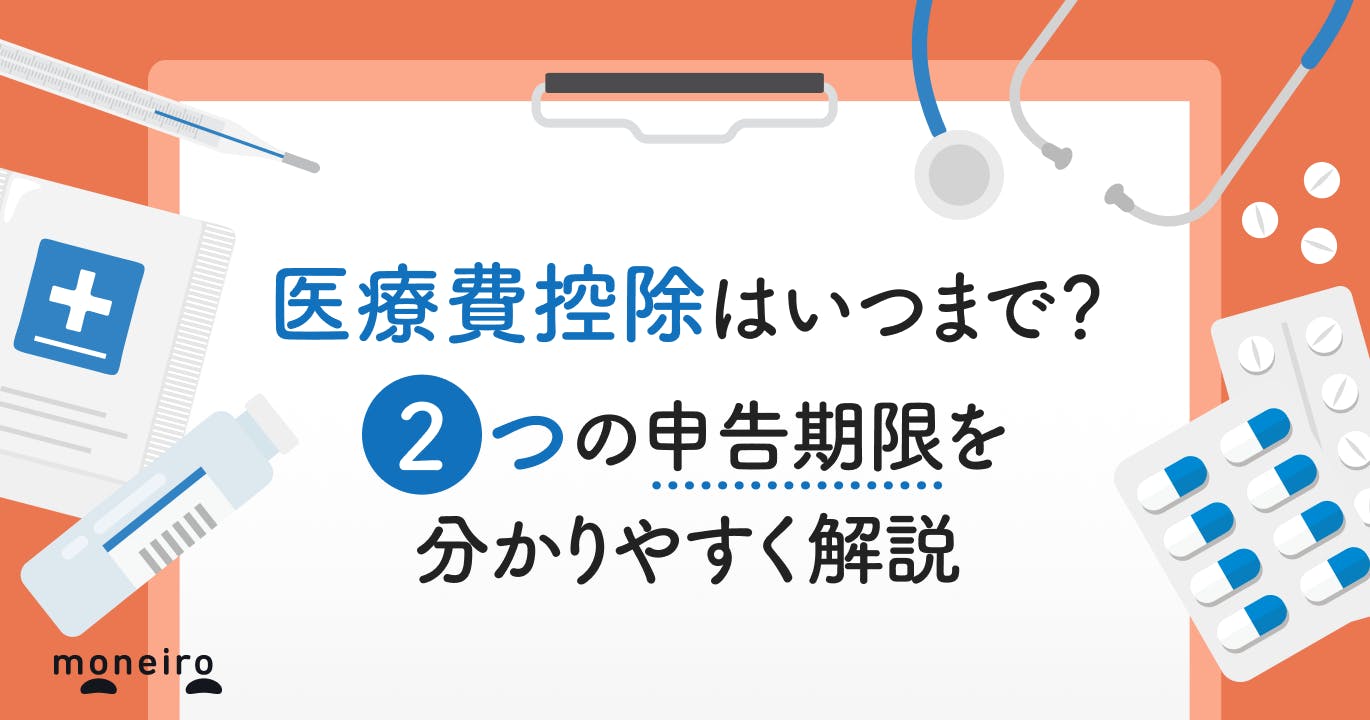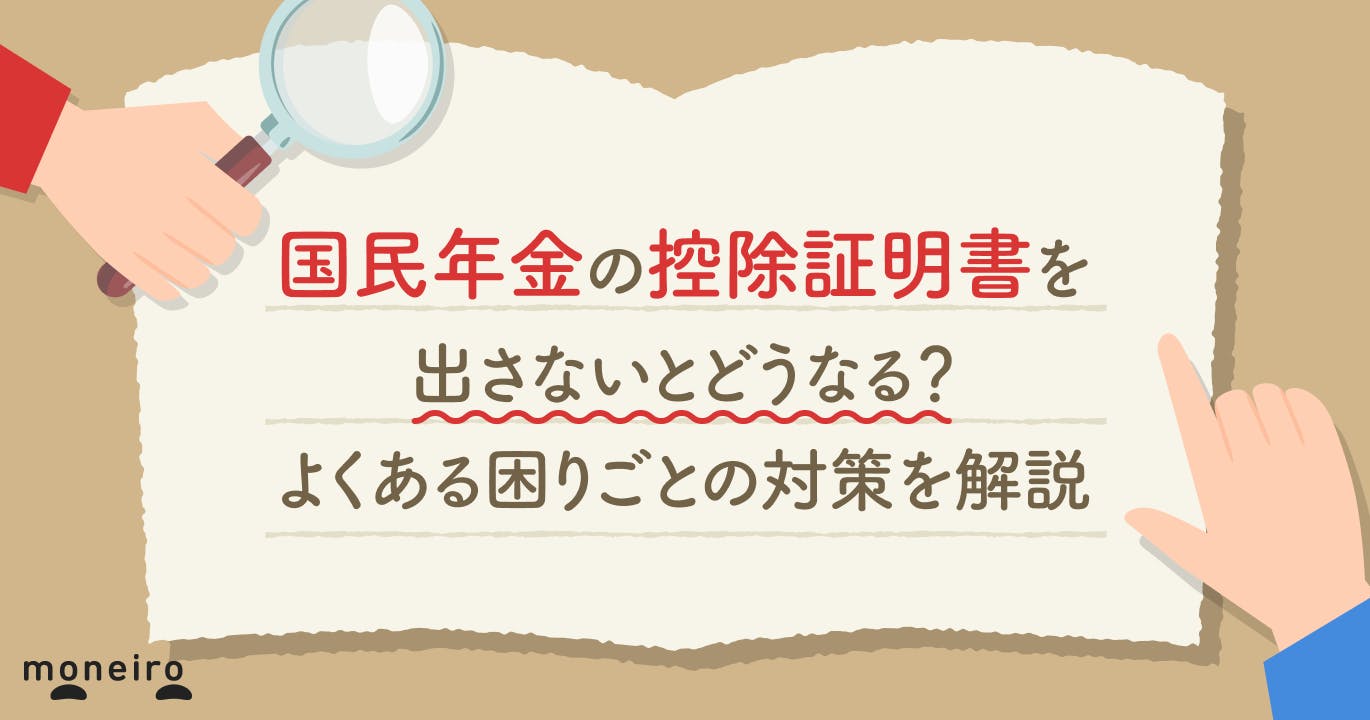
医療費控除はいつまで?2つの申告期限を分かりやすく解説
≫もしもの備えは大丈夫?将来の不足額を3分で診断
医療費控除は、自分自身または生計を一にする親族のために1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得控除を受けられる制度です。しかし、「いつまでに申請すればいいのか」「何年分までさかのぼれるのか」といった申請期限について疑問を持つ方も多いでしょう。
本記事では、会社員や自営業の方など、立場に応じて異なる医療費控除の2つの申告期限(確定申告と還付申告)を徹底解説します。また、申告に必要な要点と注意点についても紹介しますので、ぜひ制度利用の参考にしてみてください。
- 医療費控除を申請できる「確定申告」と「還付申告」の2つの期限と期間
- 医療費控除の対象となる費用や控除額の計算方法
- 通常の医療費控除と、特例であるセルフメディケーション税制の違い
医療費控除が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額を3分で診断
▶夫婦で考えるお金の基本セミナー:ライフステージごとのお金の管理がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
医療費控除とは?
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、納税者自身、または納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときに、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができる制度です。対象税目は「所得税」です。
この控除を受けることで、課税対象となる所得金額が減少し、結果としてその年の所得税が軽減(還付)されるだけでなく、翌年度の住民税も軽減されます。医療費控除の対象となる金額(最高で200万円)は、次の計算式で求められます。
(実際に支払った医療費の合計額 - (1)の金額) - (2)の金額
- (1)保険金などで補てんされる金額:生命保険契約などで支給される入院費給付金や、健康保険などで支給される高額療養費、出産育児一時金などが該当します。なお、補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引かれ、引ききれない金額が生じた場合でも他の医療費からは差し引きません。
- (2)10万円:ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額が基準となります。
医療費控除は、未払いの医療費については、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。
セルフメディケーション税制との違い
医療費控除には、通常の控除制度とは別に「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が存在します。
これは、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から施行された制度です。この特例は、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に適用が可能です。令和4年1月以降、制度が5年延長され、税制対象医薬品の範囲が拡充されました。
セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 納税者自身または生計を一にする親族のために特定一般用医薬品等購入費(OTC医薬品など)を支払っていること。
- 納税者自身がその年中に、健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っていること。
控除額は、特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等で補填される部分を除く)のうち、1万2000円を超える部分の金額であり、8万8000円を限度とします。
セルフメディケーション税制による所得控除と、通常の医療費控除を同時に利用することはできません。どちらの制度を適用するかは、納税者自身が選択することになります。また、原則として一度確定申告で選択した控除を、後からもう一方の控除に変更することはできません。 申告前にどちらが有利になるか十分に計算・検討することが重要です。
「医療費控除はいつまで?」の回答は2つ
医療費控除の申告期限には、主に納税者の状況によって2つの異なる期限が存在します。これらの期限を混同しないように注意が必要です。
- 還付申告の期限:主に会社員(給与所得者)など、通常は確定申告の義務がない方が、払いすぎた税金の還付を受けるための申告期限です。これは通常の確定申告期間とは関係なく、医療費を支払った年の翌年1月1日から5年間遡って可能です。
- 確定申告の期限:主に自営業者やフリーランスなど、元々確定申告が必要な方が、事業所得などと合わせて医療費控除を申告する場合の期限です。これは翌年2月16日から3月15日まで(3月15日が 土日祝日に当たる場合は、翌平日が期限日)と定められています。
医療費控除の還付申告はいつまでできる?
医療費控除は、給与所得者など、すでに源泉徴収によって税金を納めている方が、払いすぎた税金を取り戻すことができる「還付申告」として行うことができます。
還付申告とは?
還付申告とは、主に会社員など、給与から源泉徴収によって税金が納められている方が、医療費控除などを適用することで、払いすぎた税金を国から還付してもらう手続きです。
還付申告は、通常の確定申告期間(2月16日~3月15日)にとらわれず、税務署が開いている時期であればいつでも申告が可能です。e-Taxを利用すれば、24時間いつでも申告・提出を行うことができます。
申告できる期間は?
還付申告は、医療費を支払った年の翌年1月1日から5年間(当該年の翌年1月1日〜5年後の12月31日)の間に行うことができます。
例えば2025年分の還付申告は、2026年1月1日〜2030年12月31日の間に可能です。ただし、青色申告特別控除など特例を受けるために法定申告期限内の提出が要件となる場合は例外があります。
また、過去5年間に支払った医療費であれば、さかのぼって還付申告が可能です。もし申告期限である3月15日を過ぎてしまっても、還付申告であれば5年間の猶予がありますが、気付いたタイミングでできるだけ早く、手続きをしましょう。
医療費控除の確定申告の期限はいつまで?
医療費控除を「確定申告」として行う場合、これは主に自営業者、フリーランスなど、元々確定申告が義務付けられている方を対象とします。
確定申告が必要な方が、事業所得などと合わせて医療費控除も申告する場合、その申告期間は、対象期間(前年1月1日~12月31日)に支払った医療費について、翌年2月16日から3月15日までとなります。
例えば、2025年分(令和7年分)の医療費を申告する場合、2026年2月16日から2026年3月16日まで(3月15日が日曜日のため16日が期限日となる)に申告手続きを行う必要があります。
この確定申告の期限(原則3月15日)を過ぎて申告する場合、それは「期限後申告」として扱われます。ただし、確定申告義務のない給与所得者などが医療費控除のためだけに申告する場合は、3月15日を過ぎても「還付申告」として扱われ、ペナルティはありません。その場合、申告できる期間は翌年1月1日から5年間です。
医療費控除が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額を3分で診断
▶夫婦で考えるお金の基本セミナー:ライフステージごとのお金の管理がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
【要注意】「医療費控除の申告期限」と「医療費の対象期間」は別
医療費控除を検討する際に、多くの人が混同しやすい重要なポイントが、「申告の期限」と「医療費の対象期間」が異なる点です。
医療費控除の対象となる医療費は、「その年の1月1日から12月31日までの間に実際に支払った医療費」であることが要件です。未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。
この「支払った年」の基準が重要です。
例えば、2025年12月30日に治療を受けたものの、支払いが年をまたいで2026年1月4日になった場合、この医療費は、2025年分の医療費控除の対象とはならず、2026年分の医療費として扱われます。したがって、申告は2027年に行うことになります。
なお、クレジットカードで医療費を支払った場合、カード利用日(診療を受けた日)が医療費を支払った日として基準になります。口座からの引落日ではない点に注意が必要です。
医療費控除は「いくらから」申告すべき?
医療費控除は、実際に支払った医療費の合計額から、保険金などで補填される金額と、原則として10万円を差し引いた金額(最高200万円)が控除の対象となります。
そのため、医療費の総額が10万円(または総所得金額等の5%)を超えていなければ、控除額は発生しないのが原則です。
医療費の合計額が10万円をわずかに超える程度であっても、申告をすることで税金が還付され、手間をかけた以上のメリットがある場合も多いため、10万円の基準を超えたら積極的に申告を検討すべきでしょう。
なお、医療費が10万円を超えていなくても、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費が1万2000円超の場合)を利用できる可能性があります。この場合は、通常の医療費控除との選択適用となります。
医療費控除でいくら戻る?還付金シミュレーション
医療費控除による還付金は、控除額に、申告する人の所得税率を乗じて計算されます。還付金の計算式は以下です。
((実際に支払った医療費の合計額)-(保険金などで補てんされる金額)-(10万円または総所得金額等の5%))× 所得税率
還付金の計算例
総所得金額が400万円の給与所得者(10万円基準適用)、保険金0円、医療費総額が15万円の場合を想定します。
- 控除対象額の計算: 15万円 - 0円 - 10万円 = 5万円
- 還付金の計算: この控除対象額5万円に所得税率を乗じます。例えば、適用される所得税率が10%であった場合、還付される金額は以下となります。 5万円 × 10% = 5000円
控除額が大きくなるほど、また申告する方の所得が高く(適用される所得税率が高く)なるほど、還付される税金も増えることになります。
翌年度の住民税の軽減メリットも
さらに、所得税の還付だけでなく、翌年度の住民税も軽減されるというメリットがあります。住民税の所得割額は、所得控除後の課税所得金額をもとに計算され、税率は原則として一律10%です。
上記の例(控除対象額5万円)では、所得税の還付(5000円)に加えて、翌年度の住民税が 5万円 × 10% = 5000円 軽減されることになります。つまり、所得税と住民税を合わせて約1万円の減税効果が期待できます。
≫もしもの備えは大丈夫?将来の不足額を3分で診断
申請前に確認!医療費控除の要点と注意点
医療費控除を最大限活用し、スムーズに申告を行うために、見落としがちな要点と注意点を確認しましょう。
1.共働き夫婦は所得が高い方で申告するとお得
夫婦共働きの場合、夫婦のどちらか一方の医療費控除として、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費を合算して申告することができます。
この際、所得が高い方(すなわち適用される所得税率が高い方)で申告するほうが、結果的により多くの税金が還付(軽減)されるためお得です。
「生計を一に」していれば、例えば妻が自分のカードや現金で支払った医療費であっても、夫が家族全員分を合算して申告することが認められています。
2.医療費の領収書は提出不要でも5年間の保管義務がある
平成29年分以降の確定申告から、医療費控除の申告手続きが簡略化され、医療費の領収書を確定申告書に添付または提示する必要がなくなりました。その代わりに、「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付する必要があります。
ただし、領収書が不要になったわけではありません。税務署は、明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除く)の提示または提出を求める場合があります。したがって、申告後も5年間は領収書を自宅で大切に保管する義務があります。
なお、健康保険組合等が交付する医療費通知を添付した場合は、その通知に記載された医療費に関する領収書は保存が不要となります。また、マイナポータル連携を利用してe-Taxで申告し、医療費通知情報を取得・送信した場合も、当該医療費通知情報に含まれる医療費については領収書の保存は不要です。
3.出産育児一時金や高額療養費は支払った医療費から差し引く
医療費控除の計算を行う際、実際に支払った医療費の合計額から、「保険金などで補てんされる金額」を差し引く必要があります。
この「保険金などで補てんされる金額」には、生命保険契約などで支給される入院費給付金だけでなく、健康保険などで支給される高額療養費や出産育児一時金、家族療養費などが含まれます。
これらの給付金は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引かれます。
出産費用を医療費控除の対象とする場合、受け取った出産育児一時金は、出産にかかった医療費から必ず差し引かなければなりません。
4.遠方の実家の親の医療費も対象になるケースがある
医療費控除の対象となる医療費の要件の一つに、「納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること」があります。
この「生計を一にする」とは、必ずしも同居していることを意味しません。例えば、勤務や修学などの都合で別居している場合でも、生活費や学費、療養費などを常に送金しているなど、一体の生活単位にあると認められれば、「生計を一にする」と判断されます。
したがって、遠方の実家で暮らしているご自身の親族(親や兄弟姉妹など)の医療費をあなたが負担し、生計を一にしていると認められる場合、その親族のために支払った医療費はあなたの医療費控除の対象に含めることができます。
5.年末にまとめ買いした市販薬も対象にできる
通常の医療費控除は、治療のための医薬品の購入費が対象ですが、特例であるセルフメディケーション税制を利用すれば、特定一般用医薬品等購入費(OTC医薬品)の購入費用も控除対象にできます。
この特定一般用医薬品等購入費は、1年間(1月1日~12月31日)に実際に支払った金額が対象となります。
したがって、年間の購入額が1万2000円を超える見込みがある場合、年の瀬に翌年使う分も含めて対象となるOTC医薬品をまとめ買いし、その年の購入費に算入することで、控除を適用できる可能性があります。
ただし、この制度を利用するには、納税者がその年中に一定の健康の保持増進及び疾病の予防への取組(健診や予防接種など)を行っていることが必要です。また、通常の医療費控除とは選択適用となるため、どちらの制度が有利かを判断して申告する必要があります。
「医療費控除 いつまで」に関するQ&A
医療費控除の期限や適用に関するよくある疑問について解説します。
Q1. 医療費控除の申請を5年以内にやらないとどうなる?
医療費控除の還付申告は、医療費を支払った年の翌年1月1日から5年間が期限です。
この5年間の期限を過ぎてしまうと、その年分の医療費控除を受ける権利が時効により失われてしまい、税金の還付を受けることはできなくなります。還付申告は通常の確定申告期間(2/16~3/15)を待つ必要はないため、過去の医療費がある場合は早めに申告手続きを行うことをお勧めします。
Q2. 医療費が10万円以下でも控除を受けられる場合はある?
医療費の合計が10万円以下でも控除を受けられるケースは主に2つあります。
- 総所得金額等が200万円未満の場合:通常の医療費控除の計算において、控除額の基準が10万円ではなく、総所得金額等の5パーセントの金額となります。例えば、総所得金額等が180万円の場合、基準額は9万円(180万円 × 5%)となり、医療費が10万円未満でも控除が発生する可能性があります。
- セルフメディケーション税制を利用する場合:特定のOTC医薬品等の購入額が1万2000円を超えていれば、その超える部分について控除を受けられます。
Q3. 妻の医療費を夫の私(会社員)がまとめて申請できる?
はい、可能です。医療費控除は、納税者自身または納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が対象となります。
妻(配偶者)は通常「生計を一にする親族」に含まれるため、夫が妻の医療費をまとめて負担し、夫名義で申告することが可能です。
この場合、共働きで夫婦の所得があるなら、所得が高い方の夫が申告するほうが、一般的には適用税率が高いため、より大きな還付効果を得やすくなります。
Q. 医療費控除の申告期限(3月15日)を過ぎたらどうなる?
医療費控除は税金が還付される手続きであるため、通常の確定申告期間(2月16日~3月15日)を過ぎたとしても、「還付申告」として申請を行うことができます。
還付申告の期限は、医療費を支払った年の翌年1月1日から5年間です。例えば、2024年分の医療費について、2025年3月15日の期限に間に合わなかったとしても、2029年12月31日までは還付申告が可能です。
ただし、事業所得などがあり、医療費控除とは関係なく確定申告が義務付けられている方が申告を忘れた場合は、期限後の申告として無申告加算税などの対象になる可能性があるため、注意が必要です(医療費控除による還付のみが目的であれば、還付申告として扱われます)。
まとめ
医療費控除の申請期限は、納税者の状況によって「確定申告の期限(翌年2月16日~3月15日)」と「還付申告の期限(翌年1月1日から5年間)」の2つがあります。特に会社員(給与所得者)の方は、過去5年分さかのぼって還付申告が可能です。
申告の際は、医療費の対象期間が「実際に支払った年」(1月1日~12月31日)であること、そして、受け取った保険金や高額療養費などは差し引く必要があることに注意しましょう。
また、医療費総額が10万円に満たない場合でも、総所得金額が200万円未満であれば控除を受けられる可能性があるほか、特定のOTC医薬品購入費(1万2000円超)がある場合はセルフメディケーション税制を選択できます。ただし、両制度の同時利用はできません。
申告手続きについては、現在、医療費の領収書に代えて「医療費控除の明細書」の添付が必須となっており、領収書自体は5年間保管する義務があります。マイナポータル連携を利用することで、医療費通知情報を自動入力し、さらに領収書の保存が不要となるため、e-Taxを活用した申告が推奨されます。
≫もしもの備えは大丈夫?将来の不足額を3分で診断
医療費控除が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額を3分で診断
▶夫婦で考えるお金の基本セミナー:ライフステージごとのお金の管理がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
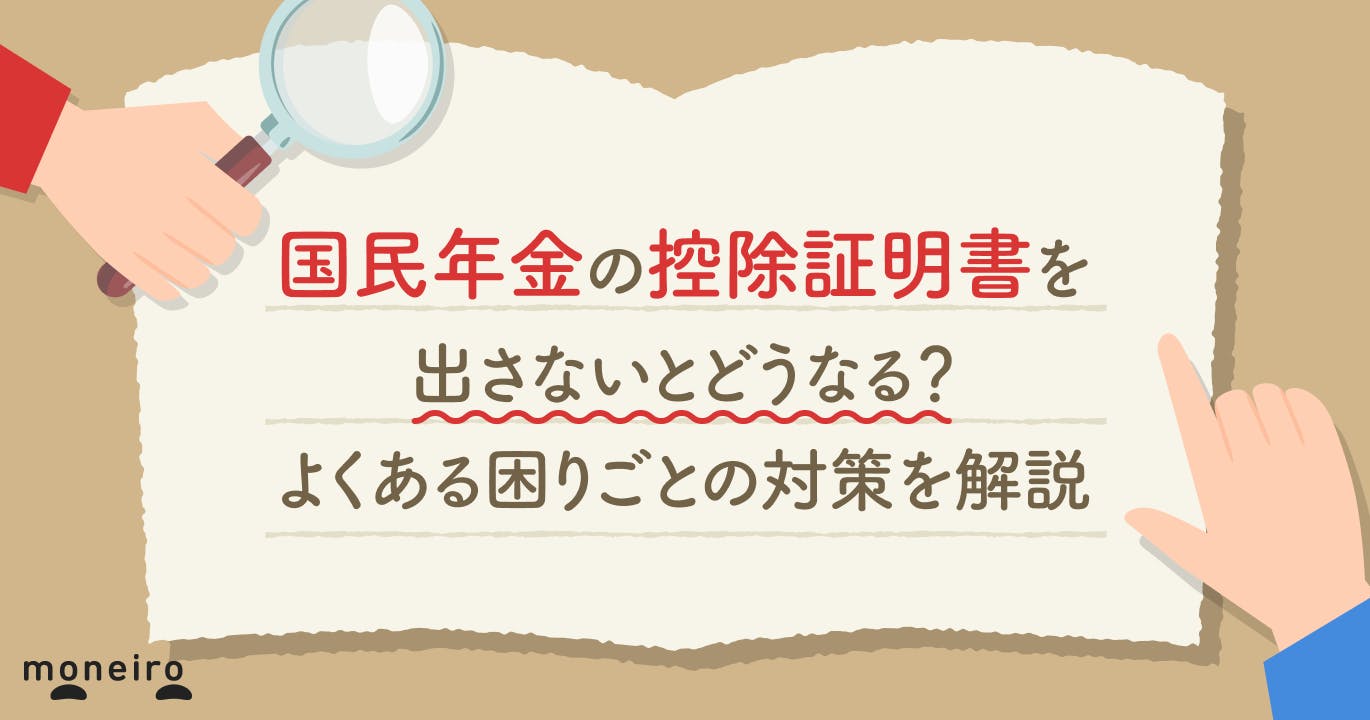
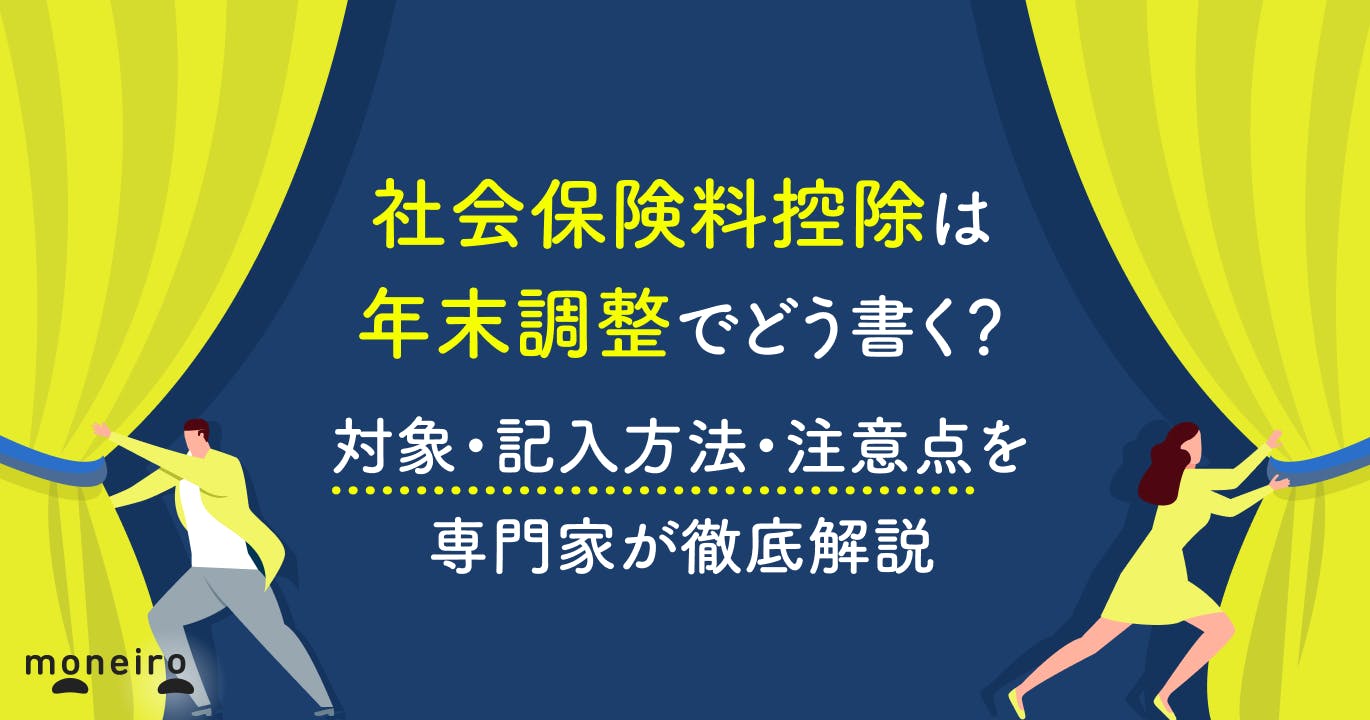
社会保険料控除は年末調整でどう書く?対象・記入方法・注意点を専門家が徹底解説
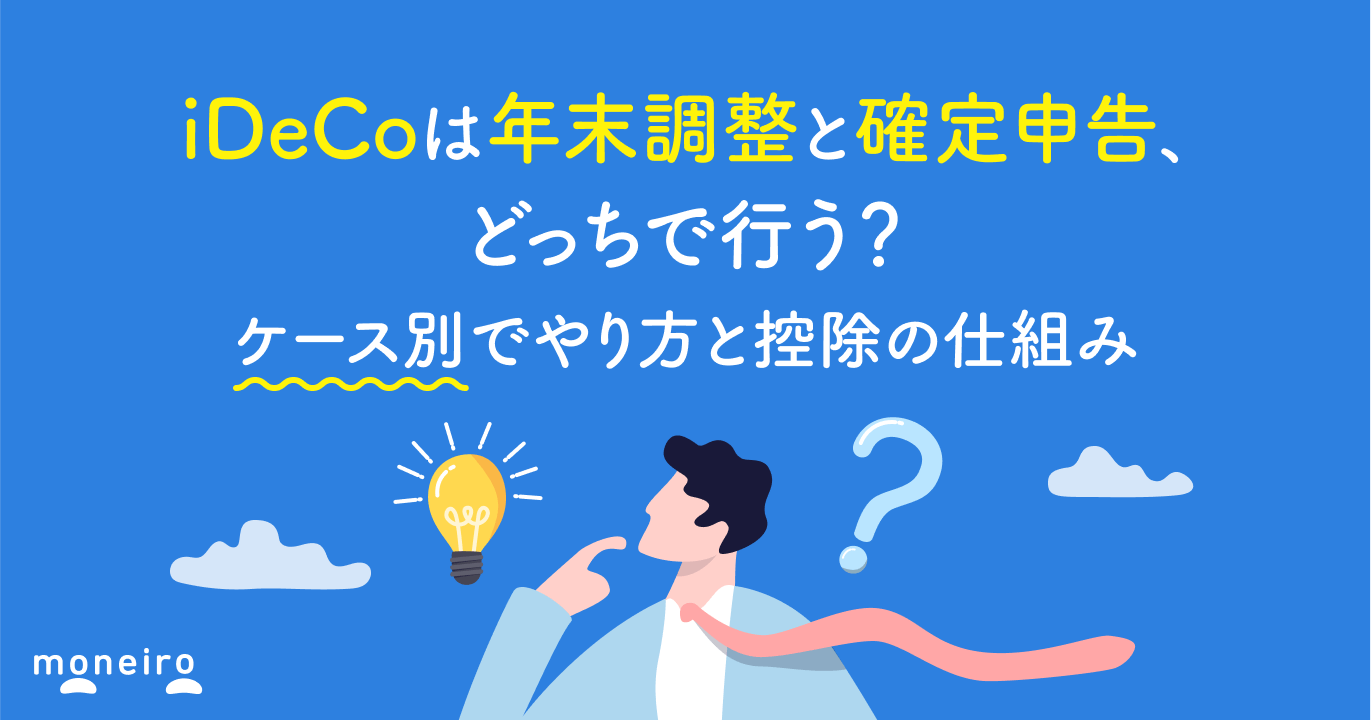
iDeCoは年末調整と確定申告、どっちで行う?ケース別にやり方と控除の仕組みを解説
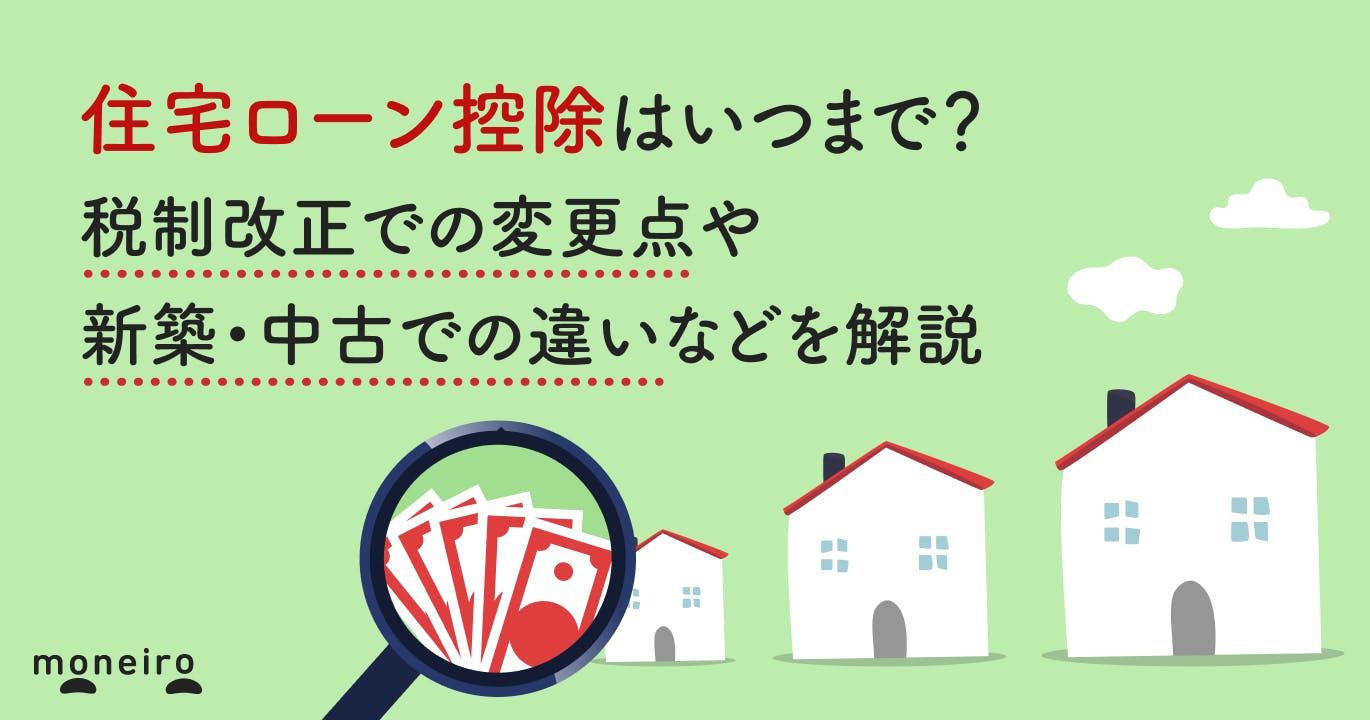
住宅ローン控除はいつまで?税制改正での変更点や新築・中古での違いなどを解説
監修
内山 智絵
- 公認会計士/税理士/AFP
大学在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人の地方事務所にて約10年間勤務し、上場企業を中心とした法定監査などの業務に携わる。出産・育児を機に監査法人を退職した後、2021年春に個人会計事務所を開業。地域の中小企業や個人事業主の身近な相談役として、法人・個人問わず税務・会計サポートを提供している。2025年夏に株式会社SheBlissを設立。自身の経験や女性起業特有の課題を踏まえ、女性が「やりたい」を形にして続けていけるように、専門性の高いサポートとコミュニティを提供している。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。