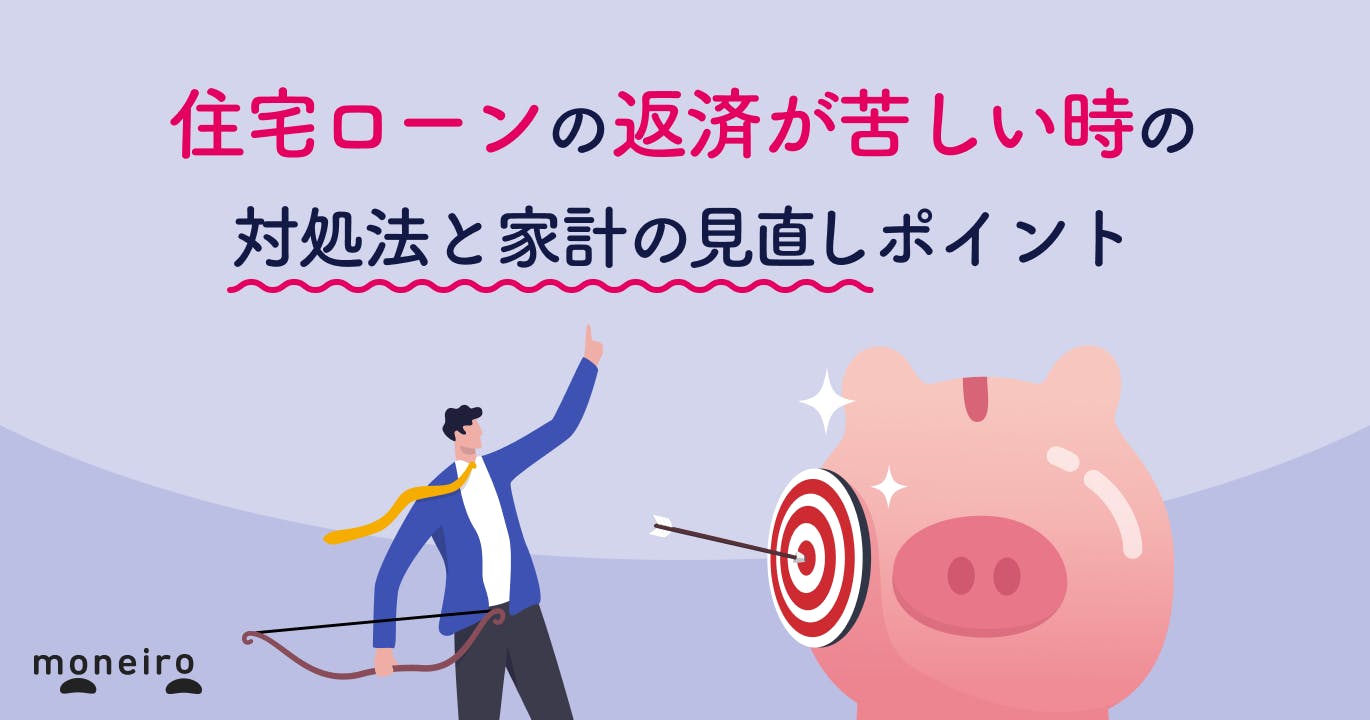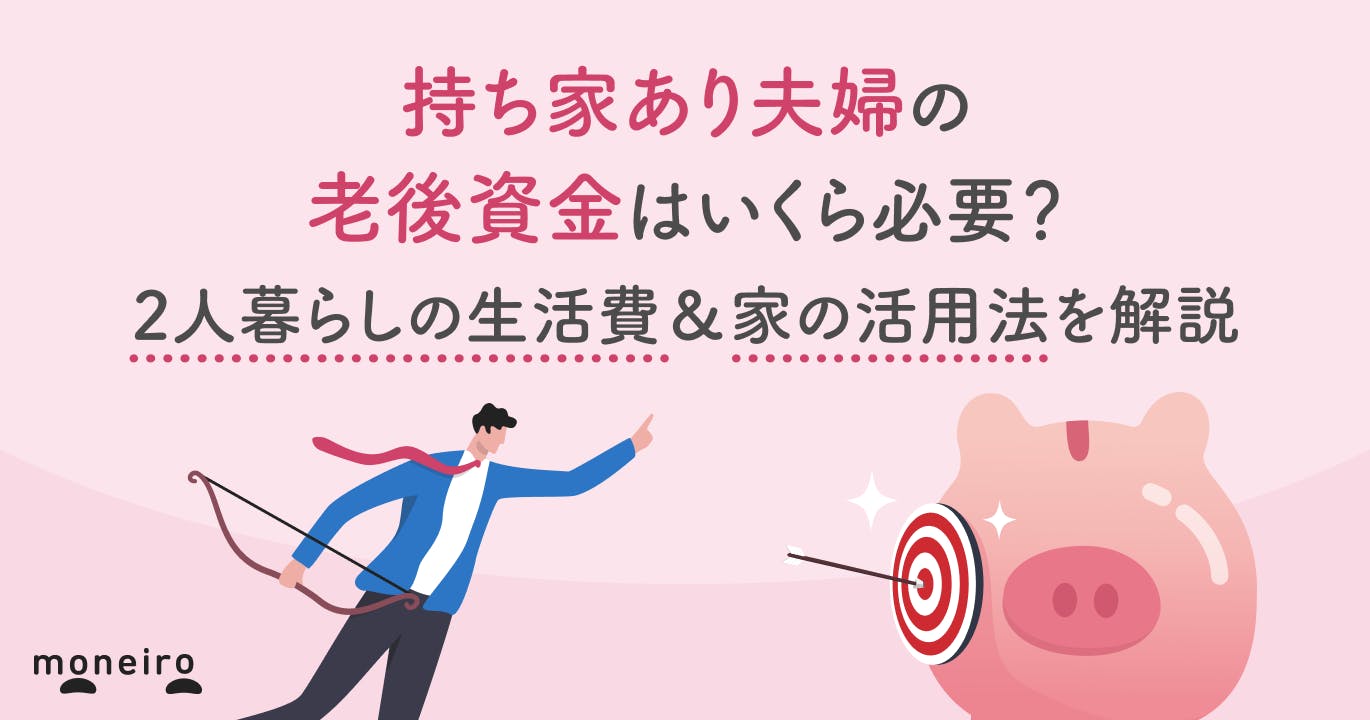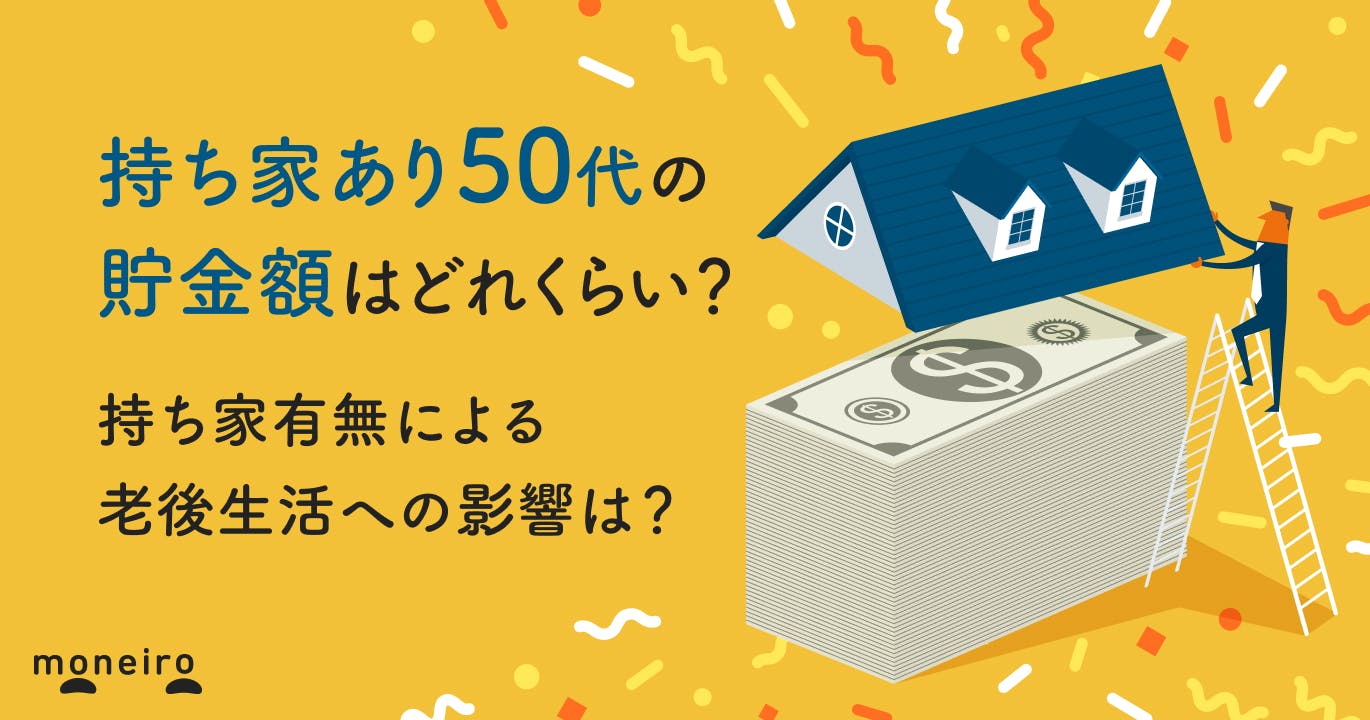住宅ローン控除はいつまで?税制改正での変更点や新築・中古での違いなどを解説
>>あなたの将来資金は足りる?不足額を3分で診断
住宅購入は人生における大きなイベントの1つですが、高額な買い物だからこそ、利用できる税制優遇制度をしっかり理解しておくことが重要です。中でも「住宅ローン控除(住宅借入金特別控除/住宅ローン減税)」は、要件を満たせば数十万円もの税金が軽減される税額控除なので、家計に大きな影響を与えます。
本記事では、この住宅ローン控除の制度概要や「制度はいつまで?」という疑問、新築・中古・リフォームといった住宅の種類ごとの違い、さらに2025年入居から適用される税制改正による変更点までを分かりやすく解説します。
- 住宅ローン控除の基本的な制度内容と適用条件
- 新築、中古、リフォームなど住宅の種類ごとの控除期間と借入限度額の違い
- 2025年入居から適用される税制改正による変更点、特に子育て世帯等への影響
住宅ローン控除が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶夫婦で考えるお金の基本セミナー:ライフステージごとのお金の管理がわかる
住宅ローン控除(住宅ローン減税)とは?いつまで?
「住宅ローン控除(住宅借入金特別控除/住宅ローン減税)」は、住宅ローンを利用して住宅の新築・取得または増改築等をした場合に、居住者の金利負担を軽減し、住宅取得を促進することを目的とした制度です。当初は2021年末で終了予定でしたが、税制改正により2025年まで延長されています。
最大13年間(既存住宅は10年間)、各年末時点の住宅ローン残高の0.7%を所得税額等から控除することができます。
所得税から控除しきれない場合は、上限9万7500円まで、翌年の住民税からも控除されます。
新築住宅・買取再販住宅の場合
新築住宅や買取再販住宅(中古住宅)の場合、住宅の環境性能によって借入限度額(減税の対象となる住宅ローンの年末残高の上限額)と控除期間が定められています。
2024年・2025年入居の場合の主な内容は以下の通りです。
参照:国土交通省「住宅ローン減税の概要について」
既存住宅の場合
既存住宅の場合も、住宅ローン控除が適用されます。2024年・2025年入居の場合の借入限度額と控除期間は以下の通りです。
参照:国土交通省「住宅ローン減税の概要について」
環境性能によって控除額に大きな差
住宅ローン控除の借入限度額は、住宅の環境性能によって大きく異なります。
例えば、新築住宅に2024年・2025年に入居する場合、「長期優良住宅・低炭素住宅」の借入限度額が子育て世帯等で5000万円であるのに対し、「その他の住宅」は原則として0円(控除対象外)となります。
ただし、2023年末までに建築確認を受けた「その他の住宅」、または2024年6月末までに建築された「その他の住宅」に2024年または2025年に入居する場合は、控除期間10年間で借入限度額2000万円が適用されます。
「ZEH(ゼッチ)水準省エネ住宅」とは、日本住宅性能表示基準における断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上の性能を持つ住宅を指します。また、省エネ基準適合住宅は、断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上の性能を有する住宅です。
これらの環境性能の高い住宅を選ぶことで、より大きな控除額が期待できるため、住宅選びの重要なポイントとなります。
適用条件
住宅ローン控除を受けるためには、以下の主な要件をすべて満たす必要があります。
- 居住用であること:その者が主として居住の用に供する家屋であること。
- 床面積要件: 床面積要件: 床面積が50平方メートル以上であること 。ただし、新築住宅の場合、2024年末までに建築確認を受けたもので、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、合計所得金額1000万円以下である場合に限り対象となります 。
- 合計所得金額要件:合計所得金額が2000万円以下であること。ただし、上記の床面積要件の特例が適用される場合は、合計所得金額1000万円以下であること。
- 居住開始時期: 住宅の引渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること。
- 店舗等併用住宅の場合:床面積の2分の1以上が居住用であること。
- 借入期間:借入金の償還期間が10年以上であること。
- 既存住宅の場合の要件:1982年1月1日以後に建築されたもの。または、建築後使用されたことのあるもので、地震に対する安全性に係る基準に適合すること(耐震基準適合証明書等で証明が必要)。
- 買取再販住宅や増改築等工事の場合:一定の工事に該当することにつき「増改築等工事証明書」等で証明されていること。増改築等の工事に要した費用の額が100万円超であること。
2025年からの住宅ローン控除の変更点は?
2025年以降の住宅ローン控除については、子育て世帯等の住宅取得環境の厳しさを踏まえ、いくつかの措置が継続・延長されることになりました。
特に注目されるのは、子育て世帯等に対する借入限度額の上乗せと床面積要件の緩和措置の継続、そして既存住宅の子育て対応リフォームに係る特例措置の延長です。
床面積要件
2025年からの住宅ローン控除において、子育て世帯等の住宅取得環境の厳しさを考慮し、子育て世帯等に対する借入限度額の上乗せに加え、床面積要件の緩和措置が令和7年(2025年)も引き続き実施されます。
具体的には、新築住宅の場合、2024年(令和6年)までに建築確認を受けた住宅であれば、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となっていますが、合計所得金額の要件は1000万円以下となります。
この措置は、子育て世帯等がより多様な選択肢の中から住宅を選べるようにするための支援策です。
既存住宅の子育て対応リフォームに係る特例措置の延長
子育て世帯・若者夫婦世帯が子育てに対応した既存住宅へのリフォームを行う場合の所得税の特例措置が、令和7年(2025年)も引き続き実施されることになっています。これは、子育て世帯等の居住環境の改善を目指すもので、子育て支援の現場からも強い要望があった施策です。
特例措置の内容としては、対象となる子育て対応リフォーム工事を行った場合、標準的な工事費用相当額の10%が所得税から控除されます。
対象工事の限度額は250万円であり、最大控除額は25万円です。
主な対象工事には、住宅内における子どもの事故防止工事、対面式キッチンへの交換、収納設備の増設、間取り変更工事などが含まれます。
また、対象工事の限度額を超過する部分や、その他の増改築等工事についても一定の範囲で5%の税額控除が適用される場合があります。
住宅ローン控除が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶夫婦で考えるお金の基本セミナー:ライフステージごとのお金の管理がわかる
控除期間はいつまで?新築・中古・リフォームのパターン別解説
住宅ローン控除の控除期間は、住宅の種類や入居時期によって異なります。
新築住宅・買取再販住宅の場合
原則として控除期間は13年間です。
ただし、「その他の住宅」に分類される住宅で、2024年以降に新築の建築確認を受けたものは、住宅ローン控除の対象外となります。
例外として、2023年末までに建築確認を受けた「その他の住宅」に2024年または2025年に入居する場合は、控除期間10年間、借入限度額は2000万円となります。
既存住宅・増改築等(リフォーム)の場合
既存住宅の場合は環境性能にかかわらず、控除期間は一律で10年間です。
また、増改築等(リフォーム)の場合は、住宅の増改築等に住宅ローンを利用したケースでも、控除期間は10年間となります。この場合の借入限度額は2000万円、控除率は0.7%です。
このように、住宅の種類や環境性能、さらには建築確認の時期によって控除期間や適用条件が細かく定められているため、ご自身のケースがどれに該当するかを事前に確認することが非常に重要です。
住宅ローン控除を受けるための手続き
住宅ローン控除を受けるためには、所定の手続きが必要です。特に、入居した最初の年と、それ以降の年で手続き方法が異なるため、注意が必要です。
1年目:入居した翌年に確定申告が必要
住宅ローン控除を初めて適用する年は、入居した翌年にご自身で確定申告を行う必要があります。確定申告の際には、以下の書類を提出します。
どの住宅にも必要な書類
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 住宅ローンの年末残高等証明書
- 登記事項証明書、請負契約書または売買契約書の写し
住宅の性能に応じて必要になる書類:
- 認定長期優良住宅・低炭素住宅の場合:認定通知書の写し、住宅用家屋証明書(の写し)または建築証明書など
- ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の場合:建設住宅性能評価書の写しまたは住宅省エネルギー性能証明書
- 既存住宅の場合:1981年12月31日よりも前の建築日の場合、耐震基準適合証明書、建設住宅性能評価書の写し、または既存住宅売買瑕疵保険付保証明書など
- 2024年以降に新築住宅に居住する場合:住宅の性能に応じた書類に加えて、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は建築確認を受けたことを証する確認済証または検査済証の写し。省エネ基準に適合しない「その他の住宅」の場合は、2023年12月31日以前に建築確認を受けたこと、または2024年6月30日以前に建築されたことを証する書類
この確定申告を行うことで、税務署は住宅ローン控除の適用を確認し、その後の住宅ローン控除の手続きをスムーズに進めることができます。
2年目以降:会社員は年末調整で手続き完了
会社員や公務員(給与所得者)の場合、2年目以降は年末調整で住宅ローン控除の手続きを行うことが可能です。
税務署から送付される「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」と、金融機関から送付される「住宅ローンの年末残高等証明書」を勤務先に提出することで、年末調整で控除が適用されます。これにより、毎年確定申告をする手間が省け、手続きが簡素化されます。
自営業者やフリーランスの方など、年末調整の対象とならない場合は、毎年自分で確定申告を行う必要があります。
住宅ローン控除を受けられないケース
住宅ローン控除は多くの住宅取得者に適用される制度ですが、状況によっては適用を受けられないケースもあります。以下に主な例を挙げます。
贈与による取得や、生計を一にする親族などから取得した場合
住宅ローン控除は、第三者からの適正な取引によって住宅を取得した場合に適用されるのが原則です。
そのため、親や祖父母などからの贈与によって住宅を取得した場合や、生計を一にする親族(配偶者、子どもなど)から住宅を取得した場合は、控除の対象となりません。
これは、税法の公平性を保つため、市場価格と乖離した不適切な取引を防ぐ目的があります。
親族や知人からの借入金で住宅を取得した場合
住宅ローン控除の対象となる借入金は、金融機関や住宅金融支援機構など、一定の者からの借入金に限られます。
そのため、親族や友人・知人など個人からの借入金で住宅を取得した場合、その借入金は住宅ローン控除の対象外となります。
これも、ローンが適正な金融取引として行われていることを前提としているためです。
居住用の住宅を2つ以上所有する場合
住宅ローン控除は、居住者が「主として居住の用に供する」1つの住宅に対して適用される制度です。
そのため、複数の住宅を所有している場合でも、実際に居住している主たる住宅のみが控除の対象となります。
別荘や投資用物件など、自身が居住していない住宅は控除の対象外です。
また、転勤などで一時的に別の場所に居住する場合、所定の手続きを行うことで、再び居住する際に控除を受けられることがあります。
土地のみ購入する場合
住宅ローン控除は「住宅」の取得や増改築が対象であり、土地のみの購入では適用されません。
ただし、住宅と一体で取得・利用される土地については、住宅ローン控除の対象となる借入金の範囲に含まれる場合があります。
例えば、住宅を新築するために土地を購入し、その土地の上に新築住宅を建てる場合は、土地の購入費用も住宅ローン控除の対象となる可能性があります。
しかし、将来的に住宅を建てる予定がない土地の購入や、既に住宅がある土地の単体購入は対象外です。
住宅ローン控除に関するよくある質問
住宅ローン控除に関するよくある質問と回答をまとめました。
Q. 住宅ローン控除は2026年以降どうなる?
現行の住宅ローン控除制度は、2025年までの期限付きとなっており、2025年9月現在、2026年以降の制度については公表されていません。
2026年以降も制度が継続される可能性はありますが、仮に延長された場合でも、控除額や適用条件が現行のまま維持されるとは限りません。
Q. 夫婦でペアローンを組んだ場合、控除はどうなる?
夫婦でそれぞれが住宅ローンを組む「ペアローン」を利用した場合、夫婦それぞれが住宅ローン控除の適用を受けることができます。
この場合、夫婦がそれぞれローンの契約者となり、各々の持分に応じた価額に対する住宅ローン残高に対して、各々に控除が適用されます。
ただし、それぞれが控除の適用要件(所得要件、床面積要件など)を満たしている必要があります。
なお、夫婦のどちらか一方しか住宅ローンを組んでいない場合は、ローンを組んだほうのみが控除の対象となります。
Q. 住宅ローン控除とふるさと納税は併用できる?
住宅ローン控除とふるさと納税は併用可能です。
しかし、両者とも所得税や住民税からの控除・軽減となるため、併用する際には注意が必要です。
ふるさと納税の控除上限額は所得によって決まりますが、住宅ローン控除によって所得税や住民税が軽減されると、ふるさと納税で控除できる金額の上限も変動する可能性があります。
例えば、ワンストップ特例を利用してふるさと納税をした場合は、住宅ローン控除は所得税から優先的に控除され、控除しきれない分は住民税から控除されます。そのため、住民税からのふるさと納税による控除可能額が想定よりも少なくなるケースもあります。
Q. 住宅ローン控除の手続きはいつやればいい?
住宅ローン控除の手続きは、入居した年によって異なります。
- 1年目:住宅に入居した翌年に、自身で税務署に確定申告を行う必要があります。この際に、必要書類を提出して控除の適用を申請します。
- 2年目以降:会社員・公務員(給与所得者)の場合、勤務先の年末調整で手続きを行うことが可能です。税務署から送付される書類と金融機関が発行した残高証明書を提出します。自営業者など年末調整の対象とならない人は、2年目以降も毎年ご自身で確定申告を行う必要があります。
なお、確定申告の期間は通常、入居した年の翌年の2月16日から3月15日です。期限内に忘れずに確定申告しましょう。
まとめ
住宅ローン控除は、住宅取得者の経済的負担を軽減し、質の高い住宅の普及を後押しする重要な税制優遇制度です。新築、中古、リフォームのいずれのケースでも適用条件が細かく定められており、特に住宅の環境性能が控除額に大きく影響を与える点が特徴です。
この制度を最大限に活用するには、住宅ローン減税の要件を満たしているか、あらかじめ自分でチェックすることが大切です。本記事で解説した情報を参考に、自分のケースに合った住宅ローン控除を活用しましょう。
>>あなたの将来資金は足りる?不足額を3分で診断
住宅ローン控除が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶夫婦で考えるお金の基本セミナー:ライフステージごとのお金の管理がわかる
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
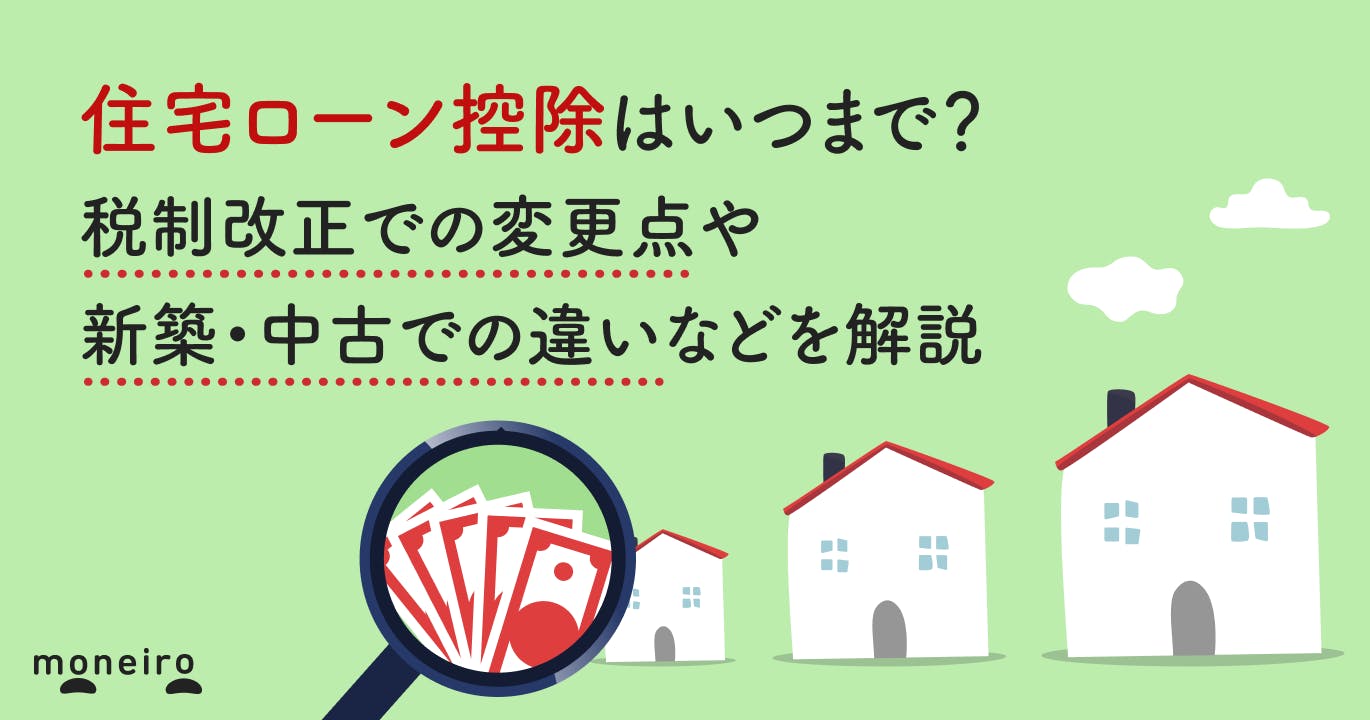
.jpg?w=1370&h=720&fit=crop&crop=faces&auto=compress,format)