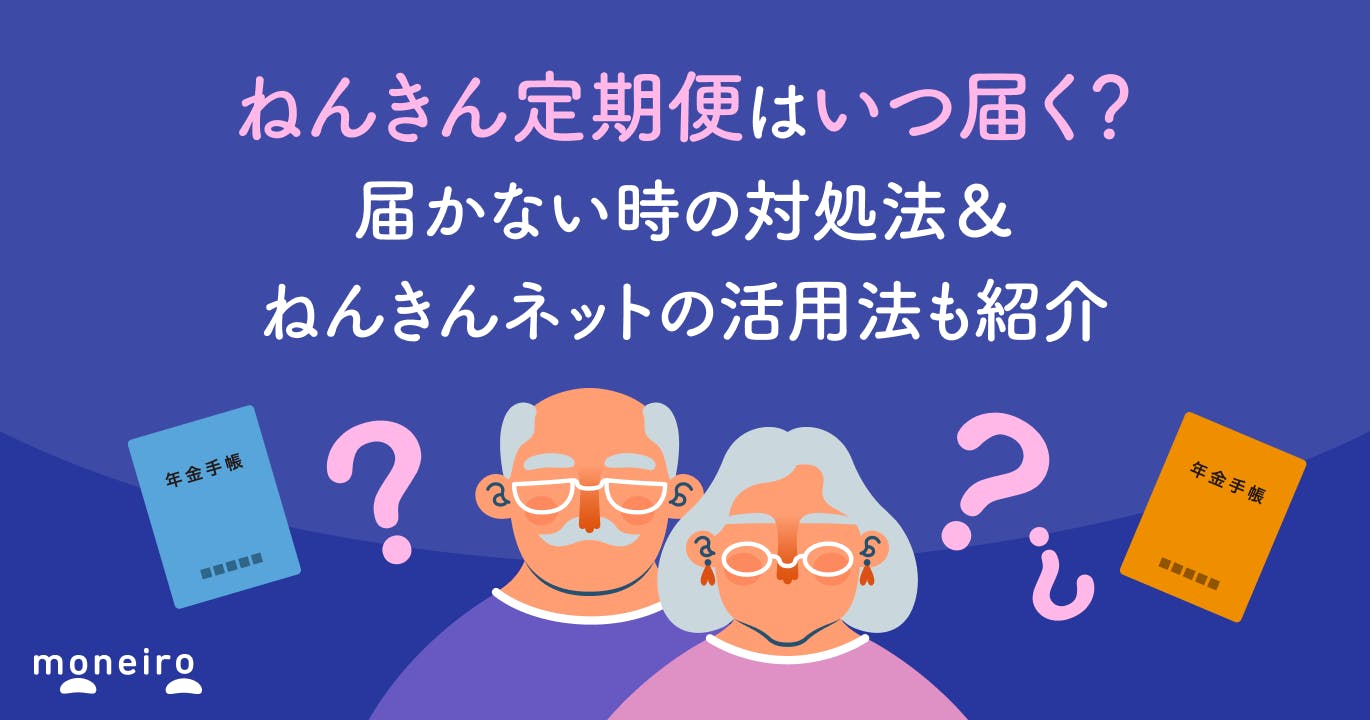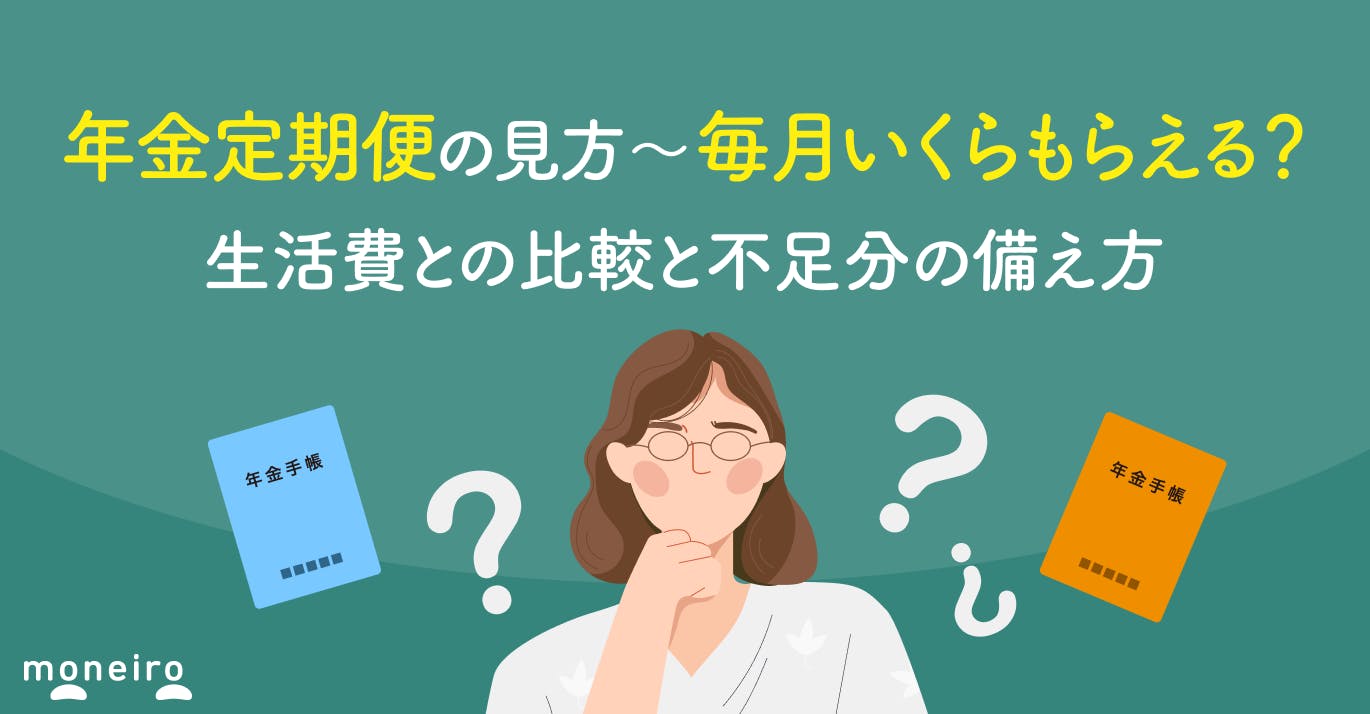
ねんきん定期便はいつ届く?届かない時の対処法&ねんきんネットの活用法も紹介
>>年金で足りる?あなたの将来の不足額を3分で診断
「ねんきん定期便はいつ届く?」と気になっていませんか?ねんきん定期便は、自身の年金記録や将来の年金見込額を確認できる大切な書類です。
この記事では、ねんきん定期便が届く時期や、年齢に応じたハガキと封書(35歳,45歳,59歳)の違い、届かなかった時の具体的な原因と対処法、さらに便利なオンラインサービス「ねんきんネット」の登録・活用法までを詳しく解説します。ぜひ、ご自身の年金記録の確認や、将来のライフプラン設計にお役立てください。
- ねんきん定期便が毎年いつ、どのような形式で届くか
- ねんきん定期便の内容が50歳を境にどのように変化するか
- オンラインサービス「ねんきんネット」の登録方法や主な機能
老後の年金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額を3分で診断
▶夫婦で考えるお金の基本セミナー:ライフステージごとのお金の管理がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
ねんきん定期便とは?いつ届く?
ねんきん定期便は、日本年金機構が毎年送付する書類で、国民に年金制度への理解を深めてもらい、各個人の年金記録を確認してもらうことを目的としています。
この定期便を通じて、これまでの保険料納付額や年金加入期間などの重要な記録を知ることができます。
ねんきん定期便は毎年誕生月に届く
ねんきん定期便は、日本年金機構が毎年、対象者の誕生月に郵送しています(ただし、1日生まれの人は誕生月の前月に届きます)。
送付対象となるのは、国民年金または厚生年金保険に加入している人(被保険者) です。
もし誕生月を過ぎても届かない場合は、住所の確認や記録漏れの疑いがあるため、後述する対処法に基づき対応が必要です。
ねんきん定期便は「ハガキ」「封書」の2種類
ねんきん定期便は、その人の年齢に応じて、主に「ハガキ」または「封書」の2種類の形式で送付されます。
特に35歳、45歳、59歳といった節目の年齢では、より詳細な情報を記載した「封書」が送付されます。
ハガキのねんきん定期便
ハガキ形式のねんきん定期便は、50歳未満の方(ただし35歳、45歳を除く)と、50歳以上の方(ただし59歳を除く)に送付されます。
ハガキに記載される主な情報は、これまでの保険料納付額、最近1年間の月別の納付状況、年金加入期間、そしてこれまでの加入実績に応じた年金額です。この情報は、現時点での年金加入状況を確認するのに役立ちます。
なお、視覚障害により障害年金等を受給している方で、直近1年間に被保険者期間がある受給者の方にもハガキ形式が送付されますが、点字を付した封筒に入れられて届きます。
封書のねんきん定期便
封書形式のねんきん定期便は、年金記録を詳細に確認するための節目として、35歳、45歳、59歳の年齢の方に送付されます。
封書形式では、ハガキ形式の情報に加え、「これまでの年金加入履歴」と「全期間の月別状況」が記載されます。
これにより、加入期間全体を通じた記録の詳細を確認し、年金記録に「漏れ」や「誤り」がないかを総合的にチェックできます。
特に59歳の方には、老齢年金の種類と、60歳まで加入し続けたと仮定した時の年金見込額が記載されます。
ねんきん定期便の内容は50歳未満と50歳以上で異なる
ねんきん定期便に記載される年金額は、50歳を境に計算方法が大きく異なります。これは、将来の年金受給見込額をより現実に即した形で確認してもらうためです。
50歳未満の人の内容
50歳未満の方(35歳、45歳を含む)のねんきん定期便には、「これまでの加入実績に応じた年金額」が記載されています。
これは、あくまでも現時点までに納付された保険料に基づき計算された年金額であり、将来受け取る年金総額の推定値ではありません。
この情報を基に、これまでの納付状況を確認し、記録に誤りがないか確認しましょう。
50歳以上の人の内容
50歳以上の方(59歳を含む)のねんきん定期便には、「老齢年金の種類と見込額」が記載されています。
これは、現在の年金制度に基づき、今後も現在の加入条件で60歳まで加入し続けたと仮定して計算された、将来受け取ることができる年金の見込額です。
これにより、より具体的な将来の年金受給イメージを持つことができ、老後の資金計画を立てる際の重要な基準となります。
ねんきん定期便が届かない原因と対処法
ねんきん定期便は毎年必ず送付されますが、届かない場合は、日本年金機構側の事務処理上のミスか、または住所や加入状況に変更があり、手続きが漏れている可能性があります。
これらの問題は年金記録の不備につながりかねないため、迅速な対処が必要です。
原因1.住所・氏名変更の手続きをしていない
住民票の住所変更を行ったとしても、年金記録上の住所や氏名が更新されていない場合、ねんきん定期便が旧住所に郵送されてしまう可能性があります。
マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者の方については、原則として住所変更の届出は不要です。
対処法
マイナンバーと基礎年金番号が結びついているにもかかわらず届かない場合や、住所や氏名に変更があったにもかかわらず届かない場合は、速やかに「ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号」またはお近くの年金事務所に連絡し、年金記録上の情報が最新のものになっているか確認しましょう。
また、オンラインサービス「ねんきんネット」に登録し、年金記録詳細を定期的に確認することも、記録漏れを防ぐ有効な対処法です。
原因2.転職・退職時の手続きが漏れている
会社を退職したり、転職したりした際に、厚生年金保険の資格喪失手続きや、国民年金への種別変更手続き が漏れていると、ねんきん定期便が届かなくなる原因となります。
特に、退職後、配偶者の扶養に入る(第3号被保険者になる)手続きや、国民年金(第1号被保険者)に加入する手続きが遅れると、その期間の記録が「未納」となり、正確な情報が反映されません。
対処法
転職・退職直後で届かない場合は、手続きが正しく完了しているかを確認するため、まずは自身で「ねんきんネット」を利用し、直近13か月の年金加入状況を確認しましょう。
もし記録に不備や空欄がある場合は、速やかに年金事務所または「ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号」に問い合わせ、加入記録を修正する手続きを行ってください。
原因3.海外に移住した
海外に移住した場合、原則として「ねんきん定期便」は海外のご住所に郵送されます。
しかし、海外転出後に住所変更の手続きが正しく行われていない場合、日本国内の旧住所に戻されてしまうなど、配達されない原因となります。
対処法
海外在住で届かない場合は、日本年金機構に登録されている海外の住所情報が正しいかを確認する必要があります。
また、海外在住期間が長い場合は、郵送による到着が遅れる可能性も考慮しつつ、日本年金機構の「ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号」またはお近くの年金事務所に連絡し、住所情報と送付状況を確認してください。
インターネット環境があれば、「ねんきんネット」で電子版の確認も可能です。
原因4.DV被害等で住民票と異なる場所に居住している
DV被害などのやむを得ない事情により、住民票上の住所地とは異なる場所に居住している場合、ねんきん定期便が意図しない相手に届いてしまうのを避けるため、郵送が滞っている可能性があります。
対処法
DV被害等の特別な事情がある場合は、年金事務所にその旨を申し出て、年金関連の書類の送付先を現在の居住地に変更する手続きが必要です。
この手続きは機密性が高いため、まずは「ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号」または年金事務所に直接相談し、適切な送付先変更手続きを進めることが重要です。
個別の状況に応じて、年金事務所が対応窓口となります。
原因5.事務処理上のミス
上記のような個人情報側の問題ではなく、日本年金機構内での事務処理上のミスによって、誤って送付が止まってしまったり、記録に不備が生じてしまったりするケースも稀に考えられます。
対処法
誕生月を大幅に過ぎても届かず、かつ住所や加入状況に問題がないと思われる場合は、事務処理上のミスが原因である可能性を疑い、早急に「ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号」または年金事務所に連絡し、送付状況の調査を依頼してください。
特に、ねんきん定期便に記載されている共済組合等(国家公務員共済組合連合会など)の記録に疑問がある場合は、該当する各共済組合等に直接問い合わせる必要があります。
老後資金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額を3分で診断
▶夫婦で考えるお金の基本セミナー:ライフステージごとのお金の管理がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
ねんきん定期便より便利「ねんきんネット」を活用しよう
ねんきんネットは、日本年金機構が提供するオンラインサービスで、インターネットを通じていつでもどこでも、PCやスマートフォンから年金記録を確認できる便利なシステムです。
紙の定期便の到着を待つことなく、最新の年金情報を確認できます。
ねんきんネットでできること
ねんきんネットに登録することで、以下のようないくつかの重要な機能を利用できます。
- 将来の年金見込額の試算: 自身で加入条件や受給開始年齢などのさまざまな条件を設定し、将来受け取る老齢年金の見込額を試算
- 年金記録の確認: 自分の年金記録を詳細に確認
- 電子版「ねんきん定期便」の閲覧・ダウンロード: 毎年郵送される「ねんきん定期便」と同一の内容をPDFファイルとして確認・ダウンロード可能
- 通知書の確認: 年金振込通知書などの通知の確認
- 届書の電子申請: 「年金請求書」や「年金生活者支援給付金請求書」など一部の届出書の電子申請
- 持ち主不明記録の検索: 国のコンピュータで管理されている年金記録のうち、現在持ち主不明になっているものの検索
ねんきんネットの登録方法
ねんきんネットの利用を開始するには、事前に登録が必要です。登録は、以下の2つの方法で行えます。
マイナポータルとの連携
マイナンバーカードを利用し、マイナポータルを通じて連携する方法です。これにより、迅速に利用開始できます。
ユーザIDの取得
ユーザIDを取得して登録する方法です。具体的には以下の方法で行います。
- アクセスキーを利用する場合:「ねんきん定期便」に記載されているアクセスキー(有効期限3ヶ月)と基礎年金番号があれば、「ねんきんネット」のサイトから即時にユーザIDを取得し、利用を開始できます。
- アクセスキーを利用しない(または期限切れの)場合:ねんきんネットのWebサイトにアクセスし、基礎年金番号などを入力してユーザIDの発行を申し込みます。後日、日本年金機構から郵送されるパスワード(ハガキ)を受け取って本登録を行います。
ねんきん定期便に関するQ&A
ねんきん定期便に関するよくある質問と回答をまとめました。
Q. ねんきん定期便をなくした場合、再発行できる?
ねんきん定期便を紛失した場合の紙の再発行については、「 ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号」に電話することで、最新の加入記録などの情報に基づいた「ねんきん定期便」を再発行できます。ただし、届くまでには2~3ヶ月ほどかかります。
ねんきんネットでは、毎年郵送される「ねんきん定期便」と同一の内容を収録した電子版(PDFファイル)を閲覧・ダウンロードできます 。この電子版をダウンロードしてパソコンなどに保存しておけば、紙の紛失の心配なく、年金記録の管理・保存に役立ちます。
紛失や保管の手間を避けたい場合は、ねんきんネットに登録し、電子版を利用することが最も確実な方法です。
Q. ねんきん定期便に記載の年金額は、手取り額?
ねんきん定期便に記載されている年金額(見込額)は、税金や社会保険料が差し引かれる前の金額(額面) です。
実際に年金を受給する際は、この額面金額から、所得税や住民税、そして国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)や介護保険料(65歳以上の場合)などが天引きされます。そのため、実際に口座に振り込まれる「手取り額」は、記載されている金額よりも少なくなります。
正確な手取り額は、お住まいの市区町村の税率や保険料率、また配偶者の有無などの状況によって異なります。老後の資金計画を立てる際は、この点を十分に考慮することが非常に重要です。
Q. ねんきん定期便は電子版(PDF)で受け取ることもできる?
はい、電子版で受け取ることができます。電子版「ねんきん定期便」は、日本年金機構が毎年郵送している「ねんきん定期便」と同一の内容をPDFファイル形式でオンラインサービス「ねんきんネット」上で確認できるサービスです。
電子版を利用するには、「ねんきんネット」への登録が必要です。マイナポータル連携またはユーザIDの取得により登録を行いましょう。
日本年金機構は、郵送費用の削減やペーパーレス化の推進のため、電子版の利用を推奨しており、希望すればハガキ版の郵送停止登録を行うことも可能です。
まとめ
ねんきん定期便は、年金記録の確認と将来設計のための重要な通知書であり、毎年誕生月に、ハガキまたは封書で送付されます。特に35歳、45歳、59歳には、全期間の記録が記載された封書が届き、記録漏れがないか確認する絶好の機会となります。
50歳未満の方の年金額は「これまでの加入実績」に基づく一方、50歳以上の方には60歳まで継続加入を仮定した「見込額」が記載されるため、年齢に応じた記載内容を正しく理解することが重要です。
もし定期便が届かない場合は、住所変更手続きの漏れや転職・退職時の手続き漏れ、事務処理上のミスなどが原因として考えられます。その際は、年金事務所または専用番号に速やかに連絡し、記録の確認と修正を行いましょう。
また、年金記録の管理や詳細な年金見込額の試算には、オンラインサービス「ねんきんネット」の活用が非常に有効です。ねんきんネットに登録することで、電子版の定期便をいつでも確認・保存でき、ライフプランに合わせた試算が行えます。こちらも積極的に活用するとよいでしょう。
>>年金で足りる?あなたの将来の不足額を3分で診断
老後資金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額を3分で診断
▶夫婦で考えるお金の基本セミナー:ライフステージごとのお金の管理がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
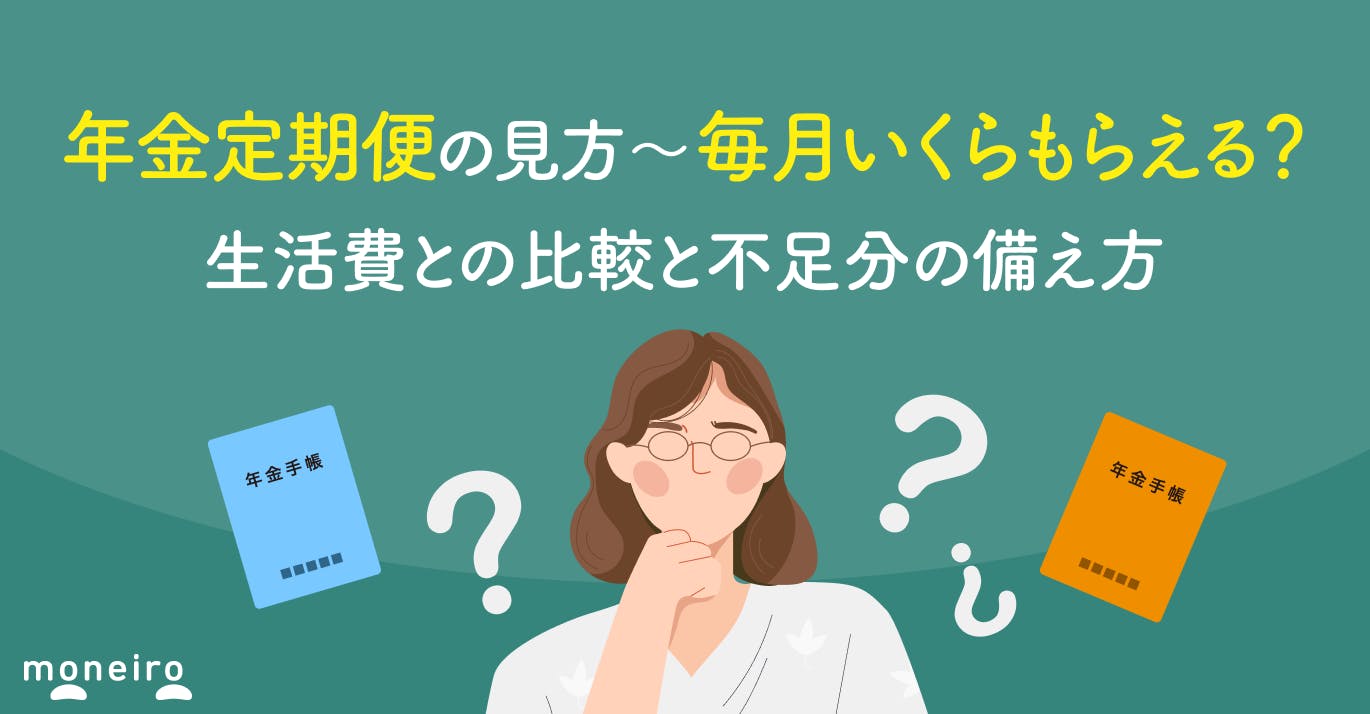
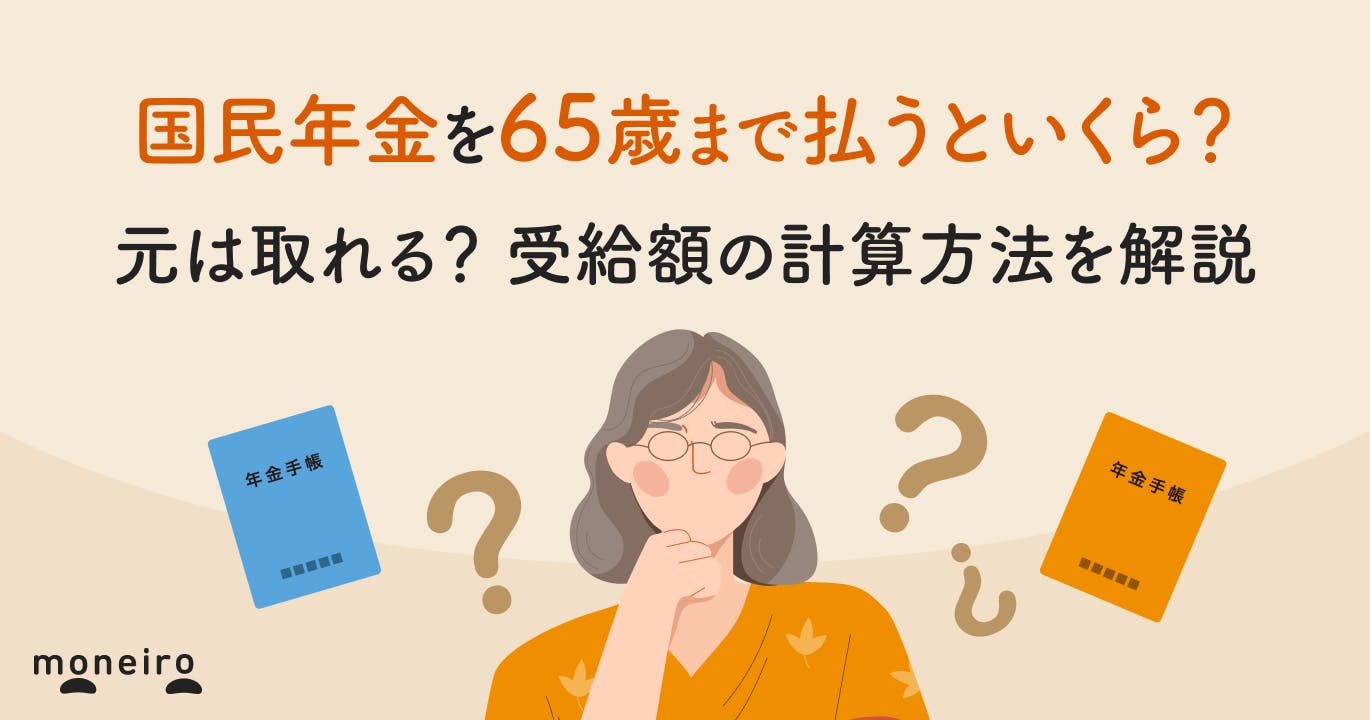
国民年金を65歳まで払うといくら?元は取れる?満額受給額と老後の不足分を徹底解説
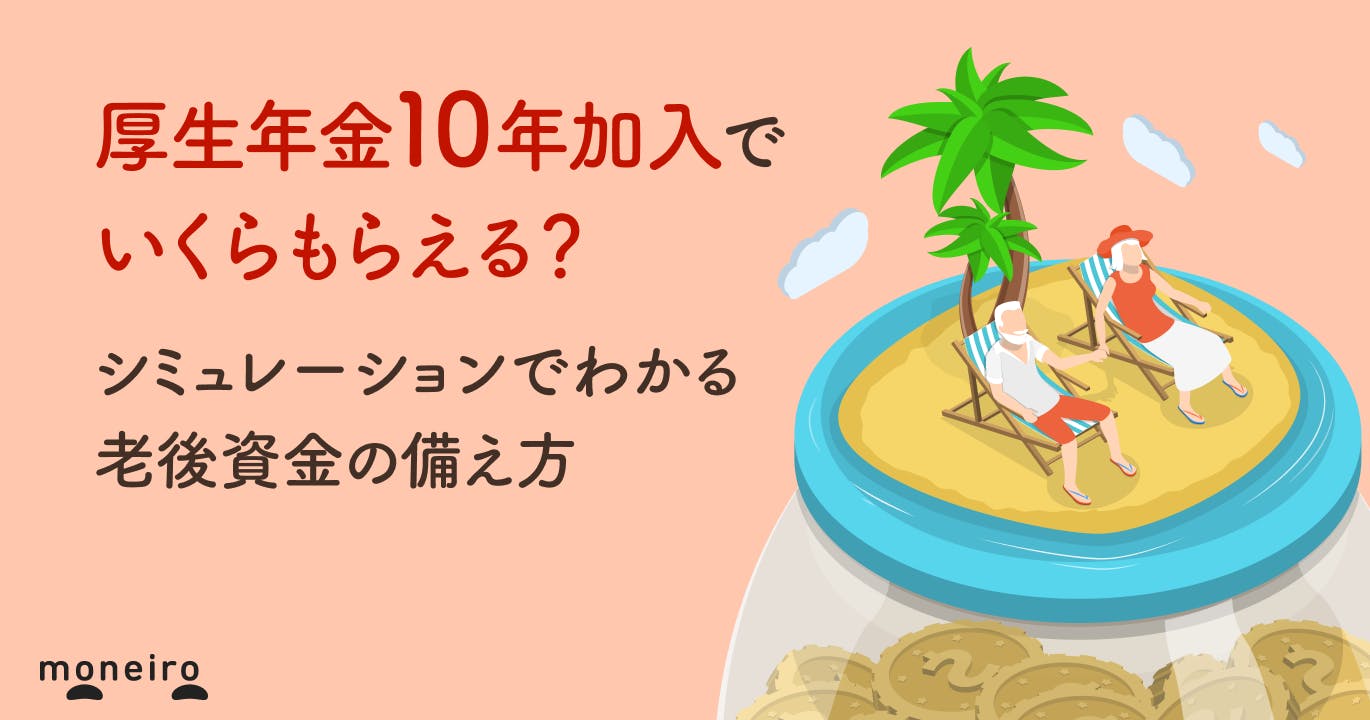
厚生年金10年加入でいくらもらえる?シミュレーションでわかる老後資金の備え方

老後に必要なお金はいくら?単身・夫婦の世帯タイプ別必要額を解説
監修
山本 務
- 特定社会保険労務士/AFP/第一種衛生管理者
東京都練馬区で、やまもと社会保険労務士事務所を開業。企業の情報システム、人事部門において通算28年の会社員経験があるのが強みであり、情報システム部門と人事部門の苦労がわかる社会保険労務士。労務相談、人事労務管理、就業規則、給与計算、電子申請が得意であり、労働相談は労働局での総合労働相談員の経験を生かした対応ができる。各種手続きは電子申請で全国対応が可能。また、各種サイトで人事労務関係の記事執筆や監修も行っている。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。