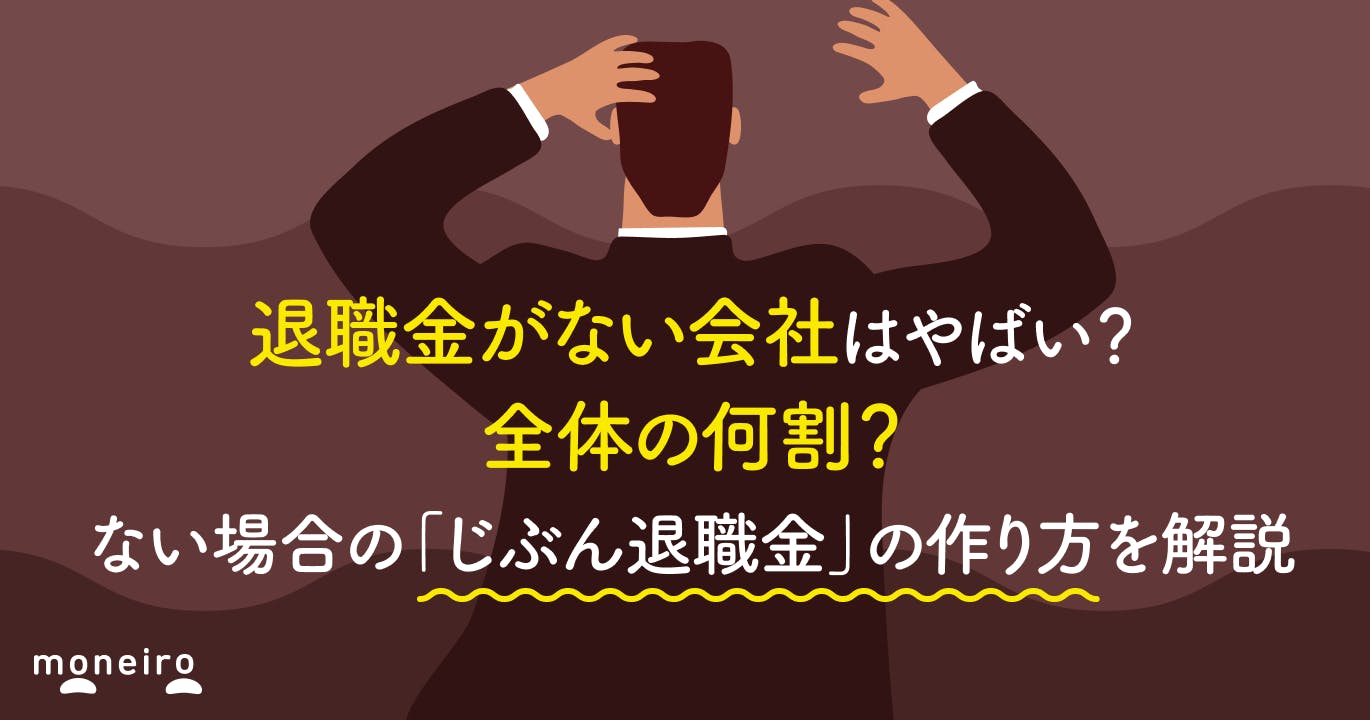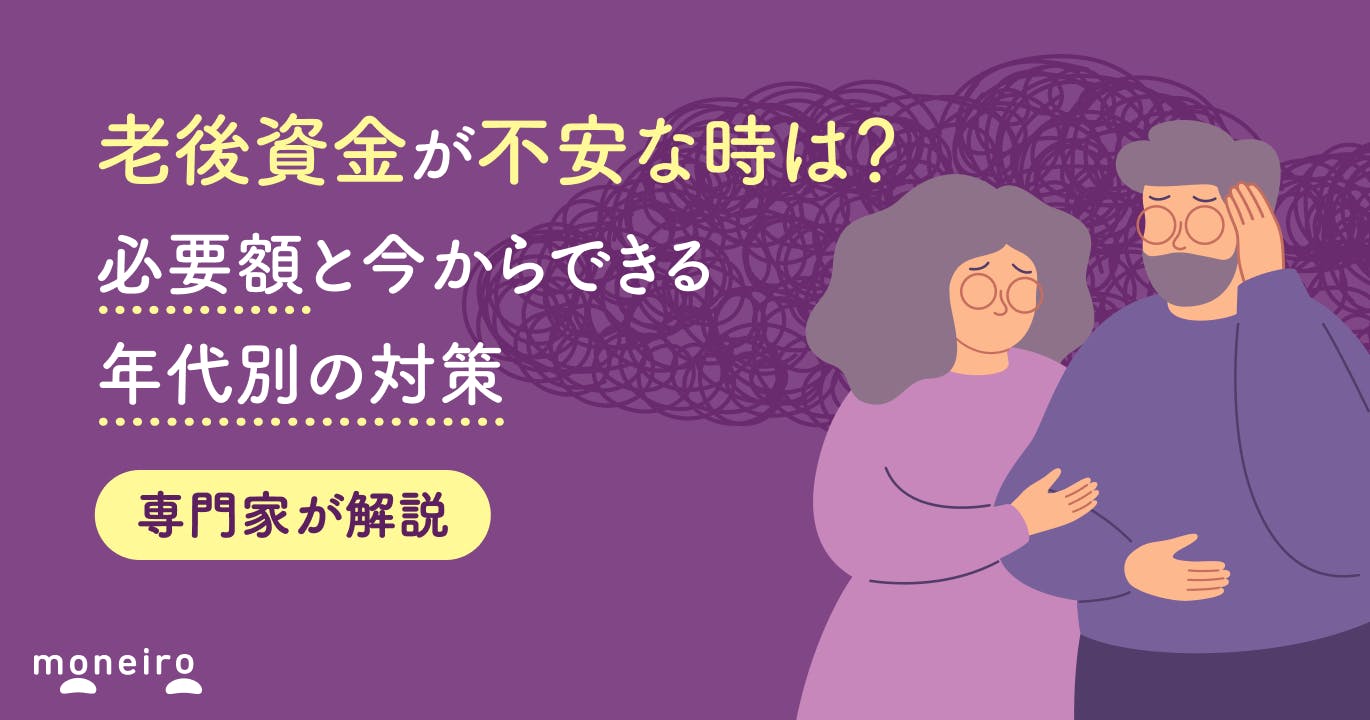退職金がない会社はやばい?全体の何割?ない場合の「じぶん退職金」の作り方を解説
>>あなたの老後にはいくら必要?将来の不足額を3分で診断
「退職金がない会社はやばい?」将来の生活資金に不安を感じている人も多いでしょう。
そこで本記事では、退職金がない企業の割合や法的な位置づけ、そして制度がないからこそのメリット・デメリットを解説します。併せて、iDeCoやNISA、企業型DCなど、自分自身で老後資金を形成する具体的な方法を詳しく解説します。
- 退職金制度がない企業の割合
- 退職金制度がないことのメリットとデメリット
- 会社に退職金制度がない場合の「老後資金を確保するための具体的な方法」
老後の資金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは自分の現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額を3分で診断
▶夫婦で考えるお金の基本セミナー:ライフステージごとのお金の管理がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ

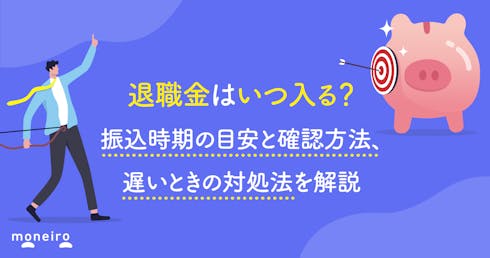
データで見る「退職金がない会社」の実態
日本では、退職金がある会社が多いのは事実です。一方で、退職金ない会社は全体のどれくらいあるのでしょうか。公的なデータからチェックしてみましょう。
退職金がない会社はどのくらい?
厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査」によると、退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合は全体の74.9%となっています。
このデータに基づくと、退職給付(一時金・年金)制度がない企業は全体の24.8%に上ります。つまり、日本国内の約4社に1社は、何らかの退職金制度を設けていないことになります。
企業規模別データ
企業規模別に見ると、制度の有無には大きな差が見られます。
企業規模が小さくなるほど、退職給付制度がない企業の割合が増加する傾向にあり、「30~99人」規模の企業では約3割が制度を持っていません。
産業別データ
また、産業別に見ると、「複合サービス事業」が97.9%、「鉱業,採石業,砂利採取業」が97.6%と制度がある企業割合が高い一方、「宿泊業,飲食サービス業」は42.2%、「サービス業(他に分類されないもの)」は54.4%と、産業によって制度の普及状況に大きなばらつきがあることがわかります。
【制度がある企業割合が高い産業】
- 複合サービス事業:97.9%
- 鉱業、採石業、砂利採取業:97.6%
- 電気・ガス・熱供給・水道業:96.4%
【制度がある企業割合が低い産業】
- 宿泊業、飲食サービス業:42.2%
- サービス業(他に分類されないもの):54.4%
- 運輸業、郵便業:69.9%
そもそも会社に退職金を支払う義務はある?
日本の法律において、企業が従業員に対して退職金を支払うことは義務付けられていません。つまり、退職金制度がないことは違法ではありません。
そんな中でも多くの企業が退職給付制度を導入しているのは、長期的な雇用維持や福利厚生の一環であるためです。退職金制度を設けている企業割合は74.9%であり、これは日本の企業慣行として広く普及していることを示しています。
ただし、就業規則や雇用契約書などで退職金制度の導入が明記されている場合は、企業はそれに従って退職金を支払う義務が発生します。制度がない企業に就職する場合は、老後資金計画においてこの点に注意が必要です。
老後の資金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは自分の現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額を3分で診断
▶夫婦で考えるお金の基本セミナー:ライフステージごとのお金の管理がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
退職金がない会社はやばい?退職金制度がない理由とは
結論からいうと、退職金制度がない企業に対して、一概に「やばい(ブラック企業である)」と判断するのは誤りです 。退職金制度がない背景には、その企業の経営戦略や事業フェーズに応じた多様な理由があります 。以下で詳しく解説します。
経営の柔軟性確保のため
退職金制度、特に退職一時金制度や確定給付型の年金制度は、将来の給付債務を負うため、企業の財務体質に大きな影響を与えます 。
特に経済環境の変化が激しい現代において、退職金制度を持たないことで、経営者は人件費の管理や将来の資金繰りに関して高い柔軟性を確保できます 。
成果主義を徹底しているため
従来の退職金制度は、勤続年数や年功序列の要素が強く反映される傾向にありました。一方で、退職金制度を設けず、その分を月々の給与や賞与に還元し、短期的な成果に応じて報酬を支払う「成果主義」を徹底する企業も増えています 。
これにより、従業員のモチベーションを現在の業務に集中させ、企業業績の向上を目指します。
事業成長への投資を優先しているため
特にスタートアップ企業や成長段階にある企業は、限られた資金を事業拡大や研究開発への投資に集中させる必要があります 。人件費を固定的な退職金債務として積み立てるよりも、成長への投資を優先することで、企業価値の最大化を図ります 。
また、これらの企業では、退職金ではなく、ストックオプション(自社株を将来特定の価格で購入できる権利)を付与することで、従業員に大きなリターンで報いる文化があることも特徴です 。
経営体力として退職金を出すのが難しい
小規模企業や収益が安定しない産業(例:宿泊業、飲食サービス業など、制度がある企業割合が低い産業)では、そもそも退職金の財源となる資金の確保が難しいという現実的な理由も存在します。また、前述の通り、30~99人規模の企業では約3割が制度を持っていません。
退職金がない場合のデメリット
退職金がない場合に個人が直面する主なデメリットは、以下の3点です。
老後の生活資金を自分で用意する必要がある
退職金は、公的年金(厚生年金・国民年金)だけでは不足しがちな老後資金の大きな柱となります 。退職金制度がない場合、退職時に企業からまとまった資金が支給されないため、老後の生活費全額を自分で計画的に貯蓄・運用し、準備しなければなりません 。
住宅ローンなどまとまった資金の返済にあてられない
多くの方が、住宅ローンや子どもの教育資金など、人生の大きな支出を退職金で一括返済したり、一部を賄ったりすることを想定して計画を立てています 。
退職金がない場合、これらの計画を見直す必要があり、現役時代の貯蓄や月々の給与からの計画的な資金捻出がより重要になります 。
長期的な勤続意欲が湧きにくい
退職金制度は、従業員に対して「長く勤めれば勤めるほど優遇される」という経済的なインセンティブを提供し、長期的な勤続意欲を維持する役割を果たしています 。
制度がない場合、社員はより高待遇な企業への転職をためらう理由が減り、企業に対する帰属意識や長期的な勤続意欲が湧きにくい可能性があります 。
退職金がない場合にはメリットも?
退職金がないことは一見デメリットばかりに思えますが、従業員にとってメリットとなる側面もあります。
月々の給与が高く設定されている場合がある
退職金制度を設けていない企業の中には、退職金として積み立てるはずだった費用を「退職金の前払い」として、毎月の給与に上乗せして支給しているケースがあります 。
この場合、月々の手取りが増えるため、現在の生活水準や自由に使える資金が増加します。特に若いうちに資金を多く得て、それを自己投資や資産運用に回したいと考える人にとっては有利でしょう 。
勤続年数に縛られず、転職しやすい
退職金制度は、勤続年数が短いと支給額が低くなる設計になっていることが一般的です。そのため、退職金を諦めきれず、不満があっても転職に踏み切れないという状況が生じやすかったのも事実です。
しかし、制度がない場合、退職金の多寡を気にすることなく、自身のキャリアアップや市場価値向上を優先して、より自由に転職先を選べるようになります 。
資産形成の自由度が向上する
企業が退職金として準備する年金制度(例:確定給付企業年金など)は、運用方針や商品が企業側で決められていることが多く、従業員が自分のリスク許容度や目標に合わせて柔軟に運用することが困難です 。
月々の給与に退職金相当額が上乗せされる場合、その資金を個人型確定拠出年金(iDeCo)やNISA(少額投資非課税制度)など、自分で選んだ制度・商品で運用する自由度が大きく向上します 。
退職金がない人のための「じぶん退職金」の作り方
会社に退職金制度がない場合でも、税制優遇を受けながら効果的に老後資金を準備できる公的な制度があります。これらを活用して「じぶん退職金」を構築しましょう。
iDeCoの活用(個人型確定拠出年金)
iDeCoは、確定拠出年金法に基づいて運営されている、自分で作る年金制度です。掛金が全額所得控除の対象となるため、節税効果が非常に高いのが特徴です。
また、運用益が非課税となる点、受け取る際にも税制優遇が受けられる点から、老後資金準備のための強力なツールとなります 。
NISAの活用(少額投資非課税制度)
NISAは、投資で得た利益(運用益や配当金)が非課税になる制度です。iDeCoとは異なり、原則としていつでも資金を引き出すことができるため、老後資金だけでなく、住宅購入など将来の大きな支出に向けた資金形成にも役立てることができます 。
iDeCoと併用することで、バランスの取れた資産形成が可能となります。
(該当者のみ)企業型DCの活用
企業型DC(企業型確定拠出年金)は、企業が導入する年金制度です。退職金制度がない企業でも、福利厚生の一環として企業型DCのみを導入している場合があります 。
企業型DCを導入している企業は、退職年金制度がある企業のうち50.3%(令和5年調査計)となっています。
企業型DCでは、掛金の拠出(企業拠出またはマッチング拠出)や運用益の非課税など、iDeCoと同様の税制優遇が受けられます。企業型DCがある場合は、まずはこの制度を最大限に活用することが「じぶん退職金」構築の第一歩となるでしょう 。
退職金制度に関するよくある質問
退職金制度に関するよくある質問と回答をまとめました。
Q. 退職金代わりの「iDeCo」と「企業型DC」はどちらを優先すべき?
企業が企業型DCを導入している場合、原則として企業型DCを優先して活用したほうがよいでしょう 。なぜなら、企業型DCは掛金の大部分または全額を企業が拠出してくれるため、従業員自身の負担が軽くなる場合が多いからです。
企業型DCを導入している場合でも、規約によってはiDeCoへの加入が可能な場合もあるため、まずは勤務している会社の制度を詳しく確認することが大切です。

Q. 退職金がない会社は「ブラック企業」?
退職金がないことだけで、その会社が「ブラック企業」であると断定することはできません 。
退職金制度がない背景には、経営の柔軟性の確保、成果主義の徹底、事業成長への投資優先といった前向きな理由が含まれている可能性があります 。特にスタートアップやベンチャー企業では、高い給与やストックオプションで報いる代わりに退職金制度を設けないケースが多く見られます 。
重要なのは、制度がない場合でも、月々の給与水準が高いか、キャリア形成の機会があるか、福利厚生が充実しているかなど、総合的な労働条件を判断することです。
Q. 入社前に退職金の有無は確認できる?
はい、入社前に退職金の有無は確認すべき重要な項目の1つといえます。確認方法としては、以下のものがあります 。
- 募集要項や求人票の確認:募集要項の「福利厚生」「退職金制度」の項目に記載があるか確認します。
- 労働条件通知書または雇用契約書の確認:内定時に提示されるこれらの書類に、退職金に関する規定(有無、計算方法)が記載されています。
- 面接時の確認:人事担当者や採用担当者に対して直接、退職金制度の有無、そして制度がない場合の老後資金に対する企業の考え方(例:企業型DCの導入予定など)を確認するのも有効です。
まとめ
退職金制度がない会社は、日本の企業全体の約24.8%となっています。しかしながら、制度がないからといって、その会社が必ずしも「やばい」わけではありません。制度がない背景には、成果主義の徹底や、給与の前払いによる資産形成の自由度向上といったメリットがある場合もあります 。
一方で、勤めている会社に退職金がない場合は、老後資金の準備をすべて自分自身で行う必要があります。そのため、iDeCoやNISA、企業型DCといった税制優遇制度を最大限活用し、計画的に「じぶん退職金」を構築することが、将来の安心につながります。
可能であれば、入社前に退職金制度の有無を確認し、自分のキャリアプランと照らし合わせつつ、賢明な選択をするようにしましょう 。
>>老後の資金は足りる?あなたの必要額を今すぐ診断
老後の資金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは自分の現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額を3分で診断
▶夫婦で考えるお金の基本セミナー:ライフステージごとのお金の管理がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事

老後資金はどうやって準備する?必要資金の計算方法と準備方法を解説
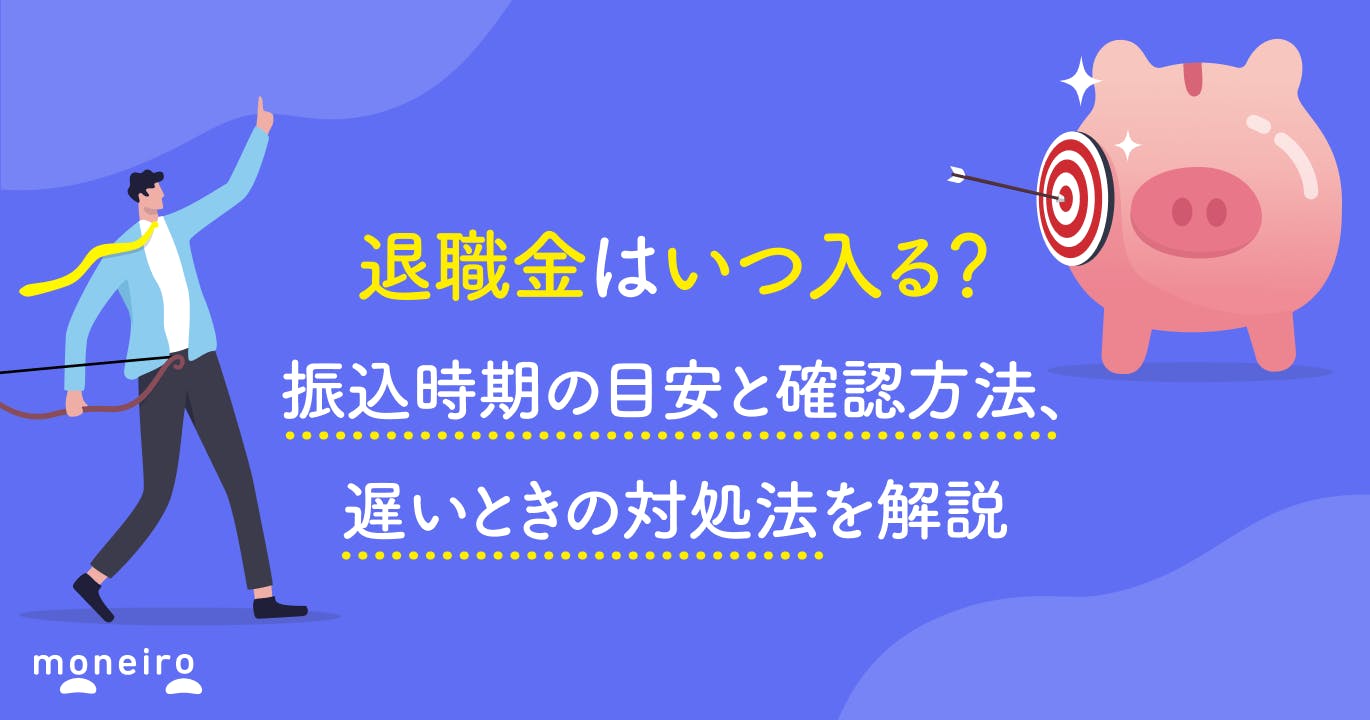
退職金はいつ入る?振込時期の目安と確認方法、遅いときの対処法を解説
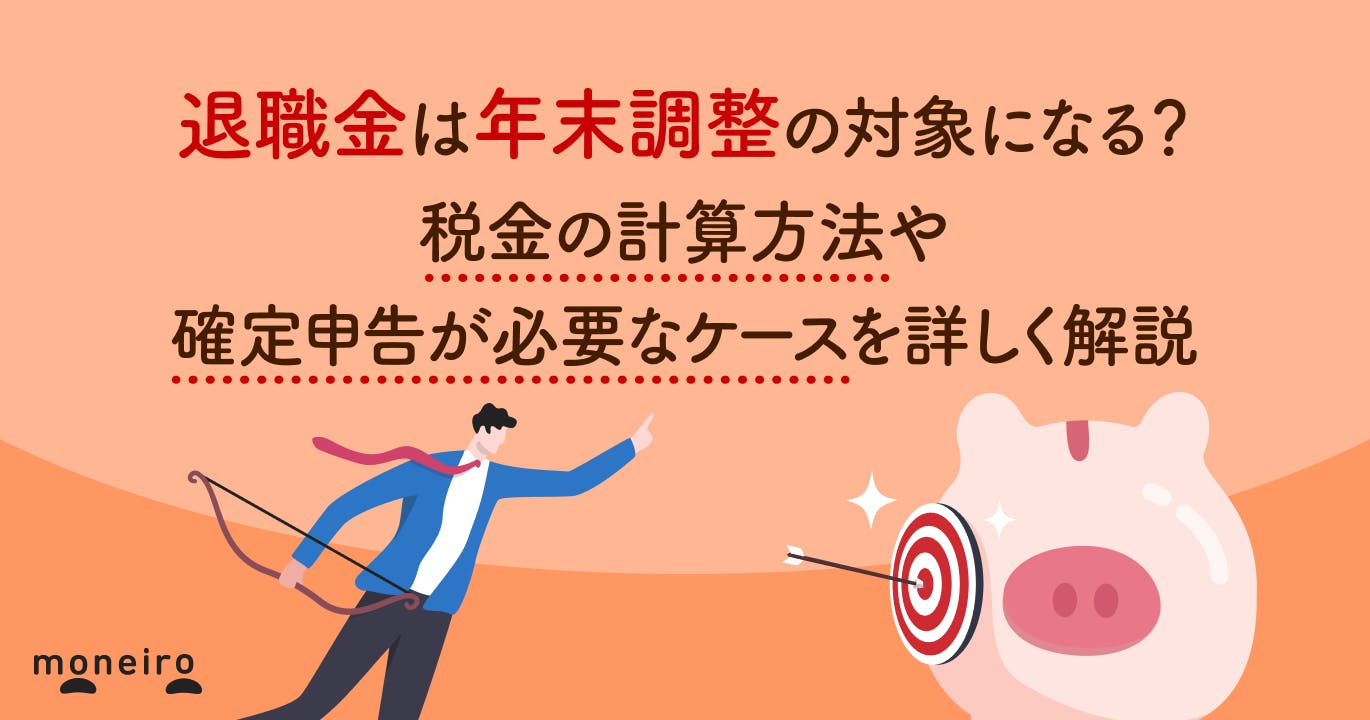
退職金は年末調整の対象になる?税金の計算方法や確定申告が必要なケースを詳しく解説
監修
高橋 明香
- ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者
みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。