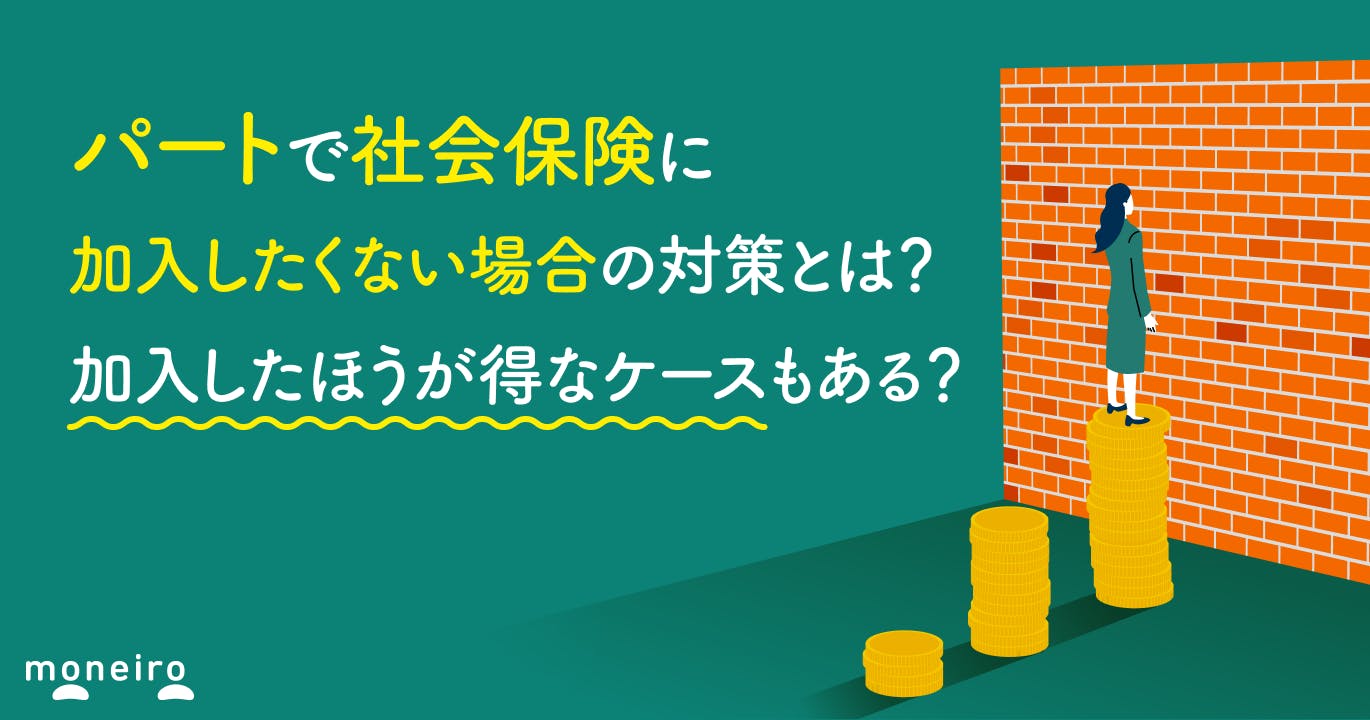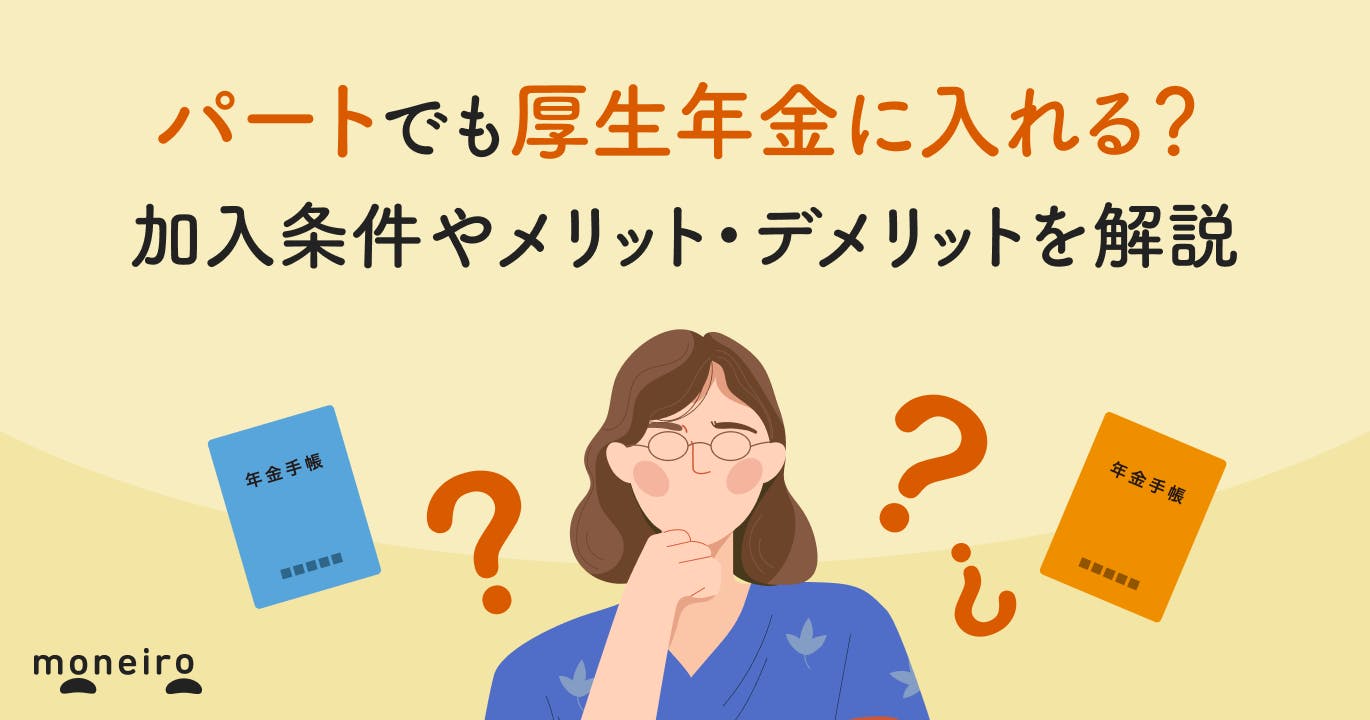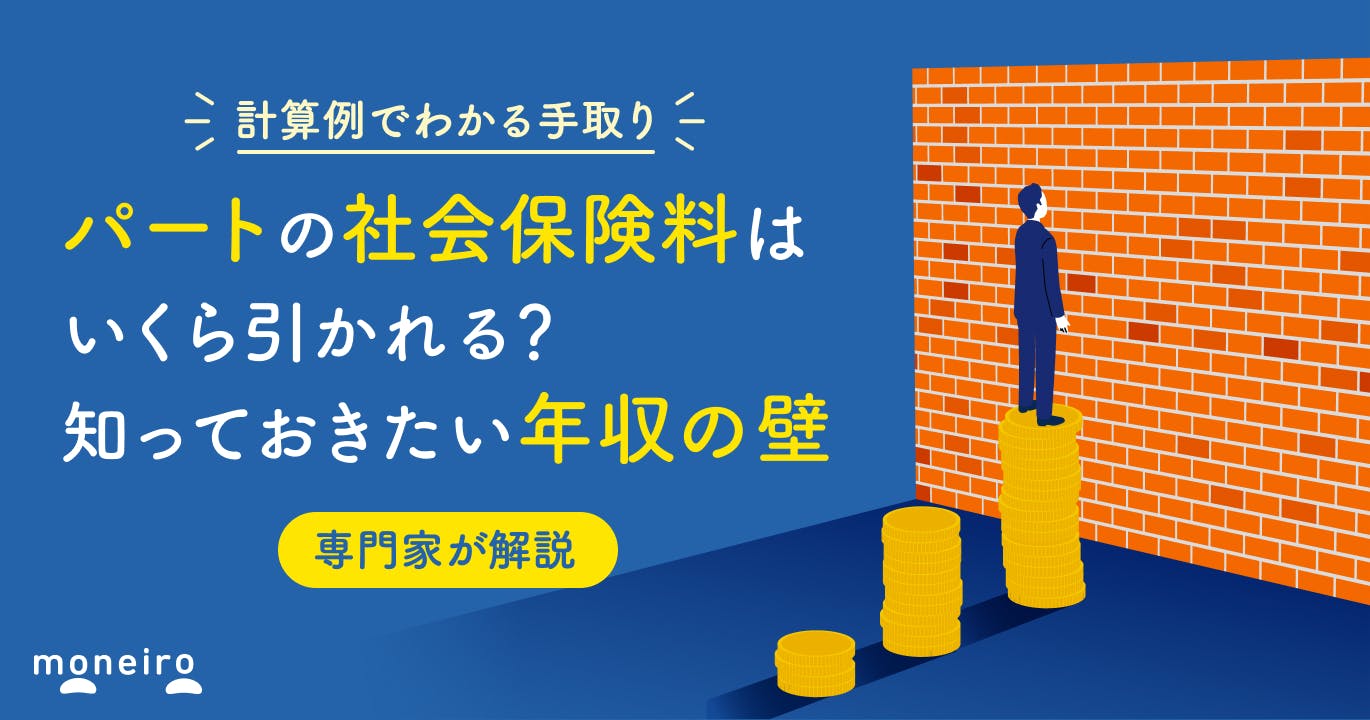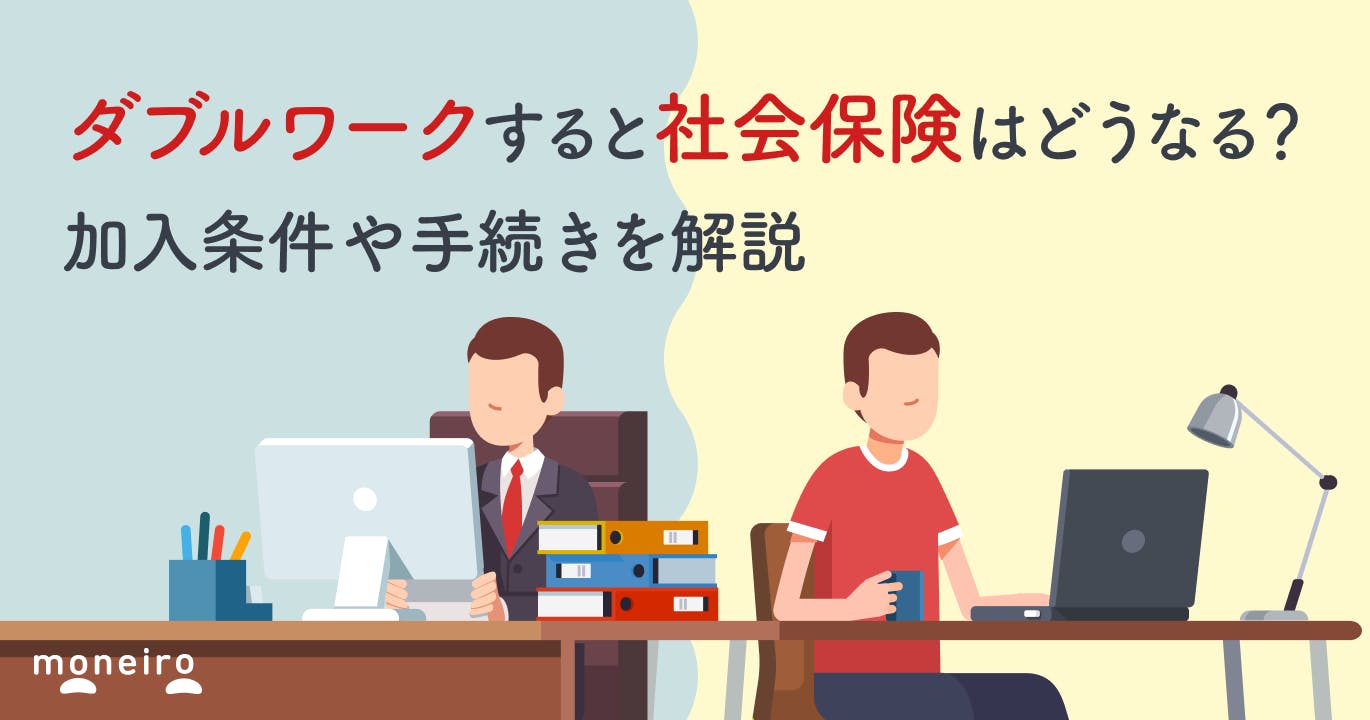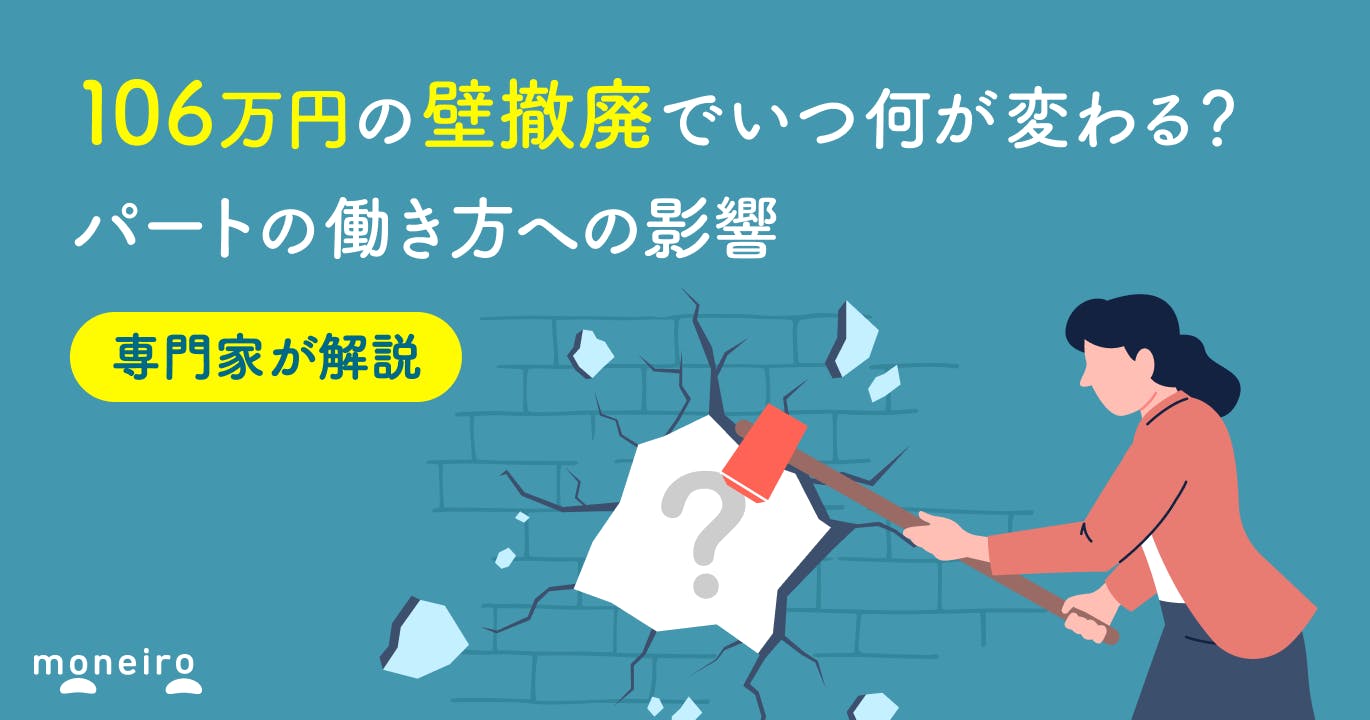
パートで社会保険に加入したくない場合の対策とは?加入したほうが得なケースもある?
>>将来、あなたに足りない金額は?今すぐ診断
「パートの社会保険に加入したくない」と悩んでいませんか?短時間で働く方にとって、年収が一定のラインを超えると社会保険料の支払いが発生し、一時的に手取り収入が減少する「年収の壁」は大きな問題です。
そこでこの記事では、社会保険の加入条件である年収の壁を解説し、手取りを減らさずに働く具体的な方法を解説します。ぜひ自分に合った働き方を見つけるための参考にしてみてください。
- 社会保険の加入条件となる「年収の壁」の具体的な基準と適用範囲
- 収入と労働時間をコントロールする方法
- 社会保険に加入するメリットとデメリット&加入したほうが得なケース
将来のお金が気になるあなたへ
これから先、お金の不安なく暮らすために、将来に必要なお金を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:あなたが将来必要になる金額を3分で診断
▶2025年に変わるお金の制度セミナー:お金に関する最新の制度をやさしく解説
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
パートで社会保険に加入したくない場合はどうする?
パートで働いていて社会保険に加入したくない場合、「労働時間」と「賃金額」が基準を超えないように管理・コントロールすることが重要です。
厚生年金や健康保険の加入義務は、勤務先の企業規模や週の労働時間、月額賃金などによって決まります。いわゆる「年収の壁」という表現がよく使われますが、実際には月額賃金や労働時間などの要件が基準になります。
本記事では、その具体的な基準と注意点を整理し、働き方を見直す際の参考になる情報を解説していきます。
社会保険の加入条件をチェック
パートタイム労働者が「年収の壁」を意識するのは、主に健康保険や厚生年金保険といった「社会保険」への加入義務が生じるためです。社会保険への加入が必要になると、それまで配偶者の扶養に入って免除されていた保険料の支払いが発生し、手取りが減少します。まずは、社会保険の加入が義務となる条件について確認しておきましょう。
【社会保険加入の5つの条件】
以下の条件を満たしている場合は、パートでも社会保険加入の対象となります。
- 賃金の月額が8万8000円以上(年収換算で約106万円)
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 継続して2ヶ月を超えて使用される見込みがある
- 学生ではない(休学中・定時制・通信制の学生は加入対象)
- 勤務先の従業員数が51人以上であること
社会保険の2つの「壁」とは?
パート労働者に関わる社会保険には、主に「106万円の壁」と「130万円の壁」があります。どちらが適用されるかは、勤務先の企業規模や労働条件によって異なります。
ここでいう「年収の壁」とは便宜的な表現で、実際には月額賃金や年間収入見込みで判定されます。
106万円の壁
「106万円の壁」は、一定規模の企業で働くパート労働者に健康保険・厚生年金保険の加入義務が発生する基準です。月額賃金8.8万円(年収約106万円)を基準に、基本給や諸手当(家族手当など)を含む総支給額で計算されます。なお、「月額賃金」には基本給や通勤手当などが含まれますが、残業代や賞与は含まれません。
なお、106万円の壁については、2025年6月13日の年金制度改革法成立により撤廃されます。ほかにも、企業規模要件撤廃など社会保険の加入対象拡大が決定しています。詳しくは、以下の記事もご覧ください。
130万円の壁
「130万円の壁」とは、勤務先が106万円の壁の対象外の場合に関係します。年間収入が130万円以上見込まれると、配偶者の社会保険上の扶養(被扶養者や第3号被保険者)から外れ、自分で国民健康保険・国民年金に加入する必要があります。
【収入の対象範囲(原則)】
- 基本給や各種手当
- 賞与
- 事業所得・不動産所得・配当所得など
130万円を超えると、社会保険料の自己負担が発生します。国民年金保険料は全国一律(年間約21万円)ですが、国民健康保険料は所得や自治体により大きく異なります。そのため、手取りが減少する程度は人によって大きく変わります。
パートで社会保険に加入したくない場合の対策
社会保険への加入義務を回避し、扶養内で手取りを確保したい場合、106万円の壁の加入要件(4つの条件)を意図的に満たさないように調整することが対策となります。
週の所定労働時間を「20時間未満」にコントロールする
106万円の壁の加入要件の一つに、「1週の所定労働時間が20時間以上」という条件があります。したがって、週の労働時間を19時間30分など、20時間未満に抑えることができれば、社会保険への加入義務は発生しません。
ただし、これはあくまで「所定労働時間」であるため、残業が恒常的に発生し、結果的に週20時間を超える場合は注意が必要です。雇用契約を見直し、労働時間の管理を徹底することが重要です。
月額賃金を「8.8万円未満」にコントロールする
106万円の壁のもう1つの主要な要件は、「賃金の月額が8万8000円以上」という条件です。月額賃金を8万8000円未満に抑えることで、社会保険の加入対象から外れることができます。
ダブルワーク(掛け持ち)で収入と労働時間を分散させる
106万円の壁の加入条件は、「勤務先の企業」ごと、つまり個別の雇用契約ごとに判断されます。
したがって、1つの職場で労働時間や月収を調整しつつ、複数の職場で働く「ダブルワーク(掛け持ち)」によって社会保険に加入することなく世帯全体の収入を増やすことが可能です。
例えば、A社で週15時間、月収6万円、B社で週10時間、月収4万円を稼ぐ場合、合計で月収10万円(年収120万円)、週25時間働いていたとしても、A社もB社も単独では106万円の壁の要件(週20時間以上かつ月額8万8000円以上)を満たさないため、社会保険への加入義務は発生しません。
ただし、この場合でも、年収130万円の壁には注意が必要です。
将来のお金が気になるあなたへ
これから先、お金の不安なく暮らすために、将来に必要なお金を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:あなたが将来必要になる金額を3分で診断
▶2025年に変わるお金の制度セミナー:お金に関する最新の制度をやさしく解説
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
あらためて社会保険に加入するメリット・デメリットを確認しておこう
社会保険料の支払いは短期的な手取りの減少につながりますが、長期的な視点で見ると、加入には大きなメリットがあります。将来のライフプランに合わせて、どちらが有利かを確認しましょう。
加入するメリット
社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入すると、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者では得られなかった手厚い保障を受けることができます。
将来の年金が2階建てに
厚生年金保険に加入して働いた場合、将来受け取ることができる年金額が増えます。年金の基礎部分(1階部分)に相当する国民年金(基礎年金)に加え、2階部分である厚生年金が上乗せされるため、老後の経済的な支えがより強固になります。
特に、加入期間が長くなるほど、受け取れる年金額は多くなります。
手厚い医療保険が受けられる
健康保険に加入することで、万が一の際の保障が充実します。
- 傷病手当金: 業務外の病気やケガで連続4日以上働けず、給与が出ない場合に、給与の約3分の2が最長1年6ヶ月間支給されます。
- 出産手当金: 産休中(出産日以前42日~出産後56日)に給与が支払われない場合に、給与の約3分の2が支給されます。
これらの手当は、健康保険組合(協会けんぽを含む)の被扶養者にはなく、健康保険組合などに加入している被保険者(本人)のみが受けられる制度です。
障害・遺族年金が充実
厚生年金に加入することで、万が一、障害を負った場合の障害年金や、自身が亡くなった場合に遺された家族が受け取る遺族年金も、国民年金のみの場合に比べて手厚くなります。これにより、個人のみならず世帯全体の経済的リスクに対する備えが強化されます。
加入するデメリット
一方で、加入することによるデメリットもないわけではありません。
手取り額の減少
社会保険への加入の最大のデメリットは、保険料の負担が発生し、結果として手取り収入が減少することです。社会保険料は、給与の13~15%程度であり、この金額が給与から天引きされます。
仮に年収が社会保険の加入ライン(106万円など)を少しだけ超えた場合、増えた収入額よりも天引きされる社会保険料のほうが多くなり、結果的に手取りが減ってしまう、いわゆる「働き損」になってしまうことがあります。
そのため、「加入しない働き方に調整する」または「加入したうえで、保険料負担をカバーできるくらい働く」という選択を迫られる可能性があります。
社会保険に加入したほうが得なケース
社会保険に加入すると、短期的には手取りが減少しますが、将来設計やキャリアアップを重視する場合、加入することが長期的に得になるケースがあります。
厚生年金の加入期間を増やせる場合
厚生年金の加入期間を増やせると、老後の年金受給額の増加につながります。加入期間が増えることで、報酬比例部分の年金が上乗せされ、生活水準の維持に役立ちます。
近い将来、離婚や夫との死別など、独り身になる可能性を考慮しておきたい場合
配偶者の扶養に頼らず、自身で社会保険に加入することで、傷病手当金や、自身が支払った厚生年金に基づく障害・遺族年金の受給権を確保できます。所定の障害状態になったとき、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金も受給できる可能性があります。
キャリアアップを目指し、将来的に年収150万円以上稼ぎたい場合
社会保険に加入しておくと、手取りの減少を受け入れたうえで収入を増やすことに躊躇しなくて済みます。
例えば、年収を130万円、150万円(2025年度より配偶者特別控除が満額適用される上限額は160万円)、201万円と増やす場合でも、加入済みなら社会保険料の負担はすでに発生しているため、収入増加の効果を素直に享受できます。
年収160万円を超えると、配偶者特別控除は段階的に減額されますが、世帯全体の手取りは概ね増加します。キャリアアップを目指す場合は、早い段階で社会保険の壁を突破し、収入増加に注力することが長期的にプラスにつながります。
パートの社会保険に関するQ&A
ここでは、パートの社会保険に関するよくある質問と回答をまとめました。
Q. 会社に「社会保険に入りたくない」と一方的に拒否できる?
いいえ。勤務先が社会保険の適用対象企業で、かつ従業員(パート労働者)が週20時間以上、月額8万8000円以上などの加入要件をすべて満たす場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入は法律上の義務です。そのため、労働者や会社の一方的な判断で加入を拒否することはできません。
社会保険への加入を避けたい場合は、週の労働時間や月額賃金などの加入要件を満たさないよう、会社と労働条件を調整する必要があります。
Q. 交通費や残業代は、年収の壁を計算する際に含まれる?
106万円の壁(社会保険加入義務)と130万円の壁(配偶者の扶養基準)では、収入の算定対象が異なります。以下で、それぞれの壁における交通費(通勤手当)や残業代の扱いを解説します。
106万円の壁
106万円の壁は、自分が勤務先で社会保険に加入するかの基準です。この判断に使われる月額8万8000円には、以下の変動的な手当は含まれません。
- 残業代・休日手当
- 通勤手当(交通費)
- 賞与(ボーナス)
あくまで、毎月決まって支払われる基本給や固定手当が計算の対象となります。
130万円の壁
130万円の壁は、配偶者など家族の社会保険の扶養から外れるかの基準です。この判断には、原則として以下すべての収入が含まれます。
- 基本給
- 残業代・休日手当
- 通勤手当(交通費)
- 賞与(ボーナス)
Q. 夫の会社に扶養から外れたことはバレるもの?
はい、扶養から外れた事実は、配偶者の会社に知られます。年収が130万円以上となり、国民健康保険や国民年金に加入する必要が生じた場合、または自身が勤め先で社会保険に加入した場合、配偶者は健康保険組合などに対して扶養(被扶養者や第3号被保険者)から外れる手続きを行う必要があります。
また、配偶者手当や家族手当といった企業独自の制度の支給要件として、配偶者の収入上限(主に103万円または130万円)が設けられていることが多く、扶養を外れるとこれらの手当の支給対象外となるため、配偶者の会社経由で必ず確認が行われます。
まとめ
パート労働者にとって「年収の壁」は、①本人の所得税や住民税、②社会保険、③配偶者手当の3つの視点で考える必要があり、特に社会保険の壁(106万円の壁・130万円の壁)は手取り収入に大きな影響を与えます。これらの壁については、以下のように考えるとよいでしょう。
- 手取り維持を最優先する場合:106万円の壁(週20時間未満、月額8万8000円未満)、または130万円の壁を厳格に超えないよう、労働時間と収入を調整する
- 将来の安定とキャリアアップを優先する場合:社会保険に加入することで、将来の年金増加や傷病・出産手当金といった充実した保障を得られる。手取り減少を一時的なコストと捉え、長期的なキャリア形成(年収150万円以上)を目指す
このように、働き方を見直す際は、現在の手取りだけでなく、将来のライフイベントやキャリアアップの目標を考慮し、各種制度を理解した上で最適な選択をすることが大切です。
>>将来、あなたに足りない金額は?3分で診断できる無料ツール
将来のお金が気になるあなたへ
これから先、お金の不安なく暮らすために、将来に必要なお金を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:あなたが将来必要になる金額を3分で診断
▶2025年に変わるお金の制度セミナー:お金に関する最新の制度をやさしく解説
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。