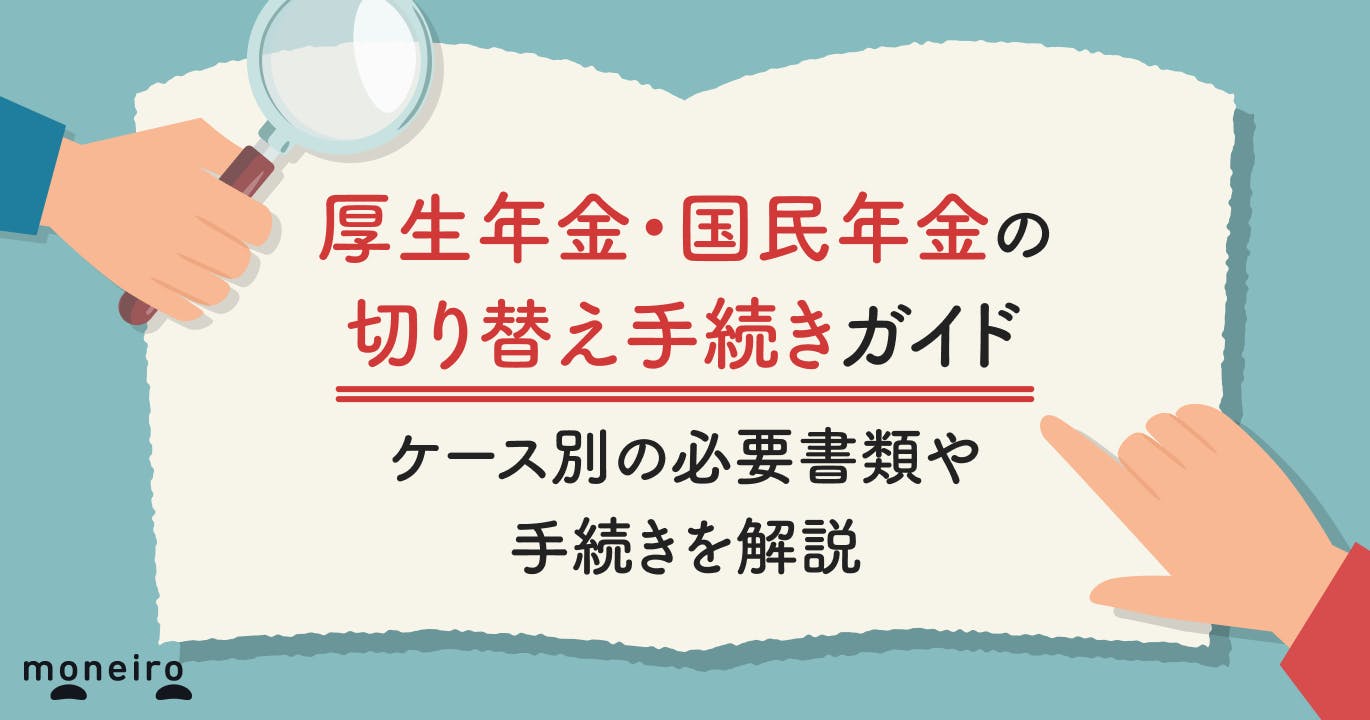厚生年金・国民年金の切り替え手続きガイド。ケース別の必要書類や手続きを解説
>>あなたの老後資金は足りる?将来の必要額を3分で診断
会社を退職したり転職したりすると、私たちの年金制度における立場が変わることがあります。特に厚生年金から国民年金への切り替えは、自ら手続きを行う必要があるため、その重要性を見落としがちです。
この記事では、厚生年金・国民年金の切り替えが必要になるケースや、それぞれの手続き、必要書類などを詳しく解説します。年金に関する不安を解消し、適切な手続きを進められるようにしましょう。
- 厚生年金と国民年金の切り替えが必要なケース
- ケース別の具体的な手続き方法と必要書類
- 手続きを忘れた場合のリスクと対処法
将来の年金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
厚生年金・国民年金の切り替えが発生する3つのケース
年金の切り替え手続きは、主に「会社を退職・独立したとき」「就職したとき」「配偶者の扶養から外れたとき」のケースで必要になります。
日本の公的年金制度は、働き方などによって加入する種類が異なり、以下の3つに分かれています。
- 第1号被保険者:自営業者、学生、無職の人など
- 第2号被保険者:会社員、公務員など
- 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者
働き方などが変わり、この被保険者の種類も変わる際に、年金の切り替え手続きが必要になります。
1. 会社を退職・独立したとき(厚生年金→国民年金)
会社員や公務員は、国民年金と厚生年金の両方に加入する「第2号被保険者」に分類されます。
この第2号被保険者が会社を退職してすぐに再就職しなかったり、独立して自営業者になったりした場合は、自営業者や学生、無職の人などが加入する「第1号被保険者」への切り替え手続きが必要です。第1号被保険者は国民年金のみに加入します。
2. 就職して会社員になったとき(国民年金→厚生年金)
学生や自営業者、無職の人などが加入する「第1号被保険者」が会社に就職した場合、厚生年金に加入し「第2号被保険者」へと切り替わります。
厚生年金は国民年金を含む2階建ての制度であるため、この手続きによって厚生年金と国民年金の両方に加入することになります。
3. 配偶者の扶養から外れたとき(第3号→第1号、第2号)
会社員や公務員である第2号被保険者に扶養されている配偶者は「第3号被保険者」となります。この第3号被保険者が、自身の収入増加や離婚、あるいは配偶者の退職などによって扶養から外れた場合、年金の切り替え手続きが必要です。
扶養から外れた後、自営業者や無職になる場合は第1号被保険者へ、自身が会社に就職して厚生年金に加入する場合は第2号被保険者へと切り替わります。
【退職時】厚生年金から国民年金への切り替え手続き
会社を退職した場合、原則として退職日の翌日から14日以内に、お住まいの市区町村役場で国民年金(第1号被保険者)への切り替え手続きが必要です。
手続きを忘れると年金の未納期間が発生し、将来の受給額に影響が出る可能性があるため、速やかに行いましょう。マイナンバーカードがあれば、スマートフォンなどからマイナポータルを利用して電子申請も可能です。
必要書類を準備する
厚生年金から国民年金への切り替え手続きには、主に以下の書類が必要です。自治体によって異なる場合があるため、事前にウェブサイトなどで確認しておくと安心です。
マイナンバーまたは基礎年金番号がわかる書類
年金の手続きの際には、マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるものが必要になります。マイナンバーカードや基礎年金番号通知書、年金手帳などを用意しておきましょう。
退職日がわかる書類(離職票、退職証明書など)
厚生年金保険の資格喪失日を証明するために、退職した事実が確認できる書類が必要です。具体的には、退職証明書、健康保険資格喪失証明書、雇用保険被保険者離職証明書(離職票)などのいずれかを用意します。
本人確認書類
窓口で手続きを行う場合、運転免許証やパスポートなど、手続きを行う人の身分を確認できる書類が必要です。これは、代理人による手続きだけでなく、本人による手続きでも提示を求められることが一般的です。
市区町村役場で手続きする
必要書類が準備できたら、退職日の翌日から14日以内に、住民票のある市区町村役場の国民年金担当窓口で手続きを行います。
窓口で「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を受け取り、必要事項を記入して提出します。手続きが完了すると、後日、日本年金機構から国民年金保険料の納付書が郵送されます。
配偶者の扶養に入る場合の手続きは?
退職後に配偶者の扶養に入る場合は、国民年金第3号被保険者への切り替え手続きが必要です。
この手続きは、自分で市区町村役場へ行くのではなく、配偶者の勤務先を通じて行います。必要書類などを配偶者の勤務先に確認し、速やかに提出しましょう。これにより、自分で国民年金保険料を納める必要はなくなります。
厚生年金から国民年金の切り替え手続きを行わないとどうなる?
上述の通り、会社を退職する場合、退職日の翌日から14日以内に、住民票のある市区町村役場の国民年金担当窓口で手続きを行う必要があります。
この期限を過ぎても、国民年金保険料の納付期限から2年以内であれば、手続きを行って保険料を納付できます。しかし、いつまでも手続きを行わなかった場合には、以下のようなデメリットがあります。
将来もらえる老齢年金が減る
国民年金の切り替え手続きをしないと、その期間は保険料の未納期間となります。老齢基礎年金(国民年金)の受給額は、保険料を納付した期間に応じて決まるため、未納期間があると将来受け取れる年金額がその分だけ減ってしまいます。
障害年金や遺族年金が受け取れない可能性
公的年金制度は、老後の生活を支えるだけでなく、病気やケガで障害が残った場合に支給される「障害基礎年金」や、加入者が亡くなった場合に遺族が受け取れる「遺族基礎年金」といった保障機能も備えています。
これらの年金を受け取るためには、一定の保険料納付要件を満たす必要があります。手続きをせず未納期間があると、この要件を満たせず、万が一の際に必要な保障が受け取れなくなる可能性があります。
最悪の場合、財産差し押さえのリスクも
厚生年金の資格を喪失すると、その情報は会社から日本年金機構に届け出られます。そのため、切り替え手続きをしていない場合でも、日本年金機構から国民年金加入の案内が届きます。
それでも放置したままでいると、国民年金保険料の納付書や督促状が送付され、最終的には特別催告状や差押えなどの強制徴収措置がとられる可能性があります。したがって、退職して14日を過ぎてしまった場合でも速やかに切り替え手続きを行うことが大切です。
なお、経済的な事情で納付が難しい場合は、市区町村役場や年金事務所に相談しましょう。所得や年齢などの条件に応じて、保険料免除や納付猶予の制度を利用できる場合があります。
将来の年金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
【就職時】国民年金から厚生年金への切り替え手続き
学生や自営業者などが会社に就職して厚生年金に加入する場合、国民年金から厚生年金への切り替え手続きが必要です。
手続きはほとんど会社が行う
国民年金から厚生年金への切り替えは、入社した会社が年金事務所へ厚生年金の加入手続きを行うことで自動的に完了します。
そのため、従業員本人が市区町村役場などに出向いて手続きをする必要はありません。基本的には会社から求められた必要書類を提出するだけで、手続きは完了します。
会社への提出書類
会社が厚生年金の加入手続きを行うにあたって、従業員はいくつかの書類を提出する必要があります。主に以下の書類が求められます。
年金手帳、基礎年金番号通知書またはマイナンバーカード
厚生年金保険の加入には基礎年金番号またはマイナンバーが必要です。そのため、入社時に「基礎年金番号通知書」や「年金手帳」、「マイナンバーカード」の提示を求められることがあります。
本人確認書類
入社手続きの一環として、本人確認のための書類(運転免許証やパスポートなど)の提示を求められることがあります。
国民年金保険料を前納していた場合は還付請求を忘れずに
国民年金保険料を前払いで納付(前納)している期間中に就職し、厚生年金に加入した場合、保険料の二重払いが発生します。
この重複して支払った国民年金保険料は、還付請求をすることで返金されます。後日、日本年金機構から「国民年金保険料還付請求書」が郵送されてくるので、必要事項を記入し、忘れずに手続きを行いましょう。
配偶者の扶養から外れた場合の切り替え手続き
会社員の配偶者に扶養されている第3号被保険者が、離婚や収入の増加などにより扶養から外れた場合、その後の状況に応じて年金の切り替え手続きが必要です。手続きは、自身で市区町村役場で行う場合と、新しい勤務先が行う場合があります。
ケース1.自営業、フリーランス、無職、学生になる場合
配偶者の扶養から外れた後、自営業を始めたり、フリーランスとして活動したり、あるいは無職や学生になったりする場合は、国民年金第1号被保険者への切り替え手続きが必要です。
この手続きは、扶養から外れた日から14日以内に、お住まいの市区町村役場の国民年金担当窓口で行います。手続きには、扶養から外れた日がわかる書類(健康保険資格喪失証明書など)や本人確認書類が必要です。
ケース2.就職して、自身が勤務先の社会保険に加入する場合
配偶者の扶養から外れて会社に就職し、勤務先の厚生年金や健康保険に加入する場合は、国民年金第2号被保険者への切り替えとなります。
この手続きは、新しい勤務先が年金事務所へ厚生年金の加入届を提出することで行われるため、自ら市区町村役場へ出向く必要はありません。会社からの案内に従って、基礎年金番号通知書などの必要書類を提出します。
年金の切り替えに関するQ&A
ここでは、厚生年金と国民年金の切り替え手続きに関して、よくある質問とその回答をまとめました。手続きで迷った際の参考にしてください。
Q. 厚生年金から国民年金への切り替えの際に離職票は必要?
離職票は必須書類ではありませんが、厚生年金の資格喪失日(退職日)を証明する書類として利用できます。
手続きには、退職した事実が確認できる書類が必要であり、離職票の他にも「退職証明書」や「健康保険資格喪失証明書」などが該当します。いずれかの書類を準備して、手続きに臨みましょう。
Q. 切り替えに際して、保険料を二重払いしてしまった場合はどうすればいい?
国民年金保険料を前納(前払い)している期間中に就職した場合など、保険料を二重に支払ってしまった場合でも、払い過ぎた分は還付(返金)されます。
通常、厚生年金への加入手続きが完了すると、日本年金機構から「国民年金保険料還付請求書」が自動的に送付されます。この書類に必要事項を記入し、返送することで、指定した口座に保険料が返金されます。
まとめ
この記事では、厚生年金と国民年金の切り替え手続きについて、ケース別に詳しく解説しました。
- 退職・独立時:厚生年金から国民年金への切り替え。退職日の翌日から14日以内に市区町村役場で手続きが必要。
- 就職時:国民年金から厚生年金への切り替え。手続きは勤務先の会社が行う。
- 扶養から外れた時:状況に応じて第1号または第2号への切り替えが必要。
年金の切り替えは、将来の自身の生活を守るための重要な手続きです。手続きを忘れると、年金の未納期間が発生し、将来の受給額が減るだけでなく、障害年金や遺族年金が受け取れなくなるリスクもあります。
ライフステージに変化があった際は、本記事を参考に、自身の状況に合った手続きを速やかに行いましょう。
>>年金で足りる?あなたの老後に必要なお金を3分で診断
将来の年金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事

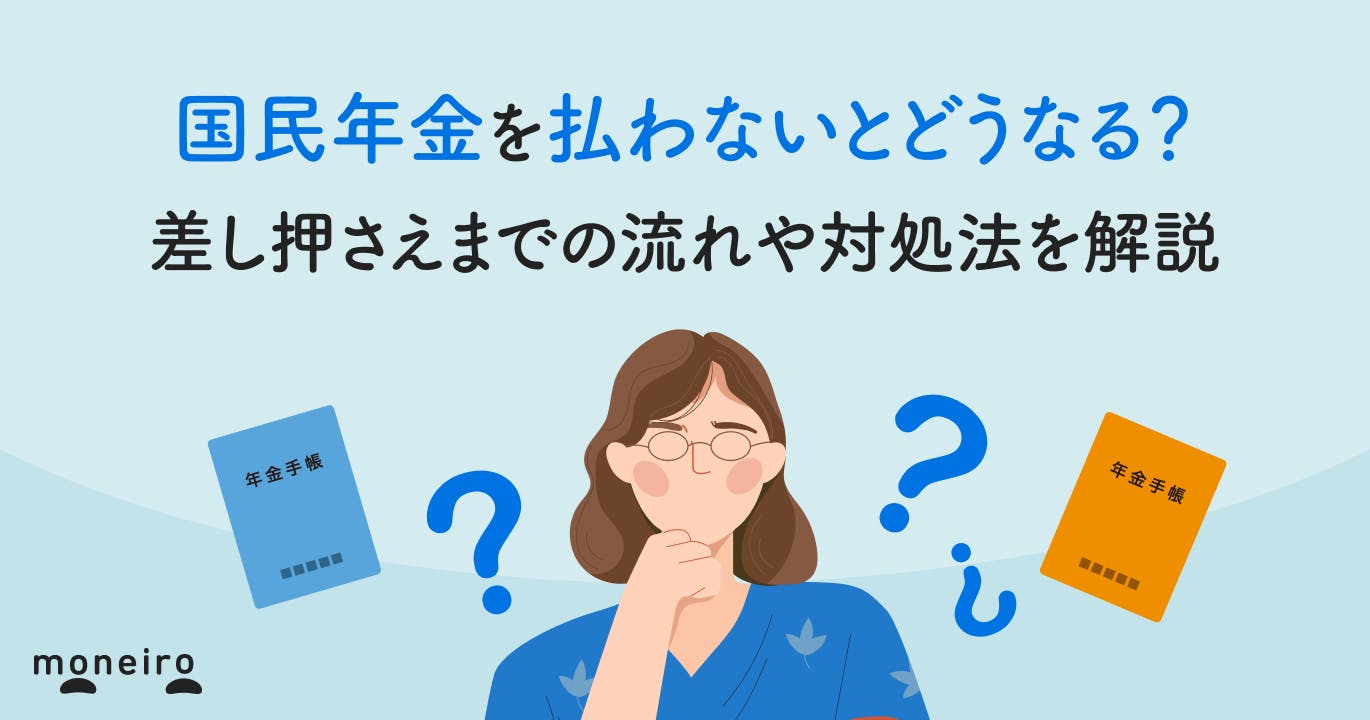
国民年金を払わないとどうなる?差し押さえまでの流れや対処法を解説
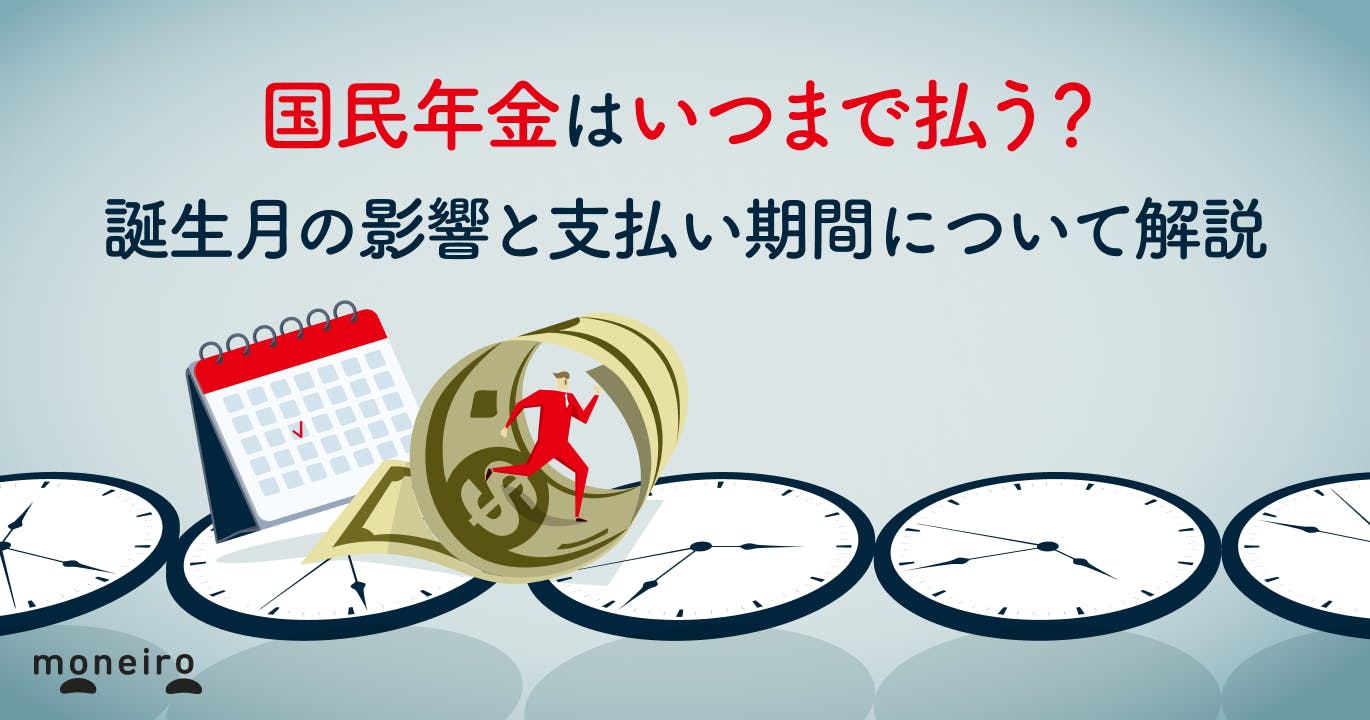
国民年金はいつまで払う?誕生月の影響と支払い期間をわかりやすく解説
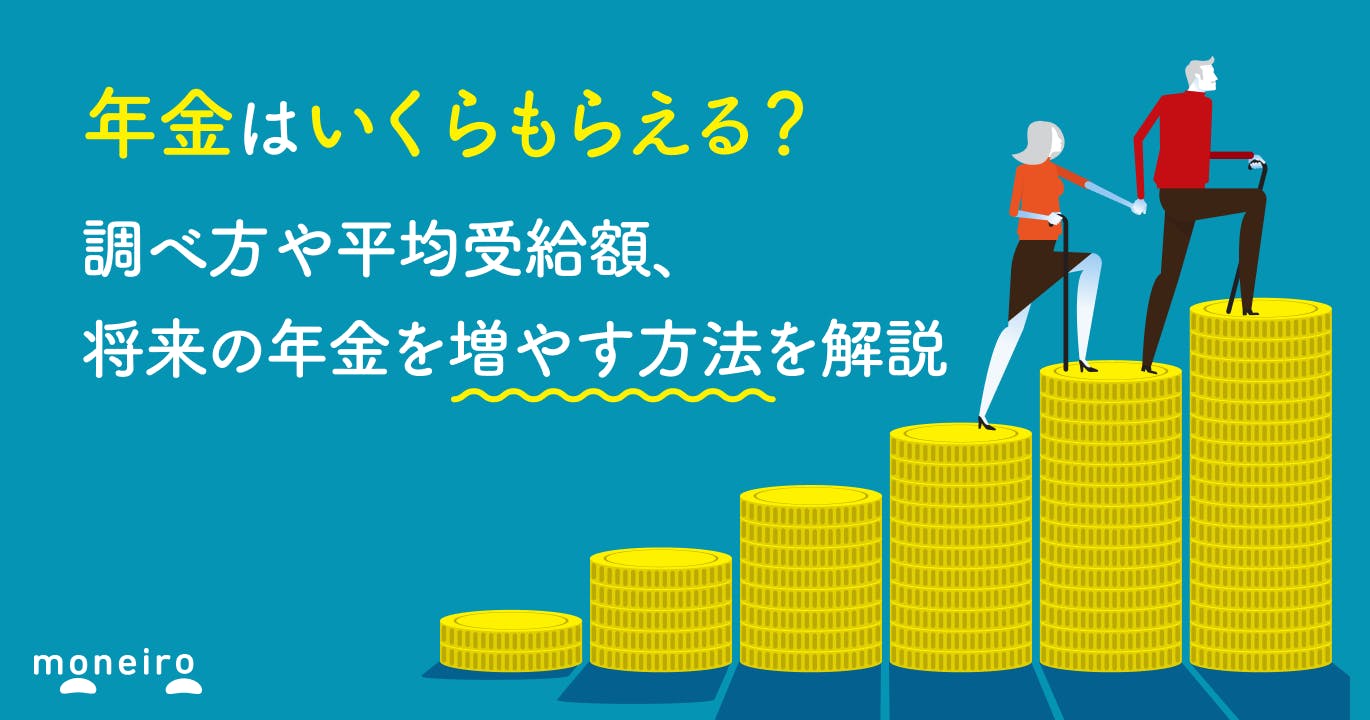
年金はいくらもらえる?調べ方や平均受給額、将来の年金を増やす方法を解説
監修
森本 由紀
- ファイナンシャルプランナー/AFP(日本FP協会認定)/行政書士
行政書士ゆらこ事務所(Yurako Office)代表。愛媛県松山市出身。神戸大学法学部卒業。法律事務所事務職員を経て、2012年に独立開業。メイン業務は離婚協議書作成などの協議離婚のサポート。離婚をきっかけに自立したい人や自分らしい生き方を見つけたい人には、カウンセリングのほか、ライフプラン、マネープランも含めた幅広いアドバイスを行っている。法律系・マネー系サイトでの記事の執筆・監修実績も多数。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。