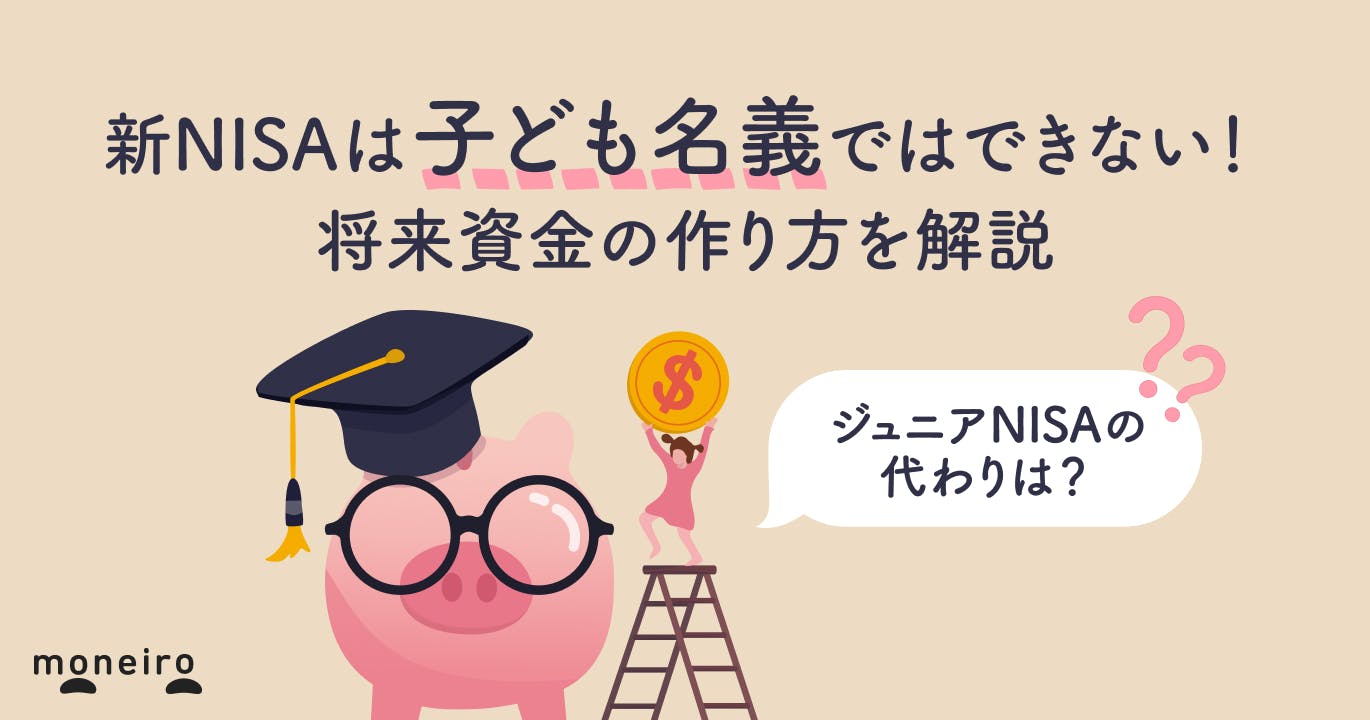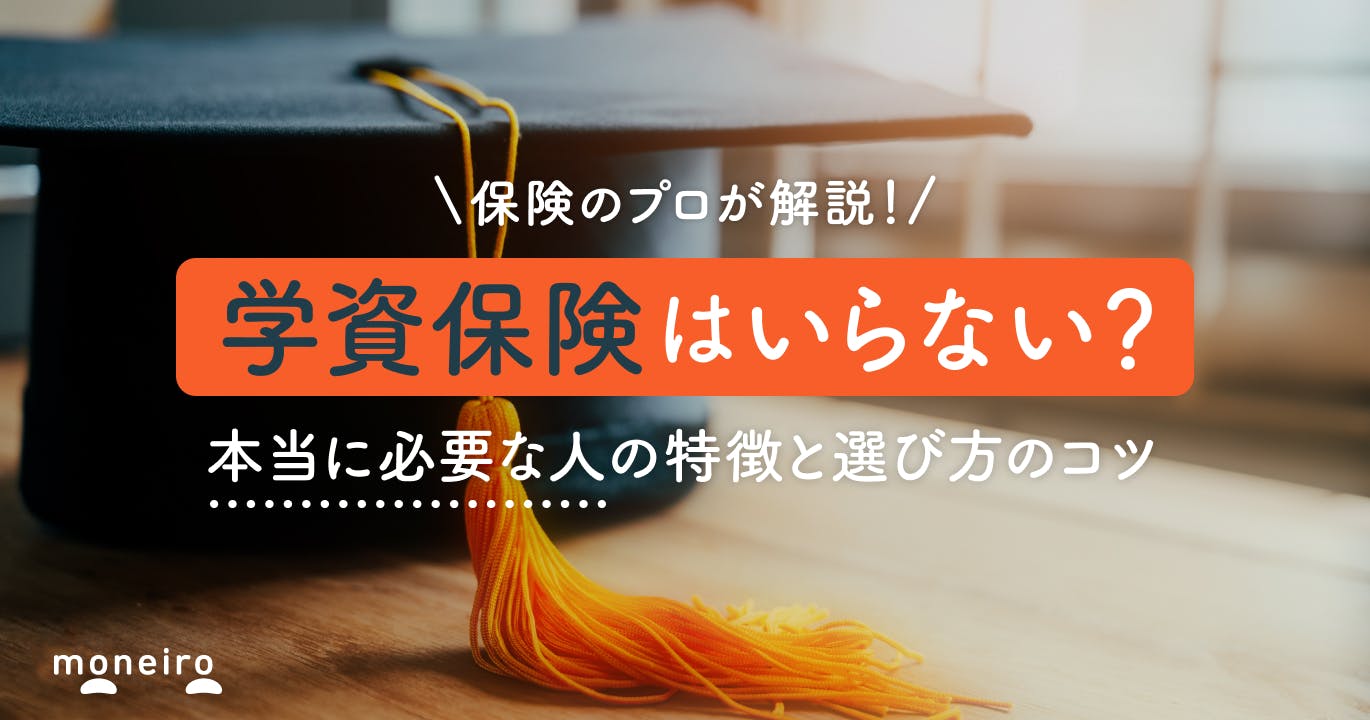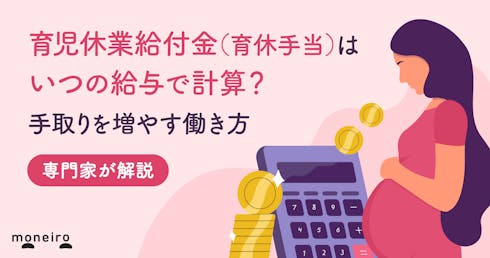
【2025年】出生後休業支援給付金とは?自分は対象?金額・申請方法をわかりやすく解説
無料診断:将来必要な金額が3分でわかる
「2025年4月から始まる出生後休業支援給付金とは?」「給与の実質10割カバーされるって本当?」そんな疑問を抱えている人も多いのではないでしょうか。
この給付金は共働き・共育てを支援するため、子の出生後に両親が14日以上育休を取った場合、育児休業給付金に加え、「出生後休業支援給付金」が最大28日間支給されます。
本記事では、出生後休業支援給付の仕組みから、もらえる条件、計算方法、そして他の給付金との違いについて、専門家がわかりやすく解説します。
(参考:出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金の創設について (令和7年4月1日))
(参考:育児休業等給付の内容と支給申請手続|厚生労働省)
- 出生後休業支援給付金とは育児休業給付金に上乗せされる給付金のこと
- 出生後休業支援給付金を含む育児休業等給付は非課税
- 出生後休業支援給付金が加算されることで、(または出生時育児休業給付金)と併せて実質「休業前賃金の10割」をカバー※上限あり
子育てのお金が気になるあなたへ
これから先、教育資金で困ることのないよう、将来必要な額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶夫婦で考えるお金の基本セミナー:ライフステージごとのお金の管理がわかる
▶2025年に変わるお金の制度セミナー:お金に関する最新の制度をやさしく解説
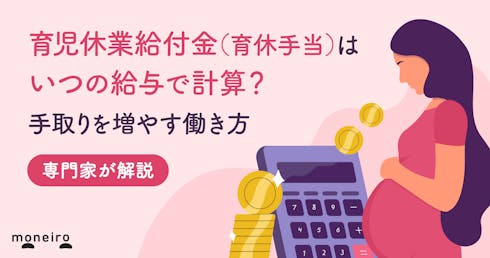

出生後休業支援給付金とは
2025年4月1日から、育児休業を取得する夫婦への新たな支援策として「出生後休業支援給付」が創設されました。
制度の目的と背景
出生後休業支援給付金制度の主な目的は、「共働き・共育て」を推進するために、子の出生直後の一定期間に、両親ともに育児休業を取得した場合に支援を行うことです。
特に男性の育児休業取得率の向上を図り、夫婦の家事・育児分担を支援することを目指しています。
これは、育児・介護休業法の改正により設けられた「出生時育児休業(産後パパ育休)」と連動する給付金です。
実質「休業前賃金の10割」カバーの仕組み
この給付金は、休業前賃金が実質10割カバーされる点が大きな特徴です。
育児休業開始から180日目までに支給される育児休業給付金(または出生時育児休業給付金)は休業開始時賃金日額の67%であるため、実質的な手取り額は休業前より減少します。
しかし、出生後休業支援給付金(休業開始時賃金日額の13%)を加算すると、休業前賃金の約8割が支給されることになります。
育児休業中は健康保険料・厚生年金保険料が免除、雇用保険料なし、給付金は非課税で給付金の全額が手取りとなるため、手取り収入は休業前とほぼ同額です。
ただし、休業開始時賃金日額には上限額(2025年4月1日時点:1万5690円|毎年8月1日に改定)がある点に留意が必要です。
従来の育児休業給付金との違い
出生後休業支援給付金は、従来の育児休業給付金とは対象期間や目的が異なります。

あなたはもらえる?支給要件と対象確認チェックリスト
出生後休業支援給付金をもらうためには、受給者本人と、対象となる子について、いくつかの具体的な条件を満たす必要があります。
支給対象者(雇用保険加入者など)の条件
・同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休(夫)を通算して14日以上取得したこと (妻の場合、育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと)
・休業期間中の賃金が、休業開始前賃金の80%以下であること
・休業期間中の就業日数が10日以下であること(10日を超える場合は給付金が減額・不支給)
支給対象期間(子の出生後8週間以内)と支給日数
給付金の支給対象となる休業は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から、「遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間内(妻は育児休業開始から8週間以内)に取得されたものが対象です 。
この期間内で、最大28日間(4週間)の休業が支給の対象となります 。
支給対象外となるケース
以下のような場合には、出生後休業支援給付金は支給されません。
・休業期間中の賃金が、休業開始前賃金の80%を超える場合
・休業期間中の就業日数が10日を超える場合 (不支給または減額)
・支給申請の期限を過ぎた場合
・出生時育児休業給付金または育児休業給付金が不支給となった場合
・2025年4月1日より前に取得した出生時育児休業または育児休業
出生後休業支援給付金の支給額と計算方法
実際にこの給付金がいくらもらえるのか、具体的な計算方法を見ていきましょう。
給付金の計算方法と支給上限・下限額
支給額は「休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数(28日が上限) × 13%」で計算されます。
「休業開始時賃金日額」は、最初の出生時育児休業または育児休業、産前産後休業の開始前直近6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額です。
なお、支給日数が28日の場合の支給上限額と支給下限額は次のとおりです。
所得税・社会保険料の取扱い
出生後休業支援給付金を含む育児休業等給付は非課税です。所得税も住民税もかかりません。
また、育児休業中は申し出により健康保険料・厚生年金保険料が免除され、勤務先から給与が支給されない場合は雇用保険料の負担もありません。
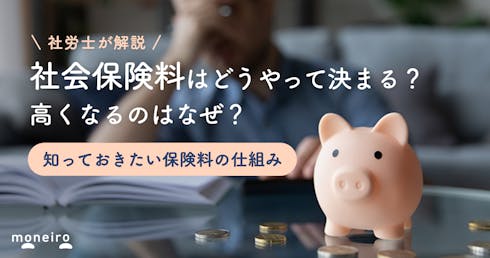
出生後休業支援給付金の申請の流れと必要書類
給付金を確実に受け取るためには、適切な申請手続きを行う必要があります。
会社が対応する手続きと本人が用意する書類
出生後休業支援給付金の支給申請は、原則として出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行うことになります。
会社が従業員に代わってハローワークに申請手続きを行います。
また、本人が用意する必要書類は、一般的には以下の書類です。
・住民票の写し(世帯全員分)
など
出生後休業支援給付金の申請の流れと必要書類
原則として、(出生時)育児休業開始日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月の末日までに申請が必要です。
出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請後に、出生後休業支援給付金の支給申請を別途行うことも可能ですが、その場合は、育児休業給付金が支給された後の申請になります。
勤務先の事業主(会社)経由で、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出します。
他の給付金との違いと併給の注意点
出産・育児に関わる給付金は複数あります。出生後休業支援給付金と、他の給付金との違いを理解し、夫婦で制度を上手く活用する方法を考えましょう。
出産手当金(産前産後休業中)
・出産日以前42日・出産後56日間が対象
・標準報酬月額(休業前12ヶ月の平均額)の67%相当
健康保険から支給される、出産で休業中の女性の収入を保障する給付金です。出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)、出産日後56日までの範囲で支給されます 。
給付率は原則として標準報酬月額(休業前12ヶ月の平均)の67%相当です。
.jpg?w=490&fit=crop&crop=faces&auto=compress,format)
育児休業給付金(育児休業中)
・支給額は賃金の67%(6ヶ月以降は50%)
雇用保険から支給される、育児休業中の収入を保障する給付金です。原則として子が1歳になるまで(最長2歳まで延長可能)支給されます。
給付率は休業開始後6ヶ月(180日)までは休業開始時賃金日額の67%、それ以降は50%です。
出生後休業支援給付金のよくある疑問
給付金に関する、よくある具体的な疑問とその回答をまとめました。
Q.配偶者が専業主婦(無職)の場合でも対象になる?
A. はい、夫(父親)がこの給付金を受ける場合、配偶者(母親)が専業主婦や無職の場合でも対象になります。
この制度の要件の一つである「配偶者の育児休業を要件としない場合」に、配偶者が無業者や雇用される労働者でない場合が含まれるためです。
Q.2025年3月生まれの子は対象外?
A. いいえ、2025年3月生まれの子どもも支給対象になる可能性があります。 この給付金は、2025年4月1日以降に取得した「出生時育児休業」「育児休業」が対象となります。
そのため、2025年3月に生まれた子であっても、2025年4月1日以降に取得した出生後8週間以内の「出生時育児休業」(妻の場合、休業開始から8週間以内の育児休業)を取得すれば、支給対象となり得ます。
Q.短期間だけ休んだ場合ももらえる?
A. はい、通算して14日以上の休業を取得すれば支給対象となります 。短期間の休業でも活用できる点が特徴です。
まとめ
「出生後休業支援給付金」は、2025年4月1日から始まる、出産直後の男性育休(産後パパ育休)を強力に支援する新しい給付金(働く女性も支援します)です。
休業前賃金の実質10割が手取りでカバーされるため、育児休業を取得する上での経済的なハードルを下げます。
支給を受けるには、雇用保険の加入や、子の出生後8週間以内に14日以上休業するなどの要件があります。
出生後休業支援給付金は、出産手当金や育児休業給付金とは異なる特徴がありますが、これらを組み合わせることで、夫婦で協力して育児休業を効果的に取得することができます。
夫婦で育休の取り方を話し合い、新たな給付金を上手に活用することで、家事や育児の分担が進み、家庭全体の生活の質を高めることにつながります。
子育てのお金が気になるあなたへ
これから先、教育資金で困ることのないよう、将来必要な額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶夫婦で考えるお金の基本セミナー:ライフステージごとのお金の管理がわかる
▶2025年に変わるお金の制度セミナー:お金に関する最新の制度をやさしく解説
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。