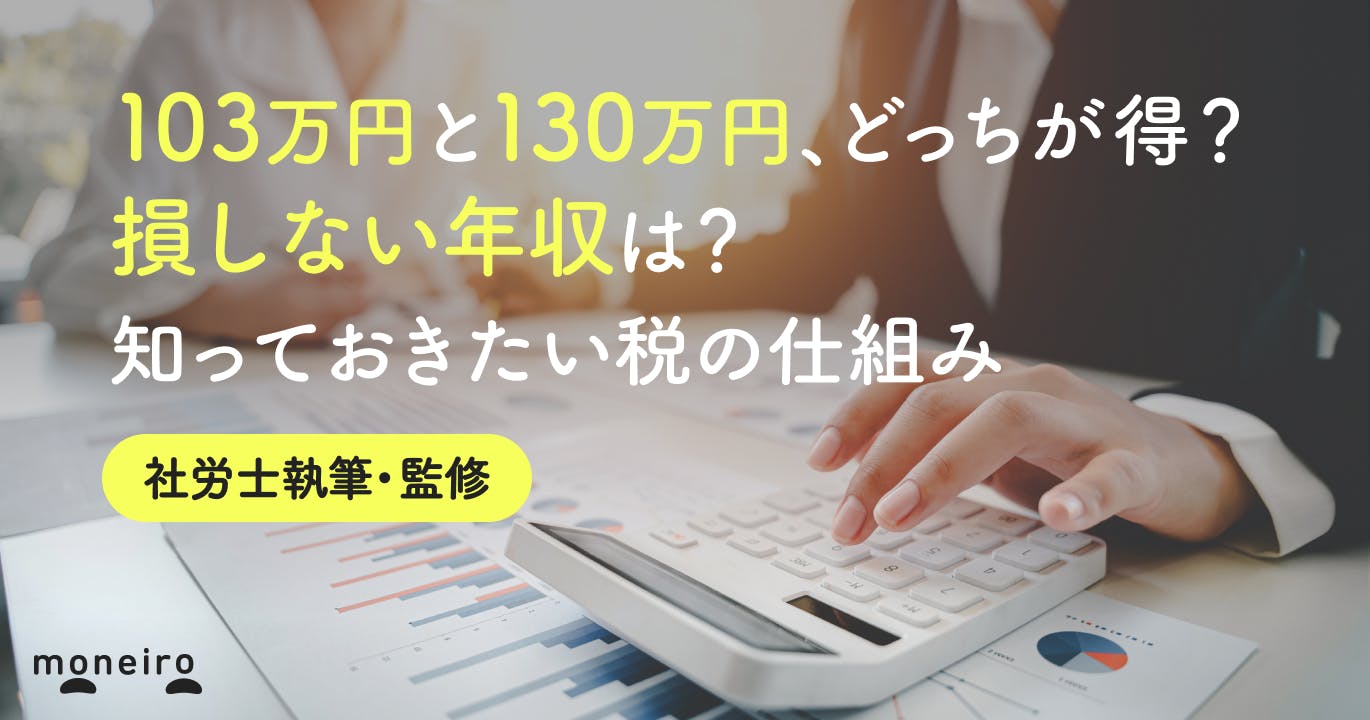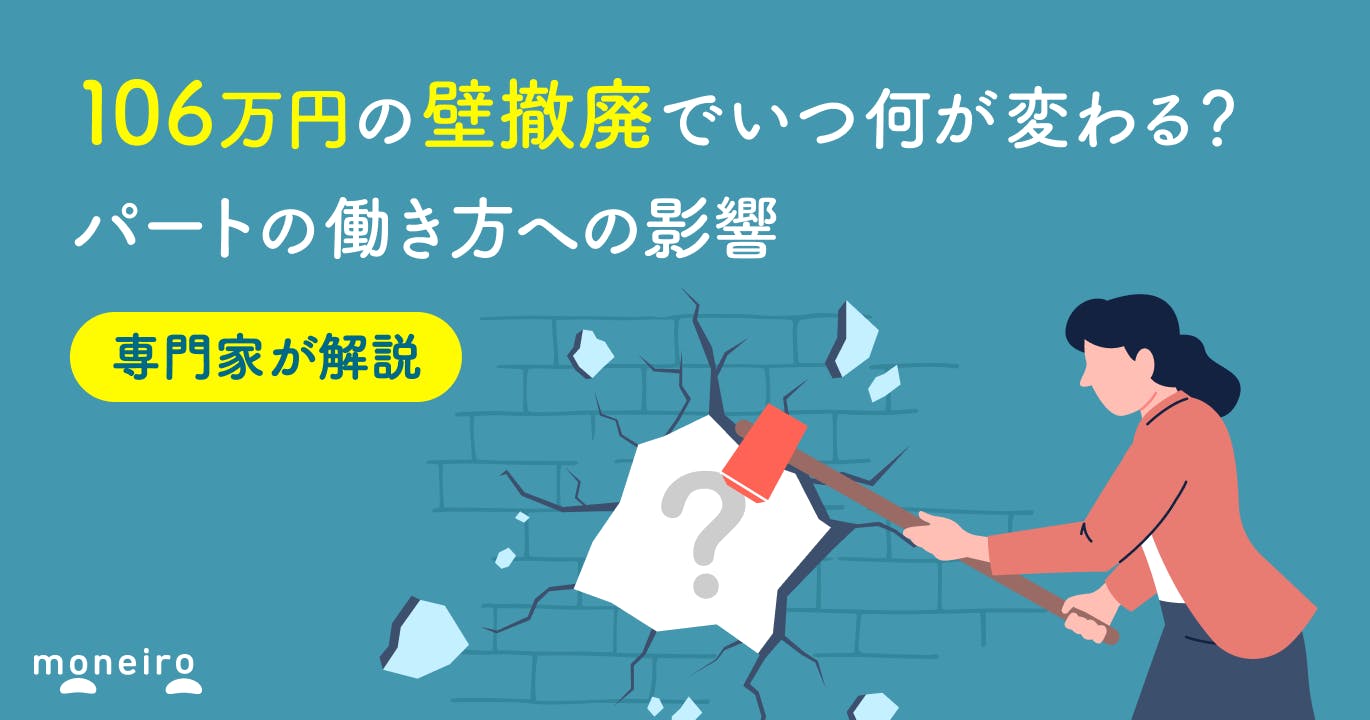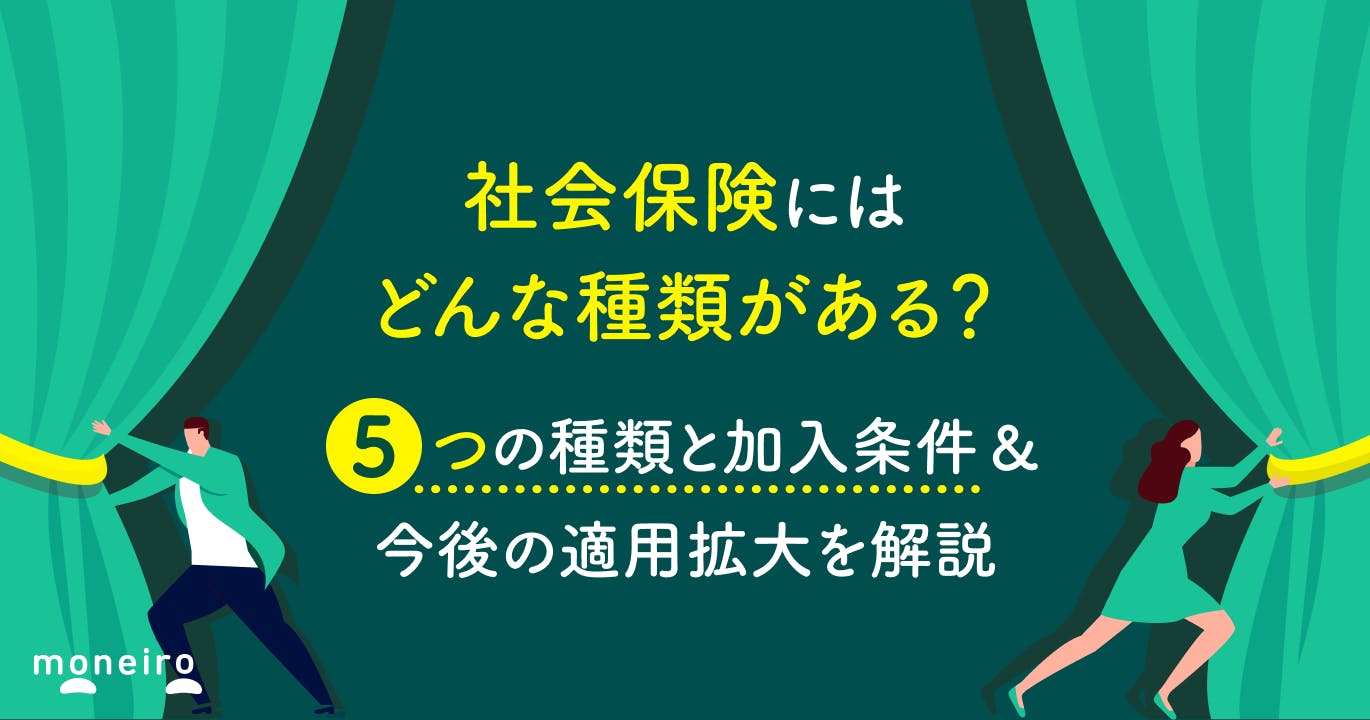
社会保険料は4~6月の給与で決まる?社労士が仕組みと注意点をわかりやすく解説
»社会保険料負担が不安…まずは将来資金を簡単診断
社会保険料は毎月給与から天引きされますが、その金額は実は「4月から6月に受け取る給与」で決まる仕組みになっています。
「なぜこの3ヶ月だけが基準になる?」と不思議に思った人も多いかもしれません。これは標準報酬月額を決める「定時決定」という制度によるもので、残業代や手当の増減が大きいと翌年1年間の保険料に影響することもあります。
本記事では、4~6月の給与と社会保険料の関係をわかりやすく解説するとともに、残業代が増えた場合のシミュレーションやメリット・デメリット、保険料を抑える工夫や会社での手続きの流れまで専門的に整理しました。
- 社会保険料が決まる「標準報酬月額」の仕組み
- 4月~6月の給与が1年間の保険料に与える影響
- 社会保険料が上がることのメリット・デメリット
社会保険料の負担が気になっているあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶2025年に変わるお金の制度セミナー:制度変更と対策がわかる
社会保険料はどう決まる?基本の仕組み
社会保険料は「標準報酬減額」という基準額を用いて計算します。社会保険料の計算方法と手取り収入への影響について解説します。
社会保険料は「標準報酬月額」で計算される
社会保険料を計算する際の基準となるのが「標準報酬月額」です。これは、毎月の給与などを一定の幅で区切った等級に当てはめて決められる基準額を指します。
健康保険は1等級から50等級、厚生年金は1等級から32等級に区分されています。実際の給与額を等級表に当てはめ、その等級に対応する金額が標準報酬月額となります。
この仕組みにより、給与が多少変動しても毎回計算し直す必要がなく、一定期間は同じ保険料が適用されます。
給与と手取りへの影響
標準報酬月額が上がると、それに比例して毎月の社会保険料も増え、給与から天引きされるため手取り額は減ります。
特に、基本給が変わらず一時的な残業代の増加で等級が上がった場合でも、その後1年間は手取りが減る可能性があります。
また、健康保険料や厚生年金保険料は会社と従業員が折半して負担する仕組みです。給与明細に載っているのは従業員負担分のみですが、企業も同額を支払っており、保険料の増加は企業の法定福利費の増加にも直結します。
なぜ4月から6月の給与が基準になるのか
社会保険料の基準となる標準報酬月額は、年に一度すべての被保険者を対象に見直されます。この手続きを「定時決定」と呼びます。
毎年7月1日時点に在籍している全被保険者を対象に、「算定基礎届」を年金事務所へ提出します。
具体的には、4月・5月・6月の3ヶ月間に支払われた給与の平均額を算出し、それを「標準報酬等級表」に当てはめて新しい標準報酬月額を決定します。これにより、昇給や労働時間の変動などによって生じた実際の給与と標準報酬月額のズレを調整します。
そのため、4〜6月の給与額は、その後1年間の社会保険料を左右する重要な基準となります。
1年間の保険料を安定させるための制度設計
定時決定で決まった標準報酬月額は、原則9月から翌年8月までの1年間固定されます。これにより、給与が多少変動しても社会保険料は毎月一定となります。
もし給与の変動ごとに保険料を再計算する仕組みであれば、事務は煩雑になります。定時決定はその煩雑さを避けつつ、年1回の見直しで保険料を実態に合わせる合理的な制度です。
この「1年間固定」というルールがあるため、基準となる4〜6月の給与はその後の手取り額に大きく影響します。
残業代や手当が多いとどう影響する?
標準報酬月額の基準となる「報酬」には基本給だけでなく残業手当や通勤手当、住宅手当、役職手当など、労働の対価として支給されるものが含まれます。
そのため、4〜6月に残業が増えると平均報酬額が押し上げられ、より高い等級の標準報酬月額が設定され、9月以降の社会保険料が1年間高くなる可能性があります。
特に給与を翌月払いにしている企業では、3〜5月の残業が4〜6月の給与に反映されるため、年度末の働き方が保険料に直結する点に注意が必要です。
ボーナスは対象外、月収だけが反映される
定時決定で使う標準報酬月額の計算において、年3回以下の頻度で支給されるボーナス(賞与)は、「報酬」には含まれません。4月から6月の間に賞与が支給されたとしても、その金額が9月以降の月々の社会保険料を直接引き上げることはありません。
一方、賞与には、「標準賞与額」という別の基準が適用され、支給される都度、その金額に応じた社会保険料が徴収される仕組みになっています。
ただし、年4回以上支給される賞与は、給与(報酬)の一部とみなされ、標準報酬月額の計算基礎に含まれるため注意が必要です。自社の賞与の支給回数を確認しておくことが大切です。
シミュレーション例
4月〜6月の残業代が社会保険料にどの程度影響するか、具体例で見てみましょう。
現在の標準報酬月額が30万円の方が、残業で4月〜6月の平均報酬月額が34万円になった場合、新しい標準報酬月額は34万円の等級に上がります。
その結果、健康保険料と厚生年金保険料の従業員負担は月に数千円増となり、この保険料の負担増は9月から翌年8月まで1年間続きます。
このように、春先の数ヶ月の働き方が、その後の手取りに大きく影響する点を理解しておくことが大切です。
社会保険料が上がるメリットとデメリット
4月から6月の給与が増え、社会保険料が上がることには、手取りが減るという短期的なデメリットがある一方で、将来受け取れる公的な給付が増えるという長期的なメリットも存在します。
健康保険からの傷病手当金や出産手当金、そして老後の生活を支える厚生年金の受給額は、いずれも納めてきた保険料の基準となる標準報酬月額に基づいて計算されます。
そのため、目先の手取り額だけでなく、将来の保障という視点も持って、両者のバランスを考えましょう。
傷病手当金や出産手当金など給付額が増えるメリット
社会保険料が上がることの大きなメリットの一つは、健康保険から支給される各種手当金の受給額が増えることです。
業務外の病気や怪我で長期間仕事を休んだ場合に支給される「傷病手当金」や、出産のために会社を休んだ際に支給される「出産手当金」の金額は、過去の標準報酬月額の平均額を基に計算されます。
目先の保険料負担は増えますが、万が一の際の生活保障が充実するという点は、長期的な視点で見ると大きな安心材料と言えるでしょう。
将来の年金受給額が増える
社会保険料の負担増は、将来受け取る老齢厚生年金の増額につながります。年金額は、加入期間と標準報酬月額(および標準賞与額)を基に算出されるため、標準報酬月額が高い期間が長いほど受給額も多くなります。
同様に、障害厚生年金や遺族厚生年金も標準報酬月額を基準に計算されます。短期的には手取りが減るものの、長期的には老後や不測の事態の備えとなるでしょう。
手取りが減るデメリットとのバランス
社会保険料が上がることの最も直接的なデメリットは、毎月の給与から天引きされる金額が増え、手取り額が減少することです。特に、基本給などの固定給は変わらず、一時的な残業代の増加によって標準報酬月額が上がった場合、その後1年間は給与の額面と手取り額に乖離を感じるかもしれません。
将来の給付が手厚くなるというメリットがある一方で、現在の生活資金が圧迫されるというデメリットも存在します。そのため、一概にどちらが良いとは言えません。
大切なのは、このメリットとデメリットを天秤にかけ、自身のライフプランや価値観に基づいて働き方を選択することです。
社会保険料の負担が気になっているあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶2025年に変わるお金の制度セミナー:制度変更と対策がわかる
社会保険料を抑えるためにできる工夫はある?
社会保険料は法律で定められているため、意図的に安くすることはできません。しかし、仕組みを理解した上で、結果的に負担を抑えることにつながる工夫はいくつか考えられます。
最も直接的なのは、標準報酬月額の基準となる4月から6月の残業を調整することです。ただし、これは将来の給付額が減る可能性と表裏一体であるため、慎重な判断が求められます。
短期的な節約と、長期的な保障のバランスをどう取るかが重要なポイントになります。
4~6月の残業・手当の調整
社会保険料の負担を抑える最も直接的な方法は、標準報酬月額の計算期間である4月から6月に支払われる給与額を調整することです。
具体的には、この期間の残業時間を意識的に減らすことが考えられます。業務に支障が出ない範囲で、他の時期に残業を分散させるなどの工夫ができれば、この3ヶ月間の平均報酬額を抑え、結果として標準報酬月額の上昇を防ぐことにつながります。
ただし、これはあくまで業務スケジュールをコントロールできる場合に限られます。
また、会社によっては残業代が翌月払いとなるため、その場合は3月から5月の残業が対象となる点に注意が必要です。
転職や昇給タイミングへの注意点
社会保険料の決定タイミングは、転職や昇給といったキャリアイベントを考える上でも一つのポイントになります。
例えば、6月1日以降に入社した場合、その年の定時決定(4月~6月の給与を基にする見直し)の対象外となります。入社時に決まった標準報酬月額が、翌年の8月まで適用されることになります。
また、昇給のタイミングが4月から6月と重なると、その昇給分が標準報酬月額に反映され、9月からの社会保険料が上がることになります。
昇給時期を調整できるのであれば、7月以降にすることで、その年の定時決定への影響を避けることができます。
ただし、これはあくまで制度上の話であり、実際には、会社の給与改定サイクルなどに制約を受けます。
短期的な節約と将来の給付をどう考えるか
4月から6月の残業を調整することで社会保険料を抑えることは、短期的に見れば手取り額を増やす有効な手段です。しかし、これは同時に、将来受け取る年金や傷病手当金などの公的給付が減ることにもつながります。
社会保険料は単なるコストではなく、将来の自分や家族のための「保険」という側面も持っています。目先の節約を優先するあまり、いざという時の保障が手薄になってしまっては本末転倒です。
どちらが正解ということはなく、個々のライフステージや価値観によって最適なバランスは異なります。若いうちは手取りを重視し、年齢を重ねるにつれて将来の保障を手厚くするなど、長期的な視点で自身のキャリアプランやライフプランと照らし合わせて考えることが賢明と言えるでしょう。
会社で行う手続きと改定の流れ
社会保険料の改定は、会社が行政機関へ所定の手続きを行うことで実施されます。毎年7月には、全従業員の4月から6月の給与を基に「算定基礎届」を提出し、これによって9月からの新しい保険料が決定します。
また、昇給や降給などで給与が大きく変動した場合は、その都度「随時改定」の手続きが必要です。
これらの手続きの流れを理解しておくことで、給与明細の変動についても納得感を持つことができるでしょう。
算定基礎届の提出(7月)
事業主は、毎年7月1日から10日までに、管轄の年金事務所へ「算定基礎届」を提出する義務があります。この届出には、7月1日時点で在籍する全被保険者の4〜6月に支払った報酬額などを記載します。
提出内容をもとに日本年金機構が各従業員の新しい標準報酬月額を決定し、この一連の流れを「定時決定」と呼びます。
この届出は、従業員一人ひとりの9月以降1年間の社会保険料を決める基礎となるため、企業には正確かつ期限内の手続きが求められます。
9月から新しい保険料が適用される
7月に提出された算定基礎届によって決定された新しい標準報酬月額は、その年の9月分から翌年8月分までの社会保険料に適用されます。
ただし、多くの企業では社会保険料を「翌月徴収(前月分を当月給与から控除)」しているため、実際に給与から天引きされる保険料額が変わるのは10月支給分の給与からとなるのが一般的です。
会社によっては「当月徴収」を採用している場合もあり、その場合は9月支給分の給与から新しい保険料が適用されます。
秋頃に手取り額が変わったと感じたら、この定時決定による社会保険料の改定が影響している可能性が高いでしょう。給与明細の控除欄を確認しましょう。
昇給・降給時の「随時改定」とは
「随時改定」とは、定時決定を待たずに標準報酬月額を見直す仕組みのことです。昇給や降給などによって固定的賃金に大きな変動があった場合に適用されます。
随時改定が行われるのは、以下の3つの条件をすべて満たした場合です。
- 昇給や降給などで固定的賃金に変動があった
- 変動後の3ヶ月間の平均給与から算出した標準報酬月額が、以前と比べて2等級以上の差が生じた
- その3ヶ月間とも、給与支払いの基礎日数が17日以上ある
この条件に該当した場合、会社は「月額変更届」を提出します。改定後の新しい標準報酬月額は、賃金が変動した月から4ヶ月目に適用され、次の定時決定(8月)まで、または再度随時改定が行われるまで使用されます。
4月から6月の報酬と社会保険料に関するよくある質問
4月から6月の報酬と社会保険料に関して、特によく寄せられる質問について回答します。
パートやアルバイトの場合はどうなる?
パートやアルバイトの場合でも、週の所定労働時間や月額賃金などの要件を満たし、社会保険に加入している場合は、正社員と同様に定時決定の対象となります。
4月から6月に支払われた給与の平均額を基に標準報酬月額が算出され、9月以降の社会保険料が決定されます。
そのため、この期間のシフトを増やすなどして収入が上がると、社会保険料も変動する可能性があります。
育休・産休中の取り扱いは?
産前産後休業や育児休業の期間中は、申し出により社会保険料の支払いが免除されます。
また、休業から復帰した後、時短勤務などで給与が下がった場合には、特例として標準報酬月額を見直すことができます。これは「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出することで適用され、復帰後の3ヶ月間の給与平均を基に新しい標準報酬月額が決定されます。
これにより、給与が下がったにもかかわらず高い保険料を払い続けるという事態を避けることができます。
扶養に入っている場合は関係ある?
配偶者などの社会保険の扶養に入っている場合、自身で社会保険料を納付する必要はありません。そのため、4月から6月の給与額によって自身の保険料が変動するということはありません。
ただし、注意が必要なのは、収入が扶養の範囲を超えてしまうケースです。4月から6月の収入が増えたことで年収が扶養の基準額(いわゆる「年収の壁」)を超えると、扶養から外れて自身で社会保険に加入し、保険料を支払う必要が出てきます。
まとめ
社会保険料は、4月~6月の報酬平均で決まる「標準報酬月額」を基準に算出し、9月から1年間適用されます。
この期間の残業代が増えると、標準報酬月額が上がり手取りは減りますが、将来の年金や傷病手当金が増えるメリットもあります。
この仕組みを正しく理解し、短期的な手取り額と長期的な保障のバランスを考えながら、ご自身のライフプランに合った働き方を検討しましょう。
»社会保険料、払いすぎてない?今すぐ将来資金をチェック
社会保険料の負担が気になっているあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶2025年に変わるお金の制度セミナー:制度変更と対策がわかる
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。
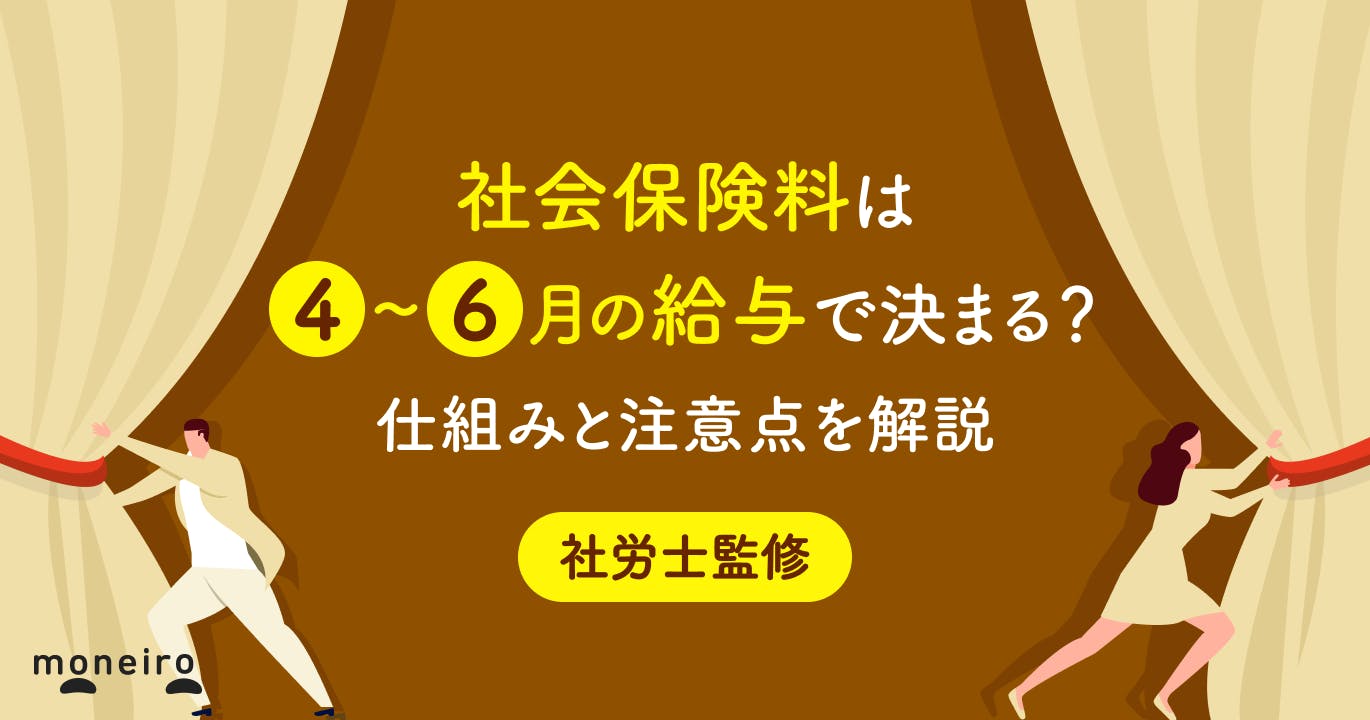
.jpg?w=1370&h=720&fit=crop&crop=faces&auto=compress,format)