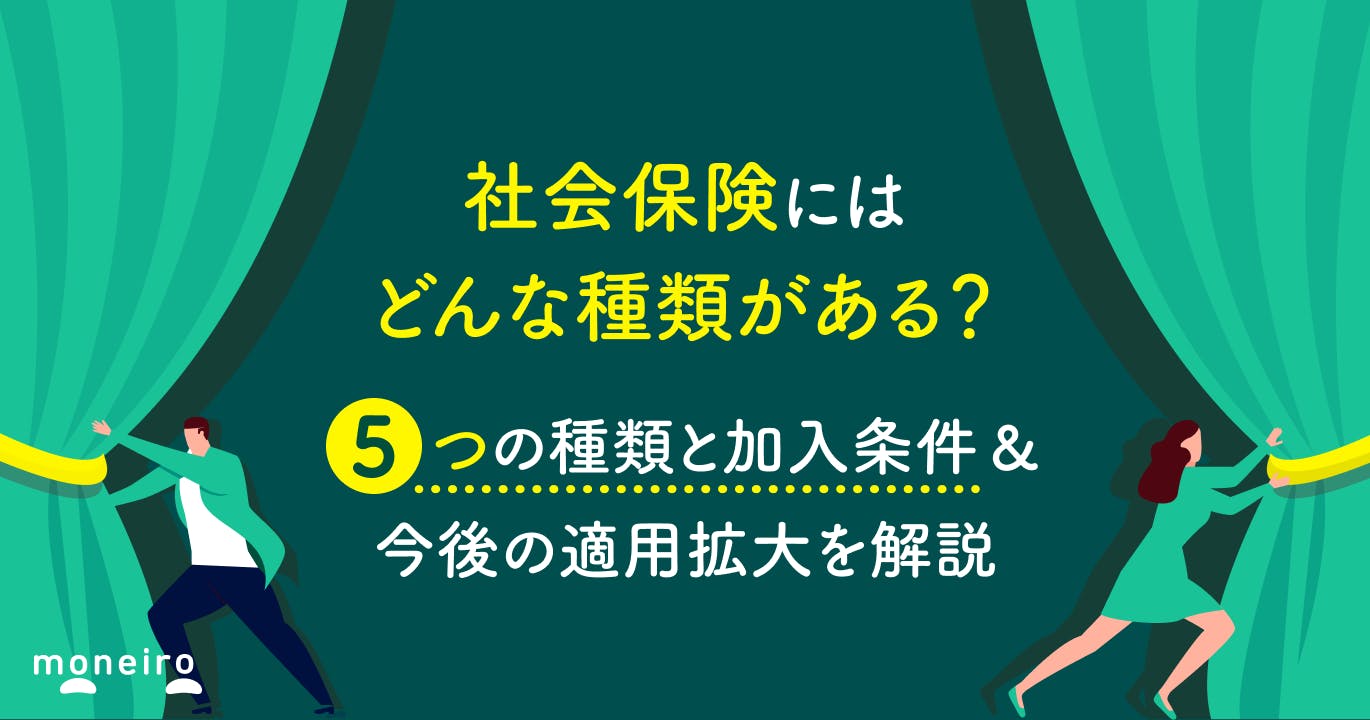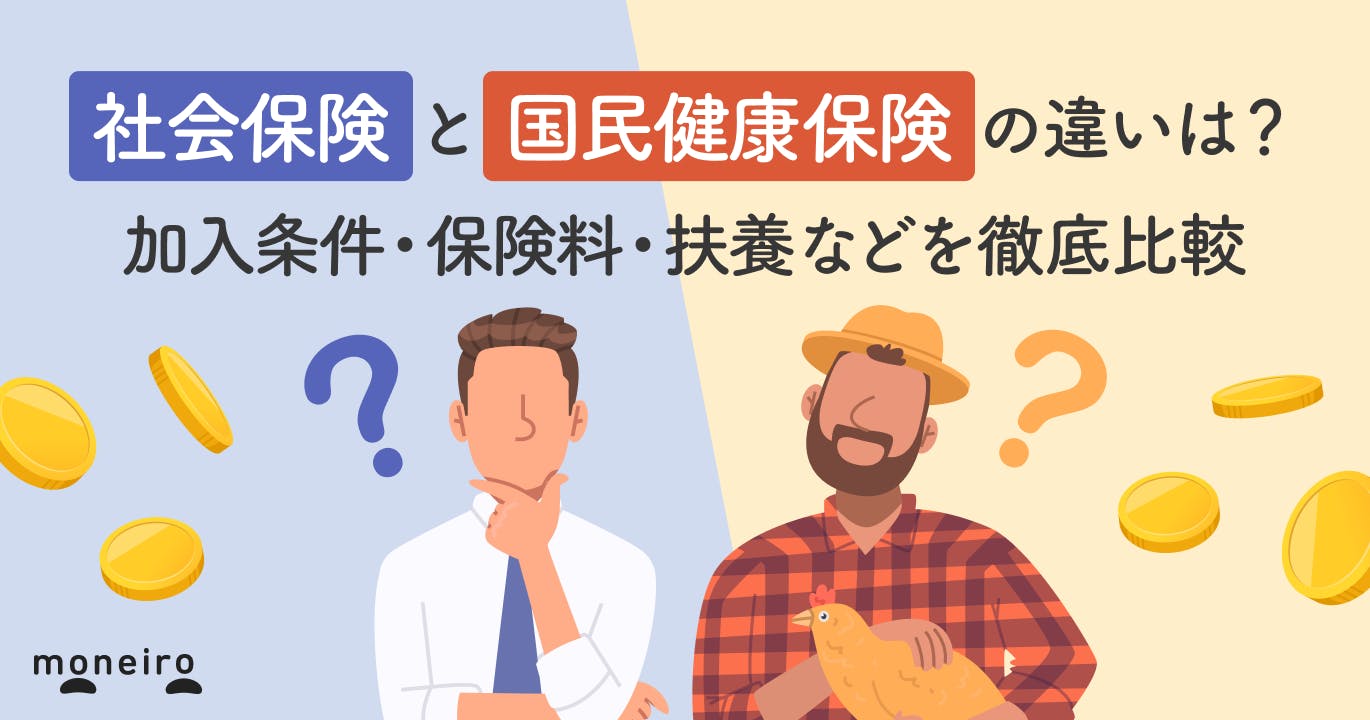
社会保険にはどんな種類がある?5つの種類と加入条件&今後の適用拡大を解説
>>将来の備えは大丈夫?あなたの老後に必要なお金を診断
「社会保険にはどんな種類があるの?」「自分の働き方だとどの保険に入るべき?」そうした疑問をお持ちではないでしょうか。日本では、私たち一人ひとりの生活を支えるために、さまざまな社会保険制度が設けられています。
本記事では、健康保険や厚生年金保険をはじめとする5つの主要な社会保険の種類をわかりやすく解説。さらに、働き方別の加入条件の違いや、近年注目される扶養の壁、そして今後の適用拡大についても詳しく解説します。
- 社会保険の5つの主要な種類とそれぞれの制度内容
- 働き方別の社会保険の加入条件や今後の適用拡大について
- 自分の加入している社会保険の確認方法や退職時・未加入時の対処法
社会保険が気になるあなたへ
長い人生、将来の負担はさまざまです。老後必要になる金額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶夫婦で考えるお金の基本セミナー:ライフステージごとのお金の管理がわかる
社会保険とは?5つの種類を解説
社会保険とは、病気、ケガ、失業、老齢、介護といった生活上のリスクに対し、国民が相互に支え合うことで生活の安定を図る公的な保険制度の総称です。
社会保険には、主に「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険(労働者災害補償保険)」の5つの種類があります。以下でそれぞれ詳しく解説します。
健康保険
業務外の病気やケガ、出産、死亡といった事態に備え、加入者とその家族の生活を保障する制度が健康保険です。
病気やケガで医療機関を受診した際の医療費負担を軽減するだけでなく、病気やケガで仕事を休んだ場合に支給される傷病手当金や、出産時に支給される出産手当金、出産育児一時金などの具体的な給付も含まれます。これらの給付は、予期せぬ事態によって収入が途絶えたり、高額な医療費が必要になったりした場合に、生活を支える重要な役割を担っています。
会社員やパートタイマーなどが加入する健康保険には、主に中小企業の従業員が加入する「協会けんぽ」と、大企業の従業員などが加入する「健康保険組合」の2種類があります。
厚生年金保険
厚生年金保険は、国民年金(基礎年金)に上乗せして給付される年金制度です。
日本の年金制度は「2階建て」と例えられ、全国民が共通で加入する国民年金が1階部分、会社員や公務員が加入する厚生年金保険が2階部分にあたります(これに、企業年金やiDeCoなどの私的年金が該当する「3階部分」も加えて「3階建て」といわれることもあります)。
厚生年金には、将来、高齢になって収入が減った際に受け取れる老齢厚生年金だけでなく、病気やケガで障害を負った場合に受け取れる障害厚生年金や、加入者が亡くなった際に遺族が受け取れる遺族厚生年金もあります。これにより、現役世代の保険料が、高齢者や障害を抱える人、そして遺族の生活を支える仕組みとなっています。
介護保険
介護保険は、高齢化社会が進む日本において、介護が必要になった際に安心してサービスを利用できるようにするための制度です。原則として40歳になると加入が義務付けられ、保険料の納付が始まります。
加入者が要介護認定または要支援認定を受けた場合に、訪問介護やデイサービス、特別養護老人ホームといった多様な介護サービスを費用の一部負担で利用できます。
この制度は、高齢者やその家族の経済的・身体的負担を軽減し、誰もが住み慣れた地域で尊厳をもって生活を続けられるよう支援することを目的としています。
雇用保険
雇用保険は、働く人々の雇用の安定と促進を目的とした制度です。
労働者が失業した場合に生活を保障するための基本手当(失業給付)が代表的ですが、他にも育児休業を取得した際に支給される育児休業給付や、介護休業を取得した場合の介護休業給付など、さまざまな給付があります。これらは、労働者が離職した場合や、職業訓練を受ける場合、キャリアアップを目指す場合など、多岐にわたる状況で活用されます。
また、事業主に対しては、雇用の維持や労働者の能力開発を支援する助成金なども提供され、労働市場全体の安定に寄与しています。
労災保険(労働者災害補償保険)
労災保険(労働者災害補償保険)は、労働者が業務中や通勤中に発生した傷病、障害、死亡に対して給付を行う制度です。
この保険は、事業主が全額保険料を負担することが最大の特徴であり、労働者側が保険料を支払うことはありません。労働者が仕事や通勤が原因で事故に遭ったり、病気になったりした場合に、医療費や休業補償、障害補償、遺族補償などが支給されます。
これにより、労働者は安心して働くことができ、万が一の事態が発生しても生活が守られるようになっています。
働き方別・社会保険の加入条件
社会保険の加入条件は、働き方によって異なります。正社員、契約社員、パート・アルバイトといった雇用形態や、労働時間、月収、企業の規模など、いくつかの要素が複雑に絡み合って加入の可否が決まります。
働き方に合わせて、どのような社会保険に加入できるのか、あるいは加入義務があるのかを正しく理解しておきましょう。
正社員・契約社員などフルタイムで働く場合
正社員や契約社員など、フルタイムで働く場合は、原則として社会保険(健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険)への加入が義務付けられています。
労災保険は原則としてすべての労働者に適用され、健康保険、厚生年金保険、介護保険(40歳以上)、雇用保険は、それぞれ定められた要件を満たす労働者が加入対象となります。
具体的な要件としては、事業所に常時雇用されることや、週の所定労働時間が、健康保険・厚生年金保険の場合は正社員の概ね4分の3以上、雇用保険の場合は週20時間以上であることなどが挙げられます。これらの条件を満たすことで、将来の安心を支える社会保障制度の恩恵を十分に受けることができます。
パート・アルバイトで働く場合
パート・アルバイトの方が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するかどうかは、いくつかの条件によって決まります。よく耳にする「106万円の壁」や「130万円の壁」は、これらの条件と深く関係しています。
加入条件(2024年10月からの現行ルール)
勤務先の従業員数に関わらず、週の労働時間などが正社員の4分の3以上である場合は、原則として社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入対象となります。
それに満たない場合でも、パート・アルバイトの方は以下の5つの要件をすべて満たすことで、社会保険の加入対象となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 月額賃金が8万8000円以上であること
- 雇用期間が2ヶ月以上見込まれること
- 勤務先が従業員数51人以上の企業であること
- 学生ではないこと(夜間や定時制の学生は加入対象となる場合があります)
106万円の壁
上記の加入条件の2つ目「月額賃金8万8000円以上」を年収に換算すると約106万円となります。これが「106万円の壁」と呼ばれています。この金額を超え、他の4つの条件も満たす場合、勤務先の社会保険への加入義務が生じます。
「106万円の壁」については3年以内に撤廃されることが令和7年の年金制度改正法で決まっています。具体的な内容や時期については厚生労働省からの発表を参照してください。
130万円の壁
130万円の壁は家族の扶養に関する基準です。年収が130万円以上になると、勤務先の従業員数などにかかわらず、社会保険の扶養から外れることになります。その場合、自分自身で社会保険に加入する必要があり、上記の5つの条件を満たせば勤務先の社会保険に、満たさなければ国民健康保険と国民年金に加入します。
パートが社会保険に加入するメリット・デメリット
パートタイマーが社会保険に加入することには、メリットとデメリットの両面があります。それぞれを確認した上、目先の収入だけでなく、将来の安心や万が一の備えという長期的な視点で加入を考えることが重要です。
メリット
- 将来の年金額が増える:厚生年金保険に加入することで、国民年金に上乗せして将来受け取れる年金額が増加します。これにより、老後の生活資金をより手厚く確保できます。
- 保障が手厚くなる:健康保険に加入すると、傷病手当金や出産手当金といった給付が受けられるようになります。
- 医療保険料の算定基礎が明確:健康保険は所得に応じて保険料が決定され、保険料の半分を会社が負担してくれます。そのため、国民健康保険よりも保険料が安くなるケースがあります。また、扶養家族がいる場合、追加の保険料なしで家族も健康保険の保障を受けられます。
- 失業時の手当:雇用保険に加入していれば、万が一失業した場合に基本手当(失業給付)が支給され、再就職までの生活を支えてくれます。
デメリット
- 手取り収入の減少:社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料など)は給与から天引きされるため、手取り収入が減少します。これが「働き損」と感じられることがあります。
- 加入手続きの負担:自身で手続きを行う必要はないものの、加入条件を満たした際の会社とのやり取りや、制度変更への理解が必要になります。
社会保険が気になるあなたへ
長い人生、将来の負担はさまざまです。老後必要になる金額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶夫婦で考えるお金の基本セミナー:ライフステージごとのお金の管理がわかる
自分の加入している社会保険の種類を確認する方法
自分がどのような社会保険に加入しているかを確認する方法はいくつかありますが、もっとも手軽で確実なのは、手元にある「保険証(健康保険被保険者証)」を確認することです。
保険証には「保険者名称」という欄があり、ここに記載されている内容で、どの健康保険に加入しているかが分かります。
- 「全国健康保険協会(協会けんぽ)」:中小企業の会社員が加入していることが多い健康保険です。
- 「〇〇健康保険組合」:大企業や同業種の企業が集まって設立した健康保険組合です。独自の付加給付やサービスがある場合もあります。
- 「国民健康保険」:社会保険ではなく、自営業者やフリーランス、年金生活者などが加入する市町村が運営する健康保険です。
また、年金については「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で加入履歴や保険料納付状況を確認できます。雇用保険の加入状況であれば、給与明細で雇用保険料が天引きされているかを確認するか、または、ハローワークで問い合わせることで分かります。
【2027年10月~】社会保険のさらなる適用拡大へ
日本では、より多くの労働者が社会保険に加入できるように、社会保険の適用拡大が進められています。これは、少子高齢化が進む中で、社会保障制度を安定的に維持し、働く人々のセーフティネットを強化することを目的としています。特にパート・アルバイトなどの短時間労働者に対する適用が段階的に拡大されています。
2024年10月の適用拡大について
2024年10月に、社会保険の適用範囲がさらに拡大されました。これまで短時間労働者の社会保険加入要件の1つであった「勤務先の従業員数101人以上」という企業規模の要件が、「従業員数51人以上」に引き下げられています。
これにより、これまで社会保険の対象外だった、従業員数51人以上100人以下の企業で働くパート・アルバイトの人も、他の要件(週20時間以上の労働、月額賃金8万8000円以上の収入、2ヶ月以上の雇用見込み、学生ではないこと)を満たせば、健康保険および厚生年金保険の加入対象となりました。
この改正により、約65万人もの短時間労働者が新たに社会保険の適用を受け、より多くの働く人々の社会保障が手厚くなっています。
さらなる適用拡大に向けた動き
政府は、2024年10月の改正に続き、2027年10月以降に企業規模などの要件をさらに段階的に引き下げ、適用を拡大していくことを目指しています。
参照:被用者保険の適用拡大について|厚生労働省
企業規模要件の撤廃
従業員数による企業規模の要件は、段階的に引き下げられ、最終的には撤廃される予定です 。今後のスケジュールは以下の通りです 。
- 2027年10月~:従業員数35人超(36人以上)の企業
- 2029年10月~:従業員数20人超(21人以上)の企業
- 2032年10月~:従業員数10人超(11人以上)の企業
- 2035年10月~:従業員数10人以下の企業
賃金要件(月額8万8000円)の撤廃
現在の加入要件の一つである「月額賃金8万8000円以上」という要件も、撤廃が予定されています 。この撤廃は、全国の最低賃金の平均が1016円以上になることを見極めた上で実施される計画で、法律の公布から3年以内の政令で施行日が定められます 。
社会保険に関するよくある質問
社会保険制度は複雑であるため、多くの人が疑問を抱いています。ここでは、社会保険に関するよくある質問とその回答をまとめました。
Q. 退職したら社会保険はどうなる?
会社を退職した場合、それまで加入していた会社の社会保険から外れるため、以下のいずれかの選択肢を選ぶことになります。
- 任意継続被保険者制度を利用する:退職前に健康保険に2ヶ月以上加入していた場合、最長2年間、会社の健康保険を任意で継続できます。保険料は全額自己負担となりますが、在職中と同じ給付を受けられます。
- 国民健康保険・国民年金に切り替える:市区町村が運営する国民健康保険と、国民年金に加入します。保険料は所得に応じて異なり、全額自己負担です。
- 家族の扶養に入る:配偶者や親など、家族が加入している社会保険の扶養に入れる条件を満たしている場合、扶養家族として保険料の負担なく健康保険の保障を受けられます。国民年金については、第3号被保険者として保険料の負担なしで加入できます。ただし、扶養に入るための収入要件などがあります。
- 再就職先の社会保険に加入する:新しい会社に就職し、社会保険の加入条件を満たせば、その会社の社会保険に加入します。
いずれの選択肢もメリット・デメリットがあるため、自身の状況や将来の計画に合わせて慎重に検討することが重要です。
Q. 社会保険に加入しないとどうなる?
社会保険への加入は、国民の義務であり、適切な社会保障を受けるための権利でもあります。事業主は、社会保険の適用事業所に該当する場合、従業員を社会保険に加入させる義務があります。労働者自身も、加入条件を満たしているにもかかわらず社会保険に加入しない場合は、以下のようなデメリットやリスクが生じます。
- 医療費の自己負担割合が高くなる可能性:適切な健康保険に加入していない場合、病気やケガをした際の医療費が全額自己負担となり、高額な出費につながる可能性があります。
- 老後の生活保障が不足する:厚生年金保険に未加入の場合、国民年金のみとなり、将来受け取れる年金額が少なくなります。
- 病気や出産時の手当が受けられない:健康保険の傷病手当金や出産手当金、雇用保険の育児休業給付など、万が一の際に生活を支えるための重要な手当が受けられません。
- 事業主への罰則:事業主が社会保険の加入義務を怠った場合、法律に基づき過去にさかのぼって保険料を徴収されたり、追徴金が課されたりする可能性があります。また、企業イメージの低下や従業員のモチベーション低下にもつながりかねません。
社会保険への加入は、個人の安心だけでなく、社会全体の安定を支えるために不可欠な制度です。
Q. 社会保険料はどうやって決まる?
社会保険料は、給与額や加入している保険の種類によって決まります。主な保険料の決まり方は以下の通りです。
健康保険・厚生年金保険料
これらの保険料は、「標準報酬月額」という基準に基づいて決定されます。標準報酬月額とは、月々の給与を一定の幅で区分した額のことで、毎年4月から6月の給与を平均して算出され、9月から翌年8月までの保険料に適用されます。健康保険料と厚生年金保険料は、この標準報酬月額にそれぞれ定められた保険料率を乗じて算出されます。事業主と従業員が折半して負担します。
賞与からも「標準賞与額」(支給された賞与を基に算出される)をもとに算出された保険料を事業主と従業員が折半して負担します。
介護保険料
40歳以上65歳未満の被保険者が負担し、健康保険料と同様に標準報酬月額に介護保険料率を乗じて算出されます。これも事業主と従業員で折半します。介護保険料も、賞与から「標準賞与額」(支給された賞与を基に算出される)を基に算出された保険料を事業主と従業員が折半して負担します。
雇用保険料
毎月の賃金総額に定められた雇用保険料率を乗じて算出されます。雇用保険料率は、事業の種類(一般の事業、農林水産・清酒製造の事業、建設の事業)によって異なりますが、従業員と事業主で負担割合が決まっています。
例えば、一般の事業の場合、労働者負担が0.6%、事業主負担が0.95%(2025年度)です。雇用保険料の場合も賞与の額を基に給与と同様の計算式に基づいた保険料を事業主、従業員のそれぞれが負担します。
労災保険料
労災保険料は、賃金総額に定められた労災保険料率を乗じて算出されますが、全額事業主が負担するため、従業員が支払うことはありません。
まとめ
本記事では、私たちの生活を支える基盤である社会保険について、その5つの種類(健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険)を詳しく解説しました。社会保険の各保険は、病気、老齢、介護、失業、災害といった多様なリスクから私たちを守るための重要な役割を担っていることが理解いただけたのではないでしょうか。
また、正社員からパート・アルバイトまで、働き方によって社会保険の加入条件が異なること、特に「106万円の壁」や「130万円の壁」がパートタイマーの加入に大きく影響することもご紹介しました。2024年10月には社会保険の適用が拡大され、より多くの人々が手厚い保障を受けられるようになりました。さらに、2027年10月にはさらなる適用拡大が予定されています。
社会保険は、個人の安心だけでなく、社会全体の持続可能性を支える重要な制度です。この機会に、社会保険について改めて理解を深め、ぜひ将来にわたる安心を確保するための参考にしてみてください。
>>将来の備えは大丈夫?あなたの老後に必要なお金を診断
社会保険が気になるあなたへ
長い人生、将来の負担はさまざまです。老後必要になる金額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶夫婦で考えるお金の基本セミナー:ライフステージごとのお金の管理がわかる
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
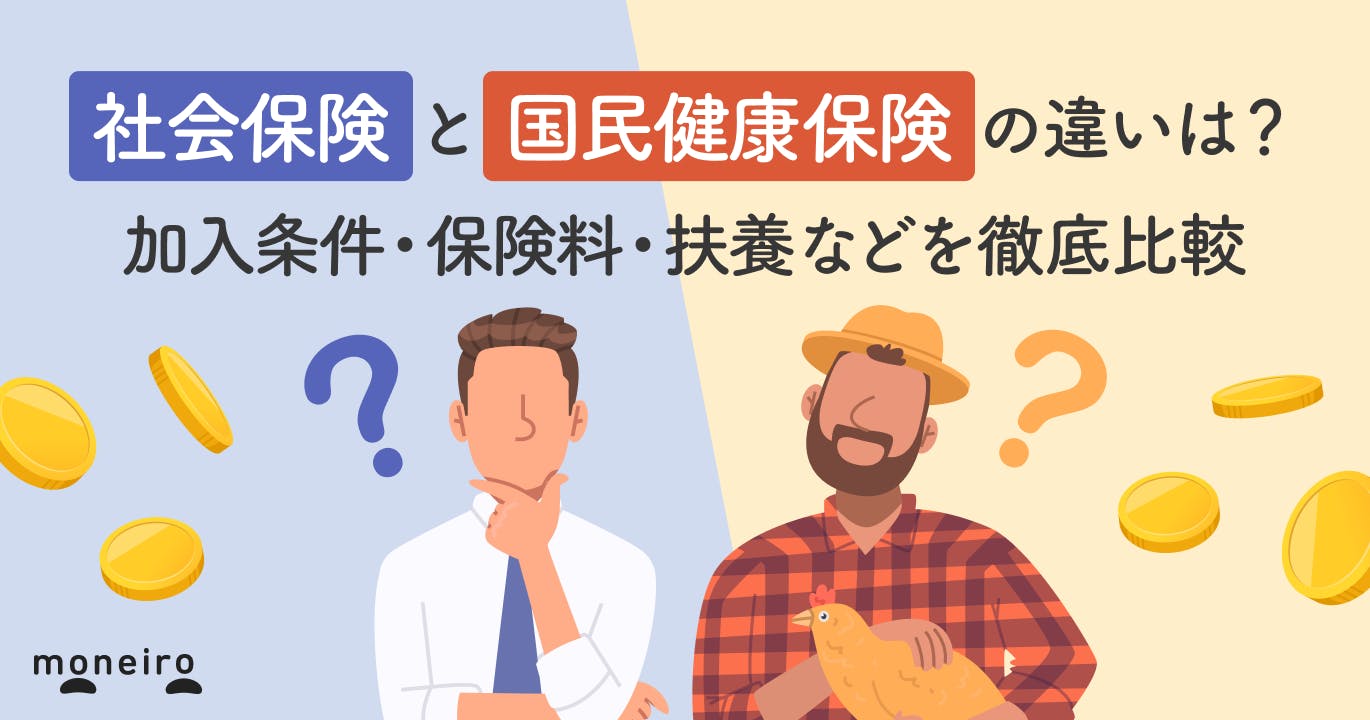

社会保険と国民健康保険、どっちが得?違いとケース別の選択肢を専門家が徹底解説
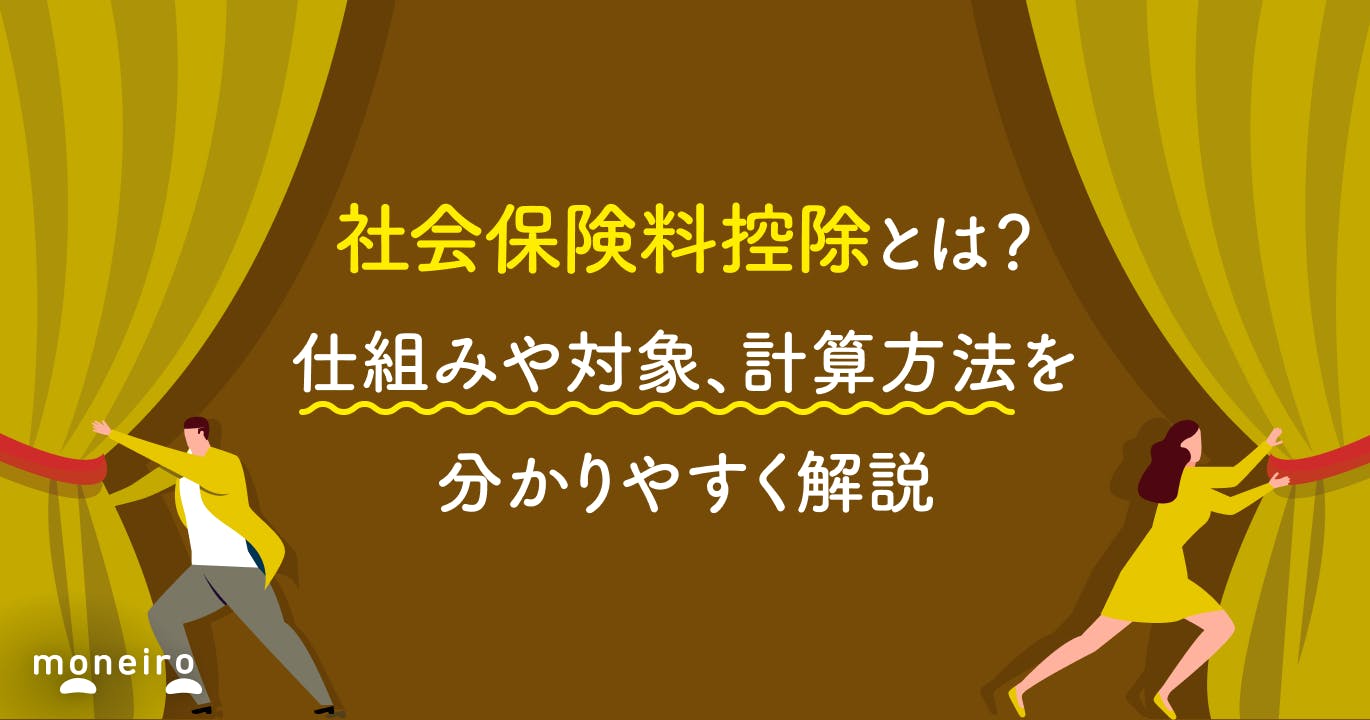
社会保険料控除とは?仕組みや対象、計算方法を分かりやすく解説
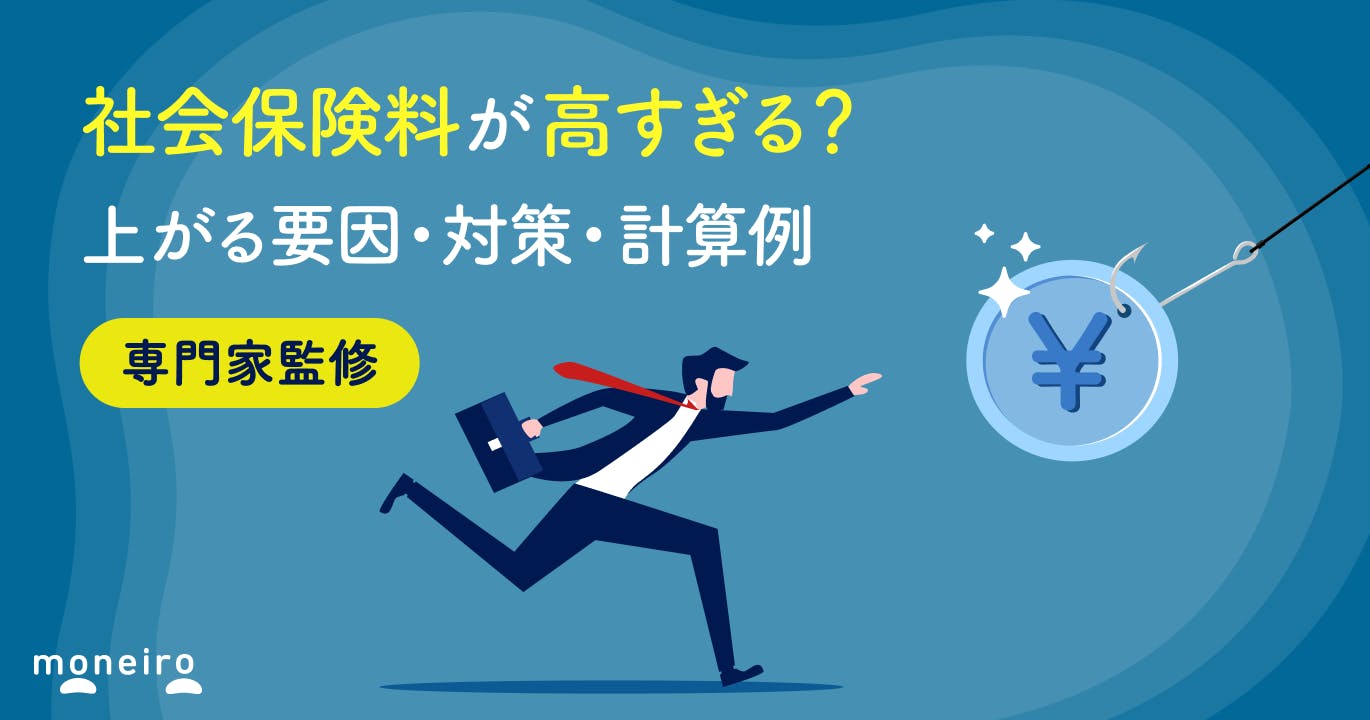
社会保険料が高すぎる?上がる要因・対策・計算例を専門家がわかりやすく解説
監修
山本 務
- 特定社会保険労務士/AFP/第一種衛生管理者
東京都練馬区で、やまもと社会保険労務士事務所を開業。企業の情報システム、人事部門において通算28年の会社員経験があるのが強みであり、情報システム部門と人事部門の苦労がわかる社会保険労務士。労務相談、人事労務管理、就業規則、給与計算、電子申請が得意であり、労働相談は労働局での総合労働相談員の経験を生かした対応ができる。各種手続きは電子申請で全国対応が可能。また、各種サイトで人事労務関係の記事執筆や監修も行っている。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。