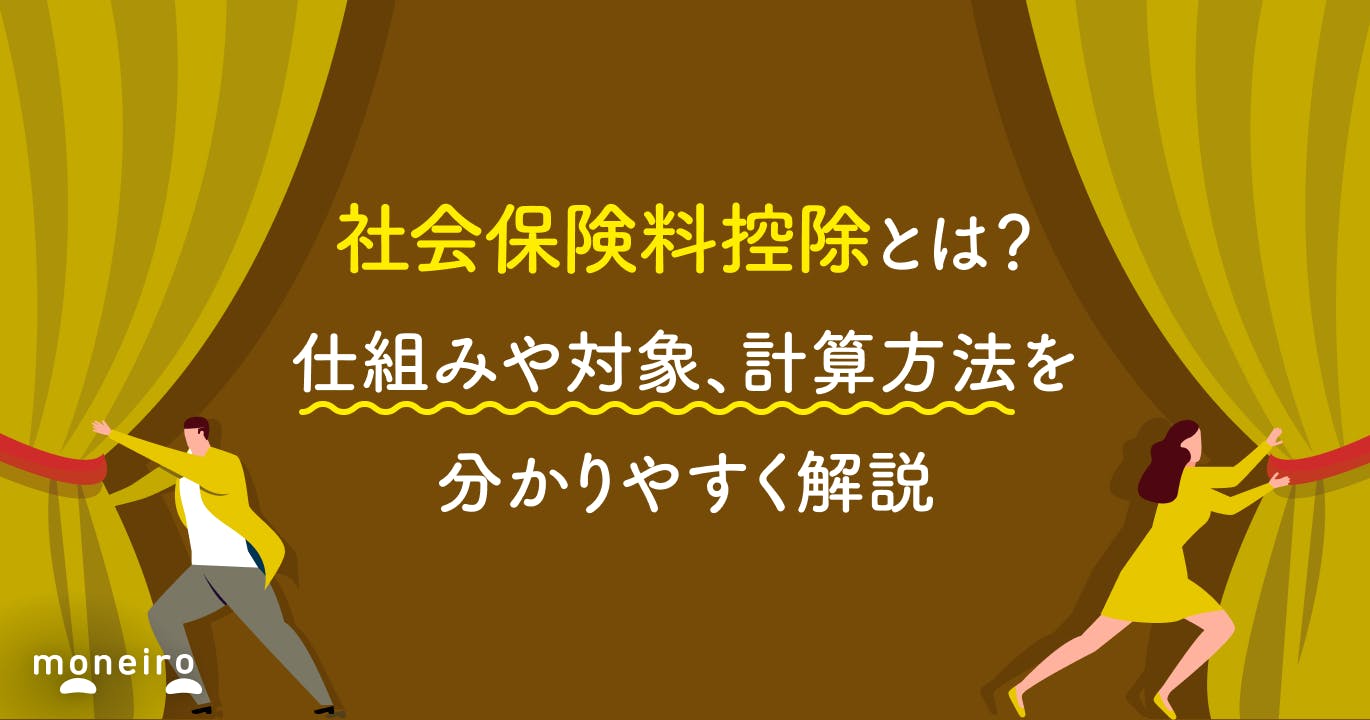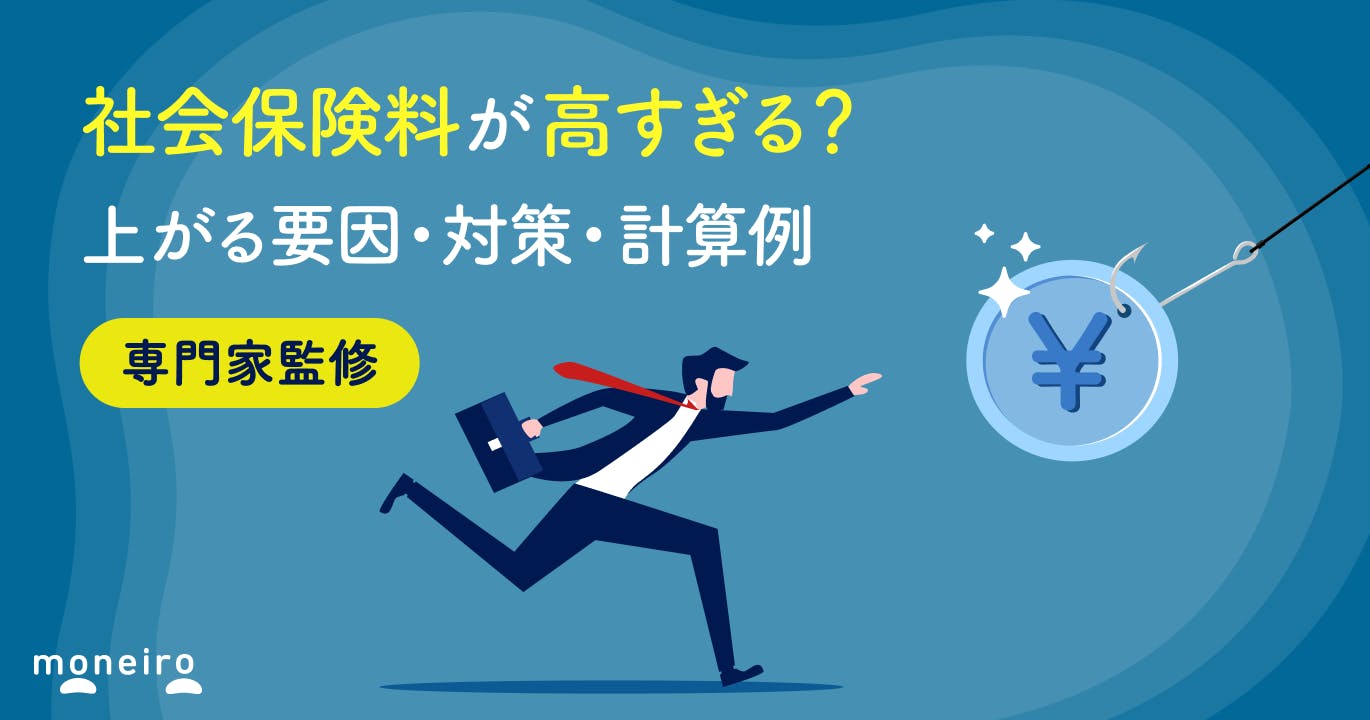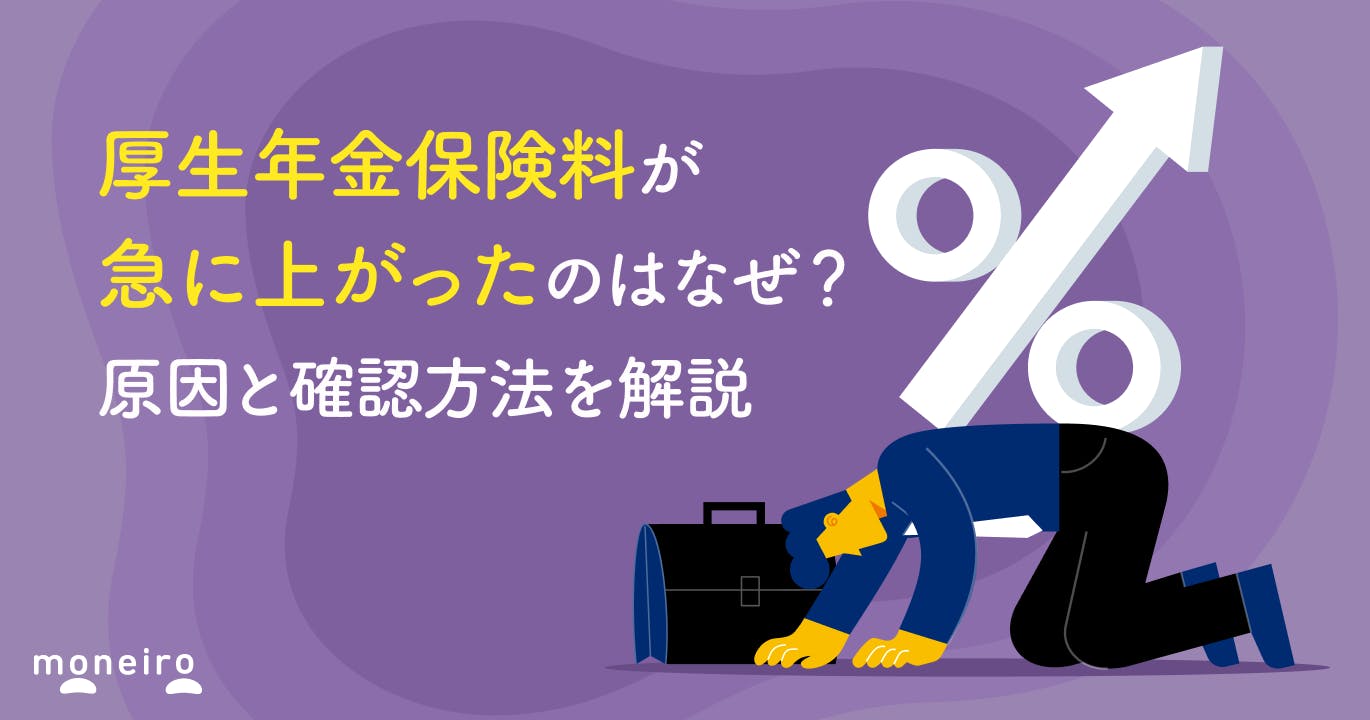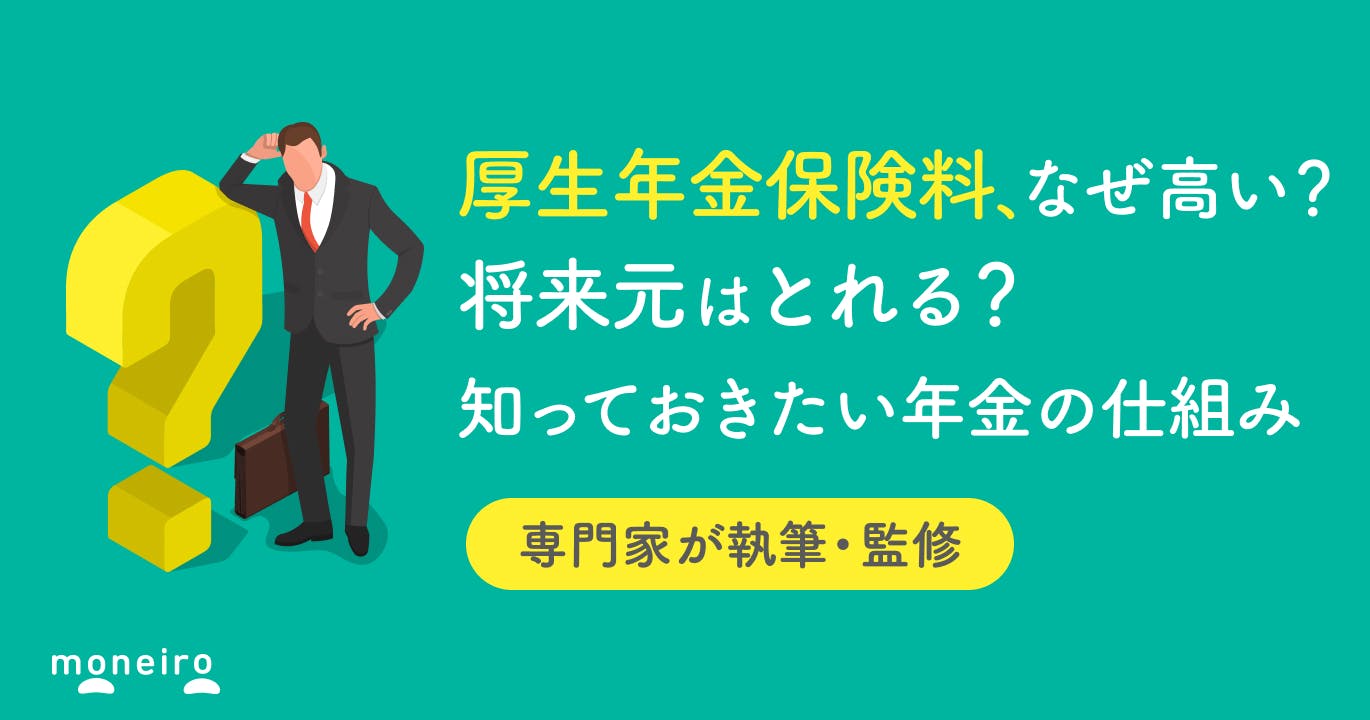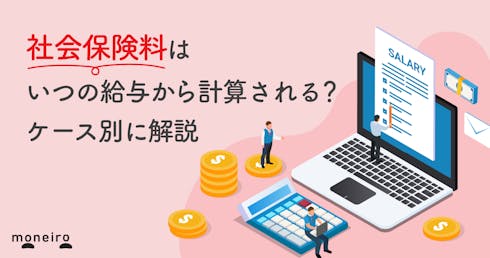
社会保険料控除とは?仕組みや対象、計算方法を分かりやすく解説
>>あなたの将来資金は大丈夫?不足額を3分で診断
社会保険料控除とは、私たちが納めている社会保険料が所得税や住民税の計算において重要な役割を果たす制度です。この控除を正しく理解し活用することで、税負担を軽減できる可能性があります。
そこで本記事では、社会保険料控除の基本的な仕組みから、対象となる保険料の種類、そして知っておくべき注意点までを分かりやすく解説します。
- 社会保険料控除の基本的な仕組みと、控除の対象となる社会保険料の種類
- 社会保険料控除によって得られる具体的な節税メリット
- 社会保険料控除に関するよくある勘違いや注意点
社会保険料のことが気になるあなたへ
この先、お金の不安なく暮らすために、将来必要になる資金を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶夫婦で考えるお金の基本セミナー:ライフステージごとのお金の管理がわかる
▶2025年に変わるお金の制度セミナー:お金に関する最新の制度をやさしく解説
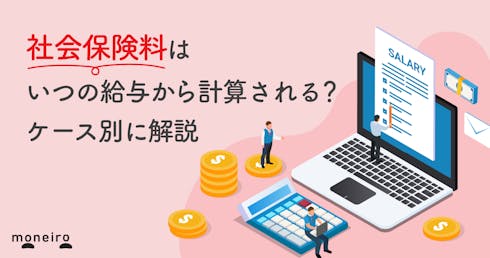
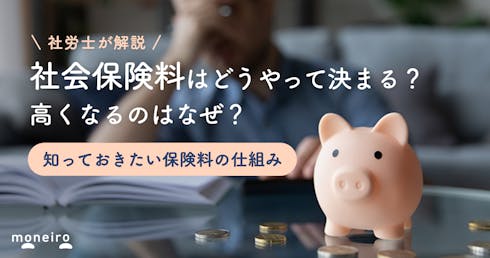
社会保険料控除とは?
まずは、社会保険料控除の基本をしっかり押さえておきましょう。
所得控除の1つで納めた保険料の分だけ税金が安くなる仕組み
社会保険料控除とは、納税者が自身や生計を一にする配偶者、その他の親族が負担すべき社会保険料を支払った場合に、その支払った金額について所得から控除を受けられる制度です。これにより、課税対象となる所得が減少し、所得税や住民税の負担が軽減されます。
控除の対象となる費用は多岐にわたり、具体的には、健康保険、国民年金、厚生年金、国民年金基金、介護保険、雇用保険などが含まれます。また、支払った社会保険料が多ければ多いほど、税金計算の元となる所得が減り、節税効果が高まるというメリットがあります。
社会保険料控除は、生活を支えるために納めている社会保険料を差し引くことで、所得税や住民税の負担を軽減する制度です。
社会保険料控除の対象者は?
社会保険料控除は、納税者自身が支払った社会保険料、または納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の社会保険料を納税者が負担した場合に適用されます。
例えば、会社員の給与から天引きされる社会保険料だけでなく、個人事業主や学生、無職の方が支払う国民健康保険料や国民年金保険料なども控除対象です。
必ずしも同居している必要はなく、例えば生活費、学費、療養費などを継続的に送金している場合や、就学や勤務等の都合で別居していても休日などに同居している場合などが該当します。つまり、親族と生活資金を共有している状態であれば、生計を一にしているとみなされます。
したがって、納税者が生計を一にする親族の社会保険料を支払った場合、その金額も自身の社会保険料控除として申告可能です。この制度は、さまざまな家族構成や生活状況に対応し、納税者に節税の機会を提供しています。
社会保険料控除の対象となる保険料一覧
社会保険料控除の対象となる社会保険料は多岐にわたります。国税庁の指針によると、以下の保険料が対象として挙げられています。
引用元:社会保険料の範囲|国税庁
これらの保険料は、その年に実際に支払った金額、または給与や公的年金などから差し引かれた金額の全額が控除の対象となります。
社会保険料控除のメリット
具体的に社会保険料控除にはどのようなメリットがあるのでしょうか。以下で詳しく解説します。
支払った社会保険料が所得から控除される
社会保険料控除の最大のメリットは、その年に支払った社会保険料の全額が所得から控除される点です。これは、他の多くの所得控除に上限額が設けられている中で、社会保険料控除には上限がないということでもあります。
具体的には、健康保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料、介護保険料など、前述した対象となる社会保険料を支払った金額がそのまま所得から差し引かれます。
この控除により課税所得が減少し、所得税や住民税の負担が軽減されます。例えば、総所得金額等から計算した所得が100万円で、社会保険料を20万円支払った場合、控除後の課税所得は80万円となり、これに所得税率が適用されるため納税額が減少します。社会保険料の支払額が多いほど、節税効果が大きくなる特徴があります。
生計を一にする家族分も合算して控除できる
社会保険料控除のもう一つの重要なメリットは、納税者自身が支払った社会保険料だけでなく、自身と生計を一にする配偶者やその他の親族が負担すべき社会保険料を納税者が支払った場合も、合算して控除を受けられる点です。前述の通り、「生計を一にする」とは、同居しているか否かにかかわらず、生活費などを共有している状態を指します。
例えば、納税者が遠方に住む高齢の親の国民健康保険料や、学生である子の国民年金保険料を代わりに支払っている場合、これらの社会保険料も納税者自身の社会保険料控除の対象となります。
ただし、重要なのは、実際に納税者自身がその社会保険料を支払っていることです。例えば、配偶者の社会保険料であっても、配偶者の給与から直接天引きされている場合は、配偶者自身が支払っているとみなされるため、納税者本人の控除対象にはなりません。
生計を一にする家族の社会保険料をまとめて申告できることで、家計全体での節税効果を高めることができます。
所得が高い人ほど節税効果が大きくなる
社会保険料控除は所得控除の1つであるため、所得税の計算方法から、所得が高い人ほどその節税効果が大きくなる傾向があります。日本の所得税は累進課税制度を採用しており、課税所得が増えるにつれて適用される税率も段階的に高くなります。
社会保険料控除によって課税所得が減少すると、その減少額に対して適用されていたもっとも高い税率分の税金が軽減されることになります。
例えば、課税所得に20%の税率が適用される人が社会保険料控除で20万円を控除した場合、所得税は20万円 × 20% = 4万円軽減されます。一方、40%の税率が適用される人なら、同じ20万円の控除で8万円の税軽減となります。
このため、高い税率が適用される高所得者ほど、社会保険料控除による税負担軽減効果が大きくなります。
年末調整で手続き可能
会社員や公務員にとって社会保険料控除の大きなメリットといえるのが、年末調整で手続きが完結できる点です。給与や賞与から天引きされる健康保険料や厚生年金保険料は、勤務先が給与計算を通じて支払額を把握しており、年末調整で自動的に所得控除として処理されます。
ただし、給与天引き以外の社会保険料(例:転職活動中に自分で納めた国民年金保険料や、生計を一にする親族の国民健康保険料)を支払った場合は、年末調整での申告が必要です。
これらの場合、「給与所得者の保険料控除申告書」の社会保険料控除欄に記入し、勤務先に指定期日までに提出することで控除を受けられます。この年末調整による簡便な手続きは、会社員にとって大きな利点です。
社会保険料控除による節税効果の計算方法
次に、社会保険料控除によって得られる具体的な節税効果の計算方法について解説します。
所得税の軽減額の計算
社会保険料控除による所得税の軽減額は、以下のシンプルな計算式で求めることができます。
所得税の軽減額 = 社会保険料控除額(支払った社会保険料の全額) × 適用される所得税率
社会保険料控除額は、その年(2025年1月1日から12月31日)に支払った社会保険料の全額です。例えば、2025年に国民年金保険料を年間21万120円(月額1万7510円 × 12ヶ月)支払った場合、この21万120円が控除額となります。
日本の累進課税制度では、課税所得に応じて税率(5~45%)が段階的に上昇します。社会保険料控除により課税所得が減少し、適用される税率分の税負担が軽減されます。
仮に課税所得300万円(税率10%)の人が21万120円の控除を受けると、21万120円 × 10% = 2万1012円の所得税が軽減されます。高所得者ほど高い税率が適用されるため、節税効果が大きくなります。
住民税の軽減額の計算
社会保険料控除は、所得税だけでなく住民税の軽減にもつながります。住民税の軽減額も、所得税と同様に社会保険料控除額に住民税率を掛けて算出されます。
住民税の軽減額 = 社会保険料控除額(実際に支払った社会保険料の全額) × 住民税率
住民税は所得割と均等割で構成され、社会保険料控除は所得割に影響します。所得割の住民税率は標準で10%(都道府県民税4%、市区町村民税6%)ですが、一部自治体では異なる場合があります。
社会保険料控除でよくある勘違い・注意点
社会保険料控除は税制優遇措置として積極的に活用していきたい制度です。正しく控除を受けられるよう、以下でよくある勘違いや注意点についてもおさらいしておきましょう。
対象となる保険料を間違える
社会保険料控除を申告する際によくある勘違いとして、控除の対象とならない保険料まで含めてしまうことが挙げられます。
前述の通り、控除の対象となる社会保険料は、健康保険、国民年金保険、厚生年金保険、国民健康保険、介護保険など、国税庁が明確に定めている種類に限られます。
特に注意が必要なのは、生命保険料や医療保険料、個人年金保険料など、民間の保険会社が提供する保険商品は社会保険料控除の対象ではないという点です。
これらは「生命保険料控除」や「個人年金保険料控除」など、別の所得控除の対象となる可能性はありますが、社会保険料控除とは区別されます。
また、生計を一にする親族の公的年金から社会保険料が特別徴収されている場合は、納税者本人が支払ったとみなされないため、控除対象外となることにも注意が必要です。
正しい申告のためには、自身が支払った保険料がどの控除に該当するかを事前に確認することが重要です。
配偶者の給与から天引きされている保険料を合算してしまう
社会保険料控除でよくある勘違いとして、配偶者の給与から天引きされている社会保険料を、納税者自身の控除額に合算して申告しようとすることが挙げられます。しかし、これは控除の対象にはなりません。
社会保険料控除は、納税者が自己または生計を一にする配偶者・親族の社会保険料を直接支払った場合に適用されます。
配偶者の給与天引き分(例:健康保険料、厚生年金保険料)は配偶者が支払ったとみなされ、納税者の控除対象になりません。家計が同一でも、支払いの主体が納税者でない場合は対象外です。
一方、納税者が自身の口座から配偶者の国民健康保険料や国民年金保険料を支払った場合は、控除対象となります。支払い主体を確認し、間違えないよう注意が必要です。
「控除証明書」の添付漏れ
社会保険料控除の適用には、国民年金保険料や国民年金基金の掛金など、一部の社会保険料について、支払額を証明する控除証明書を年末調整や確定申告時に提出または提示する必要があります。証明書を提出しないと、控除を受けられない場合があります。
国民年金保険料の控除証明書は、その年に国民年金保険料を納付した方へ、日本年金機構から毎年10月下旬から11月上旬にかけて順次郵送されます(電子送付を希望している場合は10月中旬から下旬)。また、10月1日から12月31日までに納付した方へは翌年1月下旬から2月上旬にかけて送付されます。
一方、厚生年金保険料や共済組合の保険料は、勤務先が給与天引き額を把握し、年末調整で処理するため、個別の証明書は不要です。
電子データの控除証明書は、真正性が担保された形式で提出可能です。これらの証明書は、年末調整や確定申告の手続きが終わるまで大切に保管しておくようにしましょう。
過去の未納分を追納したのに申告を忘れる
国民年金保険料には、過去に免除または納付猶予された保険料を遡って納める「追納」制度があります。追納した保険料は、その年に支払った全額が社会保険料控除の対象となります。
例えば、2025年に過去数年分の国民年金保険料を追納した場合、その全額を2025年分の社会保険料控除として申告できます。申告を忘れると税負担軽減の機会を逃すため、注意が必要です。
追納時は、年末調整や確定申告で控除証明書を提出します。追納分の控除証明書は、日本年金機構から1~9月納付分は10月下旬~11月上旬、10~12月納付分は翌年1月下旬~2月上旬に送付されます。同じく、証明書は手続き完了まで保管しておきましょう。
年末調整で申告し忘れて諦めてしまう
年末調整で社会保険料控除の申告を忘れてしまうケースもよくある失敗です。ただし、諦める必要はありません。会社員や公務員であっても、後から確定申告(還付申告)を行うことで、控除の適用を受けることが可能です。
確定申告は申告期間である翌年2月16日から3月15日までの間に行うのが一般的ですが、還付申告は、対象となる年の翌年1月1日から5年間まで提出することができます。
還付申告では、確定申告書に社会保険料の金額を記載し、控除証明書(例:国民年金保険料)や領収書を添付または提示します。年末調整の期限を過ぎても、税務署に確定申告書を提出することで税金の還付を受けられます。申告漏れに注意し、適切に対応しましょう。
社会保険料控除に関するQ&A
社会保険料控除に関するよくある質問にお答えします。
Q. 過去の年度分の国民年金保険料を払った場合、控除の対象になる?
はい、控除の対象になります。社会保険料控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に実際に支払った金額の全額が対象となります。
したがって、過去の年度分の国民年金保険料をまとめて支払った場合(追納など)でも、その支払いを実行した年の社会保険料控除として申告することができます。
実際に支払った年分の年末調整や確定申告で、日本年金機構から送付される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付して申告するようにしましょう。
Q. 社会保険料控除に上限額はある?
いいえ、社会保険料控除に上限額はありません。
社会保険料控除は、その他の多くの所得控除とは異なり、控除できる金額に上限が設けられていません。その年の1月1日から12月31日までに納税者自身や生計を一にする親族のために実際に支払った社会保険料の全額が、所得から控除されます。
したがって、高額な社会保険料を支払っている場合でも、支払った金額がそのまま全額控除されるため、より大きな節税効果を期待することができます。例えば、高額の国民年金保険料や国民健康保険料を支払っている個人事業主の人や、免除期間の国民年金保険料を追納した人などが、この上限なしのメリットを最大限に享受できます。
Q. 転職した年の社会保険料控除はどうなる?
転職した時期によって、社会保険料控除の申告方法が変わります。
その年内に再就職した場合
退職後に自身で国民年金保険料などを支払い、その年(1月1日~12月31日)の内に次の会社に再就職した場合は、転職先での年末調整で社会保険料控除をまとめて申告できます。
前職の給与から天引きされた社会保険料と、自身で支払った社会保険料の両方を合算して申告します。この際、自身で支払った社会保険料については、控除証明書や領収書などを転職先に提出する必要があります。
年をまたいで再就職した場合
例えば、2024年中に退職し、翌年の2025年に再就職した場合、2024年中に自身で支払った社会保険料(退職後の国民年金保険料など)や前職の給与から天引きされた社会保険料については、翌年の確定申告期間(2025年2月16日~3月15日)にご自身で確定申告を行う必要があります。
前職分の社会保険料の金額は、退職時に発行される源泉徴収票で確認できます。自身で支払った国民年金保険料については、日本年金機構から届く控除証明書を確定申告書に添付して提出します。この場合、2025年になってから再就職までの間に自身で支払った社会保険料は、2025年の年末調整または確定申告で申告することになります。
まとめ
社会保険料控除は、納税者が自己または生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った社会保険料の全額を所得から控除できる、重要な節税制度です。この控除に上限額はなく、支払った金額がそのまま課税所得を減らし、所得税および住民税の負担軽減につながるメリットがあります。
控除の対象となる社会保険料は、健康保険、国民年金保険、厚生年金保険など多岐にわたり、会社員であれば給与天引き分は年末調整で自動的に精算されます。しかし、自分で支払った国民年金保険料や家族分の社会保険料、転職で一時的に自己負担した期間の保険料などについては、年末調整または確定申告での申告が必要です。
もし年末調整での申告を忘れてしまっても、確定申告(還付申告)を行うことで控除を受けることが可能です。この制度を正しく理解し自身の支払い状況に応じて適切に申告することで、税負担を軽減し、家計の節約に役立てることができるでしょう。
社会保険料のことが気になるあなたへ
この先、お金の不安なく暮らすために、将来必要になる資金を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶夫婦で考えるお金の基本セミナー:ライフステージごとのお金の管理がわかる
▶2025年に変わるお金の制度セミナー:お金に関する最新の制度をやさしく解説
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。