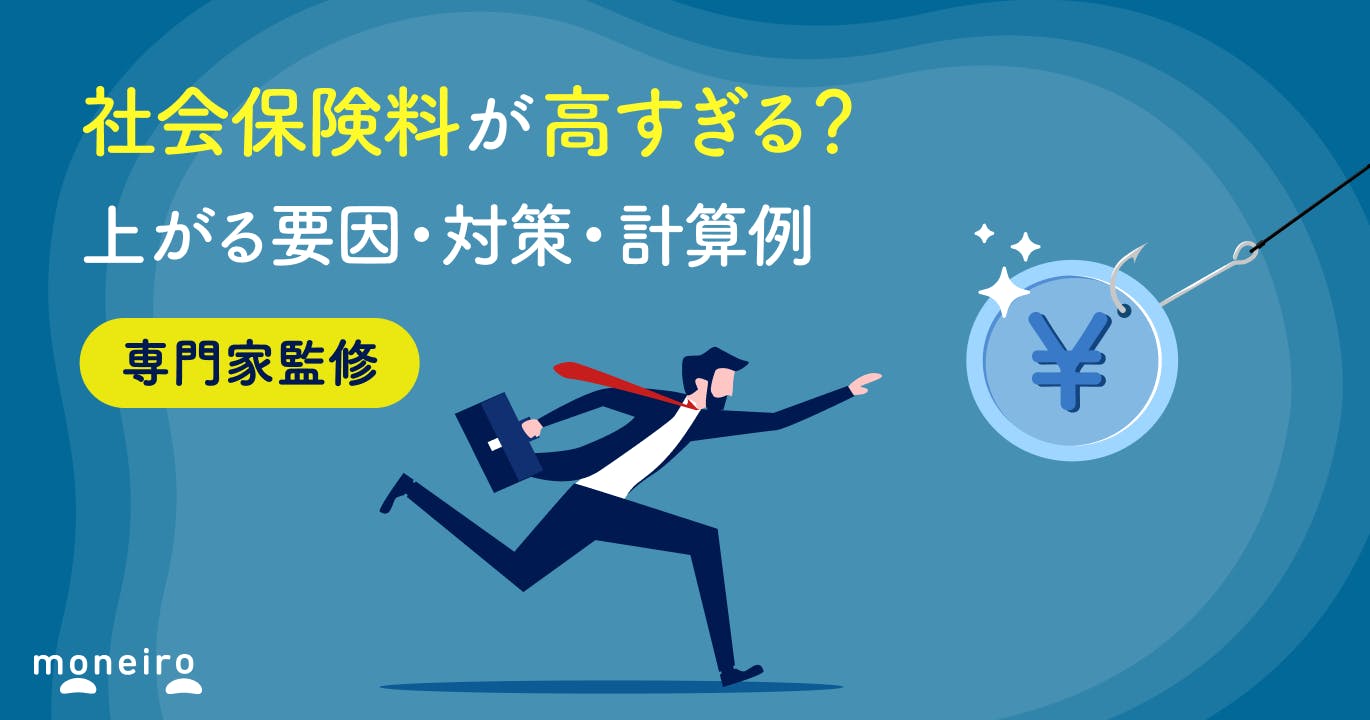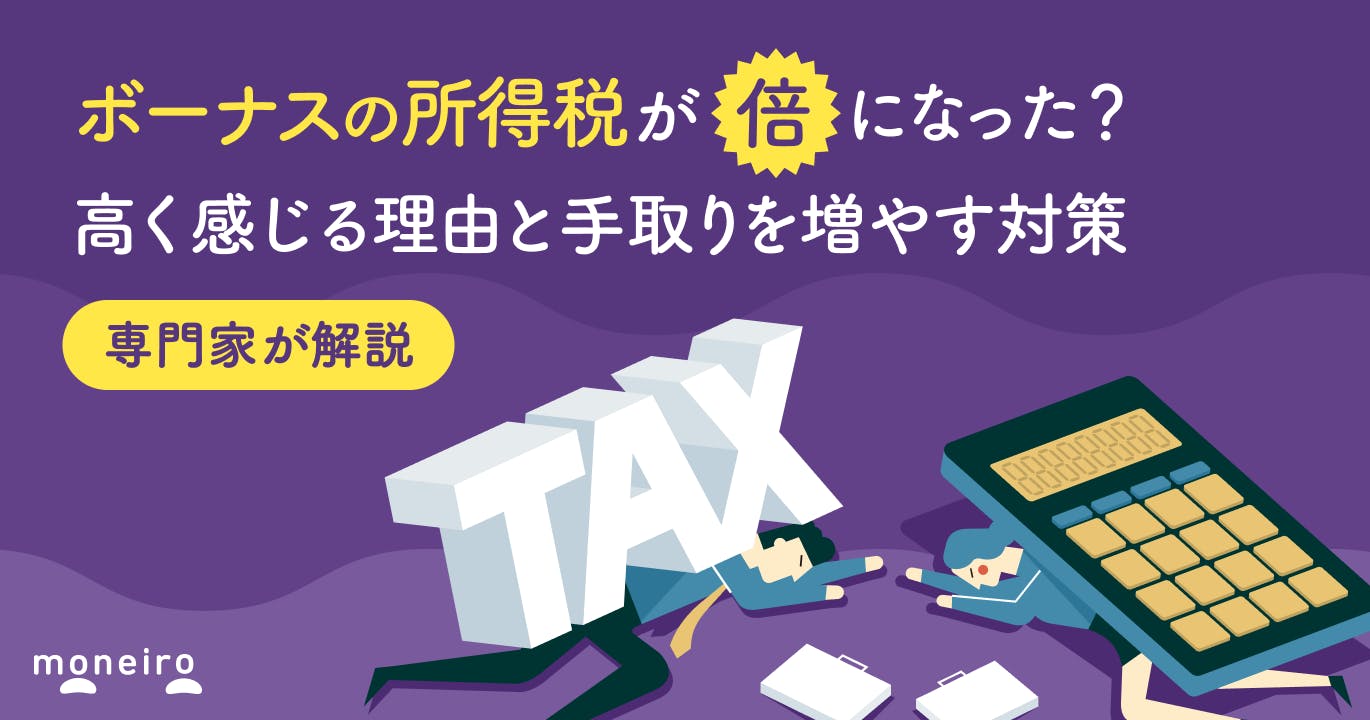
社会保険料が高すぎる?上がる要因・対策・計算例を専門家がわかりやすく解説
»今のままの貯金で老後は安心できる?無料診断
「給料明細を見ると社会保険料が高すぎる」「毎月の手取りが少ない…」と感じている人も多いかもしれません。
社会保険料は、給与から自動的に天引きされるため負担感を意識しづらい一方で、年々上昇しており家計に大きな影響を与えています。
本記事では、社会保険料の仕組みや計算方法、シミュレーション、対策について、社労士監修のもと、わかりやすく解説します。
- 社会保険料が高すぎると感じる主な理由①社会保険料率は上がり続けているため
- 社会保険料が高すぎると感じる主な理由②昇給しても手取りが思ったほど増えないため
- 社会保険料を抑えるための対策は「4月~6月の残業、手当を調整」など
社会保険料が気になるあなたへ
これから先、お金の不安なく暮らすために、将来に必要なお金を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をスムーズに進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶2025年に変わるお金の制度セミナー:お金に関する最新の制度をやさしく解説
▶賢いお金の増やし方入門:30分の無料オンラインセミナー
社会保険料の種類と役割
社会保険料とは、社会保険制度に加入している人が負担する保険料のことです。会社員の場合、毎月の給与から引かれる仕組みになっています。
給与から引かれる保険料の主な種類は以下(労災保険料は企業が全額負担)のとおりです。
会社員・自営業での違い
社会保険の加入者や保険料の負担方法は、雇用形態によって大きく異なります。
会社員の場合、会社が加入手続きを行い、保険料は会社と従業員が原則折半します。給与から天引きされるため、社会保険料がいくらか知らない人もいるでしょう。
一方、自営業者・フリーランスの場合、国民健康保険と国民年金に加入し、保険料は全額自己負担となります。
会社員のような「会社負担分」がないため、保険料の負担をより重く感じやすいのが特徴です。
「社会保険料が高すぎる」と感じる理由
予想以上に社会保険料が引かれている給与明細(控除額)を見て「なぜ社会保険料は高い?」と感じる人も多いでしょう。
社会保険料は上がり続けているため
(引用:第23回税制調査会|内閣府)
社会保険料は、少子高齢化の進展に伴う社会保障費の増大を背景に、年々上がり続けています。
特に、厚生年金保険料や健康保険料率は、将来の安定的な給付を維持するために引き上げられる傾向にあります。
ただし、保険料率の最も高い厚生年金保険料については、現役世代の負担増を抑えるために、平成29年9月以降は18.3%で固定されています。
税金より目立ちにくいが負担が大きいため
社会保険料は、所得税や住民税のように税率が頻繁に話題になることが少なく、意識されにくいかもしれません。しかし、その負担率は税金よりも大きいのが一般的です。
例えば、標準的な所得の会社員の場合、社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険の合計)だけで給与の15%程度が引かれます。
医療費支出が少なく年金を受給していない(=受益の少ない)現役世代にとって、給与の15%は高いと感じられるでしょう。
昇給しても手取りが思ったほど増えないため
昇給しても、社会保険料は「標準報酬月額」に基づいて計算されるため、昇給幅によっては、保険料負担も増えます。
昇給分の一部が社会保険料の増加で消えてしまい、手取りは思ったほど増えないこともあります。さらに、所得税率がアップすれば手取り額がほとんど変わらないと感じることもあるでしょう。
社会保険料はいくら?年収別のシミュレーション
社会保険料が具体的にいくらになるのかは、年収や加入している健康保険組合(協会けんぽは居住地)、年齢によって異なります。
計算方法と年収別の目安を見ていきましょう。
社会保険料の計算方法
社会保険料は、給与や残業代、手当などを含んだ月々の賃金をもとに計算される「標準報酬月額」(雇用保険と労災保険は賃金額)に、所定の保険料率を乗じて算出されます。
- 標準報酬月額…毎年4月から6月の平均賃金をもとに決定されます
- 保険料率…健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険でそれぞれ定められています
また、ボーナス(賞与)にも社会保険料がかかります。ボーナスは「標準賞与額」(雇用保険と労災保険は賞与額)を基に計算されます。
給与別の社会保険料・手取り額シミュレーション
健康保険料率:5.0%(労使折半、協会けんぽ全国平均を参考に仮定)
厚生年金保険料率:9.15%(労使折半)
雇用保険料:0.55%(失業保険など給付に対する保険料率を労使折半)
介護保険料:40歳未満と仮定し、負担なし
社会保険料はボーナスや残業でも引かれる
社会保険料は、毎月の固定給与だけでなく、ボーナスや残業手当でも引かれます。ボーナスは「標準賞与額」に保険料率を乗じて計算されるため、ボーナスが多ければ多いほど、社会保険料の負担も大きくなります。
また、残業代も標準報酬月額の算定に含まれるため、残業が増えると、それに伴い社会保険料が上がる可能性があります。
社会保険料が気になるあなたへ
これから先、お金の不安なく暮らすために、将来に必要なお金を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をスムーズに進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶2025年に変わるお金の制度セミナー:お金に関する最新の制度をやさしく解説
▶賢いお金の増やし方入門:30分の無料オンラインセミナー
社会保険料を抑えるための対策
社会保険料の負担が重いと感じる場合でも、合法的に保険料を減らす方法があります。個人の状況や働き方に応じて、以下のような対策が考えられます。
4月~6月の残業、手当を調整
社会保険料の計算基礎となる「標準報酬月額」は、毎年4月から6月の3ヶ月間の給与平均で決定されます。この期間の給与には残業代や通勤手当なども含まれるため、給与が大幅に増えると、それに伴い9月以降の社会保険料も上がってしまいます。
4月から6月の3ヶ月間の残業や手当を調整することで、その後の社会保険料負担を抑えられる可能性があります。
NISAやiDeCoなどの非課税制度を活用する
NISAやiDeCoは、直接的に社会保険料を減らす制度ではありませんが、節税効果により手取りを増やす効果があります。
NISAは運用益が非課税になるため、効率的に資産を増やすことができます。
また、iDeCoは支払った掛金が全額所得控除になるため、所得税・住民税の負担を軽減できます。その分、社会保険料を支払っていても手取りを増やすことができます。
働き方を見直す
社会保険料の負担が重いと感じる場合、働き方自体を見直すことも選択肢の一つです。
配偶者などの扶養に入ることが可能であれば、社会保険料の自己負担をなくすことができます。ただし、年収が下がり手取り収入もダウンする可能性があります。
また、会社員を辞めて自営業者になるなど、働き方を変えることで、社会保険から国民健康保険・国民年金に切り替える方法もあります。
国民健康保険料は所得や家族状況などによって変わるため、収入が少ない場合は社会保険料よりも安くなる場合があります。
社会保険料を払うことで受けられる保障
「高すぎる」と感じる社会保険料ですが、負担に応じてさまざまな保障を得ることができます。
病気や怪我の保障:傷病手当金など
社会保険に加入していると、病気や怪我で働けなくなった場合に「傷病手当金」が支給されます。これは給与の約2/3にあたる金額が通算1年6ヶ月支給される制度で、働けない期間の生活を支えます。
国民健康保険にはこの制度がなく、会社員ならではの保障といえます。
老後の年金受給額に反映される
社会保険料のうち、厚生年金保険料は老後の年金受給額を決定する重要な要素です。厚生年金保険料を多く支払うほど、将来受け取れる年金額が増えます。
これにより、会社員は国民年金のみの人に比べて、より手厚い老後収入が期待できます。
出産・育児で利用できる制度がある
健康保険や雇用保険に加入していると、出産手当金や育児休業給付金などの給付を受けることができます。また、産休中や育児休業中は、保険料が免除される制度もあるため、経済的な負担を軽減できます。
こうした手当や保険料免除措置は、保険料を払っているからこそ受けられる恩恵です。
まとめ
「社会保険料が高い」と感じる理由には、負担額の大きさや保険料率が上昇傾向にあることが挙げられます。
負担を軽減するには、4〜6月の残業を減らすなど標準報酬月額を下げる工夫が有効です。また、扶養に入る、国民健康保険へ切り替えるといった選択肢もあります。
しかし、社会保険料は病気や怪我、出産・育児、老後の生活などを支えるための大切な備えです。保険料を多く支払うほど、将来の年金額が増えるなど受けられる保障も手厚くなります。
「高い」と感じるだけでなく、保険料の負担と受けられる社会保障を総合的に判断することが大切です。自分にとって最適な制度や働き方を見つけましょう。
社会保険料が気になるあなたへ
これから先、お金の不安なく暮らすために、将来に必要なお金を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をスムーズに進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶2025年に変わるお金の制度セミナー:お金に関する最新の制度をやさしく解説
▶賢いお金の増やし方入門:30分の無料オンラインセミナー
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
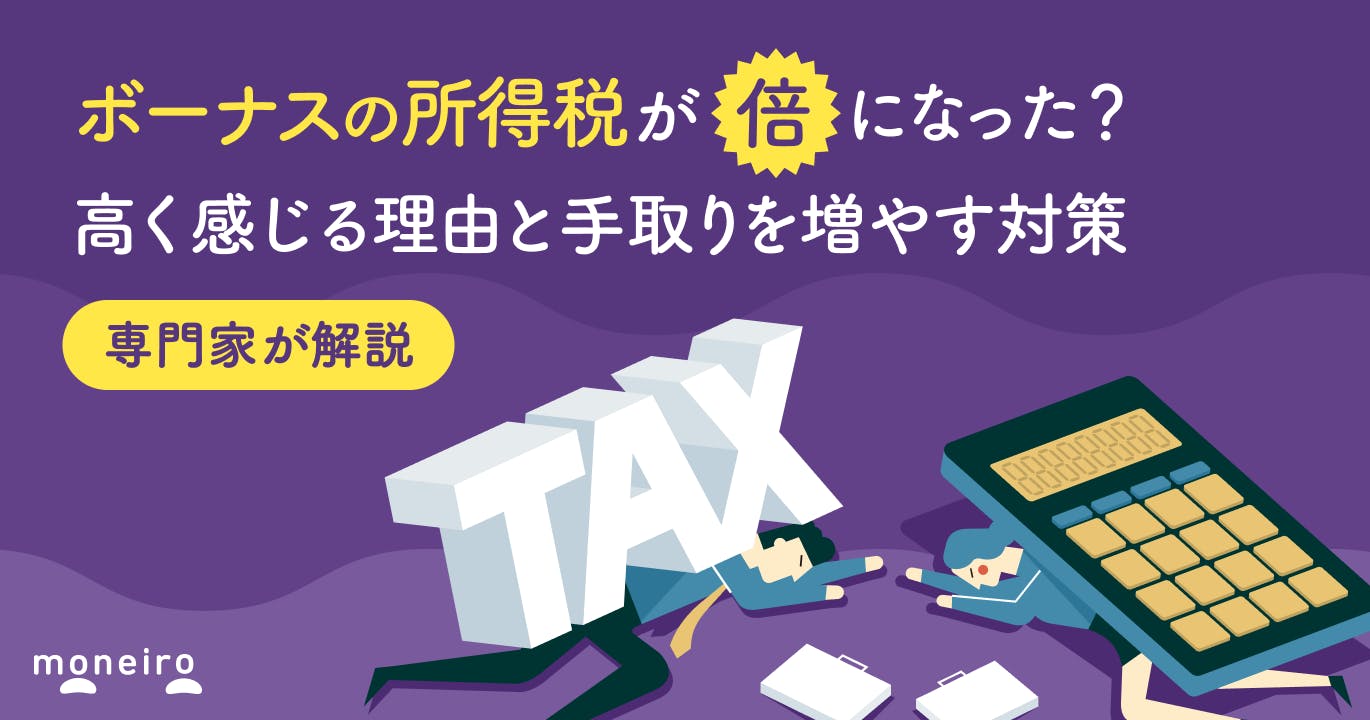
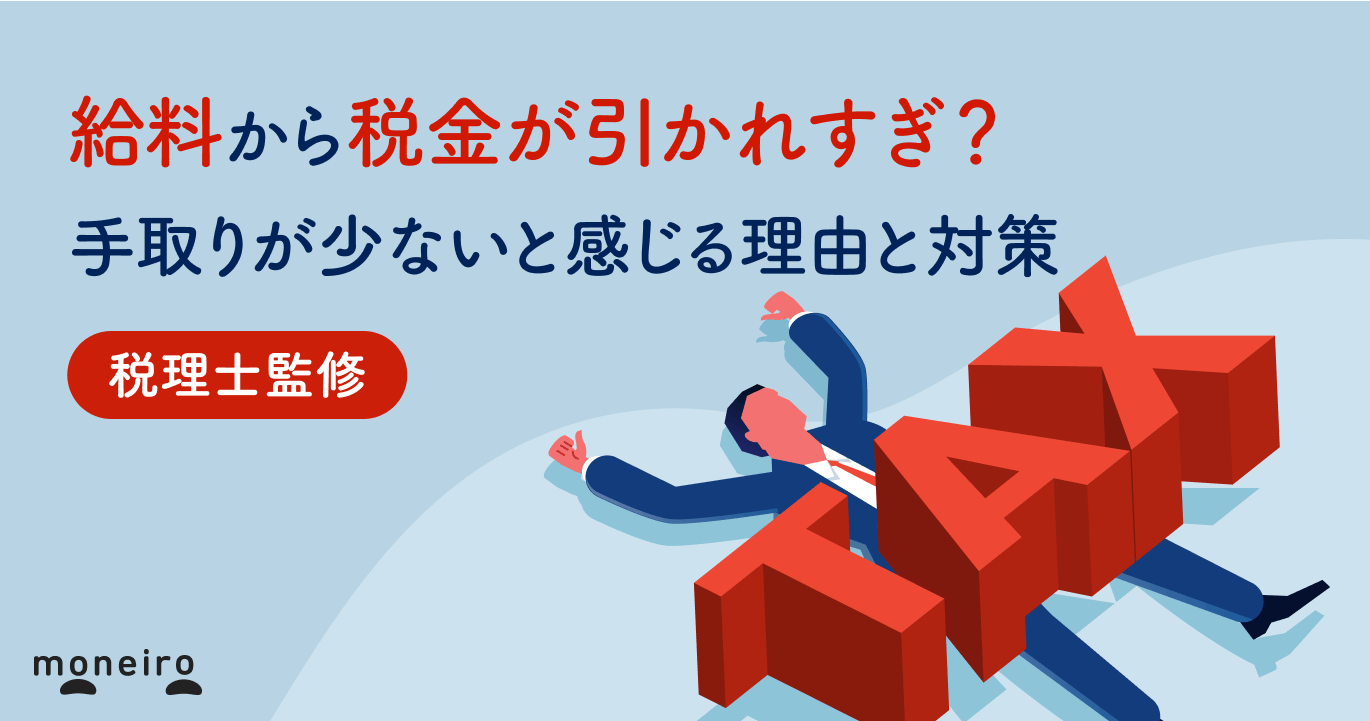
給料から税金が引かれすぎ?手取りが少ないと感じる理由と対策をわかりやすく解説
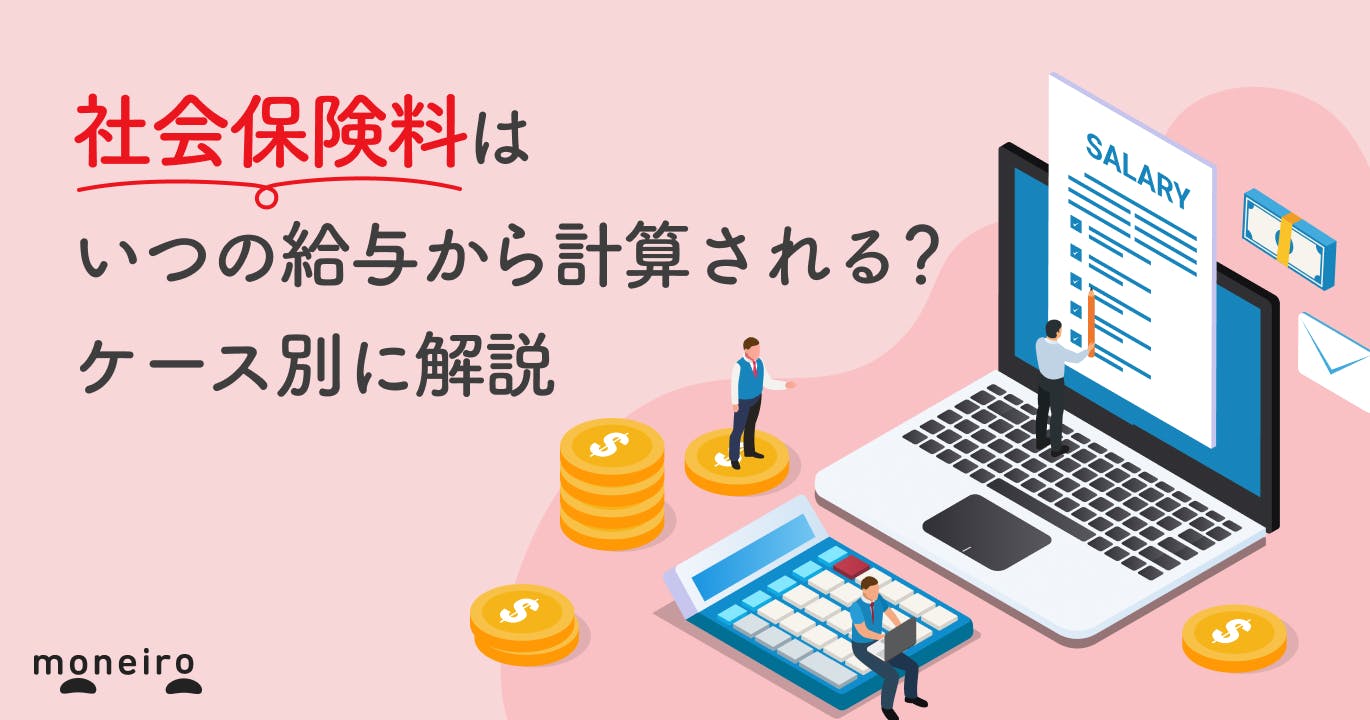
社会保険料はいつの給与から計算される?給与支払い日のケース別に解説
監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。