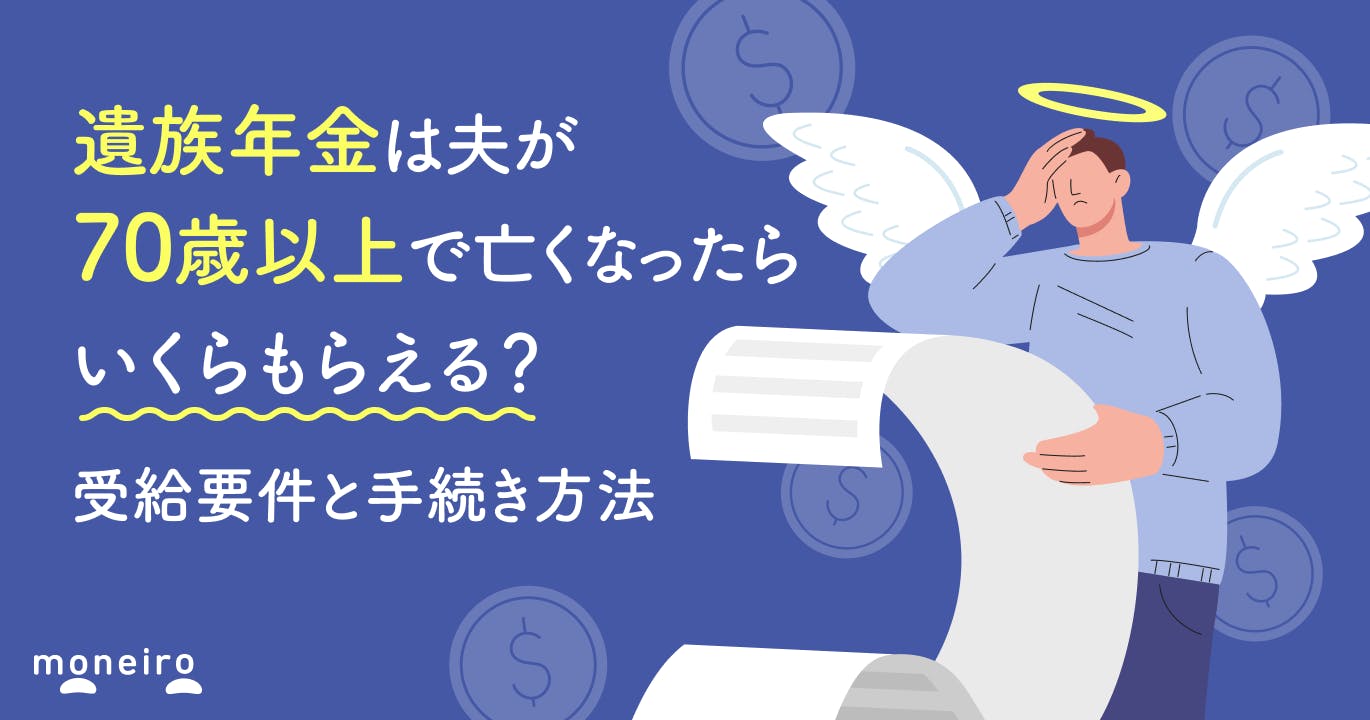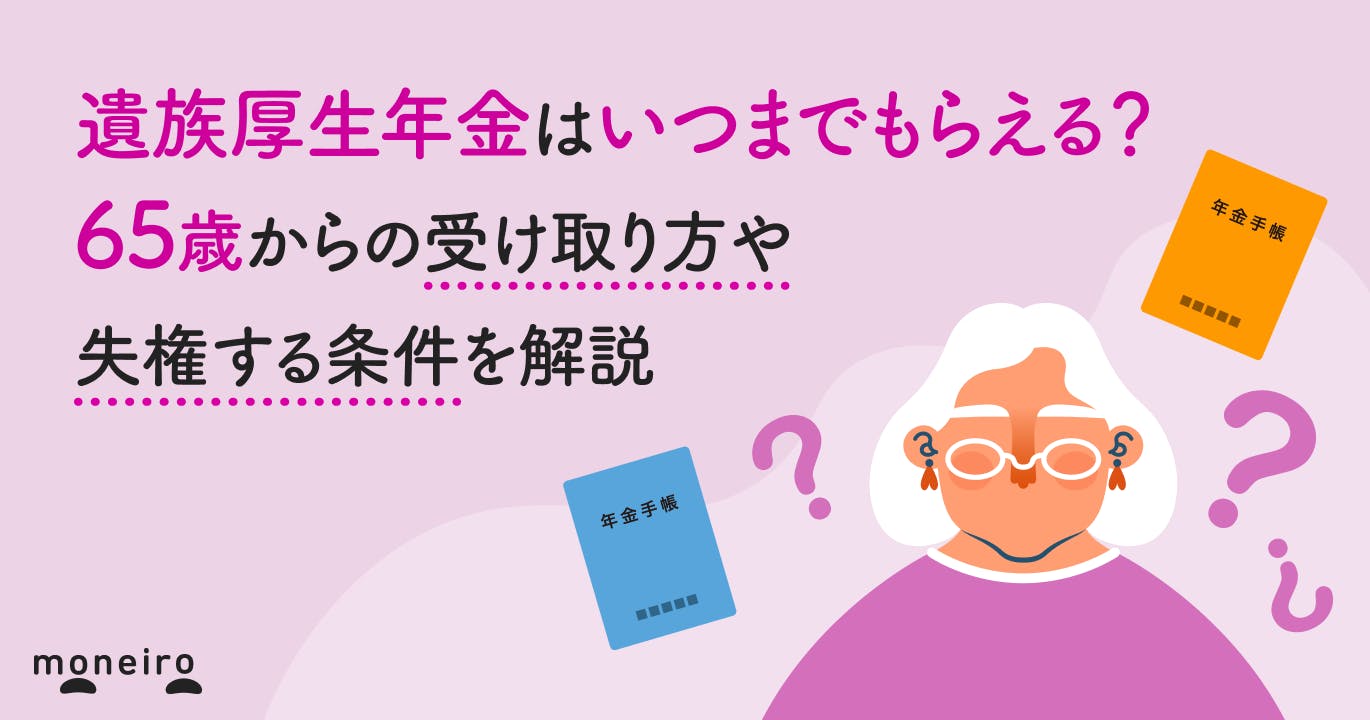
遺族年金は夫が70歳以上で亡くなったらいくらもらえる?受給要件と手続き方法
≫年金と貯金で足りる?あなたの不足金額をチェック
「夫が70歳で亡くなったが、遺族年金はもらえる?」「既に自分の年金を受け取っているけれど、併せて受け取れる?」と、70歳以上で夫を亡くした人の多くは、自身がもらえる遺族年金について詳しく知りたいと思っているでしょう。
遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、受給できるかどうかは年齢や夫の加入状況によって異なります。
本記事では、70歳以上でも受け取れる遺族年金の種類と条件、支給金額の目安、老齢年金との併給ルール、そして申請手続きの流れについて、専門家監修のもと、わかりやすく解説します。
- 遺族年金の種類と受給要件
- 遺族年金の金額の目安と計算方法
- 遺族年金と老齢年金の併給関係
年金について知りたいあなたへ
お金の疑問を解決する無料サービスをご利用いただけます
▶老後資金の無料診断:将来の必要額を3分で診断
▶年金の基本と老後資金準備:30分の無料オンラインセミナー
▶老後資金の無料相談会:老後への備えを専門家がアドバイス
70歳以上でももらえる遺族年金の種類と要件
夫が70歳以上で亡くなった場合でも、遺族基礎年金や遺族厚生年金の受給要件を満たしていれば、妻は遺族年金を受け取ることが可能です。
どちらの年金が受け取れるかは、亡くなった夫の年金加入状況や、遺族の状況によって決まります。
遺族基礎年金は主に国民年金加入者が対象で、遺族厚生年金は厚生年金加入者が対象となります。それぞれの要件を正しく理解することが重要です。
遺族基礎年金の場合
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者であった方などが亡くなった場合に、その遺族に支給される年金です。
遺族基礎年金を受け取るための要件は、「18歳になった年の3月31日まで(障害等級1級・2級の場合は20歳未満)の子ども」がいることです。
受給対象者は、亡くなった人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子ども自身」に限られます。
夫が70歳以上で亡くなった場合、子どもがこの年齢要件を満たしているケースは少なく、多くの場合、妻は遺族基礎年金の対象外となります。
また、亡くなった夫側にも要件があり、以下のいずれかに該当する必要があります。
- 国民年金の被保険者である間に死亡した
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満で、日本国内に住所を有していた人が死亡した
- 老齢基礎年金の受給者であった、または受給資格期間が25年以上あった人が死亡した
遺族厚生年金の場合
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者であった人などが亡くなった場合に支給される年金です。遺族基礎年金とは異なり、子どものいない妻も受給対象となります。
夫が70歳以上で亡くなった場合、こちらの遺族厚生年金が主な生活の支えとなるケースが多くなります。
受給できる遺族には優先順位があり、最も優先順位が高いのは「配偶者」と「子」です。妻の場合、年齢の要件はなく、夫に生計を維持されていれば受給権が発生します。
ただし、30歳未満で子どものいない妻の場合は、支給期間が5年間に限定される点に注意が必要です。
亡くなった夫側にも、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 厚生年金保険の被保険者である間に死亡した
- 厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡した
- 老齢厚生年金の受給者であった、または厚生年金保険の受給資格期間が25年以上あった人が死亡した
- 1級・2級の障害厚生年金を受給していた人が死亡した
夫が受給中に亡くなった場合・受給前に亡くなった場合の違い
夫が亡くなった状況が、老齢厚生年金をすでに受け取っていたか、まだ受け取る前だったかによって、適用される受給要件が異なります。
しかし、どちらのケースでも遺族厚生年金の対象となる可能性があります。
老齢厚生年金を受給中に亡くなったケース
70歳以上の夫が亡くなった場合、多くはこのケースに該当します。夫が既に老齢厚生年金の受給権者であった場合、その夫によって生計を維持されていた妻は、遺族厚生年金を受け取ることができます。
つまり、夫が老齢年金生活に入った後に亡くなったとしても、遺族年金の受給要件を満たしていれば、妻の生活を支える保障がなくなるわけではありません。
現役で厚生年金保険に加入中に亡くなったケース
近年では70歳を超えても働き続け、厚生年金保険に加入している方も増えています。もし夫が厚生年金保険の被保険者である間に亡くなった場合も、遺族厚生年金の支給対象となります。
この場合、厚生年金保険に加入中で、かつ保険料納付要件を満たしていれば、遺族厚生年金の受給権が発生します。
これは「短期要件」のうちの一つで、比較的短い加入期間でも遺族の生活が保障される仕組みになっています。
夫が70歳以上で亡くなった場合の遺族年金の金額目安
夫が70歳以上で亡くなった場合の遺族年金の金額の目安と計算方法について、詳しく見ていきましょう。
遺族厚生年金の基本的な計算式(報酬比例部分×3/4)
遺族厚生年金の年金額は、亡くなった方の老齢厚生年金の**「報酬比例部分」の4分の3**と定められています。
この報酬比例部分は、厚生年金保険への加入期間と、その間の給与や賞与の平均額に基づいて計算されます。具体的には、年金の計算方法が変更された平成15年(2003年)4月を境に、計算式が分かれています。
- 平成15年3月まで:平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月までの加入月数
- 平成15年4月以降:平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以降の加入月数
簡単に言えば、「現役時代の平均収入」と「加入期間」が金額を決める要素です。この計算で算出された老齢厚生年金の報酬比例部分に4分の3を乗じた額が、遺族厚生年金の基本額となります。
なお、厚生年金保険の加入期間が300月(25年)に満たない場合は、300月とみなして計算する保障措置があり、若くして亡くなった場合でも一定額が保障される仕組みになっています。
老齢年金を受け取っている場合の併給調整
妻自身が65歳以上で自分の老齢厚生年金を受け取っている場合、遺族厚生年金を満額受け取ることはできません。この場合、妻自身の老齢厚生年金が優先して全額支給されます。
その上で、夫の死亡により計算された遺族厚生年金の額が、妻自身の老齢厚生年金の額を上回る場合に限り、その差額分が遺族厚生年金として支給される仕組みです。
例えば、妻の老齢厚生年金が年額70万円、夫から計算される遺族厚生年金が年額90万円だったとします。この場合、まず妻の老齢厚生年金70万円が支給され、差額の20万円(90万円 - 70万円)が遺族厚生年金として上乗せして支給されます。
遺族厚生年金の額が妻の老齢厚生年金より少ない場合は、遺族厚生年金は支給されません。
年金について知りたいあなたへ
お金の疑問を解決する無料サービスをご利用いただけます
▶老後資金の無料診断:将来の必要額を3分で診断
▶年金の基本と老後資金準備:30分の無料オンラインセミナー
▶老後資金の無料相談会:老後への備えを専門家がアドバイス
遺族年金と自分の老齢年金は併給できる?
遺族年金と自身の老齢年金を両方満額受け取ることはできません。
年金の種類によって、どちらか一方を選択するか、調整された金額が支給される仕組みになっています。
特に65歳を過ぎて自身の老齢年金の受給が始まると、この併給調整が重要になります。
どの組み合わせで受け取るのが最も有利になるかは個々の状況によって異なるため、制度を正しく理解しておくことが大切です。
遺族基礎年金と老齢年金は「どちらか一方のみ」
遺族基礎年金と自身の老齢基礎年金は、同時に両方を受け取ることはできません。受給権が両方発生した場合は、どちらか一方の年金を選択して受給することになります。
一般的に、自営業者だった方などが受け取る老齢基礎年金のみの場合、遺族基礎年金の額のほうが大きくなることが多いため、遺族基礎年金を選択する方が有利になる傾向があります。
一方で、会社員だった場合などで老齢厚生年金も受け取れる場合は、老齢年金の合計額のほうが多くなることがほとんどです。
遺族厚生年金と老齢年金は「併給可」だが条件あり
遺族厚生年金と自身の老齢年金の組み合わせは、遺族基礎年金の場合よりも複雑です。併給できるケースと、調整が必要なケースがあります。
併給できる主なケース(老齢基礎年金+遺族厚生年金)
65歳以上の人が受け取る年金の組み合わせとして最も一般的なのが、自身の「老齢基礎年金」と、亡くなった配偶者の「遺族厚生年金」を同時に受け取るケースです。
日本の公的年金制度は、国民年金(基礎年金)が1階部分、厚生年金保険が2階部分という構造になっています。このルールでは、異なる階層の年金(1階部分の老齢基礎年金と2階部分の遺族厚生年金)であれば、それぞれ満額を併給することが認められています。
これにより、自身の基礎的な老後保障を確保しつつ、配偶者が遺した厚生年金分を上乗せして受け取ることが可能になります。
選択が必要なケース(老齢厚生年金+遺族厚生年金)
自身の老齢厚生年金と遺族厚生年金は、同じ2階部分の年金であるため、両方を満額受け取ることはできません。65歳以降、この2つの年金の受給権がある場合は、調整が行われます。
基本的なルールは、自身の老齢厚生年金が全額優先して支給され、遺族厚生年金の額がそれを上回る場合に、その差額分が支給されるというものです。
ただし、より有利な受給額となるよう、実際には以下のいずれか大きい方の金額が支給額として選択されます。
- 亡くなった人の老齢厚生年金額の4分の3(本来の遺族厚生年金額)
- 亡くなった人の老齢厚生年金額の2分の1 + 自身の老齢厚生年金額の2分の1
この計算により、自身で納めた保険料が年金額に反映されにくくなるという不公平感をなくすための配慮がなされています。
遺族年金を受け取るための手続きと必要書類
遺族年金は自動的に支給されるものではなく、自身で請求手続きを行う必要があります。手続きには期限があり、必要書類も多岐にわたるため、事前に準備を進めることが重要です。
今後の生活を支える大切な収入源ですので、落ち着いて一つずつ進めていきましょう。
請求の期限は「死亡日の翌日から5年以内」
遺族年金の請求権には時効があり、原則として死亡日の翌日から5年以内に手続きを行う必要があります。この期間を過ぎてしまうと、年金を受け取る権利そのものが消滅してしまうため、注意が必要です。
夫の死後、さまざまな手続きに追われることになりますが、遺族年金の請求は特に重要な手続きの一つです。他の手続きと並行して、できるだけ早めに準備を始めることを推奨します。
手続き先は夫の年金加入状況で異なる
遺族年金の請求手続きを行う窓口は、亡くなった夫の年金加入状況によって異なります。間違った場所に行くと二度手間になってしまうため、事前に確認しておきましょう。
厚生年金加入者 → 年金事務所
亡くなった夫が会社員や公務員で、厚生年金保険に加入していた場合(または加入歴があった場合)は、近くの年金事務所または街角の年金相談センターが手続きの窓口となります。
遺族厚生年金と遺族基礎年金の両方を請求する場合も、年金事務所で一括して手続きができます。事前に予約をしてから訪問すると、スムーズに相談や手続きを進めることができます。
国民年金加入者 → 市区町村役場
亡くなった夫が自営業者などで、国民年金のみに加入していた場合は、住んでいる市区町村役場の国民年金担当窓口で手続きを行います。
このケースでは、請求する年金は遺族基礎年金のみとなります。手続きに必要な書類など、不明な点があれば事前に電話で確認しておくと良いでしょう。
必要書類一覧(戸籍謄本・死亡診断書・年金証書など)
遺族年金の請求には、亡くなった方との関係や生計維持関係を証明するために、さまざまな書類が必要です。事前に準備しておくことで、手続きが円滑に進みます。
一般的に必要となる主な書類は以下の通りです。
- 年金請求書
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 戸籍謄本(死亡者との続柄を確認)
- 世帯全員の住民票の写し
- 死亡者の住民票の除票
- 死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
- 請求者の収入が確認できる書類(所得証明書など)
- 受取先金融機関の通帳
なお、請求書にマイナンバーを記入することで、住民票や所得証明書などの一部の書類は省略できる場合があります。
また、死亡の原因や家族構成によって追加で書類が必要になることもあるため、手続き先の窓口に事前に確認することを推奨します。
まとめ
今回は、70歳以上の夫が亡くなった場合の遺族年金について、種類や要件、金額の目安、手続き方法などを解説しました。
- 70歳以上でも要件を満たせば遺族年金は受給可能
- 遺族基礎年金は「子のいる配偶者」が対象だが、遺族厚生年金は「子のいない妻」も対象となる
- 遺族厚生年金の額は、夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4が目安
- ご自身の老齢年金と併給する場合、満額を両方もらえるわけではなく調整が行われる
- 請求手続きは死亡日の翌日から5年以内に行う必要がある
遺族年金は、残された家族の生活を支えるための重要な制度です。しかし、制度が複雑で、ご自身のケースでいくら受け取れるのか判断が難しい場合も少なくありません。
まずは制度の基本を理解し、不明な点があれば年金事務所や社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。
もしもの時のお金の不安解消へ。遺族年金だけでは足りない分を3分で見える化しませんか?
≫あなたの不足額はいくら?将来の必要額を3分で診断(無料)
年金について知りたいあなたへ
お金の疑問を解決する無料サービスをご利用いただけます
▶老後資金の無料診断:将来の必要額を3分で診断
▶年金の基本と老後資金準備:30分の無料オンラインセミナー
▶老後資金の無料相談会:老後への備えを専門家がアドバイス
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
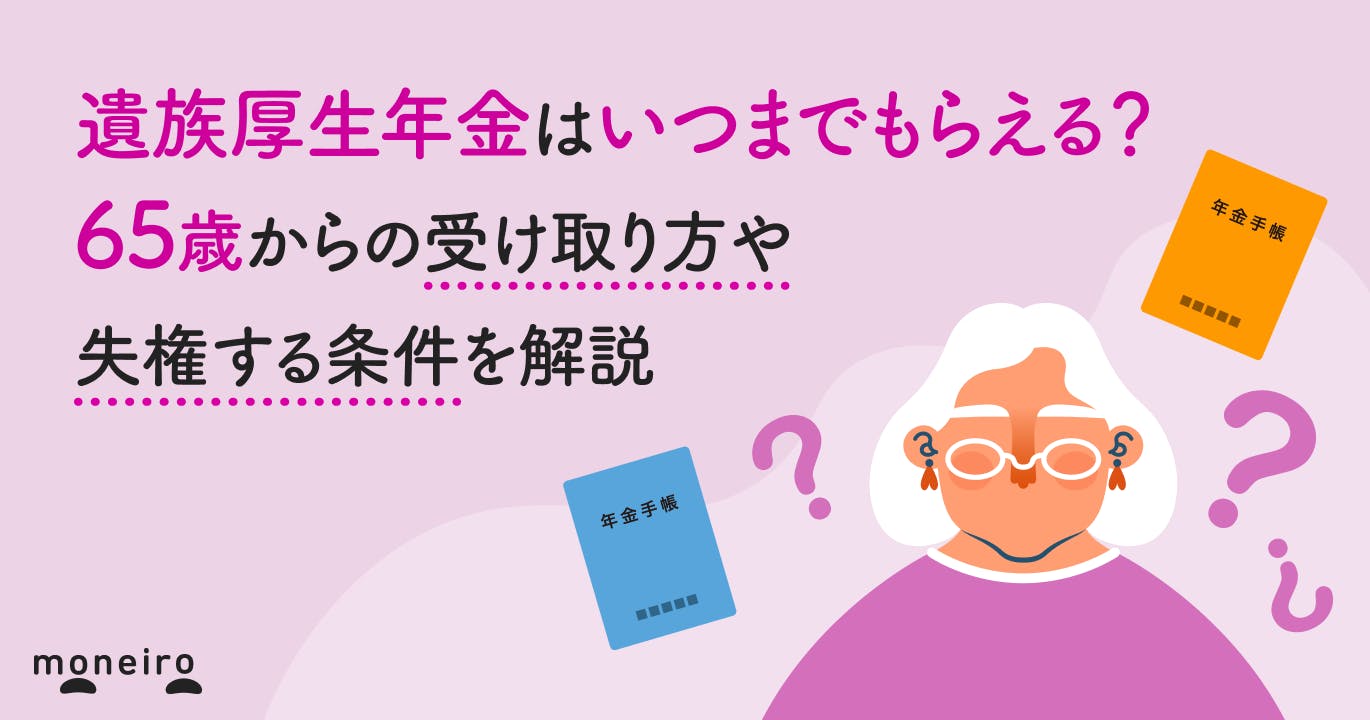
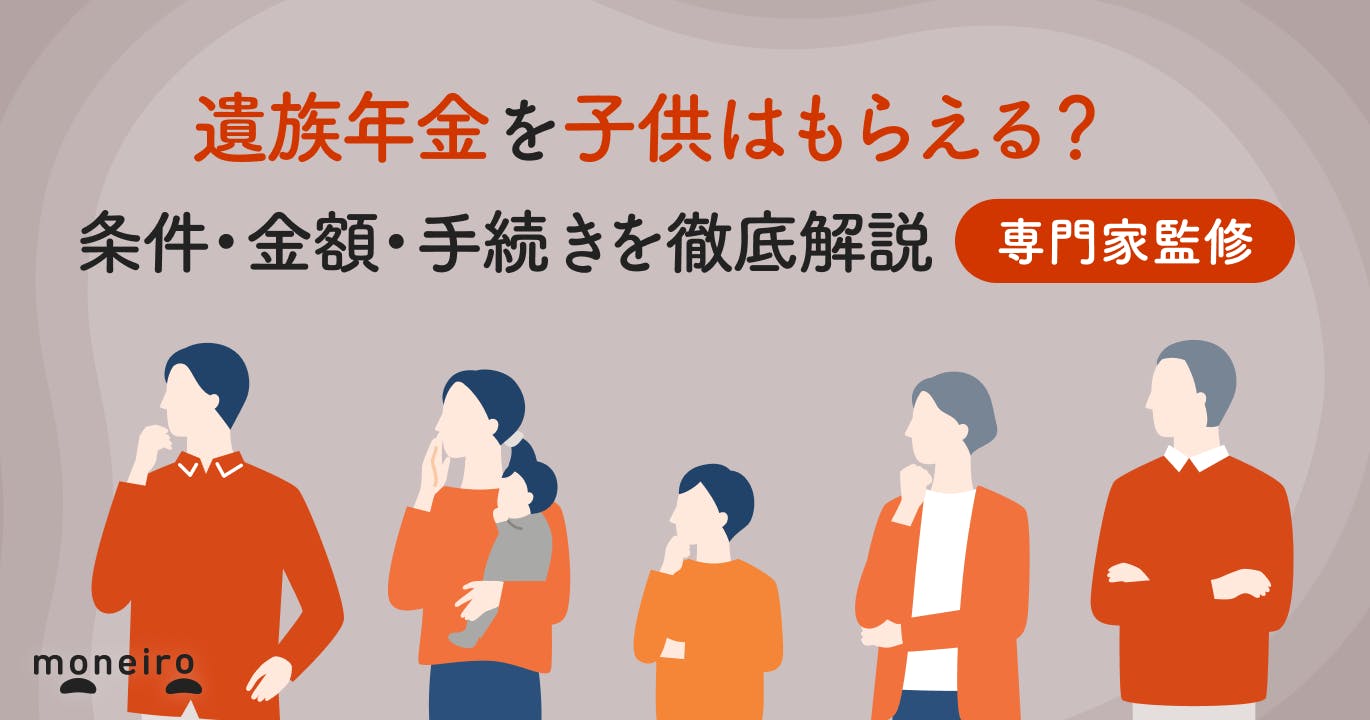
遺族年金を子供はもらえる?専門家が条件・金額・手続きをわかりやすく解説
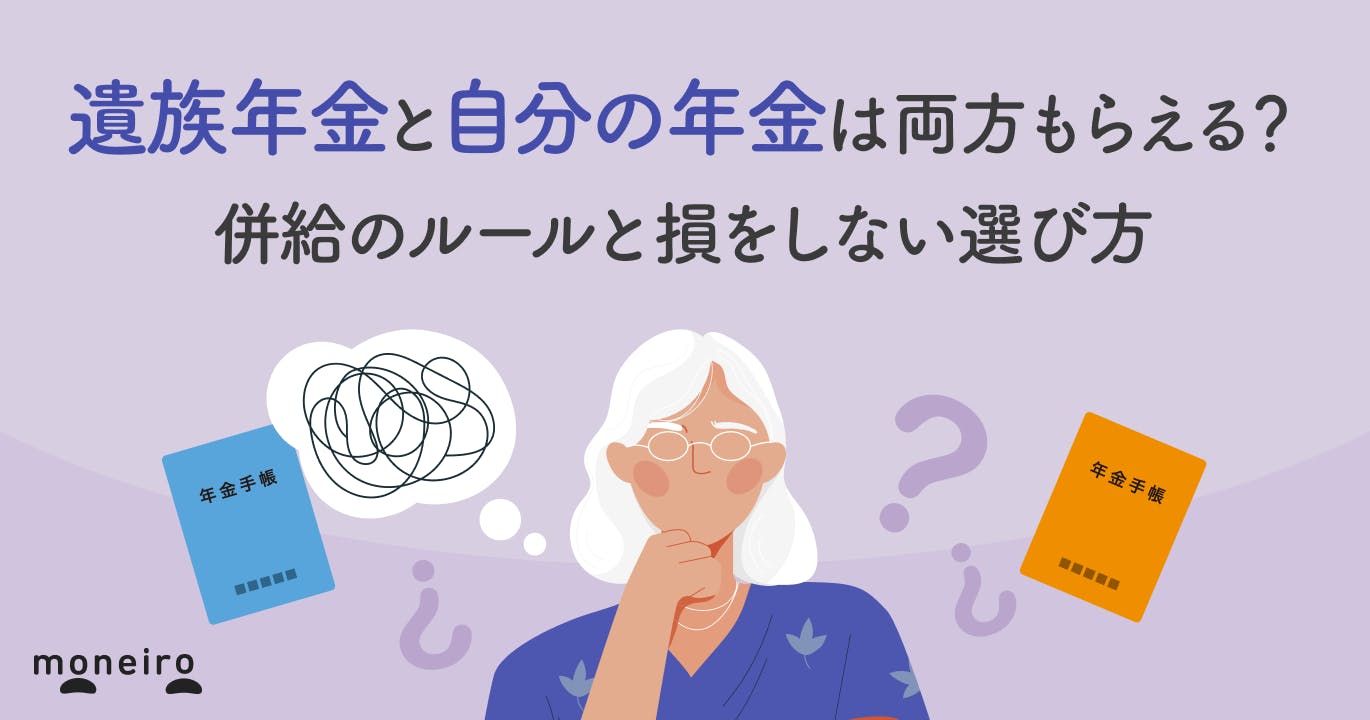
遺族年金と自分の年金は両方もらえるの?併給のルールと損をしない選び方を解説
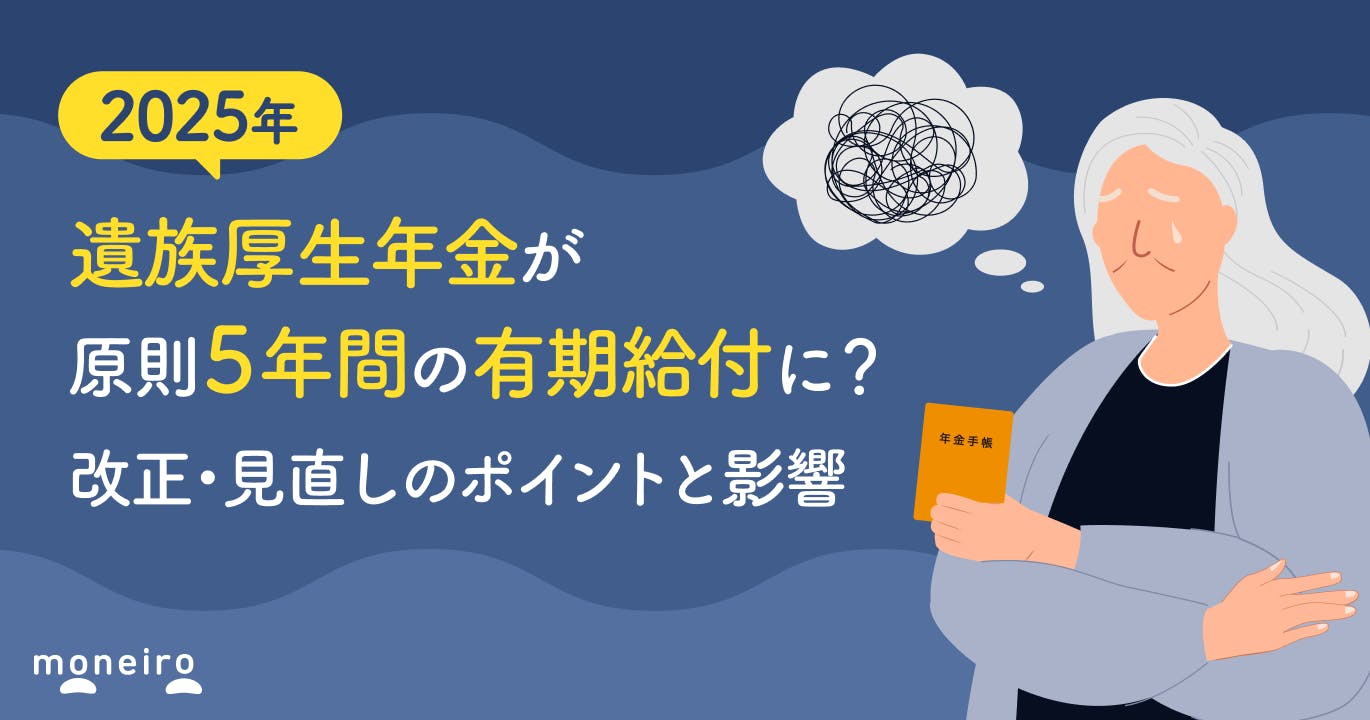
遺族厚生年金が改正で原則5年間の有期給付に?2025年制度見直しのポイントと影響
監修
山本 務
- 特定社会保険労務士/AFP/第一種衛生管理者
東京都練馬区で、やまもと社会保険労務士事務所を開業。企業の情報システム、人事部門において通算28年の会社員経験があるのが強みであり、情報システム部門と人事部門の苦労がわかる社会保険労務士。労務相談、人事労務管理、就業規則、給与計算、電子申請が得意であり、労働相談は労働局での総合労働相談員の経験を生かした対応ができる。各種手続きは電子申請で全国対応が可能。また、各種サイトで人事労務関係の記事執筆や監修も行っている。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。