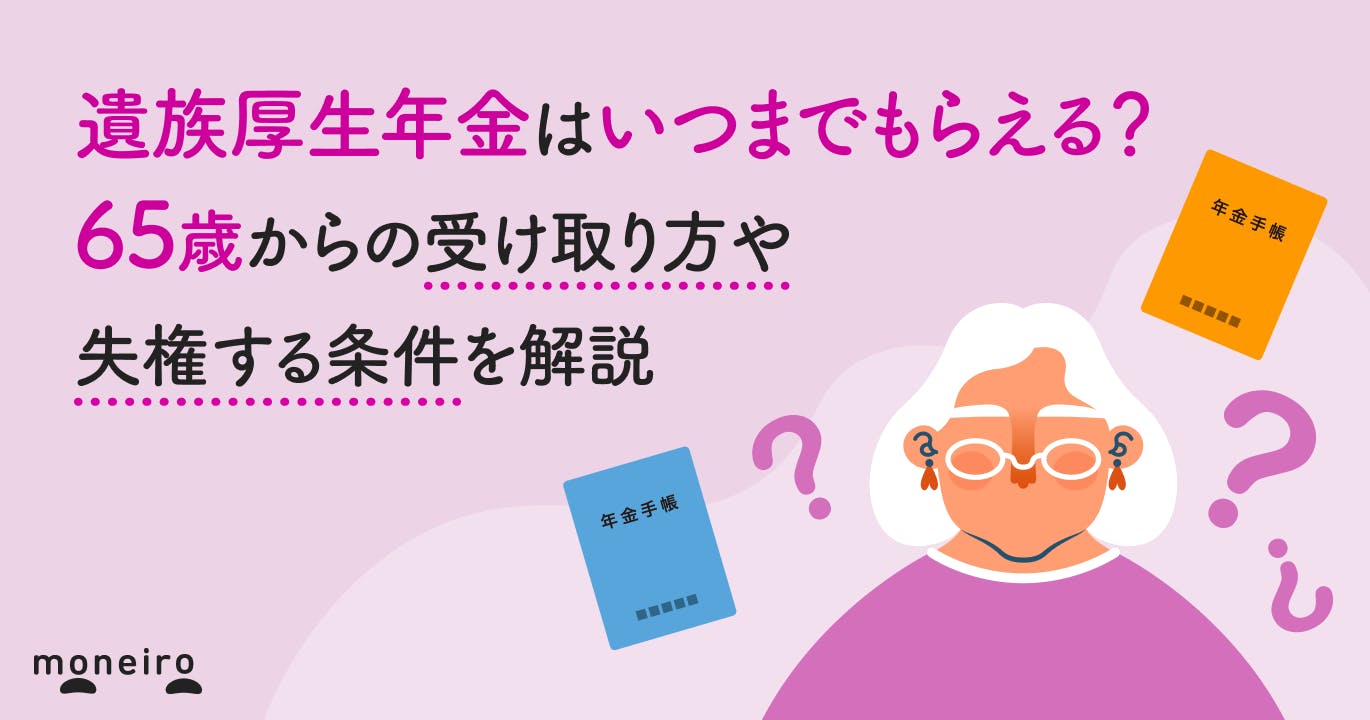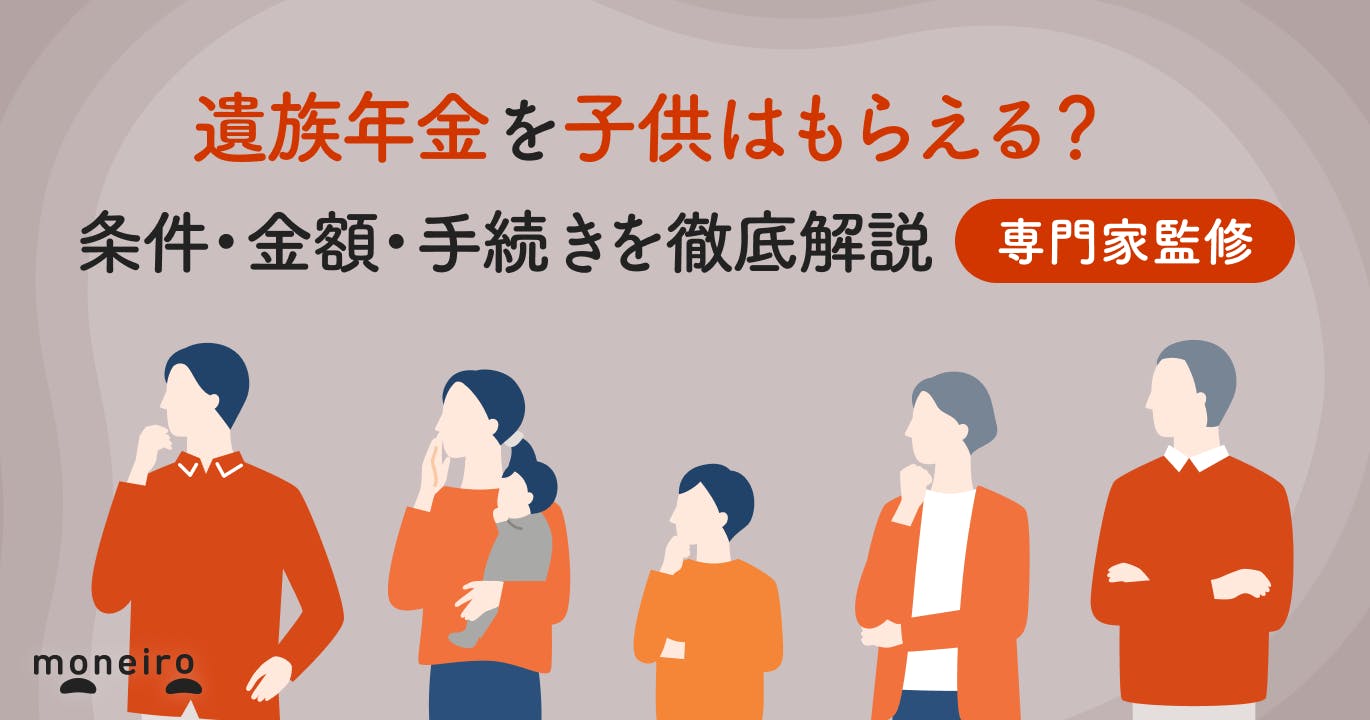
遺族厚生年金はいつまでもらえる?65歳からの受け取り方や失権する条件を解説
>>もしもの備えは大丈夫?将来の必要金額を簡単診断
「遺族厚生年金がもらえるのはいつまで?」そんな疑問を抱えていませんか?遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者、または被保険者だった人が亡くなった場合に、遺族の生活を支えるために支給される大切な制度です。
この記事では、遺族厚生年金の基本的な受給期間や、妻・夫・子といった立場別の具体的な受給条件、さらには65歳以降の受け取り方、さらに2028年の制度見直しも含めてわかりやすく解説します。ぜひ、年金制度の理解を深め、将来に備えるための参考にしてみてください。
- 遺族厚生年金の原則的な受給期間と、受給資格を失う具体的な条件
- 妻、夫、子、父母、孫など、遺族の立場に応じた受給期間や条件の詳細
- 65歳以降の自分の年金との調整方法や加算の特例
将来のお金が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
遺族厚生年金の受給期間はいつまで?立場ごとに解説
遺族厚生年金は、遺族の所得を保障するために支給される年金です。しかし、その受給期間は遺族の立場や状況によって異なります。
例えば、子がいない30歳未満の妻は、遺族厚生年金を5年間しか受給できません。一方、子がいる配偶者や、一定年齢以上の配偶者など、特定の要件を満たす場合には、より長期間、または一生涯にわたって受給できるケースもあります。
自分のケースがどの要件に該当するか、以下でしっかり把握しておきましょう。
妻の場合
死亡した人に生計を維持されていた妻は、遺族厚生年金の受給対象の第一順位(子のある妻)に位置づけられます。子がいない妻の場合は、年齢によって受給条件が異なり、30歳未満であれば支給期間は5年間に限定されます。
一方で、子がいて遺族基礎年金を受給していた妻が、その後子の成長により遺族基礎年金の支給が終了しても、妻自身が40歳以上65歳未満であれば「中高齢寡婦加算」が加算され、引き続き遺族厚生年金を受けることができます。
夫の場合
死亡した人に生計を維持されていた夫も、遺族厚生年金の受給対象となります。子のある夫は、妻と同様に第一順位に位置づけられ、遺族基礎年金と合わせて遺族厚生年金を受給できます。
一方、子のいない夫の場合は、死亡当時に55歳以上であることが受給資格の条件となります。この場合、年金の支給は原則として60歳から開始されます。ただし、遺族基礎年金を同時に受け取れる場合に限り、55歳から60歳の間でも遺族厚生年金を受け取ることが可能です。
子の場合
遺族厚生年金の受給期間は、子の場合、原則として18歳到達年度末(3月31日)までです。
ただし、20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある場合は、20歳になるまで受給期間が延長されます。
遺族厚生年金の受給順位は、配偶者と子が同順位ですが、配偶者が受給している場合、子が直接年金を受け取ることはできません。
父母・祖父母の場合
死亡した方に生計を維持されていた父母や祖父母も、遺族厚生年金の受給対象者となる場合があります。
受給順位は配偶者と子に次ぐ第二順位が父母、第三順位が孫、そして第四順位が祖父母となります。父母および祖父母が遺族厚生年金を受給できるのは、原則として死亡当時に55歳以上である場合に限られ、年金の支給は60歳からとなります。
孫の場合
孫が遺族厚生年金を受給できるのは、子と同様に、原則として18歳になった年度の3月31日までです。ただし、20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある場合は、特例として20歳になるまで受給が継続されます。
孫が遺族厚生年金の受給対象となるのは、死亡した被保険者の子がすでに死亡しているなど、受給順位で孫が最上位となる場合に限られます。
65歳になったら遺族厚生年金はどうなる?受け取り方の変更点
65歳以降は、自身の老齢厚生年金を受け取る権利も発生するため、遺族厚生年金との関係が複雑になります。実際の受け取り方について確認しておきましょう。
65歳未満の受け取り方
65歳未満で(特別支給の)老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方の受給権がある場合、原則としていずれか一方を選択して受給することになります。多くの場合、額の多いほうを選択することになるでしょう。
65歳以降の受け取り方
65歳以降の遺族厚生年金の受け取り方は次のように考えます。
まず、自分が納めてきた保険料に基づく「老齢厚生年金」が、全額そのまま支払われます。
次に、遺族年金の金額とご自身の老齢年金の金額を比べて、もし遺族年金の金額のほうが高ければ、その差額分だけが「遺族厚生年金」として上乗せで支払われます。逆に、老齢厚生年金のほうが高い場合は、遺族年金からの支払いはありません。
「2つの年金のうち、金額の高いほうの額が保障される」仕組みと考えると分かりやすいでしょう。自分自身の年金を基本とし、それで足りない分を遺族年金が補ってくれる、というイメージです。
将来のお金が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
遺族厚生年金がプラスされる「加算の特例」とは?
遺族厚生年金には、特定の条件を満たす場合に年金額が加算される特例があります。これらの加算は、主に遺族の生活をより手厚く保障することを目的として設けられています。詳しく確認しておきましょう。
中高齢寡婦加算
中高齢寡婦加算は、夫が亡くなった場合に、特定の条件に該当する妻が受ける遺族厚生年金に、40歳から65歳になるまでの間、年額62万3800円が加算される制度です。この加算を受けるための主な条件は以下の通りです。
- 夫が亡くなった時に、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻。
- 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳到達年度の末日(障害の状態にある場合は20歳に達した)等の理由で遺族基礎年金を受給できなくなった時。 ただし、夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上であることなど、さらに細かな要件も定められています。この加算は、配偶者を亡くした中高年の女性が経済的に困難な状況に陥ることを防ぐための重要な支援策です。
経過的寡婦加算
経過的寡婦加算は、昭和31年4月1日以前に生まれた妻を対象とした加算制度です。具体的には、以下のいずれかに該当する場合に遺族厚生年金に加算されます。
- 昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生した時。
- 中高齢寡婦加算を受けていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達した時。この加算の目的は、中高齢寡婦加算が終了する65歳以降も、老齢基礎年金と合わせて中高齢寡婦加算と同額程度の年金が受け取れるように調整することで、長期的な生活の安定を図ることにあります。加算額は、昭和61年4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の額と合わせると、中高齢寡婦加算の額と同額程度となるよう決められています。
遺族厚生年金がもらえなくなる(失権する)主なケース
遺族厚生年金は一度受給が始まっても、特定の状況になると受給する権利を失う(失権する)ことがあります。主なケースをチェックしておきましょう。
1.受給者が死亡した場合
遺族厚生年金は、受給者の生計を支えるための制度であるため、受給者本人が死亡した場合には、その受給権は失われることになります。これは、年金制度の基本的な原則の1つです。
2.受給者が再婚(または事実婚)した場合
遺族厚生年金は、受給者が再婚した場合、または事実上の婚姻関係に入った場合にも受給権が失われます。これは、再婚によって新たな配偶者から生計を維持される状況になったとみなされるためです。事実婚も同様に、法律上の婚姻関係でなくとも、社会通念上夫婦と認められる関係であれば失権の対象となります。
なお、このルールは、配偶者だけでなく、父母、孫、祖父母など、すべての遺族に適用されます。
3.30歳未満の子のない妻の5年経過
子がなく、かつ30歳未満の妻が遺族厚生年金を受給する場合、受給開始から5年が経過するとその受給権が失われます。これは、子のいない比較的若い妻には、再就職や再婚などにより自立する機会が多いため、一定期間の経済的支援に限定されているためです。
4.子が18歳年度末に到達
子が遺族厚生年金を受給している場合、その子が18歳になった年度の3月31日を迎えると、原則として受給権は失われます。ただし、子が障害年金の障害等級1級または2級の状態にある場合は、特例として20歳になるまで受給が継続されます。
5.障害状態の回復
遺族厚生年金の受給要件として障害状態が定められている場合、その状態が回復し、障害等級に該当しなくなった場合には、遺族厚生年金の受給権は失われます。
2028年4月、遺族厚生年金の見直しへ
遺族厚生年金制度は、社会経済の変化に対応するため、2028年4月に見直しが実施される予定です。この見直しは、多くの受給者や将来の受給権者に影響を与える可能性があります。
主な変更点
2028年4月に施行予定の遺族厚生年金の見直しにおける主な変更点は以下の通りです。
有期給付の対象者と期間
18歳になった年度の末日までの子がいない、2028年度末時点で40歳未満の女性(年間約250人)が、原則5年間の有期給付の対象となります。
また、18歳になった年度の末日までの子がいない60歳未満の男性(年間約1万6千人)も、新たに5年間の有期給付の対象となります。
有期給付の増額と継続給付
5年間の有期給付の額には新規で「有期給付加算」が上乗せされ、現在の遺族厚生年金の額の約1.3倍になります。
また、5年間の有期給付終了後も、障害状態にある方(障害年金受給権者)や収入が十分でない方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受給できる「継続給付」の対象となります。
単身の場合、就労収入が月額約10万円(年間122万円、2025年度税制改正を反映すると132万円見込み)以下の人は、継続給付が全額支給されます。収入が増加するにつれて年金額が調整され、月額20~30万円を超えると継続給付は全額支給停止となる場合があります。
子がいる場合の変更点
18歳になった年度の末日までの子が養育されている間は、現行制度と同じであり、見直しの影響はありません。子が18歳になった後も、さらに5年間は増額された有期給付+継続給付の対象となります。
また、遺族基礎年金の「こどもがいる場合の加算額」が年間約23万5000円から28万円に増額されます。
見直しの影響を受けない人
以下に該当する人は今回の見直しによって受ける影響はありません。
- すでに遺族厚生年金を受給している人
- 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する人
- 18歳になった年度の末日までの子を養育する間にある人の給付内容
- 2028年度に40歳以上になる女性
遺族厚生年金に関するよくある質問
ここでは、遺族厚生年金に関してよく聞かれる質問とその回答をまとめました。
Q. 遺族厚生年金と自分の厚生年金はどちらももらえる?
遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金は、状況によって併給のルールが異なります。
- 65歳未満の場合:65歳になるまでは、遺族厚生年金と老齢厚生年金の両方を受け取ることはできません。原則として、金額の高いほうを選択して受け取ることになります。
- 65歳以降の場合:老齢厚生年金が優先して全額支給され、遺族厚生年金は差額分のみ上乗せされます。
なお、具体的な遺族厚生年金の支給額は、以下のどちらか高いほうが支給されます。
- 亡くなった人の年金の4分の3
- 亡くなった人の年金の半分と、自分の年金の半分を合わせた額
Q. 働きながらでも遺族厚生年金はもらえる?
遺族厚生年金は、受給者が働きながら収入を得ている場合でも受給は可能です。ただし、65歳以降は自分の老齢厚生年金との併給調整が行われるため、遺族厚生年金は全額支給されない場合があります。
2028年4月からの制度見直し後には、特に「継続給付」の対象者(有期給付終了後の受給者など)に対して、収入による調整が行われるようになります。
具体的には、就労収入が年間132万円(月額約10万円)を超えると、収入と年金の合計額が緩やかに増加するように年金額が調整されます。
Q. 遺族厚生年金の他に受け取れるお金はある?
遺族厚生年金の他に受け取れる公的な給付として、「寡婦年金」と「死亡一時金」があります。これらは、国民年金の第1号被保険者だった人が亡くなった場合に、遺族の生活を支える目的で支給されます。
遺族基礎年金や遺族厚生年金の受給要件を満たさない場合や、より手厚い保障が必要な場合に検討すべき、重要な制度です。
それぞれの給付には詳細な受給条件がありますので、自身の状況に合わせて確認することが大切です。
まとめ
遺族厚生年金は、被保険者が亡くなった際に遺族の生活を支えるための重要な年金制度です。原則として生涯受給が可能ですが、受給者の状況(年齢、子の有無、再婚など)に応じて期間が限定されたり、受給権が失われたりする場合があります。特に65歳以降は、自身の老齢厚生年金との併給調整の仕組みが適用されるため、自身の年金計画に影響を与える可能性があります。
また、中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算といった加算の特例は、特定の条件下で遺族の経済的支援を強化するものです。さらに、2028年4月には制度見直しが施行され、新たな有期給付や継続給付の仕組み、遺族基礎年金の加算額変更などが導入される予定です。
状況に合わせた年金受給計画を立てるには、記事で紹介した情報の他、厚生労働省などの情報も確認し、必要に応じて日本年金機構や年金相談窓口などの専門機関に相談することが重要です。適切な知識を持つことで、安心して将来に備えることができるでしょう。
>>もしもの備えは大丈夫?将来の必要金額を簡単診断
将来のお金が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
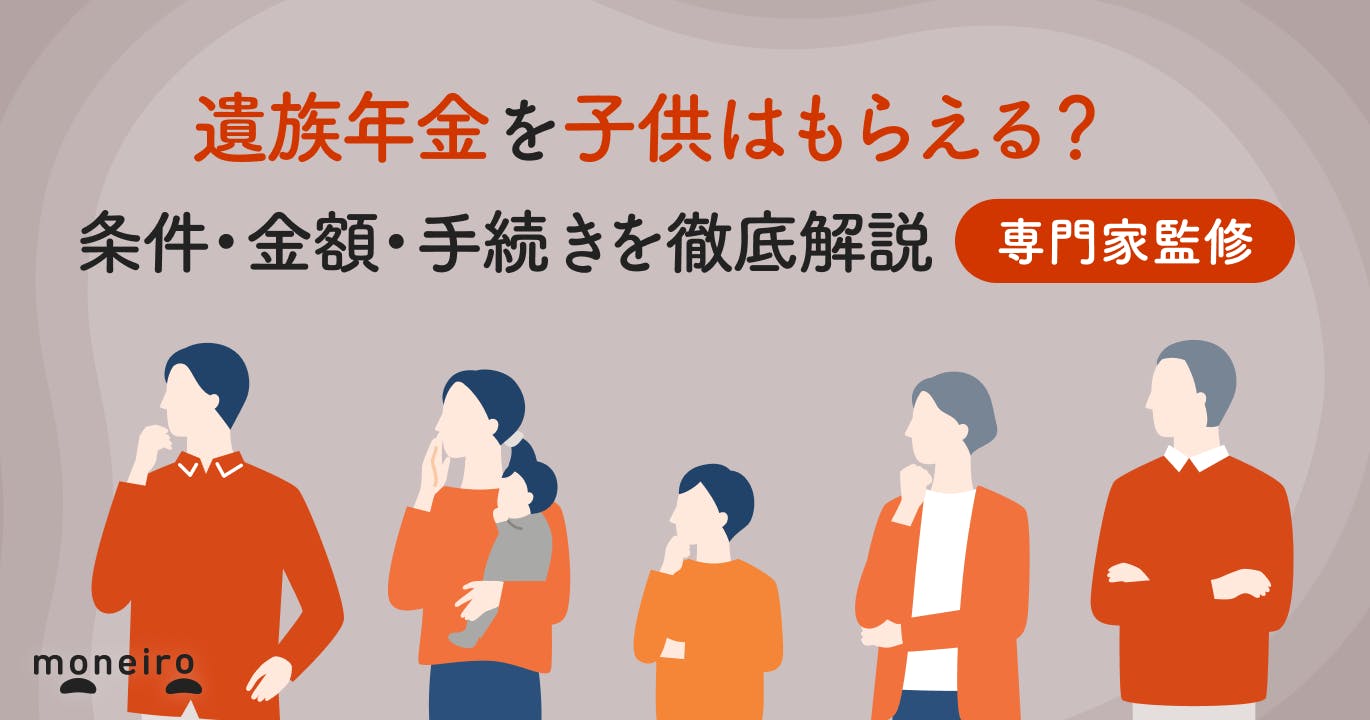
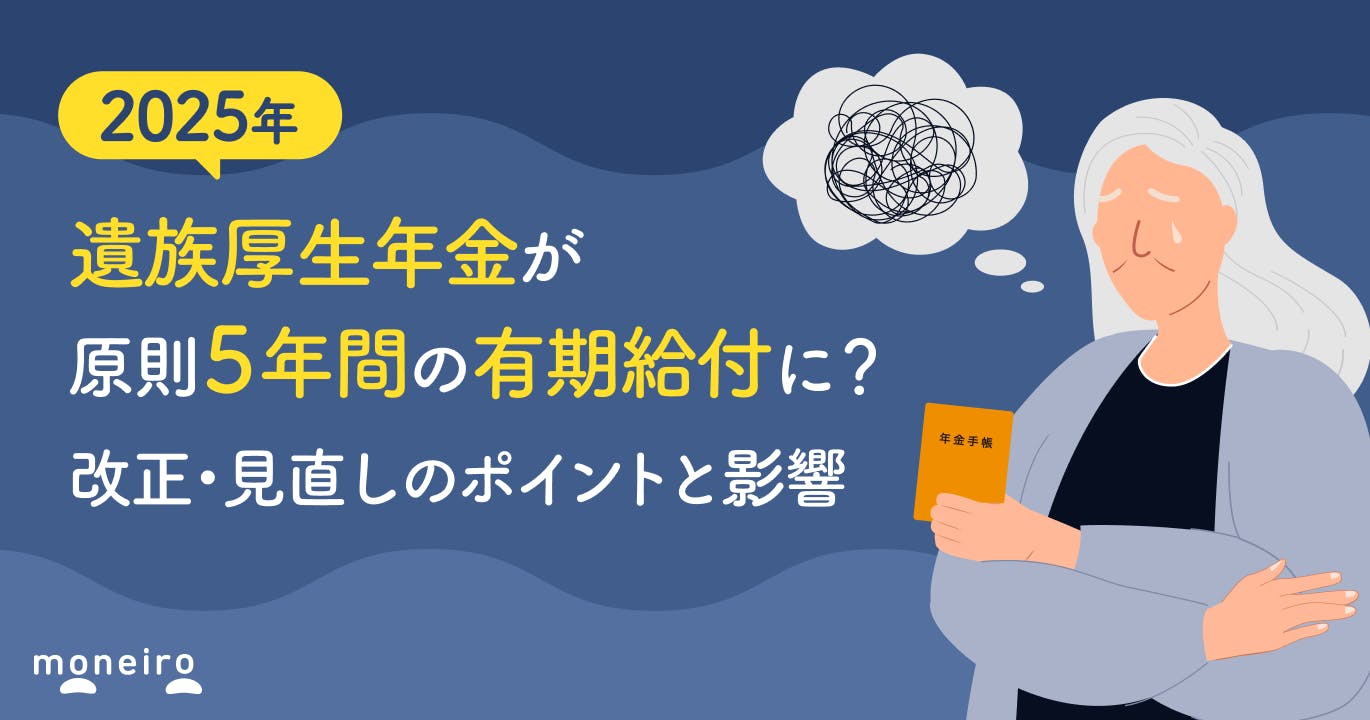
遺族厚生年金が改正で原則5年間の有期給付に?2025年制度見直しのポイントと影響
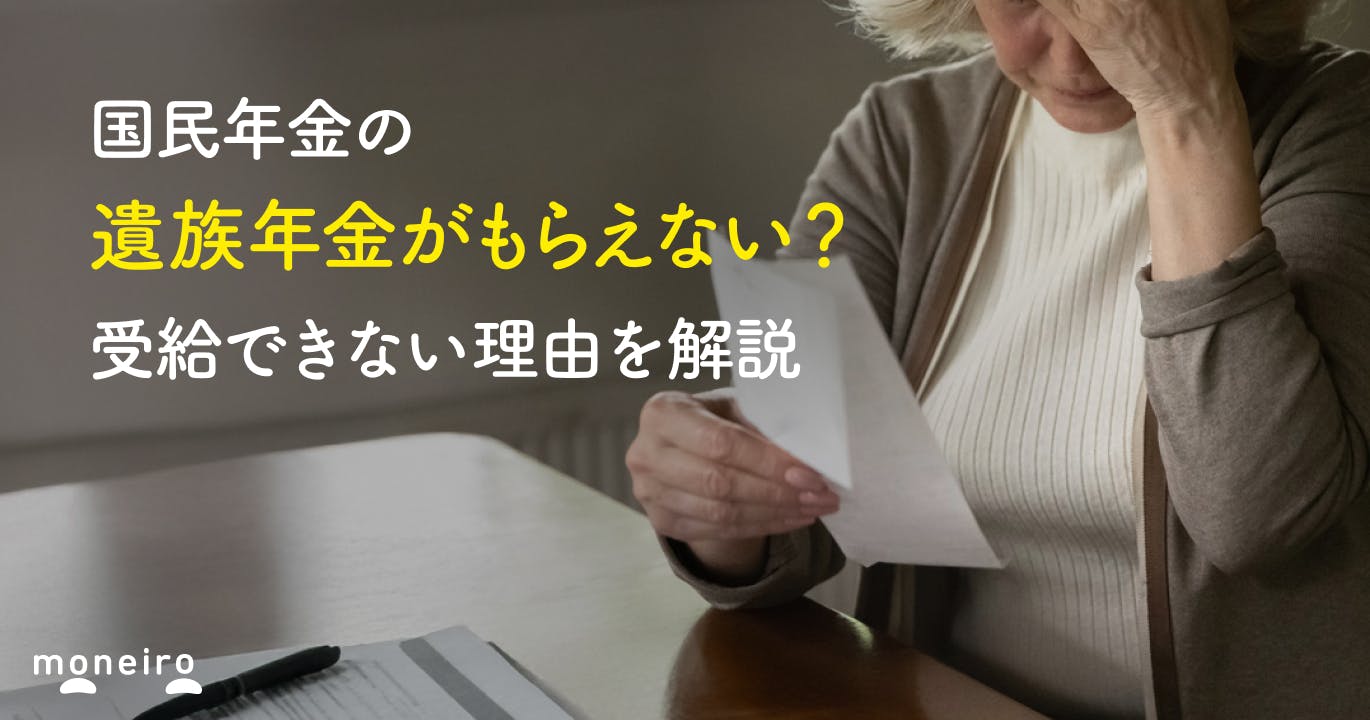
国民年金の遺族年金がもらえない?受給できない理由と対処法をわかりやすく解説
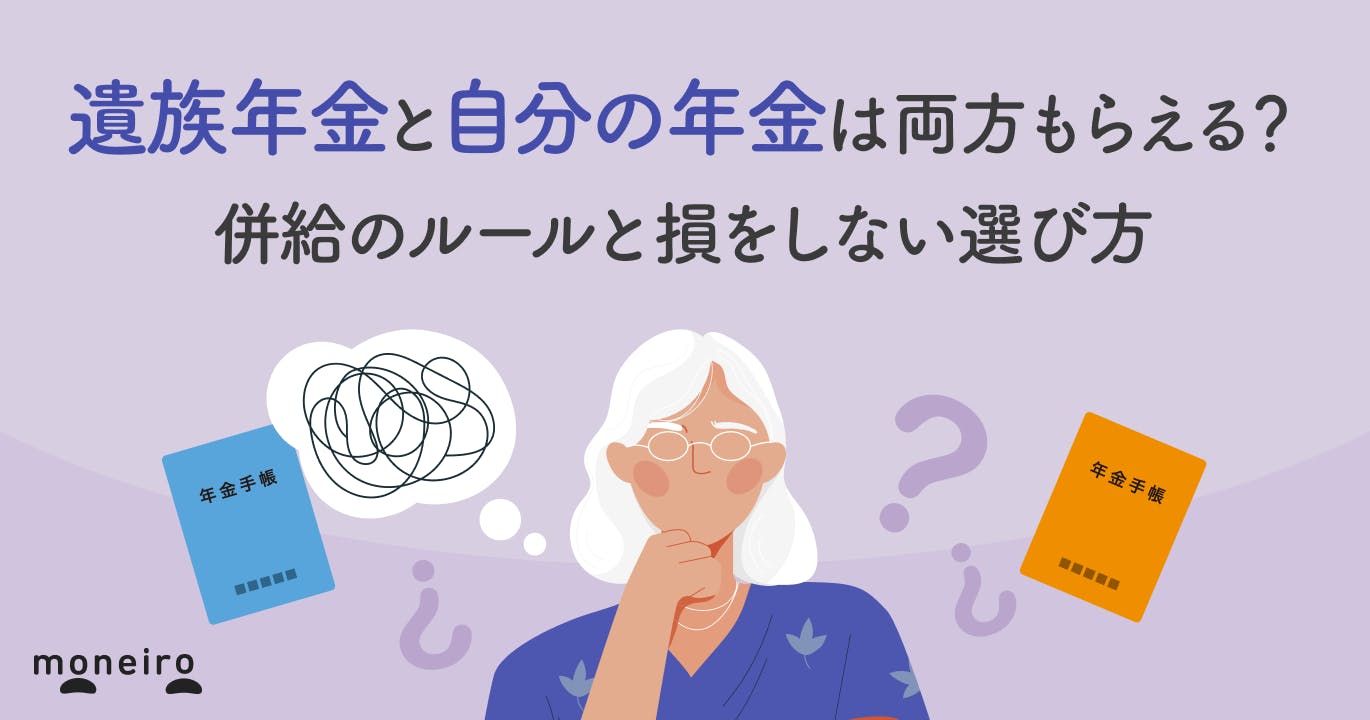
遺族年金と自分の年金は両方もらえるの?併給のルールと損をしない選び方を解説
監修
山本 務
- 特定社会保険労務士/AFP/第一種衛生管理者
東京都練馬区で、やまもと社会保険労務士事務所を開業。企業の情報システム、人事部門において通算28年の会社員経験があるのが強みであり、情報システム部門と人事部門の苦労がわかる社会保険労務士。労務相談、人事労務管理、就業規則、給与計算、電子申請が得意であり、労働相談は労働局での総合労働相談員の経験を生かした対応ができる。各種手続きは電子申請で全国対応が可能。また、各種サイトで人事労務関係の記事執筆や監修も行っている。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。