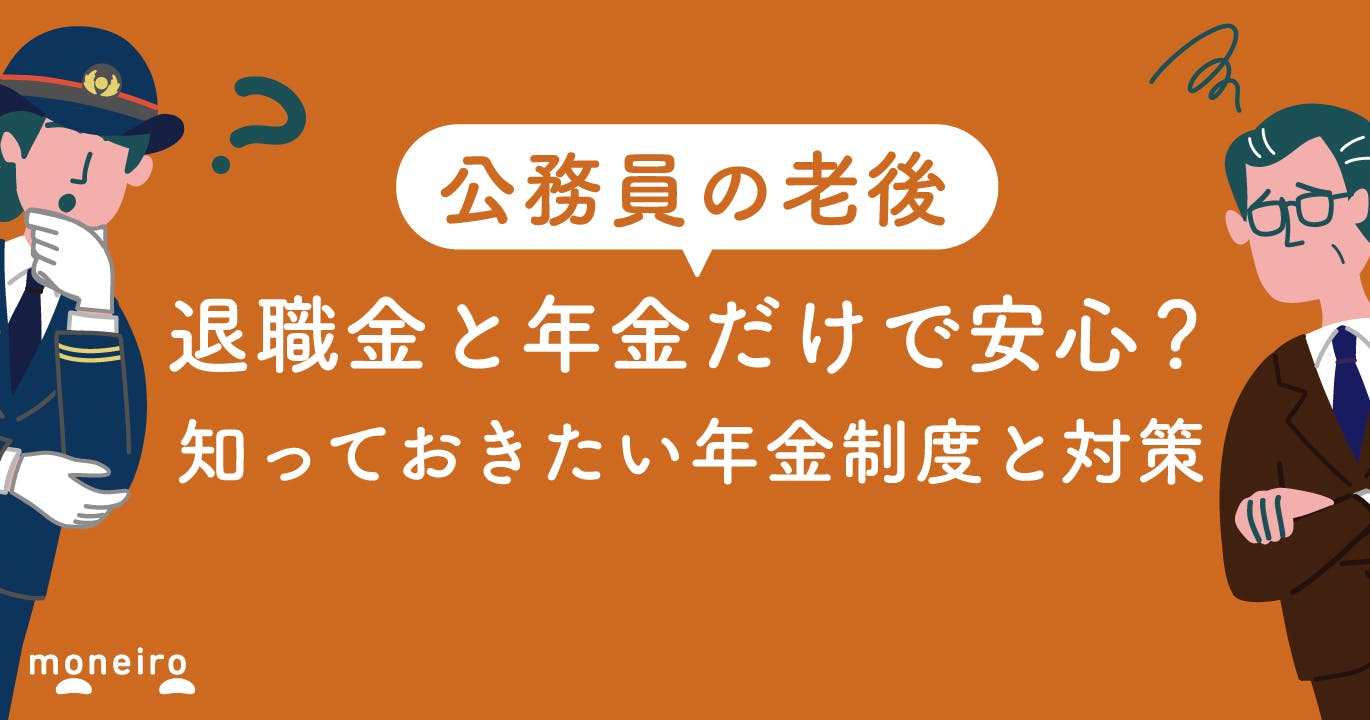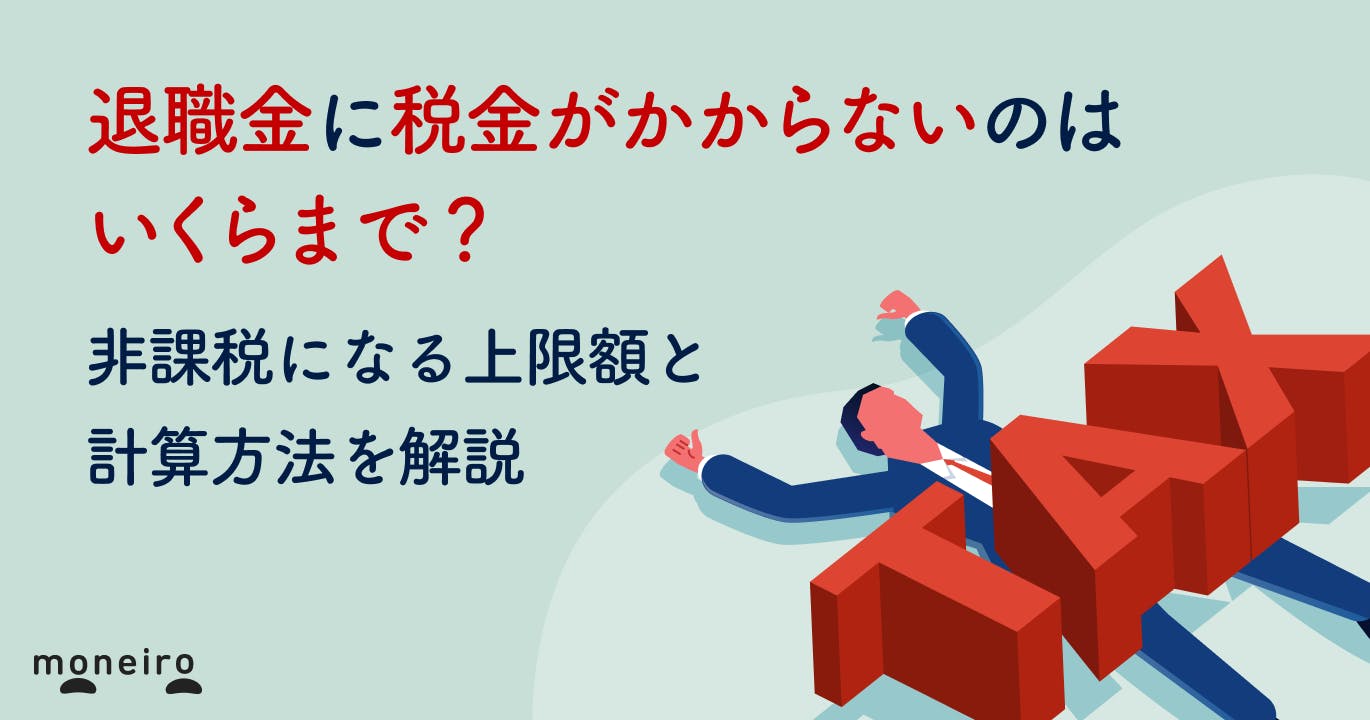公務員の退職金はいくら?平均額や算定方法、税金の仕組みを解説
≫退職金で足りる?あなたの老後に必要な金額を3分で診断
公務員の退職金は、将来の生活設計を立てる上で非常に重要な要素です。一体いくらもらえるのか、どのように算定されるのか、税金はどれくらいかかるのか、といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。
この記事では、国家公務員と地方公務員に分けて、最新のデータに基づいた退職金の平均額や、退職金の算定方法などを網羅的に紹介します。ぜひ将来の資金設計にお役立てください。
- 国家公務員と地方公務員の退職金平均額
- 公務員の退職金がどのように計算されるかの概要
- 退職金にかかる税金や制度の仕組み
退職金が気になるあなたへ
これからの人生をお金の不安なく暮らすために、老後資金の準備は大切です。マネイロでは、将来資金を賢く準備するための無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
▶退職金を“減らさず使う”100歳までの資産活用術:資産を長持ちさせる方法がわかる
公務員の退職金の平均額はいくら?
公務員の退職金は、国家公務員と地方公務員でそれぞれ異なる統計データが公表されています。ここでは、それぞれの平均額について見ていきましょう。
国家公務員の退職金平均額
国家公務員の退職手当は、内閣官房内閣人事局による「退職手当の支給状況(令和5年度)」で確認できます。令和5年度に退職した常勤職員の退職理由別の平均支給額は以下の通りです。
定年退職の場合、常勤職員全体では平均2147万3000円となっています。一方、自己都合退職では、常勤職員全体で平均303万9000円と、定年退職と比較して大幅に低い金額となっています。
地方公務員の退職金平均額
地方公務員の退職金は、総務省が公表している「地方公務員給与の実態(令和6年)」のデータで確認できます。
退職事由別の支給額
まず、全地方公共団体における退職事由別の平均支給額は以下の通りです。
定年退職(25年以上勤続)の場合、一般職員で平均2212万6000円、教育公務員で平均2294万7000円、警察官で平均2311万4000円となっています。いずれの金額も、国家公務員の定年退職の金額を上回る傾向があるのが分かります。
団体区分別の支給額
また、どの団体区分別の職員かによっても退職金の傾向は変わります。以下は団体区分別ごとの一般職員(25年以上勤続後の定年退職等)の平均支給額です。
このデータから、地方公務員の退職金は、基本的に所属する団体区分の規模が大きくなるにつれて退職金も高くなる傾向が見て取れます。
公務員の退職金はどうやって決められる?
公務員の退職金は、その根拠となる法令や計算式に基づいて決定されます。
根拠となる法令
公務員の退職金(退職手当)の根拠となる法令は、国家公務員と地方公務員で異なります。
・地方公務員:勤務先の都道府県や市区町村が定める「退職手当条例」に基づきます。
地方公務員の退職手当条例は、それぞれの自治体が独自に定めるものですが、その内容は国の「国家公務員退職手当法」に準拠しているのが一般的です。
これは、全国の公務員の間で待遇に大きな差が生まれないようにするためです。
算定の計算式
公務員の退職手当は、基本的に以下の計算式で算定されます。
「基本額」とは、退職手当の本体部分です。基本額は、「退職日の俸給月額 × 勤続年数に応じた支給率」で求めます。長く勤め、退職時の給与が高いほどこの金額は大きくなります。
また、「調整額」は在職期間中の役職や貢献度を反映させるための加算額です。民間企業のポイント制退職金に近い考え方で、より上位の役職に長く就いていた人ほど高くなります。
退職日の俸給月額とは
基本額の計算式に出てくる「退職日の俸給月額」とは、退職した日の基本給のことを指します。この金額が、退職手当の基本額を算出する際の基準となります。俸給月額が高いほど、退職手当の基本額も増えることになります。
支給率とは
また、「支給率」とは、退職日の俸給月額に何ヶ月分を乗じて退職手当の基本額を算出するかを示す割合です。この支給率は、勤続年数や退職理由(定年退職、自己都合退職など)によって細かく定められています。一般的に勤続年数が長くなるほど、支給率も高くなる傾向にあります。
退職金が気になるあなたへ
これからの人生をお金の不安なく暮らすために、老後資金の準備は大切です。マネイロでは、将来資金を賢く準備するための無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
▶退職金を“減らさず使う”100歳までの資産活用術:資産を長持ちさせる方法がわかる
退職金の手続きは?いつもらえる?
退職金を受け取るためには、所定の申請手続きが必要です。
退職手当の請求手続き
公務員が退職する際、退職手当を受け取るためには、所属する省庁や自治体の担当部署(通常は人事または総務部門)に所定の請求手続きを行う必要があります。手続きに必要な書類は以下の通りです。
・その他の書類:自治体や省庁によっては、身分証明書(例:戸籍謄本)や在職期間を確認するための書類が求められる場合があります。
なお、退職手当が実際に支給されるのは通常、退職月の翌月となります。
退職金にかかる税金(所得税・住民税)と控除の仕組み
退職金は「退職所得」として扱われ、所得税と住民税の課税対象となりますが、税負担を軽減するための特別な控除制度が設けられています。
退職金は「退職所得」として扱われる
退職金は、税法上「退職所得」として分類され、給与所得などの他の所得とは分離して課税される「分離課税」の対象となります。そのため、他の所得と合算せずに税額が計算されます。
さらに、退職所得には勤続年数に応じた退職所得控除が適用され、課税対象額が1/2に軽減される特例があるため、高額な退職金でも税率の急激な上昇が抑えられ、税負担が軽減されます。
節税のカギ「退職所得控除」の計算方法
退職所得には、「退職所得控除」という大きな控除が適用されます。この控除額は勤続年数によって異なり、勤続年数が長いほど控除額も大きくなります。
・勤続年数20年を超える場合:800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)
退職金からこの控除額を差し引いた残額が課税対象となり、さらにその額の1/2が課税所得として所得税が計算されます。この仕組みにより、退職金の税負担が大幅に軽減されます。
定年延長による公務員退職金への影響
日本では従来、公務員の定年は60歳でしたが、「国家公務員法等の一部を改正する法律」と「地方公務員法等の一部を改正する法律」が施行されたことにより、2023年度から定年を2年ごとに1歳ずつ、段階的に65歳へ延長されることになっています(2031年度に完了)。
公務員の定年延長は、退職金の金額にプラスとマイナスの両面から影響を与える可能性があります。詳しく確認しておきましょう。
プラス要素とマイナス要素
定年延長による退職金への影響には、以下のプラスとマイナス要素が考えられます。
・マイナス要素:60歳以降は給与が下がる「役職定年」などの制度が適用されることが多く、退職直前の俸給月額が退職金の計算基準となるため、この給与減が退職金を減少させる要因となる可能性があります。
このように、定年延長は退職金に単純な増加だけでなく、複雑な影響を及ぼすことが予想されます。
実際の影響範囲は?
人事院の制度設計では、定年延長が退職金に与える影響を考慮し、以下のような調整がされています。
・60歳以降の給与減による退職金の大幅減少を避ける調整:定年延長に伴う俸給月額7割措置によって60歳以降の給与減が退職金に与える影響を緩和する配慮がされています。60歳までの退職金には60歳時の俸給月額と支給率を使用し、それ以後の分は変更後の俸給月額ならびに支給率を使用して退職金を計算します。定年引上げ前後で分けて計算するため、定年引上げに伴うマイナスの影響はありません。
これにより、定年延長をしても、勤続年数の増加による退職金のメリットを享受しつつ、給与減による不利益を過度に受けないよう配慮されているといえるでしょう。
まとめ
公務員の退職金は、国家公務員と地方公務員でそれぞれ平均額が公表されており、特に定年退職の場合には、いずれの場合でも2000万円を超える水準となります。一方、自己都合退職の場合は大きく金額が下がる傾向にありますが、今回紹介した自己都合退職のケースの金額は平均額であり、勤続年数を加味していない数字である点には注意が必要です。
なお、現在公務員の定年は延長の最中にあり、定年延長による影響は、勤続年数の増加によるプラス面と、60歳以降の給与減によるマイナス面の両方があります。とはいえ、過度な不利益がないような制度設計がなされているため、さほど心配する必要はないでしょう。
また、退職金は退職所得として課税対象となりますが、退職所得控除を活用することで税負担を軽減できます。今回紹介した情報を参考に退職金の目安を把握し、計画的に将来に向けた準備を進めていきましょう。
≫退職金で足りる?あなたの老後に必要な金額を3分で診断
退職金が気になるあなたへ
これからの人生をお金の不安なく暮らすために、老後資金の準備は大切です。マネイロでは、将来資金を賢く準備するための無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
▶退職金を“減らさず使う”100歳までの資産活用術:資産を長持ちさせる方法がわかる
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
山本 務
- 特定社会保険労務士/AFP/第一種衛生管理者
東京都練馬区で、やまもと社会保険労務士事務所を開業。企業の情報システム、人事部門において通算28年の会社員経験があるのが強みであり、情報システム部門と人事部門の苦労がわかる社会保険労務士。労務相談、人事労務管理、就業規則、給与計算、電子申請が得意であり、労働相談は労働局での総合労働相談員の経験を生かした対応ができる。各種手続きは電子申請で全国対応が可能。また、各種サイトで人事労務関係の記事執筆や監修も行っている。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。