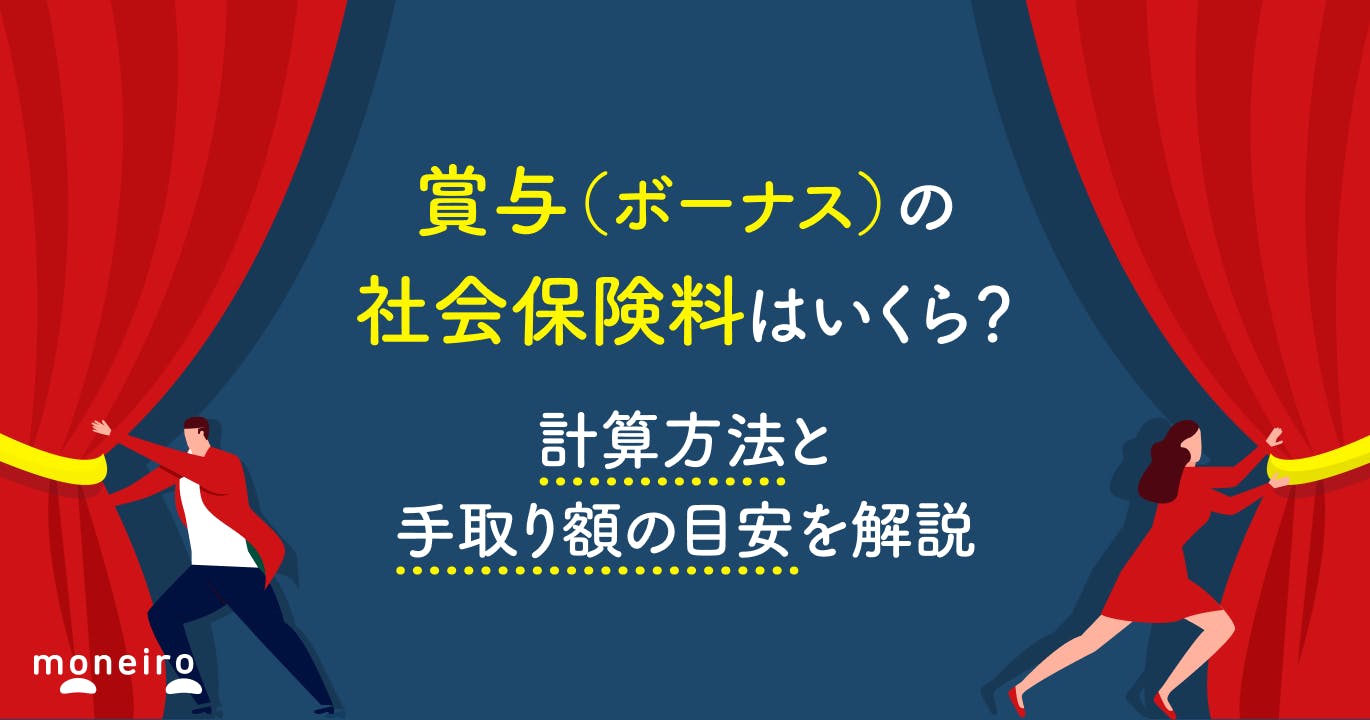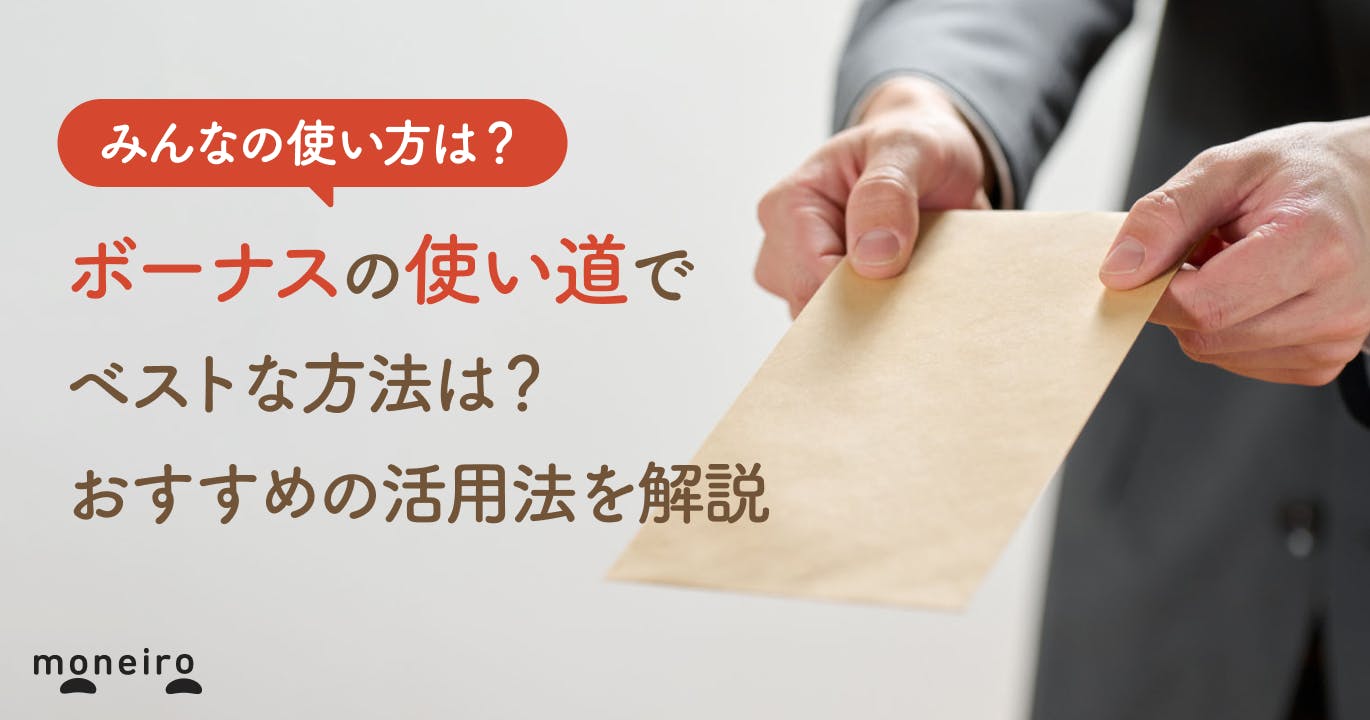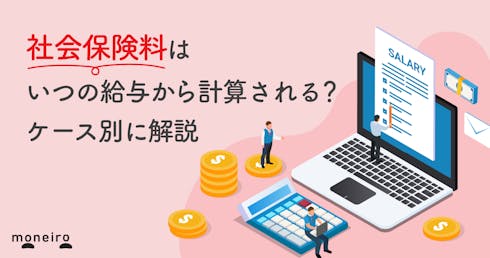
賞与(ボーナス)の社会保険料はいくら?計算方法と手取り額の目安を解説
>>あなたの「将来の必要額」が3分で分かる無料ツール
「賞与からも社会保険料は引かれる?」「いくら引かれる?」そんな疑問を感じている方も多いでしょう。
そこでこの記事では、賞与の手取り額を正しく把握するために、引かれる社会保険料の種類や保険料、さらにそれらを計算する方法を解説します。正しく理解して疑問を解消しましょう。
- 賞与から天引きされる社会保険料の計算手順と方法
- 「標準賞与額」の定義や社会保険料における上限額の具体的なルール
- 特殊なケースでの社会保険料の取り扱い
社会保険料が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
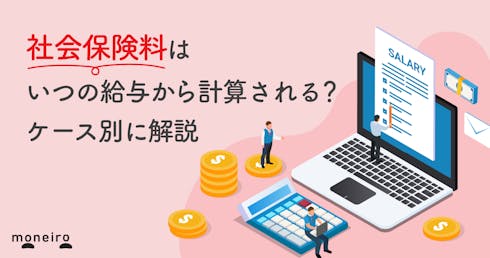
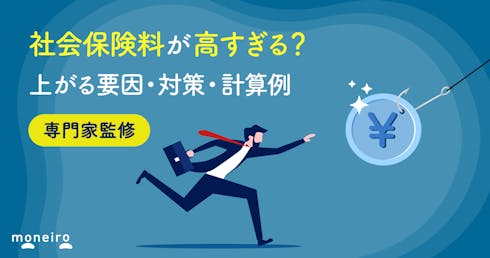
賞与(ボーナス)からも社会保険料は引かれる?
賞与(ボーナス)は、一般的に「報酬」の一部として扱われます。そのため、毎月の給与と同じく、健康保険、厚生年金保険、雇用保険といった社会保険料の算定対象となります。
賞与からこれらの保険料が天引きされる仕組みを正しく理解することは、手取り額を予測し、家計の計画を立てる上で非常に重要です。
賞与(ボーナス)から引かれる社会保険料
賞与から天引きされる社会保険料には、主に健康保険料、介護保険料(40歳以上の場合)、厚生年金保険料、雇用保険料の4種類があります。これらの保険料は、それぞれ異なる計算方法と料率に基づいて算出されます。
健康保険料
健康保険は、病気やケガをした際、または出産や死亡の際に必要な医療給付を行うための公的な制度です。賞与から天引きされる健康保険料は、労使で折半して支払うのが一般的です。
【計算方法】
健康保険料は、「標準賞与額」に加入している全国健康保険協会(協会けんぽ)の各都道府県支部または健康保険組合が定める「健康保険料率」を乗じて算出されます。この料率は、地域(協会けんぽの場合)や加入団体によって異なるため、各Webサイトなどで最新の料率を確認する必要があります。
【計算式】
健康保険料(被保険者負担分)= 標準賞与額 × 健康保険料率 × 1/2
介護保険料(40歳以上が対象)
介護保険料は、40歳から64歳の被保険者(第2号被保険者)に対してのみ徴収されます。
これは、高齢化に伴い増加する介護費用を社会全体で支えるための保険制度です。
【計算方法】
介護保険料が必要な対象者である場合、健康保険料に加えて介護保険料が徴収されます。これは、「標準賞与額」に定められた「介護保険料率(加入団体によって異なる)」を乗じて算出され、これも労使で折半されます。
【計算式】
介護保険料(被保険者負担分) = 標準賞与額 × 介護保険料率 × 1/2
厚生年金保険料
厚生年金保険料は、将来老齢年金などを受け取るために積み立てる保険料です。企業に勤める労働者は、国民年金に上乗せして厚生年金に加入することが義務付けられています。
【計算方法】
厚生年金保険料は、「標準賞与額」に「厚生年金保険料率(一律18.3%)」を乗じて算出されます。健康保険料と同様に、この保険料も労使で折半して負担します。
【計算式】
厚生年金保険料(被保険者負担分) = 標準賞与額 × 厚生年金保険料率 × 1/2
雇用保険料
雇用保険は、労働者が失業した場合や、育児・介護などで休業した場合に給付を行うための保険です。他の社会保険料とは異なり、雇用保険料は失業手当の財源にも充てられるため、保険料率は景気の状況などにより変動する可能性があります。
【計算方法】
雇用保険料は、「賞与の支給総額」(標準賞与額ではない)に「雇用保険料率(業種により異なる)」を乗じて算出されます。雇用保険料率は、事業主と被保険者で負担割合が異なります。
【計算式】
雇用保険料(被保険者負担分)= 賞与支給総額 × 雇用保険料率(被保険者負担分)
【参考】所得税は引かれるが、住民税は原則引かれない
社会保険料の他に、賞与からは所得税が源泉徴収されます。
一方、住民税は、賞与から直接天引きされることは原則ありません。住民税は前年の所得をもとに税額が決定され、毎月の給与から分割して天引き(特別徴収)される仕組みだからです。
ただし、賞与もその年の所得には含まれるため、翌年の住民税額の算定基礎にはなります。
賞与(ボーナス)の社会保険料の計算手順
賞与の手取り額を把握するためには、社会保険料と所得税を正しい順序で計算する必要があります。
ステップ1.標準賞与額を算出する
社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)を計算する際の基礎となるのは、「標準賞与額」です。標準賞与額とは、税金や社会保険料が引かれる前の「賞与額」から、千円未満の端数を切り捨てた金額を指します。
具体例:賞与の支給額が 50万1500円 であった場合、千円未満の 500円 を切り捨て、標準賞与額は 50万1000円 となります。また、賞与の支給額が 49万9900円 であった場合は、千円未満の 900円 を切り捨て、標準賞与額は 49万9000円 となります。
ステップ2.各種社会保険料を計算する
ステップ1で算出した標準賞与額(または賞与支給総額:雇用保険の場合)に、各保険料率を乗じて、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料を個別に計算します。
例えば、標準賞与額が50万1000円だった場合、これに厚生年金保険料率(被保険者負担分)や健康保険料率(被保険者負担分)を乗じることで、実際の保険料が算出されます。具体的には以下のように計算します。
- (例)厚生年金保険料:50万1000円 × 厚生年金保険料率(被保険者負担分)
- (例)健康保険料:50万1000円 × 健康保険料率(被保険者負担分)
ただし、標準賞与額には後述する上限があります。
ステップ3.所得税を計算する
社会保険料の計算が完了したら、次に所得税の計算に進みます。所得税は、賞与の支給総額から、ステップ2で算出した社会保険料の合計額を控除した後の金額(課税対象額)に対して課税されます。
所得税を計算する際の流れは以下の通りです。
- 課税対象額の算出:賞与支給総額 - 社会保険料合計額
- 税率の特定:前月の給与(社会保険料控除後)と扶養親族の人数に基づき、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を用いて源泉徴収税率を求めます。
- 所得税の計算:課税対象額 × 源泉徴収税率
所得税の計算は、控除額(社会保険料)を確定した後に行う必要があり、計算の仕組みを理解することが重要です。
社会保険料が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
賞与(ボーナス)の社会保険料で注意すべき5つのケース
通常の賞与計算とは異なる、特殊な状況下での社会保険料の取り扱いや、上限に関する重要なルールが5つあります。
1.産休・育休中に賞与が支給された場合
産前産後休業および育児休業期間中の従業員に対して賞与が支給された場合、その賞与に係る社会保険料(健康保険料および厚生年金保険料)は、被保険者本人分および事業主負担分ともに免除されます。ただし、育休取得期間が1ヶ月超など一定要件を満たす場合です。
この免除を受けるためには、事業主が年金事務所などに対して、産前産後休業や育児休業の取得に関する所定の手続き(申出)を行う必要があります。手続きが適切に行われれば、従業員の手取り額が増えることになります。
2.社会保険料の「上限額」を超えた場合
社会保険料の計算には、年金や健康保険の制度を公平に保つため、「上限額」が設定されています。特に高額の賞与が支給される場合には注意が必要です。
厚生年金保険料の上限
厚生年金保険の標準賞与額には、1回の支給につき150万円の上限が設けられています。もし賞与が150万円を超えて支給された場合でも、厚生年金保険料は150万円を標準賞与額として計算されます。
健康保険料の上限
健康保険の標準賞与額には、年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)の累計で573万円の上限が設けられています。年度内に支給されたすべての賞与の標準賞与額を合算し、この累計額が573万円を超えた場合、超えた部分については健康保険料の算定対象とはなりません。
3.年4回以上支給される賞与の場合
賞与が年間に4回以上支給される場合、その取り扱いが通常の年3回以下の賞与とは大きく異なります。年4回以上支給される賞与は、社会保険制度上「標準報酬月額」の算定対象に含まれる報酬として扱われます。
これは、実質的には毎月の給与と同じ性質を持つとみなされ、社会保険料の計算方法が変わります。このルールは、企業が社会保険料の負担を不当に軽減するために、本来の報酬を細かく分割して支給する「実質的な節税対策」を防ぐ目的で設けられています。
4.退職月に賞与が支給された場合
退職する月に賞与が支給された場合、社会保険料の取り扱いは「退職日」によって異なります。
社会保険料は、資格喪失日が属する月の前月分まで支払う義務があるためです。
月の末日に退職する場合(例:12月31日に退職する場合)
社会保険の資格喪失日は翌月の1日(例:1月1日)となります。この場合、資格喪失日が属する月の前月、つまり退職月(12月)分の社会保険料の支払い義務が発生します。したがって、退職月に支給された賞与からも、毎月の給与と同様に社会保険料が徴収されます。
末日より前に退職する場合(例:12月20日に退職する場合)
この場合、社会保険の資格喪失日は退職日の翌日(例:12月21日)となります。月の末日より前に退職する場合、その月の社会保険料の支払い義務は発生しないため、退職月(12月)分の社会保険料の支払い義務は発生しません。したがって、退職月に支給された賞与からも社会保険料は徴収されません。
5.パート・アルバイトへの賞与の場合
パートタイマーやアルバイトといった雇用形態であっても、社会保険の加入条件を満たしている場合、賞与が支給されれば正社員と同様に社会保険料の計算が行われます。
社会保険の加入条件には、週の所定労働時間や月額賃金などが関係し、これらの条件を満たせば、雇用形態にかかわらず報酬に対する社会保険料の支払い義務が発生することを理解しておく必要があります。
賞与の社会保険料に関するQ&A
賞与にかかる社会保険料に関するよくある質問と回答を以下にまとめました。
Q. 産休・育休中に支給された賞与からも社会保険料は引かれる?
いいえ。産前産後休業期間中や育児休業期間中に支給された賞与については、健康保険料と厚生年金保険料が免除(育休取得期間など一定要件あり)されます。
本人・事業主双方の負担が免除されますが、免除を受けるには会社が年金事務所等に所定の届出を行う必要があります。
なお、雇用保険料については免除の対象外のため、通常どおり控除されます。
Q. 試用期間中に支給された賞与からも社会保険料は引かれる?
はい、試用期間中であっても、社会保険の被保険者資格を取得していれば、賞与は社会保険料の算定対象となります。
雇用形態や在籍期間にかかわらず、社会保険の適用条件を満たしている限り、賞与が支給されれば正規の計算方法で保険料が徴収されます。
Q. 計算が合わない場合、どこに相談すればいい?
支給された賞与から控除された社会保険料の計算に疑問が生じた場合や、計算額が合わない場合は、まず会社の給与計算担当者や総務部に相談することがもっとも早い解決策となります。
それでも解決しない場合や、制度に関する疑問がある場合は、加入している健康保険組合や年金事務所に問い合わせることができます。
まとめ
本記事では、賞与(ボーナス)から天引きされる社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料)の計算手順と、手取り額を決定する要素について解説しました。
社会保険料は「標準賞与額」(賞与額から1000円未満を切り捨てた額)を基礎として、所定の料率を用いて計算されます。また、高額な賞与に対する上限額(厚生年金は1回150万円、健康保険は年度累計573万円)や、産休・育休中の免除規定など、注意すべき重要なルールが存在します。
賞与の計算プロセスは複雑ですが、これらの仕組みを理解することで、自身の報酬と手取り額について正確に把握することができるでしょう。
>>あなたの必要額は?老後に不足する金額を3分で診断
社会保険料が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
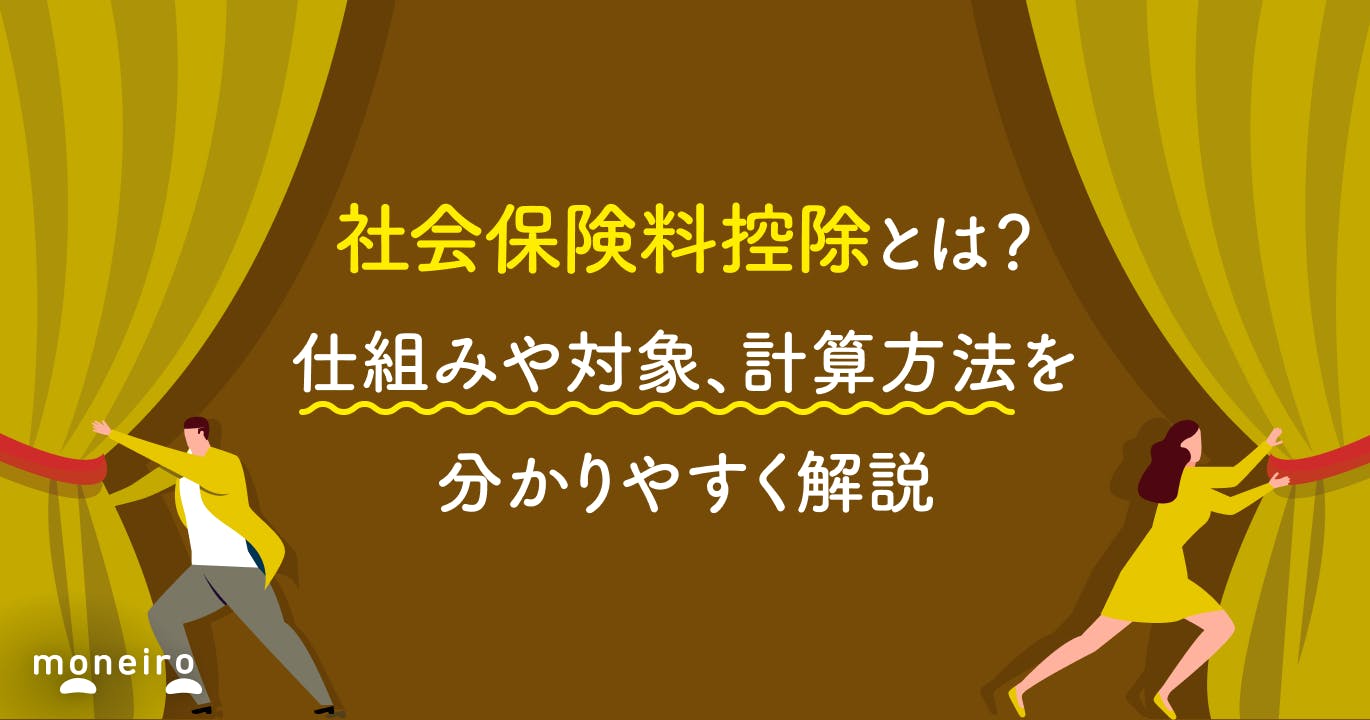
社会保険料控除とは?仕組みや対象、計算方法を分かりやすく解説
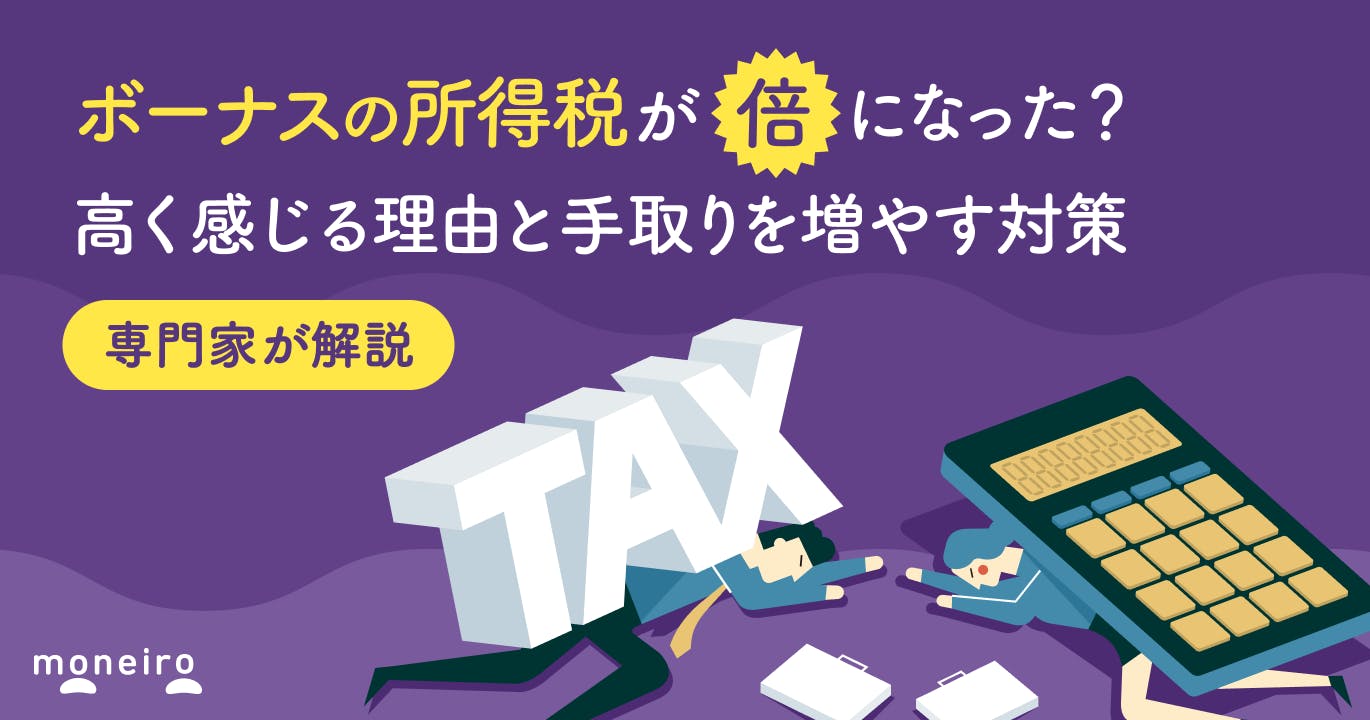
ボーナスの所得税が倍になった?高く感じる理由と手取りを増やす対策を専門家が解説
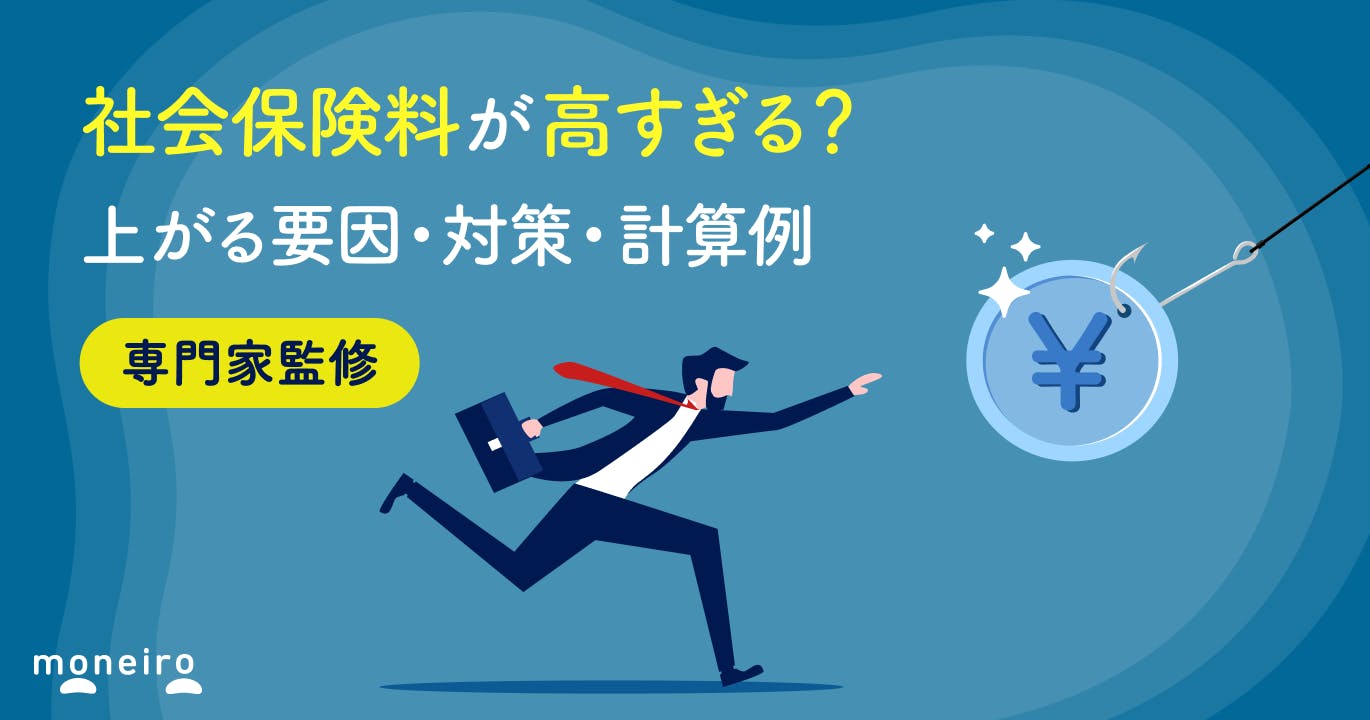
社会保険料が高すぎる?上がる要因・対策・計算例を専門家がわかりやすく解説
監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。