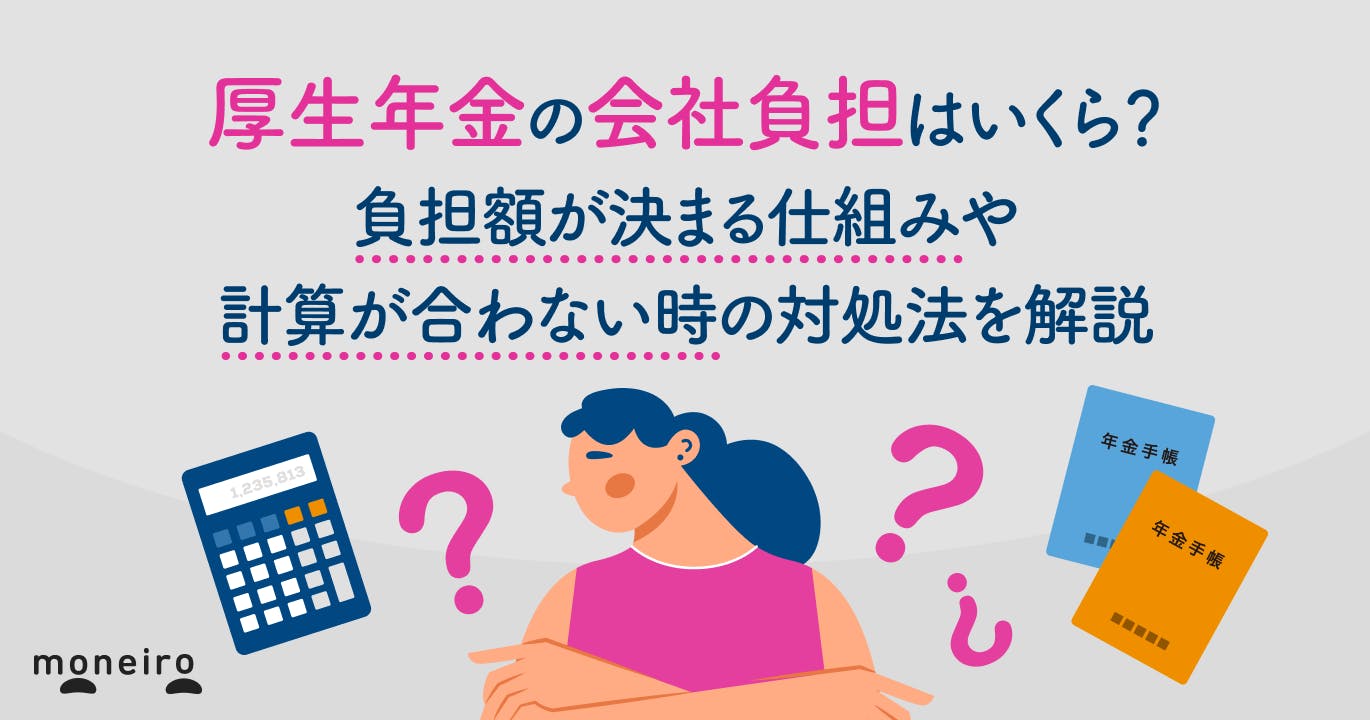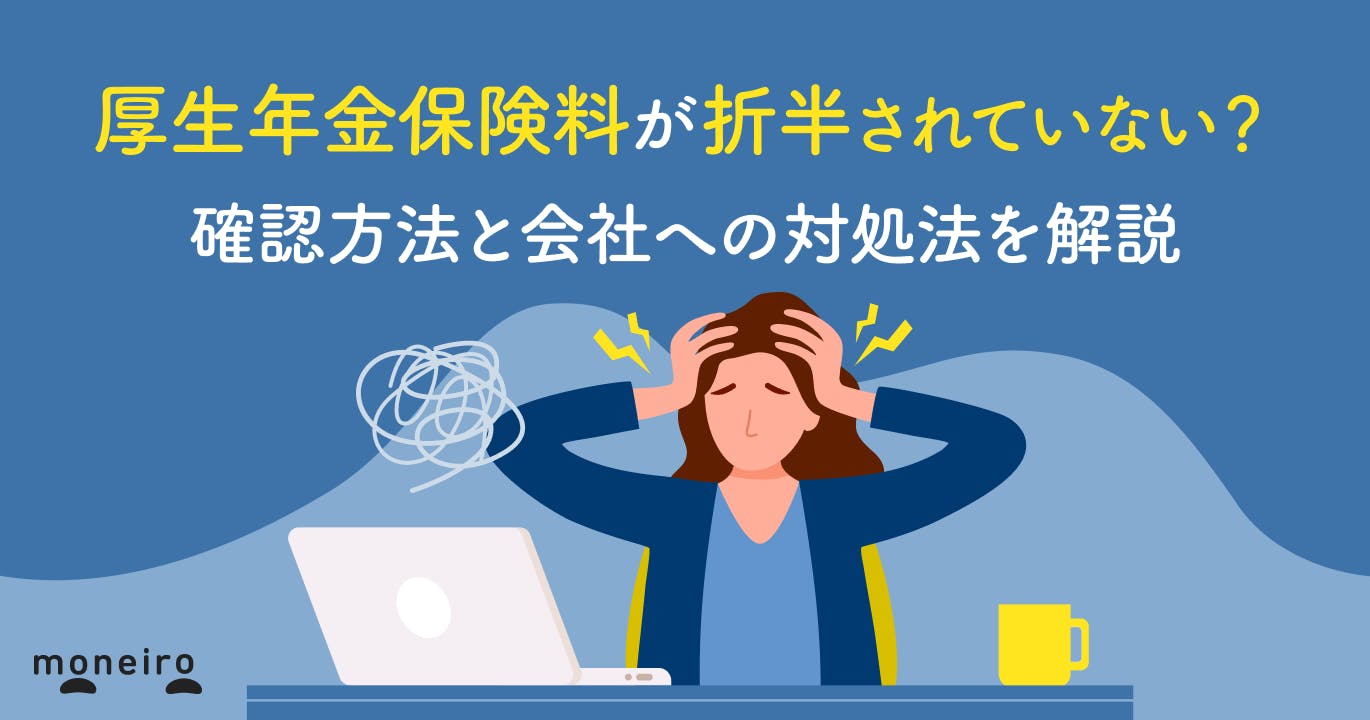
厚生年金保険の会社負担はいくら?金額が決まる仕組みや計算が合わない時の対処法を解説
>>あなたに必要な老後資金をチェック。無料診断ツール
給与明細を見て、「厚生年金保険の会社負担はどれくらい?」と疑問に思ったことはありませんか?厚生年金保険料は、会社と従業員が折半して支払うことが法律で定められています。しかし、具体的な計算方法や、自分の給与明細に記載されている金額が正しいのかどうか、不安に感じる方もいるかもしれません。
そこでこの記事では、厚生年金保険料の会社負担額がどのように決まるのか、計算の仕組みから、給与明細との照合方法、さらにはもし計算が合わなかった場合の対処法まで分かりやすく解説していきます。
- 厚生年金保険料の会社と従業員の負担割合や、負担額の計算方法
- 厚生年金保険料が正しく計算されているか確認する方法
- 計算が合わない場合の原因や、解決しない場合の対応策
老後資金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
厚生年金保険料は会社と従業員で折半(労使折半)
厚生年金保険料は、会社と従業員が半分ずつ負担する「労使折半」という仕組みが法律で定められています。これは、従業員が支払う保険料と同額を会社も負担する仕組みを指します。
例えば、従業員が月1万5000円の厚生年金保険料を支払っている場合、会社も同額の1万5000円を負担し、合計3万円が従業員の厚生年金保険料として納付されることになります。
この労使折半の仕組みは、日本の社会保険制度における重要な特徴の1つです。会社が従業員の社会保障を支えるという考え方に基づいており、これにより従業員は自身の負担額の2倍の保険料が積み立てられるため、将来受け取る年金額が国民年金のみの場合よりも手厚くなります。
厚生年金保険料の会社負担額が決まる仕組み
厚生年金保険料の会社負担額は、従業員の給与などに基づいて決まります。その計算の基礎となるのが、「標準報酬月額」と「保険料率」です。
厚生年金保険料(会社負担額)の計算式
厚生年金保険料の会社負担額は、以下の計算式で算出されます。
会社負担額 = 標準報酬月額 × 保険料率(18.3%) ÷ 2
この計算式は、まず従業員と会社が合わせて負担する総保険料を算出し、それを半分にすることで会社負担分を割り出しています。
- 標準報酬月額: 毎月の給与を一定の範囲(等級)に区分したもの(後述)
- 保険料率(18.3%): 厚生年金保険料率は、2017年9月以降、18.3%で固定されています。この18.3%という数字は、従業員負担分と会社負担分の合計の割合です
例えば、標準報酬月額が30万円の場合、総保険料は「30万円 × 18.3% = 5万4900円」となります。このうち会社が負担する額は「5万4900円 ÷ 2 = 2万7450円」です。
この計算式を理解していれば、自分の給与明細に記載されている厚生年金保険料が正しいかどうかの目安を知ることができます。
計算の基礎「標準報酬月額」とは?
厚生年金保険料の計算において、もっとも重要となるのが「標準報酬月額」です。これは、毎月の給与をそのまま保険料の計算に使うのではなく、一定の幅で区切られた「等級」に当てはめたものです。
厚生年金保険では、給与額に応じて1級から32級までの等級が定められており、それぞれの等級に該当する報酬月額の範囲と標準報酬月額が設定されています。
例えば、月給が20万円台の人であれば何級、30万円台の人であれば何級、というように分類されます。この標準報酬月額に保険料率をかけて保険料を計算することで、事務処理を簡素化し、公平な保険料負担を実現しているのです。
つまり、給与の幅に合わせて大まかなグループ分けをし、そのグループごとの平均的な給与額を「標準報酬月額」としている、と考えるとわかりやすいでしょう。
標準報酬月額の決まり方・変更されるタイミング
標準報酬月額は、通常年に一度、見直しが行われますが、昇給などで給与が大きく変動した際にも改定されることがあります。
- 定時決定(算定基礎届): 毎年4月、5月、6月の3ヶ月間の給与の平均額をもとに、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額が決定されます。この手続きは「算定基礎届」として会社から日本年金機構に提出されます。
- 随時改定(月額変更届): 昇給や降給などにより、固定的賃金(基本給など)が大幅に変動し、月額の給与が2等級以上変わる場合、変動した月から3ヶ月間の平均給与を基に、標準報酬月額が改定されます。これは「月額変更届」として会社から提出され、変動後の4ヶ月目から新しい標準報酬月額が適用されます。
- 育児休業等終了時改定:育児休業を終えて職場に復帰した際、時短勤務などで給与が下がった場合に、申し出により標準報酬月額を改定できる制度です。これは、復帰後の給与水準に保険料を合わせ、当面の保険料負担を軽減するための措置です。
このように、標準報酬月額は、従業員の実際の給与水準に合わせて、定期的に、または必要に応じて適正な状態に保たれるように設計されています。
賞与(ボーナス)にも会社負担はある?
賞与(ボーナス)にも厚生年金保険料の会社負担はあります。賞与から計算される保険料は、「標準賞与額」をもとに算出されます。
標準賞与額とは?
標準賞与額は、税引き前の賞与の金額から1000円未満の端数を切り捨てた額で、1回につき150万円(同じ月に複数回支払われた場合は合算)が上限とされています。年に3回まで支給される賞与が対象となり、これを超える頻度で支給される場合は月々の報酬として扱われることがあります。
計算式: 標準賞与額に対する厚生年金保険料の計算式は、以下の通りです。
賞与の会社負担額 = 標準賞与額 × 保険料率(18.3%) ÷ 2
例えば、標準賞与額が50万円の場合、厚生年金保険料は「50万円 × 18.3% = 9万1500円」となります。このうち会社が負担する額は「9万1500円 ÷ 2 = 4万5750円」です。 このように、会社は毎月の給与だけでなく、賞与に対しても厚生年金保険料を負担しています。
これにより、従業員は賞与分も年金に反映させることができ、将来の年金受給額を増やすことにつながります。
老後資金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
厚生年金が正しく折半されているかチェックする方法
自分の給与明細に記載されている厚生年金保険料が、会社と正しく折半されているか確認することは重要です。以下のステップでチェックしてみましょう。
ステップ1.自分の「標準報酬月額」を確認する
保険料計算の土台となる、正確な「標準報酬月額」を確認します。以下のいずれかの方法が確実です。
- 標準報酬決定通知書を見る:毎年7~9月頃に会社から渡される「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」に、その年の9月から適用される標準報酬月額が明記されています。
- 会社の人事・総務部に直接問い合わせる:「私の現在の標準報酬月額を教えてください」と担当部署に確認するのが簡単で確実です。
- 「ねんきん定期便」「ねんきんネット」で確認する:毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」やオンラインの「ねんきんネット」にも、直近の標準報酬月額が記載されています。
給与明細に記載の「総支給額」は、残業代などで毎月変動するため、保険料計算の基準となる「標準報酬月額」とは異なります。この2つを混同しないようにしましょう。
ステップ2.保険料額表で厚生年金保険料(折半額)を確認
標準報酬月額がわかったら、以下の手順で実際に照合してみましょう。
- 日本年金機構のサイトで最新の「厚生年金保険料額表」を開きます。
- ステップ1で確認した自分の標準報酬月額を探します。
- その等級の欄に記載されている「被保険者負担分(折半額)」の金額と、給与明細の厚生年金保険料の控除額が一致するかを確認します。
金額が一致していれば、あなたの厚生年金保険料は正しく計算されています。
会社負担額の計算が合わないときの原因と対処法
給与明細と保険料額表を照らし合わせた結果、厚生年金保険料の計算が合わない場合、いくつかの原因が考えられます。不安を感じたら、適切な対処をすることが大切です。
考えられる原因とは?
厚生年金保険料の計算が合わない場合、主に以下の原因が考えられます。
会社側の計算ミス
もっとも一般的な原因として、会社の人事や経理担当者の計算ミスが挙げられます。例えば、保険料率の適用間違い、標準報酬月額の等級適用間違い、端数処理のミスなどが考えられます。人間が行う作業である以上は、こうしたミスは起こる可能性があります。
標準報酬月額の改定が反映されていない
標準報酬月額は、毎年9月に定時決定により改定されますが、昇給などで給与が大幅に変わった場合は随時改定も行われます。これらの改定が、会社の事務処理の遅れなどによって、給与明細にすぐに反映されていない可能性があります。
特に、年度の途中での昇給があった場合などは、タイミングがずれることがあります。
(稀なケース)会社が意図的に多く徴収している
非常に稀なケースですが、会社が意図的に従業員から保険料を多く徴収している可能性もゼロではありません。このような行為は違法であり、労働基準法や社会保険関連法規に違反します。この場合は、個人で解決するのが難しい場合が多いため、外部の専門機関への相談が必要となります。
計算が合わない時はどうする?
給与明細の厚生年金保険料に疑問を感じたら、以下の手順で対処しましょう。
- まずは冷静に事実確認: 焦らず、もう一度日本年金機構の保険料額表と自分の給与明細をじっくりと見比べて、計算に間違いがないか確認してみましょう。特に、標準報酬月額の等級が正しく特定できているか、報酬月額の対象となる手当が漏れていないかなどを細かくチェックします。
- 会社の人事・経理担当者に問い合わせる: 自分で確認してもやはり計算が合わない場合は、会社の人事や経理の担当部署に、疑問点を具体的に伝えて説明を求めましょう。多くの場合、会社側の事務的なミスであれば、この段階で解決し、差額が調整されるはずです。
大切なのは、疑問を放置せず、早めに確認・相談することです。
それでも解決しない場合の相談先
会社に問い合わせても解決しない場合や、納得のいく説明が得られない場合は、外部の専門機関に相談することも検討しましょう。
年金事務所(日本年金機構)
会社との話し合いで解決しない場合、最初に相談すべき専門的な窓口が、全国の年金事務所です。 年金事務所は厚生年金制度を運営する公的機関であり、公的な年金記録に基づいて、登録されている正しい「標準報酬月額」を確認してくれます。
さらに、制度のルールに則って保険料が正しいかどうかの的確なアドバイスを受けられるほか、もし会社の手続きに誤りがあると判断されれば、年金事務所から会社へ是正指導が行われることもあります。
弁護士や社会保険労務士
弁護士や社会保険労務士などの外部の専門家へ相談するのも有効な手段です。
社会保険労務士は、年金や労働問題の専門家として、行政への手続きや会社との交渉について具体的な助言をしてくれます。一方、弁護士は、未払い分の請求や悪質なケースにおいて、代理人として法的な交渉や訴訟手続きを進めることができます。
まずは無料相談などを利用して、どのような対応が可能かアドバイスを求めるとよいでしょう。
労働基準監督署
給与そのものの未払いや他の不当な天引きなど、厚生年金保険料の問題だけでなく、より広範な労働問題が背景にある場合には、労働基準監督署も相談先となります。
労働基準監督署は主に賃金や労働時間といった労働基準法に関わる違反を取り締まる機関です。そのため、保険料の計算違いという単独の問題であれば年金事務所の管轄となりますが、特に会社全体の労務管理に問題があるような悪質なケースでは適切な相談先となります。
厚生年金保険の会社負担に関するQ&A
厚生年金保険の会社負担に関するよくある質問と回答をまとめました。
Q. 厚生年金保険以外の社会保険(健康保険など)の会社負担はどうなっている?
厚生年金保険以外の社会保険についても、会社は保険料の一部または全額を負担しています。主な社会保険の会社負担は以下の通りです。
- 健康保険・介護保険: 厚生年金保険と同様に、会社と従業員が折半して保険料を負担します。介護保険は40歳以上の従業員が対象となり、健康保険料と合わせて徴収されます。
- 雇用保険: 雇用保険料は、会社と従業員で負担しますが、会社側の負担割合が従業員よりも高くなっています。保険料率は業種によって異なります。
- 労災保険: 労災保険料は、従業員の保険料負担はなく、全額を会社が負担します。これは、労働災害が発生した場合に、従業員が安心して療養や生活補償を受けられるようにするための制度です。
このように、会社は厚生年金保険だけでなく、従業員の医療、失業、介護、労働災害といった幅広いリスクに対して、手厚い社会保険料を負担しています。これは、従業員にとって非常に大きなメリットといえるでしょう。
Q. パートやアルバイトが厚生年金保険に加入する場合でも会社負担はある?
はい、パートやアルバイトの方でも、厚生年金保険の加入要件を満たして加入すれば、会社負担が発生します。正社員と同様に、会社と従業員が労使折半で保険料を負担することになります。
厚生年金保険の加入要件(短時間労働者の場合)
以下のすべての要件を満たす場合、パートやアルバイトでも厚生年金保険に加入義務があります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8万8000円以上
- 雇用期間が2ヶ月を超える見込みであること
- 学生でないこと(休学中や夜間学生は加入対象)
- 勤務先の従業員数が51人以上であること
これらの条件を満たすパートやアルバイトの方は、厚生年金保険に加入することで、将来の年金受給額を増やすことができるだけでなく、万一の際の障害年金や遺族年金といった保障も手厚くなります。会社側も、これらの従業員に対して厚生年金保険料を負担する義務があります。
Q. 産休・育休中の保険料はどうなる?
産前産後休業(産休)や育児休業(育休)を取得している期間は、厚生年金保険料と健康保険料が、従業員・会社双方とも免除されます。 これは、子育て期間中の経済的負担を軽減するための重要な支援制度です。
免除の対象期間
保険料が免除されるのは、休業を開始した日の属する月から、休業が終了する日の翌日が属する月の前月までです。
- 産前産後休業期間:出産予定日以前42日(多胎妊娠は98日)から、出産翌日以後56日までの範囲内
- 育児休業期間:原則、子が3歳になるまでの範囲内
免除のメリット
この制度には、従業員・会社双方にとって大きなメリットがあります。
- 保険料負担がゼロに:期間中、従業員本人と会社の保険料負担が両方ともなくなります。
- 将来の年金額は減らない:厚生年金保険料の免除期間は、保険料を納付した期間として記録されます。そのため、将来受け取る年金額がこの期間によって減ることはありません。
- 健康保険は通常通り使える:健康保険料も免除されますが、被保険者としての資格は継続します。したがって、期間中に病気やケガをしても、通常通り保険証を使って医療機関を受診できます。
この制度は、会社からの申請に基づいて適用されます。産休や育休を取得する際は、忘れずに会社に確認し、手続きを進めてもらいましょう。
まとめ
厚生年金保険料は、会社と従業員が半分ずつ負担する「労使折半」の原則に基づいており、これは従業員にとって非常に手厚い社会保障制度です。保険料は「標準報酬月額」と「標準賞与額」に保険料率18.3%を掛けて算出され、その半分が会社負担となります。
給与明細に記載されている厚生年金保険料が正しいかどうかの確認は、日本年金機構の「厚生年金保険料額表」と照らし合わせることで簡単に行えます。
もし計算が合わない場合は、まずは会社の人事・経理担当者に問い合わせ、それでも解決しない場合は年金事務所や労働基準監督署、あるいは弁護士や社会保険労務士といった専門機関に相談することを検討しましょう。
本記事の内容をもとに厚生年金保険制度への理解を深め、ぜひ将来の安心を築くための参考にしてみてください。
>>将来不足する金額はいくら?無料診断ツールでチェック
老後資金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
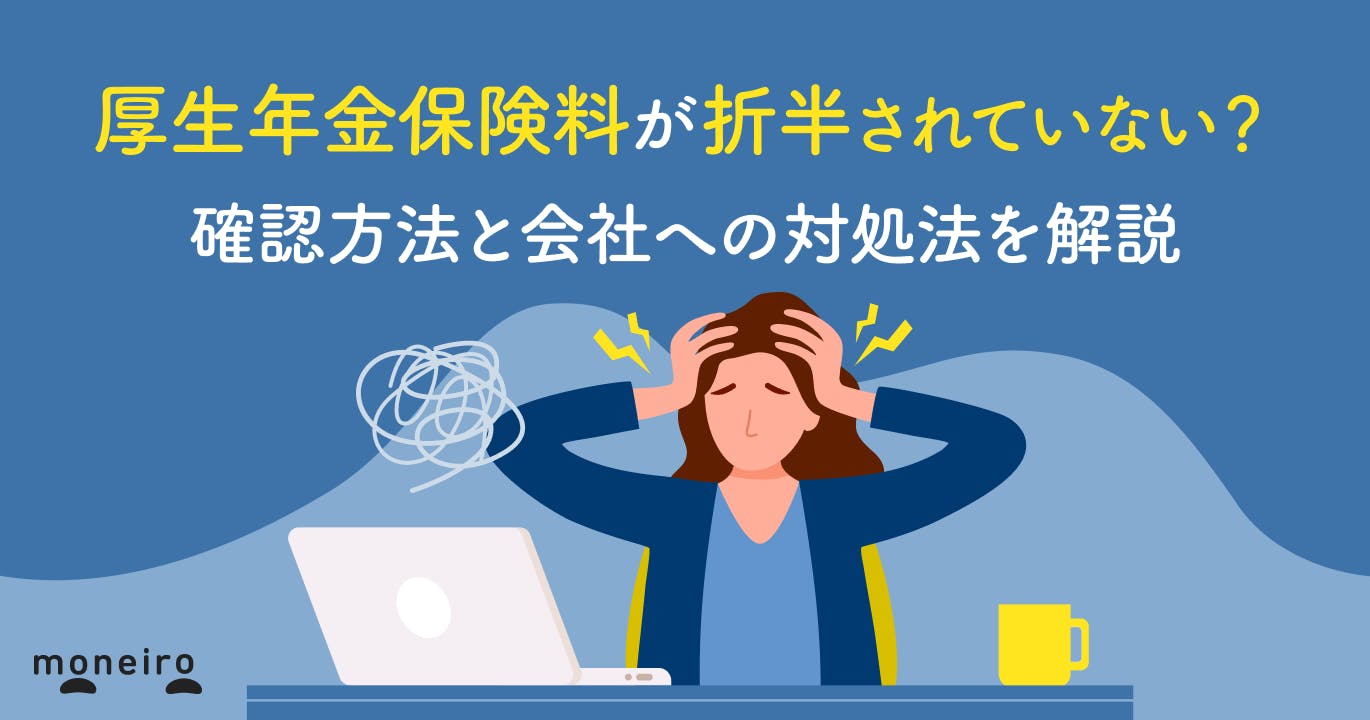
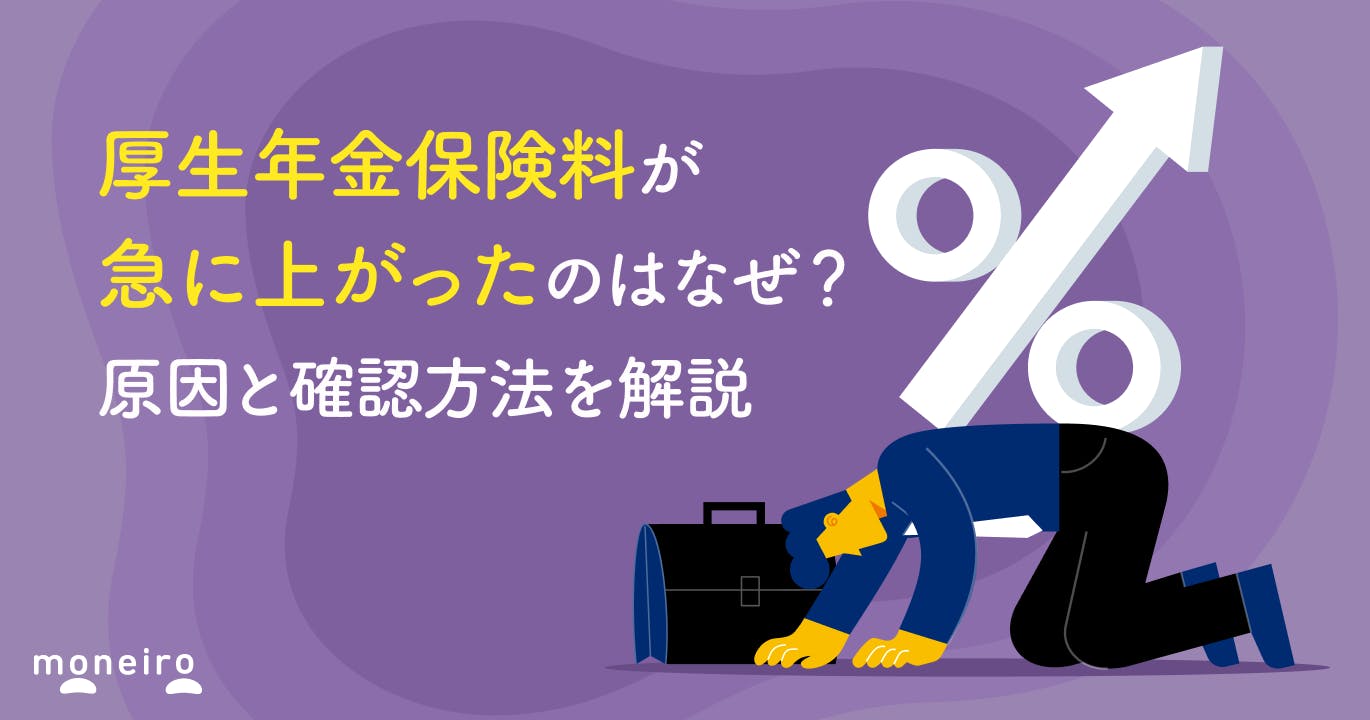
厚生年金保険料が急に上がったのはなぜ?考えられる原因と確認方法を解説
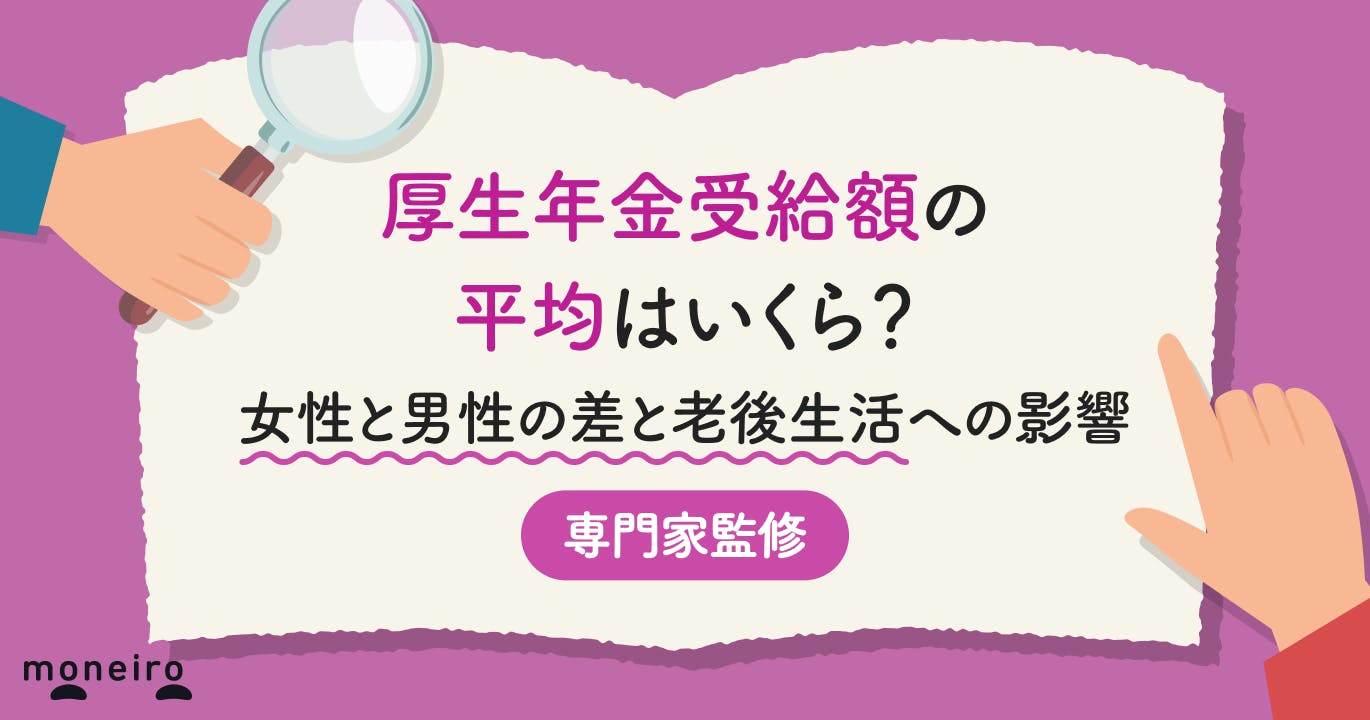
厚生年金受給額の平均はいくら?女性と男性の差と老後生活への影響を徹底解説
監修
山本 務
- 特定社会保険労務士/AFP/第一種衛生管理者
東京都練馬区で、やまもと社会保険労務士事務所を開業。企業の情報システム、人事部門において通算28年の会社員経験があるのが強みであり、情報システム部門と人事部門の苦労がわかる社会保険労務士。労務相談、人事労務管理、就業規則、給与計算、電子申請が得意であり、労働相談は労働局での総合労働相談員の経験を生かした対応ができる。各種手続きは電子申請で全国対応が可能。また、各種サイトで人事労務関係の記事執筆や監修も行っている。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。