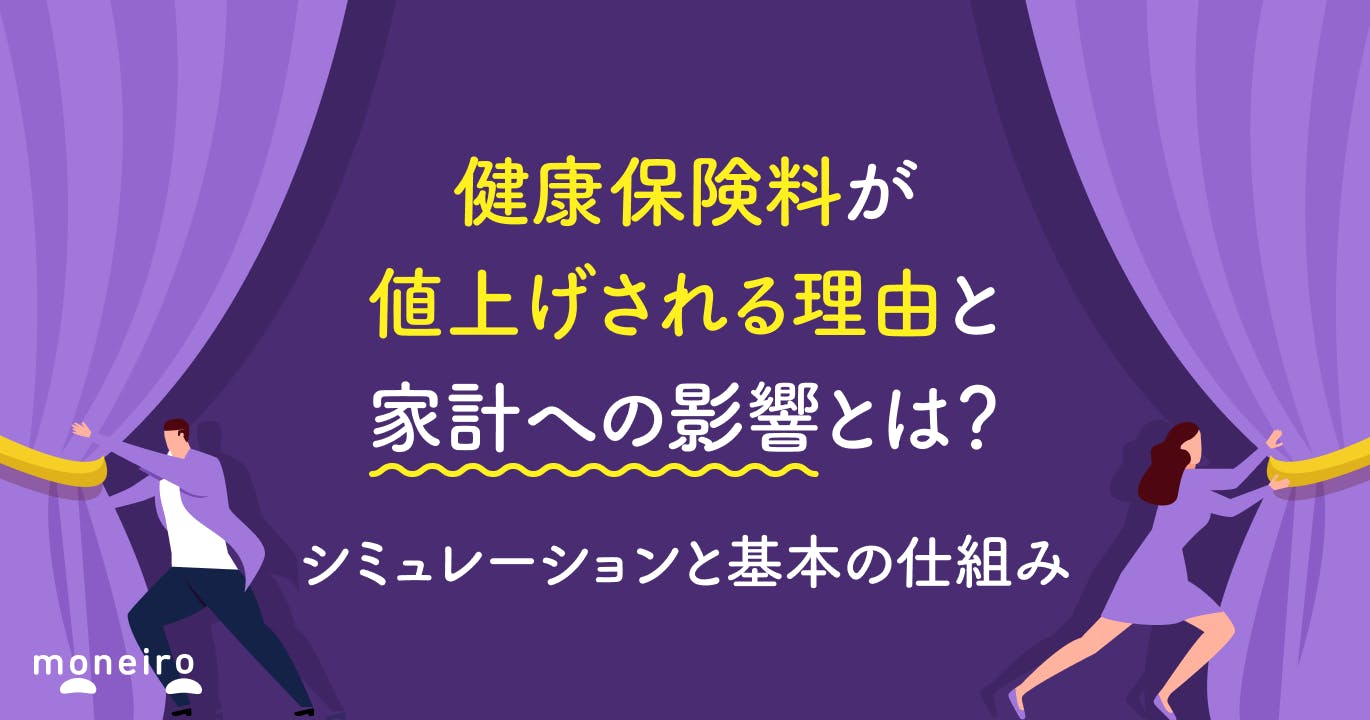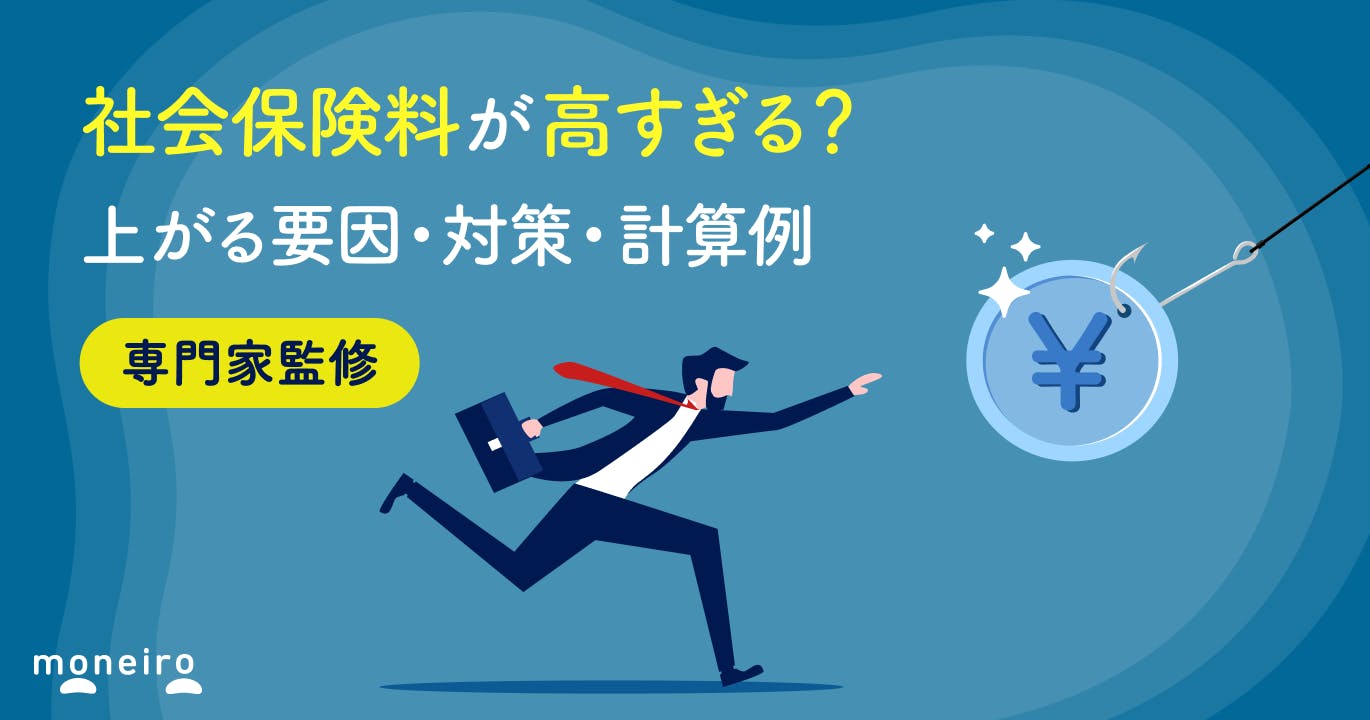
健康保険料が値上げされる理由と家計への影響とは?シミュレーションと基本の仕組み
負担が増える今だからこそ»3分でお金の将来を診断
給与明細や通知書を見て「健康保険料が上がっている」と感じる人は少なくありません。
2025年度には国民健康保険料の上限が引き上げられ、協会けんぽや組合健保でも料率の改定が続いています。背景には少子高齢化による医療費増大や制度維持のための仕組みがありますが、家計にとっては手取りの減少につながる深刻な問題です。
本記事では、健康保険料が値上げされる理由や年収・所得別の負担増をシミュレーション、基本の仕組みを専門家視点でわかりやすく解説します。
- 国民健康保険と協会けんぽの改定内容
- 健康保険料が値上げされる背景
- 保険料負担を軽減するための具体的な対策
将来資金が気になるあなたへ
マネイロでは、将来資金の準備をスムーズに進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶2025年に変わったお金の制度セミナー:お金に関する最新の制度をやさしく解説
▶賢いお金の増やし方入門:30分の無料オンラインセミナー
2025年度以降の健康保険料改定のポイント
2025年度は、国民健康保険料の年間上限額が3万円引き上げられます。また、協会けんぽの保険料率も都道府県ごとに改定され、多くの地域で負担が増加、一部地域では減少します。
(参考:国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額について|厚生労働省保険局)
国民健康保険料の上限引き上げ
2025年度から、自営業者やフリーランスなどが加入する国民健康保険の年間保険料に設定されている上限額が、3万円引き上げられることになりました。
具体的には、医療保険制度を支えるための「医療分」の上限が89万円から92万円へと変更されます。
この3万円の引き上げは、加入者の医療費を賄う「基礎賦課分」と、後期高齢者医療制度を支援する「後期高齢者支援金等賦課分」の増額によるものです。
一方で、40歳から64歳までの方が支払う介護保険料の上限額は、年間17万円で据え置かれます。この結果、医療分と介護分を合わせた国民健康保険料の年間上限総額は、従来の106万円から109万円へと引き上げられます。
なお、この上限額の引き上げは4年連続となり、保険財政の厳しさを反映しています。
協会けんぽ・組合健保の料率改定
主に中小企業の会社員が加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)では、健康保険料率が毎年見直されます。
保険料率は全国一律ではなく、各都道府県支部の医療費水準などに基づいて個別に決定されるのが特徴です。そのため、地域によって保険料率が引き上げられる場合もあれば、引き下げられる場合もあります。
2025年度の改定では、一部の都道府県で保険料率が引き上げられる一方、東京や大阪などでは引き下げられました。新しい保険料率は、2025年3月分(4月納付分)から適用されています。
また、大企業などが独自に設立している健康保険組合(組合健保)においても、協会けんぽと同様に、各組合が独自に保険料率を決定します。
したがって、すべての会社員の健康保険料が一律に値上げされるわけではなく、加入している健康保険組合の方針によって異なります。
健康保険料が値上げされる理由
健康保険料が値上げされる主な理由は、少子高齢化の進展に伴う医療費の増大です。
特に後期高齢者医療費は現役世代が高齢者の医療費を支援する制度になっているため、今後さらに進むであろう少子高齢化に対してその財源確保が急務となっています。
高齢化による医療費の増加
日本が直面する最も大きな課題の一つが、急速な少子高齢化です。特に、いわゆる「団塊の世代」が75歳以上となる「2025年問題」を迎え、高齢者人口は増加の一途をたどっています。
一般的に、年齢が上がるにつれて医療機関を利用する頻度は高くなるため、高齢者の増加は国民全体の医療費増大に直結します。
この傾向は今後も続くと予測されており、2040年には人口の約35%が高齢者になると推計されています。これは、現役世代約1.5人で1人の高齢者を支える計算です。
増え続ける医療費を現行の保険料収入だけで賄うことは困難であり、医療保険制度の持続可能性を確保するためには、社会保険料の引き上げによる財源確保が不可欠な状況となっています。
後期高齢者医療制度への支援金
日本の公的医療保険制度は、現役世代が高齢者の医療費を支える構造になっています。具体的には、75歳以上の人が加入する「後期高齢者医療制度」の財源の一部を、現役世代が納める健康保険料から「支援金」として拠出しています。
この仕組みにより、世代間の支え合いで制度全体が成り立っています。高齢化に伴い、後期高齢者の医療給付費は年々増加しており、それに伴って現役世代が負担する支援金の額も増大しています。
国民健康保険料の内訳を見ると、「後期高齢者支援金等賦課額」という項目があり、これが支援金に該当します。
2025年度の国民健康保険料上限額の引き上げも、この支援金部分の増額が大きな要因となっています。
低所得者層への負担軽減による影響
国民健康保険の加入者には、自営業者やフリーランス、退職者などが多く含まれており、会社員などが加入する被用者保険の加入者と比較して、平均所得が低い傾向にあります。
そのため、保険料率を一律で引き上げてしまうと、所得が低い世帯の家計を直接圧迫してしまう懸念があります。
そこで、低所得者層や中間所得者層への急激な負担増を避けるため、所得の高い層に対してより多くの負担を求める「応能負担」の考え方が採用されています。
年間保険料の上限額(賦課限度額)を引き上げることで、高所得者層の負担を増やし、その財源を全体の保険料率の上昇抑制に充てています。
これは、医療保険制度が持つ所得再分配の機能を維持するための措置でもあります。
将来資金が気になるあなたへ
マネイロでは、将来資金の準備をスムーズに進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶2025年に変わったお金の制度セミナー:お金に関する最新の制度をやさしく解説
▶賢いお金の増やし方入門:30分の無料オンラインセミナー
健康保険料はどのくらい上がる?負担増シミュレーション
健康保険料の値上げによる具体的な影響額は、加入している保険の種類、所得、お住まいの地域によって大きく異なります。
特に国民健康保険料の上限引き上げは、高所得者層に限定的な影響を与えます。
会社員(年収別)の負担額
会社員が加入する協会けんぽの健康保険料は、標準報酬月額と各都道府県の保険料率によって決まります。2025年度の改定では、保険料率が引き上げられた都道府県と引き下げられた都道府県があります。
例えば、東京都の保険料率は9.98%から9.91%に引き下げられました。一方、長崎県では10.17%から10.41%に引き上げられています。年収が同じでも勤務先の所在地によって負担額は変動します。
自営業(所得別)の負担額
自営業者やフリーランスが加入する国民健康保険料は、所得に応じて負担額が増える仕組みですが、年間保険料には上限が設けられています。2025年度の改定は、この上限額が引き上げられるというものです。
今回の引き上げで直接的な影響を受けるのは、主に高所得者層です。具体的には、給与収入に換算して年収約1170万円(所得約970万円)以上の単身世帯などが、新たな上限額に達する見込みです。
この層に該当する世帯は、全加入世帯の約1.5%と試算されています。
例えば年収500万円など、多くの中間所得者層にとっては、上限額引き上げによる直接的な保険料の増加はありません。
ただし、全体の保険料率が自治体によって見直された場合は、負担額が変動する可能性があります。
世帯構成による違い
国民健康保険料は、個人の所得だけでなく世帯単位で計算される点に注意が必要です。保険料の算定には、所得に応じて計算される「所得割」のほかに、加入者一人ひとりにかかる「均等割」が含まれます。
そのため、同じ世帯所得であっても、加入人数が多い世帯ほど均等割の負担が大きくなり、保険料総額は高くなります。
例えば、単身世帯と夫婦2人世帯では、所得が同じでも保険料は異なります。
また、40歳から64歳までの場合は介護保険料も合わせて納付するため、世帯に該当する年齢の人がいるかいないかによっても、年間の負担額は変わってきます。
保険料を考える際は、世帯全体の所得と構成人数、年齢を考慮する必要があります。
今後も上がり続ける?健康保険料の将来見通し
健康保険料は、今後も上昇傾向が続くと予測されます。その背景には、日本の構造的な課題である少子高齢化と、それに伴う医療費の継続的な増加という避けられない現実があります。
少子高齢化と医療費のシナリオ
日本の健康保険制度は、主に現役世代が納める保険料で、高齢者を含む国民全体の医療費を支える仕組みです。
しかし、少子化によって保険料を納める現役世代が減少する一方で、高齢化によって医療サービスを多く利用する高齢者層は増加し続けています。
この人口構造の変化は、保険財政のバランスを崩す大きな要因です。厚生労働省の推計では、2040年には現役世代約1.5人で1人の高齢者を支える社会になると予測されています。
医療技術の進歩による医療費の高額化も相まって、今後も医療費は増大し続けるシナリオが有力です。この状況が続く限り、保険料の引き上げは避けられないと考えられます。
政府・自治体の制度改正の動向
増え続ける医療費に対応するため、政府や自治体は継続的に制度の見直しを行っています。
近年の動向としては、国民健康保険料の上限額を段階的に引き上げることで、高所得者層からの保険料収入を増やし、全体の保険料率の急激な上昇を抑える方針が取られています。
今後も医療保険制度の持続可能性を確保するために、給付と負担のバランスを見直す議論は続くでしょう。
例えば、医療費の自己負担割合の引き上げや、保険料算定方法の変更など、さまざまな制度改正が検討される可能性があります。
制度改正の動向を注視し、自身の家計に与える影響を常に把握しておく必要があるでしょう。
保険料値上げによる影響と備える方法
健康保険料の値上げは、家計に直結する負担増となります。特に給与から天引きされるため実感しづらい一方で、手取り収入の減少や将来の生活費圧迫につながります。
こうした影響に備えるには、まず制度改正の内容や将来の見通しを理解することが大切です。そのうえで、家計の固定費を見直し、無駄な支出を抑えることから始めましょう。通信費や保険料の見直しは効果が出やすい方法です。
さらに、将来の負担増を見据えて資産形成に取り組むことも重要です。少額からでも積立投資を始めることで、将来の備えを効率的に進められます。
保険料が払えないとどうなる?滞納時のリスク
健康保険料の滞納は、通常の保険給付が受けられなくなることによる医療費の負担増、そして最終的には財産の差し押さえといった深刻な事態につながります。
万一支払いが困難になった場合は、滞納する前に必ず役所の窓口に相談し、減免・猶予制度や分割納付の相談を行いましょう。
まとめ
健康保険料の値上げは今後も続く可能性があり、家計への影響は無視できません。だからこそ、日頃から制度の動向を確認し、負担増に備えた家計管理や資産形成を進めることが大切です。
必要に応じて専門家や自治体の窓口に相談しながら、無理のない対策を積み重ねていきましょう。
»マネイロの3分診断で、今からできる資産づくりを確認しませんか?
将来資金が気になるあなたへ
マネイロでは、将来資金の準備をスムーズに進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶2025年に変わったお金の制度セミナー:お金に関する最新の制度をやさしく解説
▶賢いお金の増やし方入門:30分の無料オンラインセミナー
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
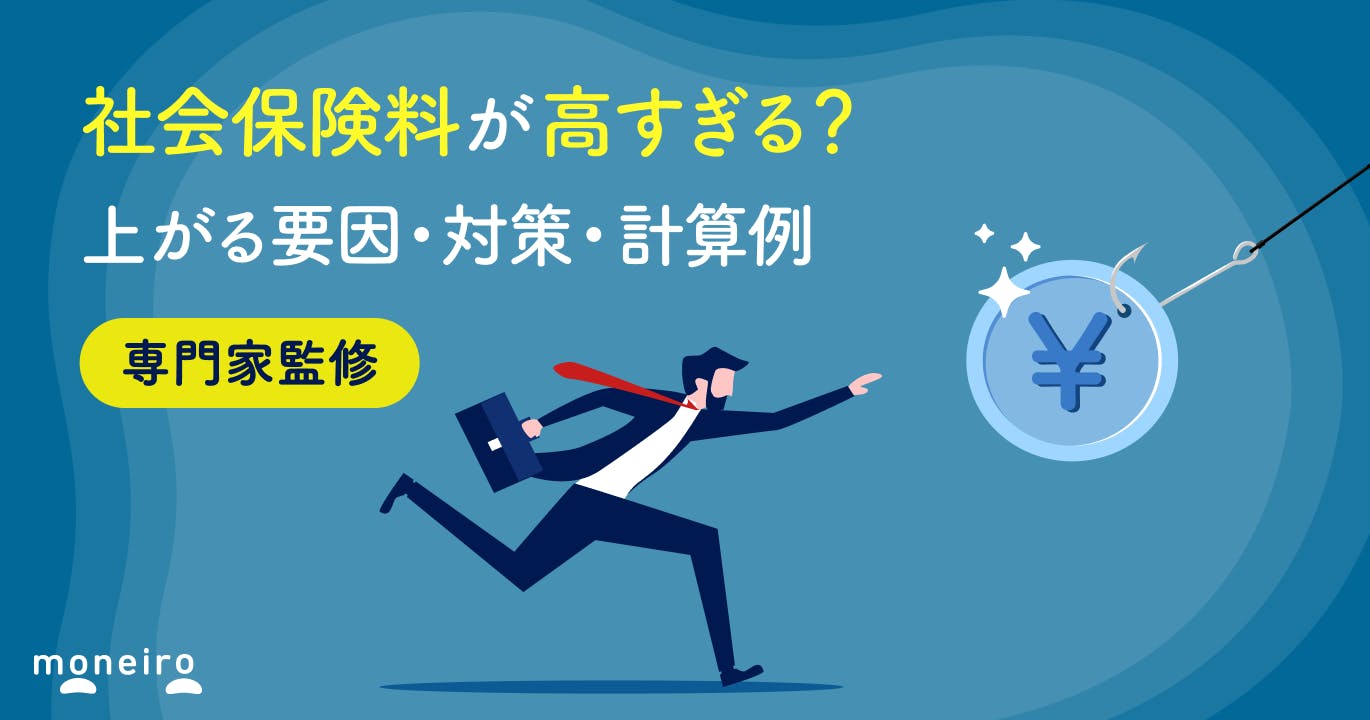
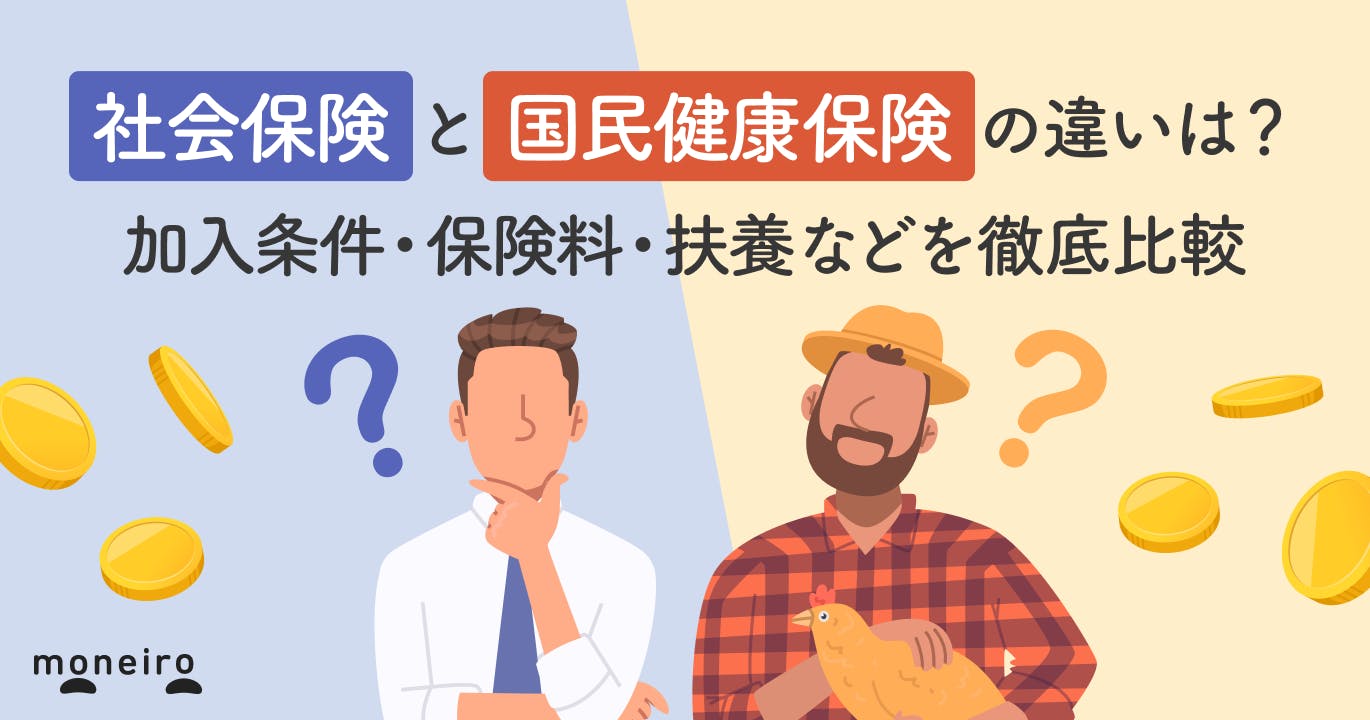
社会保険と国民健康保険の違いは?加入条件・保険料・扶養などを徹底比較
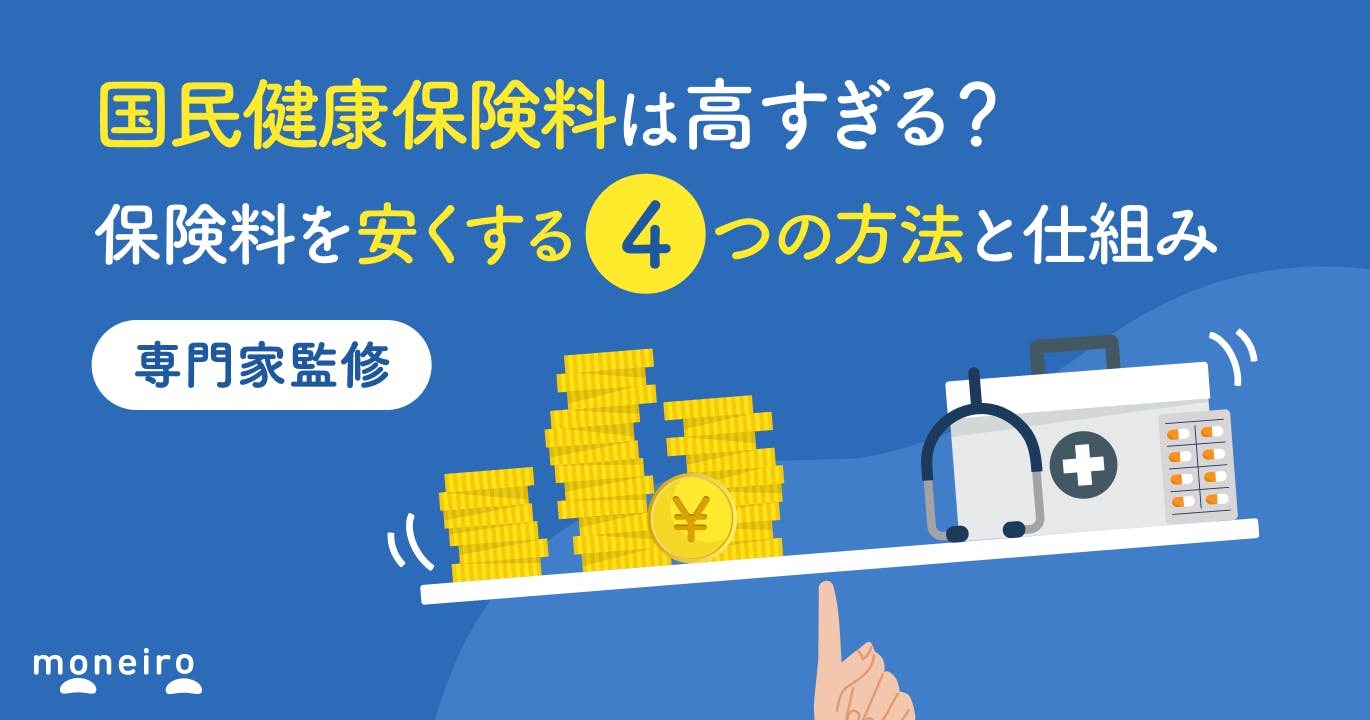
国民健康保険料は高すぎる?保険料を安くする4つの方法と知っておきたい基本の仕組み

国民健康保険vs扶養どっちが得?年収別のシミュレーションと判断ポイントを徹底解説
監修
山本 務
- 特定社会保険労務士/AFP/第一種衛生管理者
東京都練馬区で、やまもと社会保険労務士事務所を開業。企業の情報システム、人事部門において通算28年の会社員経験があるのが強みであり、情報システム部門と人事部門の苦労がわかる社会保険労務士。労務相談、人事労務管理、就業規則、給与計算、電子申請が得意であり、労働相談は労働局での総合労働相談員の経験を生かした対応ができる。各種手続きは電子申請で全国対応が可能。また、各種サイトで人事労務関係の記事執筆や監修も行っている。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。