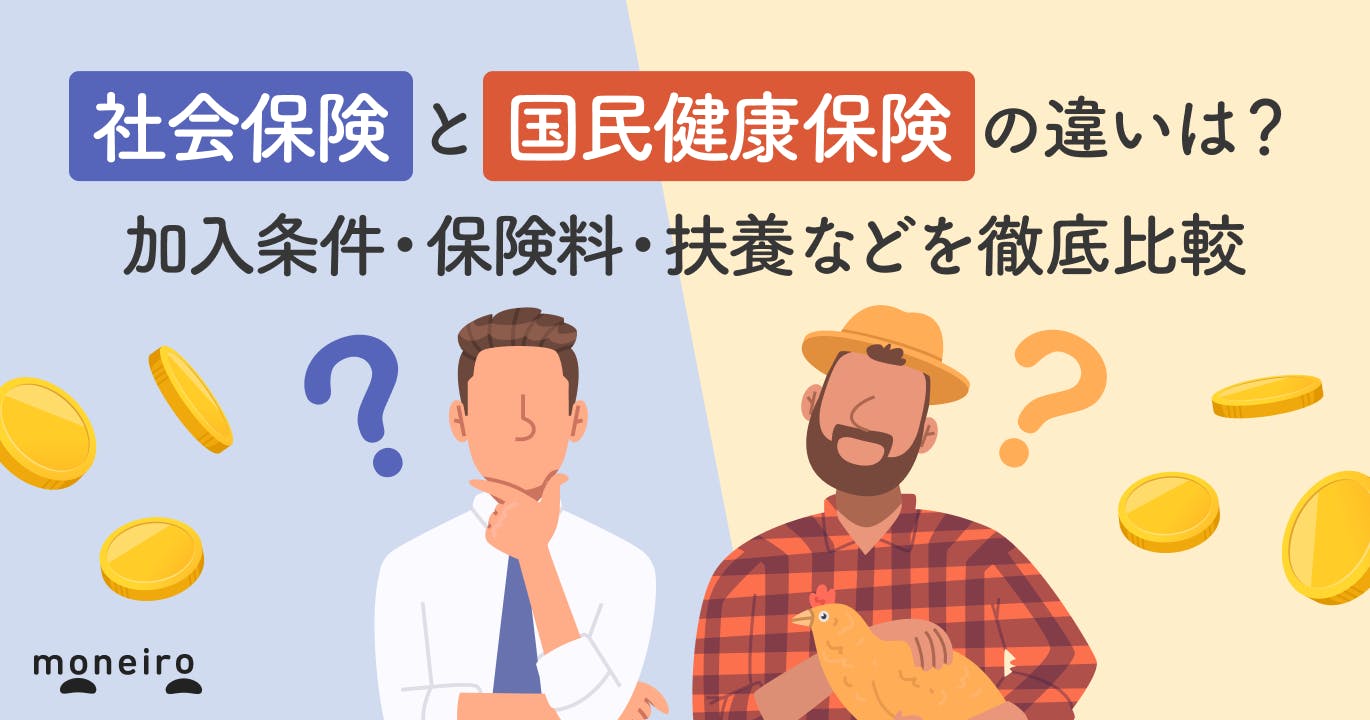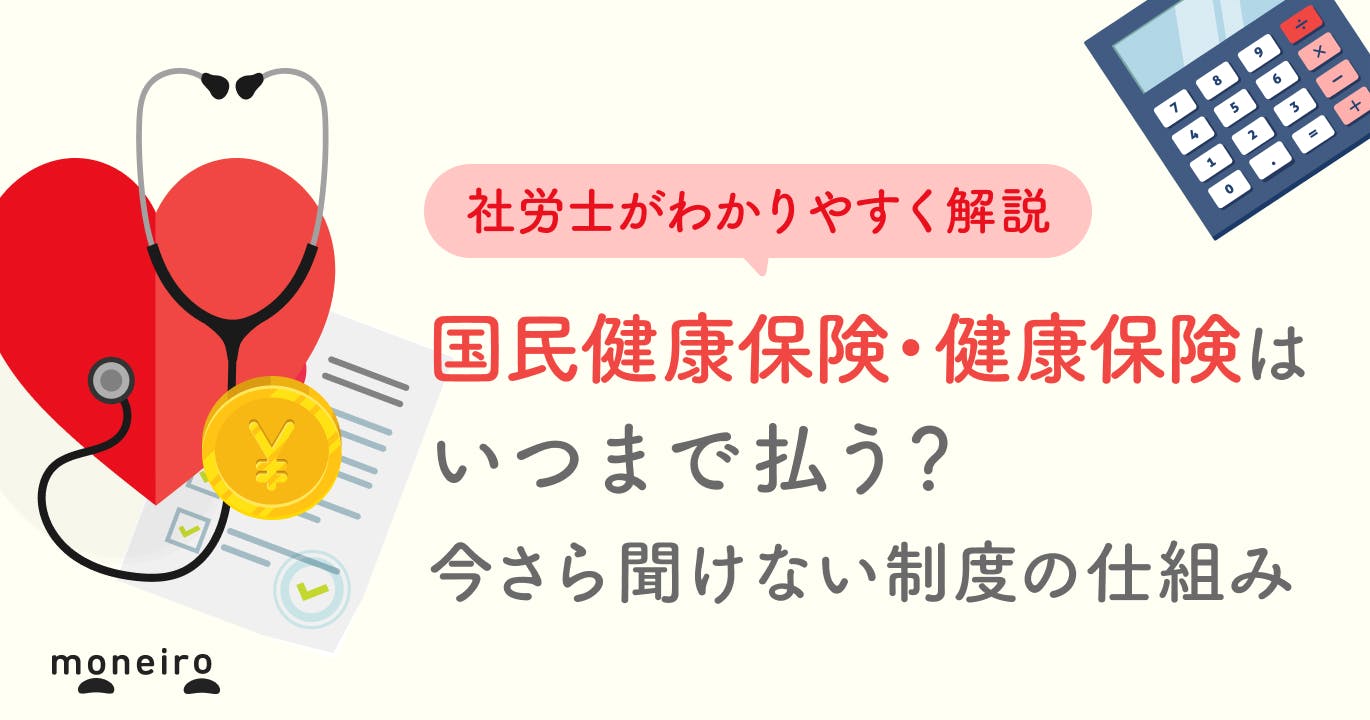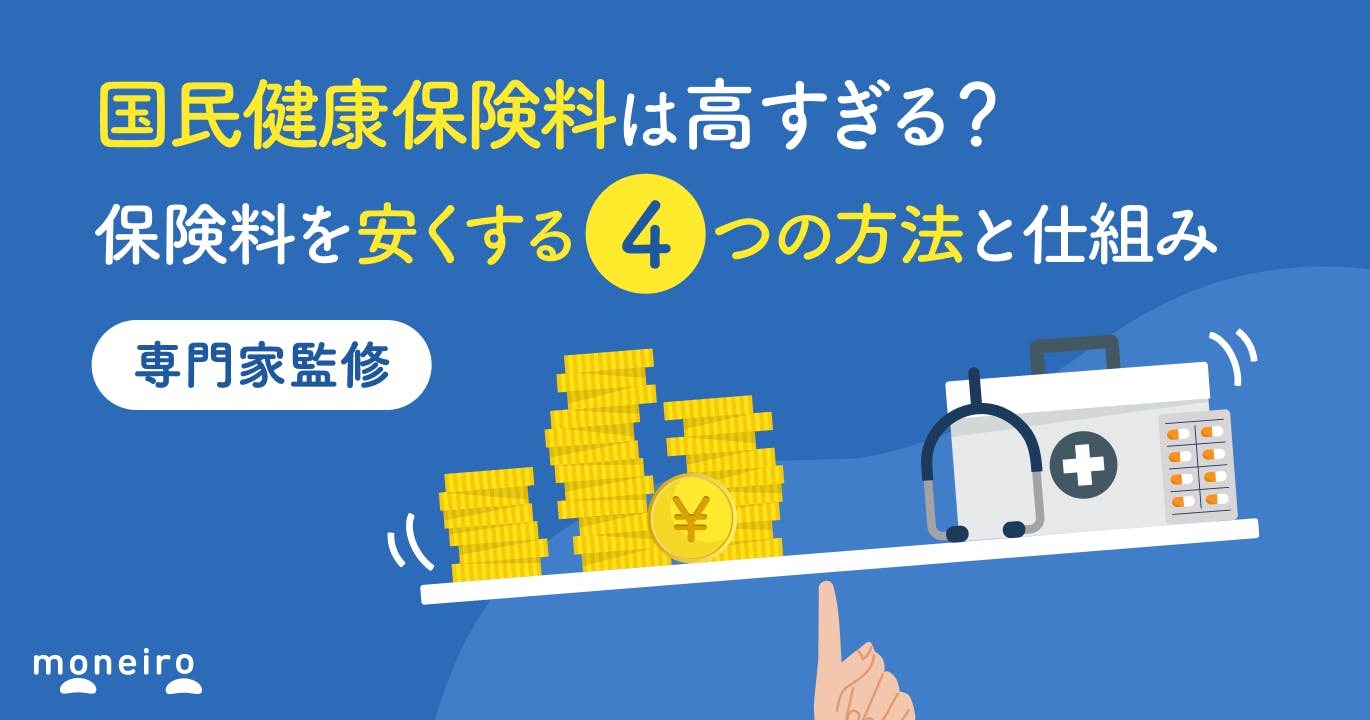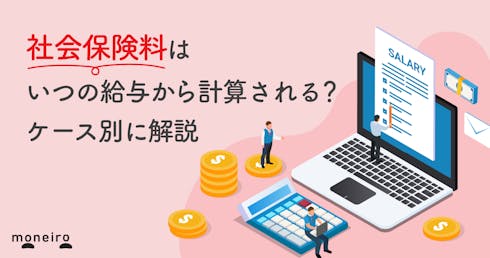
社会保険と国民健康保険の違いは?加入条件・保険料・扶養などを徹底比較
【無料】将来の備えは大丈夫?あなたに必要な資金を3分で診断
「社会保険と国民健康保険の違いは何?」「自分はどちらに加入するべき?」といったお悩みはありませんか?
本記事では、社会保険と国民健康保険の違いについて、加入条件から保険料、扶養の有無などさまざまな観点で比較し詳しく解説します。
退職後や独立時など、状況に合わせた最適な保険の選択と、必要な手続きが分かります。ぜひ参考にしてみてください。
- 社会保険と国民健康保険の基本
- 社会保険と国民健康保険の具体的な違い
- 社会保険・国民健康保険の切り替え方法とポイント
健康保険が気になるあなたへ
将来を健やかに過ごすためには、医療や介護などに関する十分な備えが必要です。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
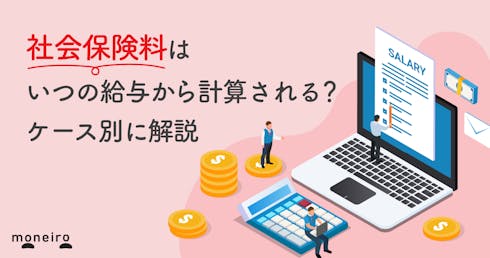
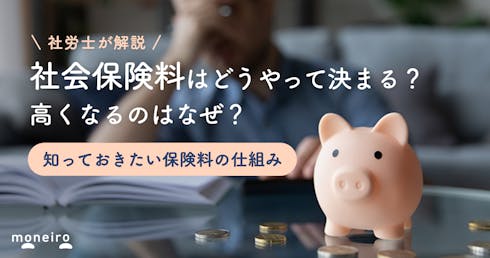
そもそも社会保険・国民健康保険とは?
日本の公的医療保険制度は、誰もが安心して医療を受けられるように、国民全員がいずれかの医療保険に加入する「国民皆保険制度」を採用しています。
その中で、会社員や公務員が加入する「社会保険」と、自営業者や年金受給者などが加入する「国民健康保険」の2つの大きな柱があります。
社会保険
社会保険とは、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の総称です。
一般的に「社会保険」という言葉は、これらの保険制度全体を指しますが、この記事では、「国民健康保険」との比較のため、上記のうち、主に医療保険としての「健康保険」に焦点を当てて解説します。
健康保険は、病気やけがをした際に医療費の一部を負担してくれる公的な制度であり、主に会社に勤める人が加入します。
国民健康保険
国民健康保険は、社会保険に加入していないすべての国民を対象とする「地域の保険」です。
会社を退職した人、フリーランスや自営業者、農業・漁業従事者、そしてそれらの人々の家族など、社会保険の適用を受けない人が加入します。各市区町村が運営しており、病気やけがの際に医療費の負担を軽減する役割を担っています。
【徹底比較】社会保険と国民健康保険の違い
社会保険と国民健康保険は、日本の公的医療保険制度の根幹をなすものですが、その仕組みや対象者には、以下のような違いがあります。
各項目の違いについて、以下の項目で詳しく解説していきます。
加入対象者
- 社会保険(健康保険):主に会社などの事業所で働く従業員とその扶養家族が対象となります。正社員だけでなく、一定の条件を満たすパートタイマーやアルバイトも加入義務があります。
- 国民健康保険:社会保険の加入者とその扶養家族、および後期高齢者医療制度の対象者や生活保護者を除いた全ての日本国民が加入対象です。具体的には、自営業者、フリーランス、年金受給者、無職の人などが該当します。
加入方法
- 社会保険:勤めている会社を通じて加入手続きが行われます。会社が従業員の入社時に必要な手続きを行い、従業員自身が個別に手続きをする必要は原則ありません。
- 国民健康保険:原則として個人で手続きを行います。市区町村の役所窓口で、転入時や会社を退職した際などに自身で届け出をする必要があります。
保険料の決まり方
- 社会保険の保険料:加入者の給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決定されます。保険料は法律により、会社と従業員が原則として半分ずつ(折半)負担する仕組みです。
- 国民健康保険の保険料:前年の所得、世帯の人数、加入者数などをもとに、市区町村が定めた保険料率や計算方式に従って算出されます。自治体ごとに制度設計が異なるため、同じ所得や家族構成でも、居住地によって保険料額に差が生じることがあります。
保険料の支払い方法
- 社会保険の保険料:給与から天引きされる形で支払われます。毎月の給与から自動的に差し引かれるため、個人で支払い手続きをする手間がかかりません。
- 国民健康保険の保険料:保険料は原則として本人が納付します。支払い方法は自治体によって異なり、口座振替、納付書による金融機関・コンビニ等での支払い、クレジットカード払いやスマホ決済などの方法があります。支払いが遅れると延滞金がかかる場合もあるため注意が必要です。
給付内容
社会保険(健康保険)と国民健康保険は、どちらも病気やけがをした際の医療費の自己負担割合を原則3割に抑えるという基本的な給付内容は共通しています(就学前は2割、高齢者は1〜2割)。
また、出産育児一時金や死亡時の給付(国保では「葬祭費」、社会保険では「埋葬料」など)は、両制度に共通する給付として存在します。
一方で、傷病手当金(病気やけがで仕事を休んだ際の所得補償)や出産手当金(出産で仕事を休んだ際の所得補償)など、働けない期間の生活を支えるための手当金制度は社会保険のみにあり、国民健康保険にはありません。
扶養制度
- 社会保険:配偶者や子、親などを扶養に入れる制度があります。扶養されている家族は、追加の保険料負担なしで健康保険の給付を受けることができます。
- 国民健康保険:扶養という概念はありません。世帯主がまとめて保険料を支払いますが、加入者全員がそれぞれ国民健康保険の被保険者として扱われるため、家族の人数に応じて保険料が加算されます。
社会保険・国民健康保険の切り替えの方法は?手続きガイド
働き方やライフスタイルが変わった際には、加入する医療保険も切り替える必要があります。ここでは、社会保険と国民健康保険を切り替える際の手続き方法について解説します。
社会保険から国民健康保険への切り替え
会社を退職するなどして社会保険の資格を喪失した場合、原則として世帯主が14日以内に国民健康保険への加入手続きを行う必要があります。
手続きには、会社から発行される「健康保険資格喪失証明書」や「退職証明書」、本人確認書類、マイナンバーカードなどが必要です。手続きは、お住まいの市区町村の役所窓口で行います。
期限を過ぎてしまうと、医療費を一時的に全額自己負担しなければならない期間が発生する可能性があるため、速やかに手続きを行いましょう。
国民健康保険から社会保険への切り替え
就職して社会保険が適用される会社に勤めることになった場合、国民健康保険から社会保険への切り替え手続きは、原則として就職先の会社が行います。入社時に必要な書類を会社に提出することで、会社が健康保険の加入手続きを進めてくれます。
なお、国民健康保険の脱退手続きは自動的には行われません。必要書類を揃えて市区町村の役所窓口で脱退手続きを行います。脱退手続きは電子申請(オンライン申請)でも可能です。
社会保険の保険証が発行されたら、手元にある国民健康保険証は、お住まいの市区町村の役所窓口に速やかに返却する必要があります。
健康保険が気になるあなたへ
将来を健やかに過ごすためには、医療や介護などに関する十分な備えが必要です。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
退職・独立したら社会保険・国民健康保険はどうなる?
次に、退職や独立といった具体的なシーン別に、適用される保険と、どちらがお得になるかを解説します。
ケース1.会社を退職した場合
会社を退職した場合、医療保険の選択肢は大きく分けて2つあります。
1つ目は「国民健康保険に加入する」方法、2つ目は「社会保険を任意継続する」方法です。どちらがお得になるかは、退職時の状況や収入によって異なるため、状況に合わせてシミュレーションすることが重要です。
社会保険の任意継続とは?
社会保険の任意継続とは、会社を退職した後も、最長2年間、これまで加入していた社会保険(健康保険)を継続できる制度です。任意継続の加入条件は、以下の2点です。
- 退職日までに継続して2ヶ月以上被保険者期間があること
- 退職日の翌日から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
任意継続の最大のメリットは、在職中と同様に扶養制度を利用できる点です。ただし、保険料はこれまで会社が負担していた分も自己負担となります。そのため、保険料は退職前の約2倍になる点には注意が必要です。
ケース2.フリーランス・自営業者として独立した場合
フリーランスや自営業者として独立した場合、原則として国民健康保険に加入することになります。
会社員時代の社会保険とは異なり、国民健康保険には扶養制度がないため、家族がいる場合は家族全員分の保険料を支払う必要があります。
保険料は前年の所得によって決まるため、収入が安定しない独立直後は負担に感じるかもしれません。青色申告による所得控除など、所得を抑える節税対策を積極的に行うことで、保険料負担を軽減できる場合があります。
ケース3.配偶者の扶養に入る場合
配偶者が社会保険に加入している場合、自分の年収が年間130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)など、一定の条件を満たせば、配偶者の健康保険の扶養(被扶養者)として加入することができます。
被扶養者になると、自分で健康保険料や年金保険料を支払う必要がなくなり、保険料の負担を大幅に軽減できます。手続きは、配偶者の勤務先を通じて行います。年収見込みなどを申告する必要がありますので、加入条件を満たしているかどうかを事前に確認しておきましょう。
まとめ
社会保険と国民健康保険には、加入条件や保険料の決まり方、給付内容、扶養制度など、多くの点で違いがあります。
これらは私たちの生活を支える重要な公的医療保険制度であり、会社員であれば社会保険、フリーランスや自営業者であれば国民健康保険が原則的な加入先となります。
退職時などには任意継続や扶養に入る選択肢もありますので、自身の働き方やライフスタイルの変化に合わせて、それぞれの保険の特徴を理解し、適切な選択をすることが大切です。
健康保険が気になるあなたへ
将来を健やかに過ごすためには、医療や介護などに関する十分な備えが必要です。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
山本 務
- 特定社会保険労務士/AFP/第一種衛生管理者
東京都練馬区で、やまもと社会保険労務士事務所を開業。企業の情報システム、人事部門において通算28年の会社員経験があるのが強みであり、情報システム部門と人事部門の苦労がわかる社会保険労務士。労務相談、人事労務管理、就業規則、給与計算、電子申請が得意であり、労働相談は労働局での総合労働相談員の経験を生かした対応ができる。各種手続きは電子申請で全国対応が可能。また、各種サイトで人事労務関係の記事執筆や監修も行っている。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。