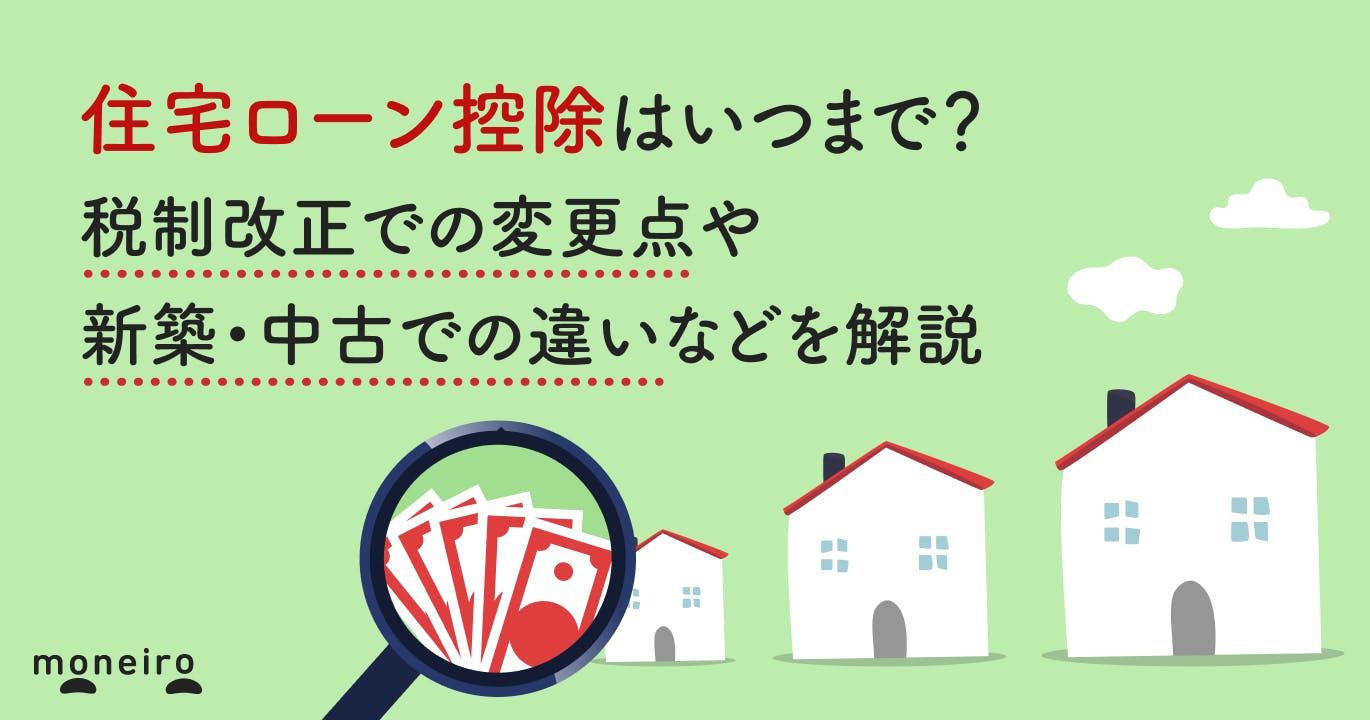
住宅ローン控除とふるさと納税は併用できる?損しないための注意点を解説
>>あなたは足りる?老後の不足額をツールで簡単診断
住宅ローン控除(住宅ローン減税)とふるさと納税は、どちらも家計の負担を軽減する人気の節税制度です。しかし、「これらは併用できるのか?」「併用すると損をするケースがあるのか?」といった疑問を持つ方もいらっしゃるでしょう。
本記事では、これら2つの制度の基本的な仕組みから、併用時の注意点、控除上限額のシミュレーション、そして住宅ローン控除初年度の確定申告方法まで、わかりやすく解説します。賢く節税し、手元に残るお金を増やすためのポイントを確認しておきましょう。
- 住宅ローン控除とふるさと納税が併用の可否、併用時の基本的な考え方
- 「損をするケース」と「損をしないケース」の違い
- 併用時の確定申告やワンストップ特例制度の選択基準
節税が気になるあなたへ
現在の収入や資産で、将来どれくらいの貯金が貯まるのか、また老後生活にはどれくらい足りないのかを早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
住宅ローン控除とふるさと納税の基本
まずは住宅ローン控除とふるさと納税の基本からしっかり押さえておきましょう。
住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)とは、住宅を確保する上での負担軽減を目的とした制度です。
具体的には、住宅ローンを利用してマイホームの新築、取得、または増改築等を行った場合に、年末時点の住宅ローン残高の0.7%を所得税から、一部は翌年度の住民税から、最大13年間にわたって控除されます。
ふるさと納税とは?
ふるさと納税とは、「応援したい自治体」に寄附(寄付金)をすることで、その寄附金のうち2000円を超える部分が、所得税と住民税から控除される制度です。
寄附を行うと、その自治体からお礼として特産品などの「返礼品」が贈られる点が大きな特徴です。また、寄附の際に「寄付金受領証明書」が発行され、これを用いて確定申告やワンストップ特例制度を利用することで税金が控除されます。
住宅ローン控除とふるさと納税は併用できる?
住宅ローン控除とふるさと納税は併用が可能です。
ただし、一部では「併用は損」といわれることもあります。その理由について解説します。
住宅ローン控除とふるさと納税は併用すると損?
住宅ローン控除とふるさと納税の併用が「損」と言われる主な理由は、税金の控除額の計算順序にあります。日本の所得税と住民税の計算では、所得税が先に計算されます。住宅ローン控除は、まず所得税から控除され、控除しきれない分が翌年度の住民税から控除されます。一方、ふるさと納税の控除は、住宅ローン控除の適用後の所得税や住民税を基に計算されます。
そのため、住宅ローン控除によって所得税や住民税の納税額が大きく減少すると、ふるさと納税で控除できる税額の上限が下がり、結果としてふるさと納税のメリットを最大限に享受できない可能性があります。特に、所得税の控除額が大きいと、ふるさと納税の寄附金控除に使える税額が減少し、自己負担額2000円を超えても控除しきれない部分が生じることがあります。
損をしないケースもある
一方で、住宅ローン控除とふるさと納税を併用しても「損をしないケース」もあります。これは、主に個人の所得が高く、住宅ローン控除を適用した後でも所得税や住民税の納税額が十分に大きい場合です。
具体的には、住宅ローン控除によって税額が減額されたとしても、依然としてふるさと納税の控除上限額を適用できるだけの納税額があれば、両方の制度の恩恵を最大限に受けることができます。この場合は、両方のメリットを享受できます。
また、ふるさと納税の目的が単なる節税だけでなく、特定の自治体への貢献や返礼品による家計の助けにある場合は、税制上のメリットが多少減少したとしても、総合的な満足度やメリットは大きいと考えることもできるでしょう。
住宅ローン控除とふるさと納税を併用する際の注意点
次に住宅ローン控除とふるさと納税を併用する際の具体的な注意点について詳しく解説していきます。
住宅ローン控除の初年度は確定申告が必須
住宅ローン控除を初めて受ける年は、税務署への確定申告が法律で義務付けられています。これは、住宅の取得やローンの内容を税務署が把握する必要があるためです。
ふるさと納税には、原則として確定申告が不要となる ワンストップ特例制度があります。しかし、住宅ローン控除の初年度は確定申告が必須のため、この制度は利用できません。
そのため、住宅ローン控除の確定申告を行う際には、ふるさと納税による寄附金控除もあわせて申告する必要があります。確定申告を行うと、すでに提出済みのワンストップ特例の申請はすべて無効となります。
なお、複数の自治体にふるさと納税を行った場合でも、確定申告でまとめて寄附金控除を申告可能です。寄付金受領証明書など必要書類を忘れずに準備し、手続きを進めましょう。
ふるさと納税の控除上限額に注意
住宅ローン控除とふるさと納税を併用する際にもっとも注意すべき点は、ふるさと納税の控除上限額です。ふるさと納税で税額控除される金額には、個人の所得や家族構成に応じた上限が設けられており、この上限額は所得税と住民税の納税額に基づいて計算されます。
住宅ローン控除は、所得税と住民税から税額を直接控除する効果が非常に大きいため、この控除を適用すると、ふるさと納税の控除上限額が変動(減少)する可能性があります。具体的には、住宅ローン控除によって所得税が大幅に減額されると、その分、ふるさと納税の控除に使える税額の枠が小さくなり、結果として自己負担分が増えてしまうことがあります。
控除上限額を超えて寄附した分は、自己負担額2000円とは別に全額が自己負担となります。そのため、自分の年収や家族構成、住宅ローンの残高などを考慮し、総務省やふるさと納税サイトなどのシミュレーションツールで事前に正確な控除上限額をシミュレーションしておくことが大切です。
医療費控除などを併用する場合の注意点
住宅ローン控除やふるさと納税のほかにも、医療費控除や生命保険料控除など、さまざまな所得控除が存在します。これらを併用する際は、それぞれの控除が全体の税額にどう影響するかを理解しておくことが重要です。特に注意すべきは、控除の種類による違いです。
- 所得控除:医療費控除や生命保険料控除は「所得控除」であり、課税所得を減らす効果があります。
- 税額控除:住宅ローン控除は「税額控除」であり、算出された所得税額そのものから直接差し引かれます。
そのため、医療費控除などの所得控除を適用して課税所得が減ると、それに伴い所得税額も減少します。その結果、ふるさと納税の控除上限額にも影響を及ぼす可能性があります。
控除の組み合わせによっては最大限の節税効果を得られない場合があるため、複数の控除を併用する際は、全体の税額を最適化するためのシミュレーションを行うことが大切です。
節税が気になるあなたへ
現在の収入や資産で、将来どれくらいの貯金が貯まるのか、また老後生活にはどれくらい足りないのかを早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
ワンストップ特例制度と確定申告、どちらを選ぶべき?
ふるさと納税を利用した際に寄附金控除を受けるには、ワンストップ特例制度と確定申告、2つの方法があります。自分に合った方法を選択するために、それぞれの特徴を理解しておきましょう。
ワンストップ特例制度のメリット・デメリット
ふるさと納税を利用する際に選択できる「ワンストップ特例制度」は、確定申告が不要になる簡便な制度です。
ワンストップ特例制度のメリット
ワンストップ特例制度の最大のメリットは、確定申告の手間を省ける点にあります。この制度を利用すれば、ふるさと納税の控除手続きのために税務署へ行ったり、複雑な書類を作成したりする必要がなくなります。手続きは非常に簡単で、以下の条件を満たせば利用できます。
- 給与所得者などで、もともと確定申告が不要な人
- ふるさと納税を行った自治体が、年間5団体以内であること
これらの条件を満たせば、寄附先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」と本人確認書類を郵送するだけで手続きが完了します。
この手軽さから、普段確定申告をする機会がない会社員や公務員にとって、非常に便利な制度です。
ワンストップ特例制度のデメリット
一方で、ワンストップ特例制度にはいくつかのデメリットがあります。まず、医療費控除や雑損控除など、他の所得控除や税額控除を適用するために確定申告が必要な場合は、ワンストップ特例制度を利用できません。この場合、ふるさと納税分も合わせて確定申告を行う必要があります。
また、寄附先の自治体が年間6団体以上になると、ワンストップ特例制度の対象外となり、確定申告が必須となります。
さらに、一度ワンストップ特例制度の申請をした後に確定申告を行うと、ワンストップ特例制度による申請はすべて無効となるため、注意が必要です。
確定申告のメリット・デメリット
確定申告は、自身の所得や税金を税務署に申告する手続きです。ふるさと納税や住宅ローン控除を適用する際にも利用されます。
確定申告のメリット
確定申告の最大のメリットは、さまざまな所得控除や税額控除をまとめて申告できる点にあります。これにより、以下の控除を一度の手続きで適用できます。
- 医療費控除
- 生命保険料控除
- 寄附金控除(ふるさと納税を含む)
- iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金
特に、住宅ローン控除の初年度は確定申告が義務付けられているため、ふるさと納税を併用する場合は、この機会にまとめて申告することで手続きを一度で済ませることができ、非常に効率的です。
また、ふるさと納税において、ワンストップ特例制度では寄付先の自治体数が年間5団体以内という制限がありますが、確定申告にはこの制限がありません。そのため、6団体以上に寄付した場合でも手続きをすることで控除を受けられます。
確定申告のデメリット
確定申告の最大のデメリットは、手続きが複雑で手間がかかる点です。普段確定申告をしない給与所得者にとっては、税金の専門知識が必要となるだけでなく、以下の負担が伴います。
- 多くの書類準備:源泉徴収票や控除証明書など、様々な書類を漏れなく集めなければなりません。
- 記入と計算:複雑な申告書を作成し、正確な控除額を自分で計算する必要があります。
e-Tax(電子申告)を利用すれば自宅から手続きが可能ですが、初期設定や操作に慣れるまで時間がかかることもあります。また、確定申告には期間が限定されているという制約もあります。
- 申告期間:原則として毎年2月16日から3月15日まで
- ペナルティ:期限を過ぎると、税金が控除されなかったり、延滞税や無申告加算税などのペナルティが発生する可能性があります。
これらの点を考慮すると、確定申告はメリットがある一方で、時間や労力、そして正確さが求められる点がデメリットだといえます。
住宅ローン控除とふるさと納税に関するよくある質問(Q&A)
住宅ローン控除とふるさと納税に関するよくある質問と回答をまとめました。
Q. 夫婦ペアローンや収入合算の場合はどうなる?
夫婦でペアローンを利用している場合や、収入合算で住宅ローンを組んでいる場合、夫婦それぞれが住宅ローン控除の適用を受けることができます。この場合、それぞれの持ち分割合に応じて、年末のローン残高が夫婦それぞれの住宅ローン残高として計算され、その金額に基づいて個別に住宅ローン控除が適用されます。
ふるさと納税に関しても、夫婦それぞれが納税者であるため、それぞれの所得に応じて個別に控除上限額が設定されます。
そのため、夫婦それぞれが自身の控除上限額の範囲内でふるさと納税を行うことで、夫婦合わせて最大限の節税効果を得ることが可能です。
Q. 確定申告とワンストップ特例を間違えて申請してしまった場合どうする?
ワンストップ特例制度を申請した後に、医療費控除などの理由で確定申告を行った場合、ワンストップ特例制度による申請はすべて無効となります。
これは、確定申告がその年間のすべての所得や控除を網羅的に申告する最終的な手続きであり、ワンストップ特例制度に優先して適用されるためです。この場合、以下の手続きが必要となります。
- 改めて確定申告書にふるさと納税の寄附金控除に関する情報を記載する
- 寄附先の自治体から発行された「寄附金受領証明書」を添付して申告する
もし、確定申告でふるさと納税の申告を忘れてしまった場合でも、5年以内であれば「更正の請求」という手続きを行うことで、税金の還付を受けることが可能です。
期限内に正しい手続きを行うことで、本来受けられるはずの税制優遇を確実に受けましょう。
Q. ふるさと納税の上限額を超えて寄付してしまった場合どうなる?
ふるさと納税の控除上限額を超えて寄附をしてしまった場合、上限額を超過した部分の金額は、税金からの控除対象とはなりません。この超過分は、純粋な「寄附金」として自己負担となります。
例えば、控除上限額が5万円の人が10万円を寄附した場合、5万円分は税金から控除されますが、残りの5万円は自己負担となり、自己負担額2000円と合わせて合計5万2000円が自己負担となります。
ふるさと納税を行う際は、各ふるさと納税サイトなどで提供されているシミュレーションツールなどを活用し、自身の年収や家族構成、他の控除の有無などを考慮した上での正確な控除上限額を把握しておくことが重要です。
まとめ
住宅ローン控除とふるさと納税は、それぞれ異なる仕組みで家計の税負担を軽減する、非常に有効な制度です。これらは併用が可能ですが、最大限の節税効果を得るためには、その相互作用と注意点を正確に理解しておくことが不可欠です。
特に、住宅ローン控除の初年度は確定申告が必須となり、ふるさと納税も合わせて申告する必要があります。また、住宅ローン控除によって所得税や住民税が減少するため、ふるさと納税の控除上限額が変動(減少)する可能性がある点に注意が必要です。自身の年収や家族構成、他の所得控除の状況などを踏まえ、事前に正確なシミュレーションを行うことが、賢い節税のためのカギとなります。
今回初回した内容を参考に知識を深め、計画的に節税を行うことで、手元に残るお金を増やし、豊かな生活設計を実現しましょう。
>>あなたは足りる?老後の不足額をツールで簡単診断
節税が気になるあなたへ
現在の収入や資産で、将来どれくらいの貯金が貯まるのか、また老後生活にはどれくらい足りないのかを早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
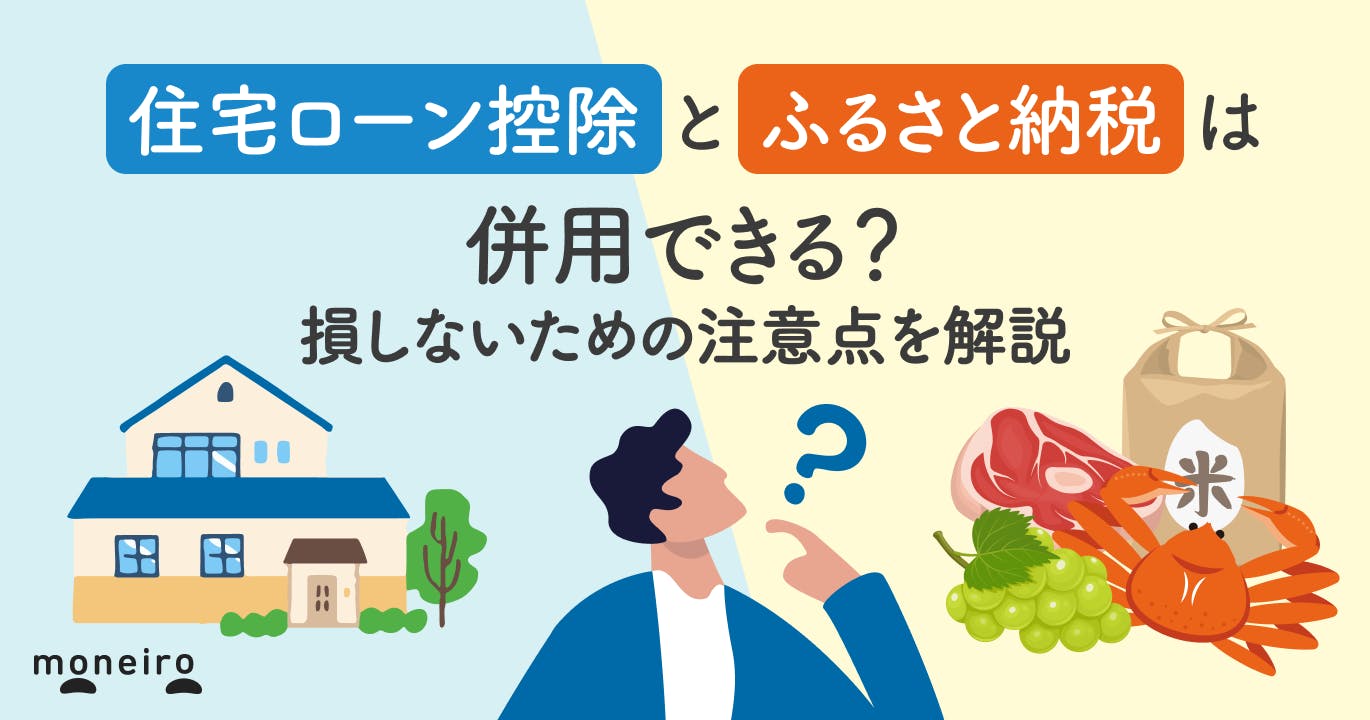
.jpg?w=1370&h=720&fit=crop&crop=faces&auto=compress,format)
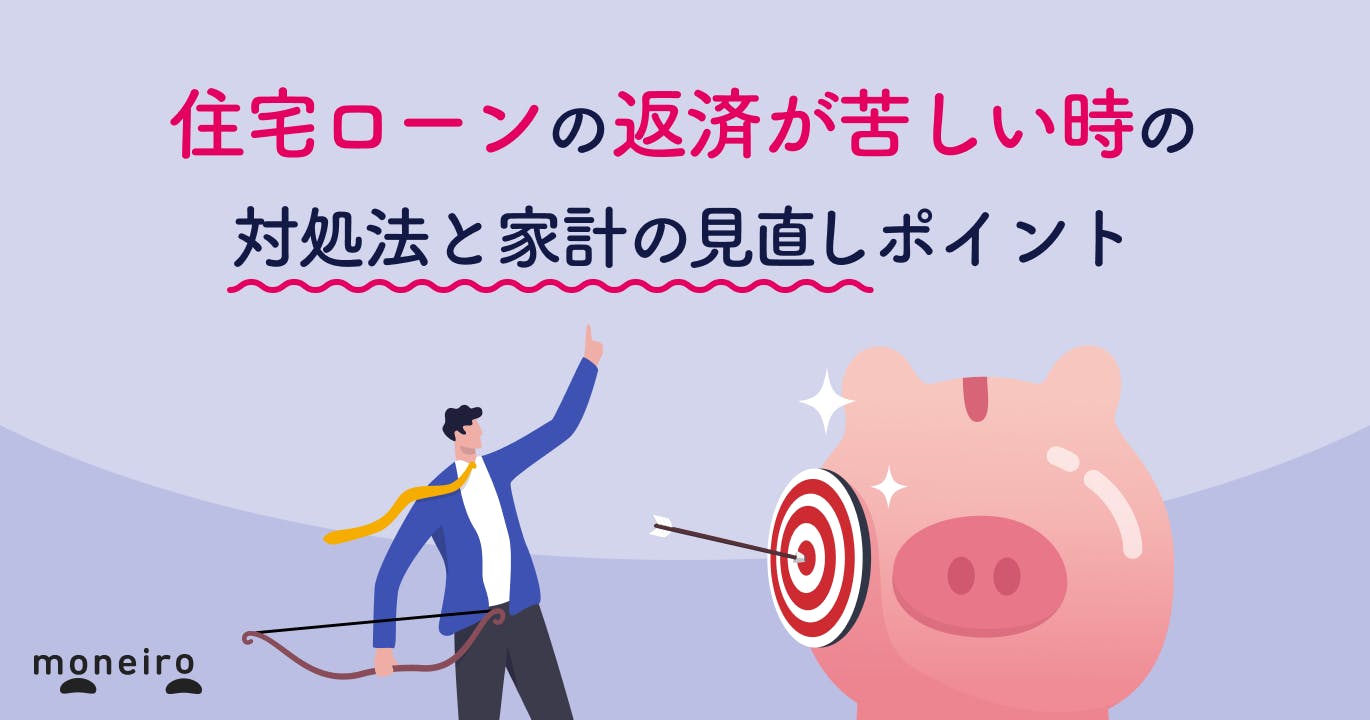
.jpg?w=1370&h=720&fit=crop&crop=faces&auto=compress,format)