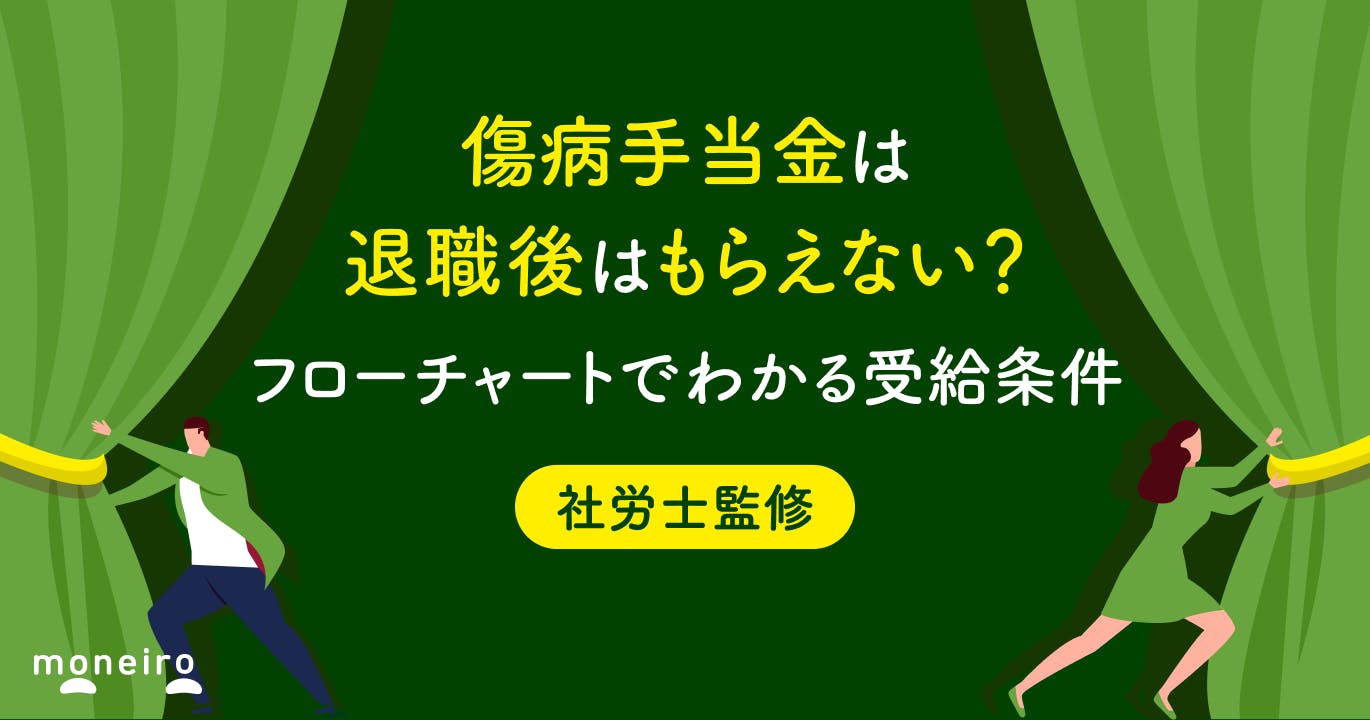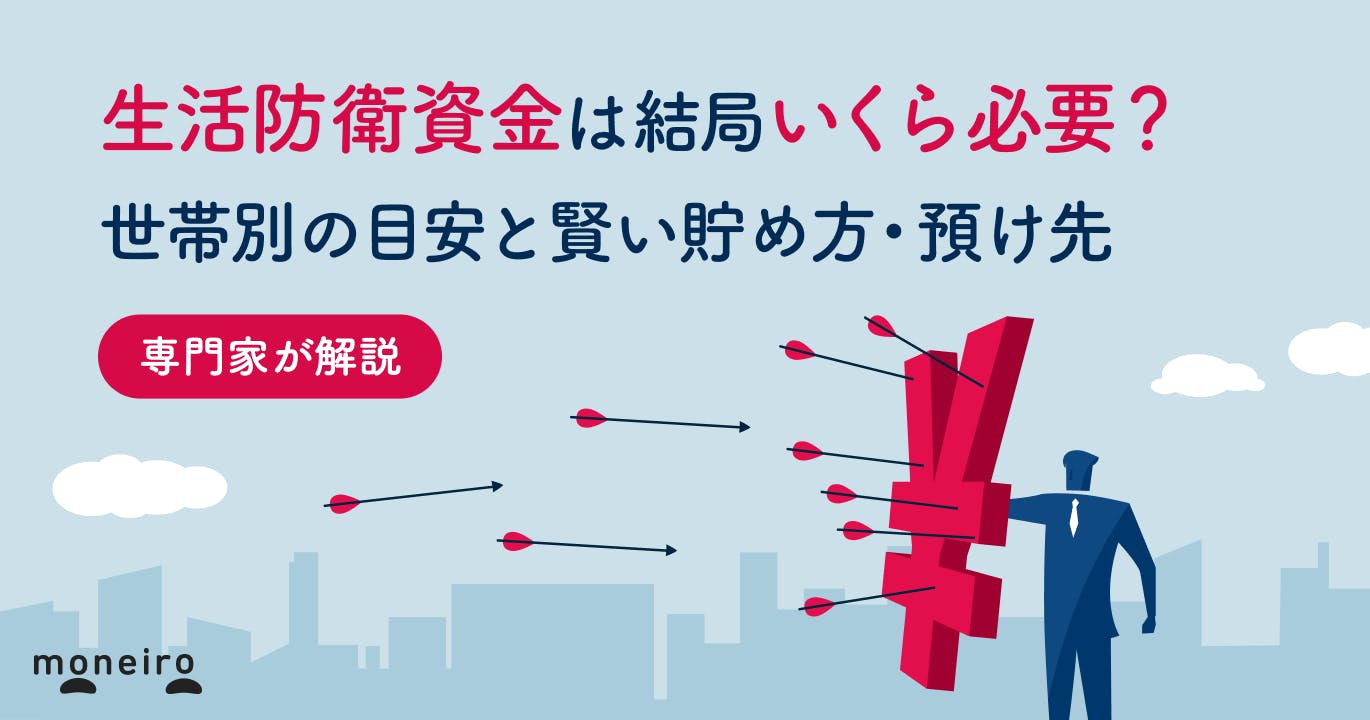傷病手当金は退職後はもらえない?フローチャートでわかる受給条件と代替策を解説
»万が一の備えはいくら必要?3分無料診断
「傷病手当金は退職後ではもらえない?」と傷病手当金をもらうための条件について調べている人も多いでしょう。
傷病手当金とは、病気や怪我で働けない時に収入を補うための制度です。しかし、退職後はいくつかの条件を満たさなければ受給できません。「在職中に支給を受けていたのに退職後はもらえない」「申請したが不支給だった」というケースも少なくありません。
本記事では、退職後に受給できる条件、もらえない理由、代わりに利用できる制度、そして退職前に準備しておくべきことを、協会けんぽや健康保険組合の公的情報をもとに専門的に解説します。制度を正しく理解し、損失を防ぎましょう。
(参考:傷病手当金について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会)
- 退職後でも条件を満たしていれば傷病手当金はもらえる
- 退職後に傷病手当金をもらうための条件は「退職日までに1年以上健康保険に加入している」「退職後も労務不能状態が継続している」など
- 傷病手当金がもらえない場合の代替制度には「雇用保険の傷病手当(失業給付の延長制度)」などがある
将来資金が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
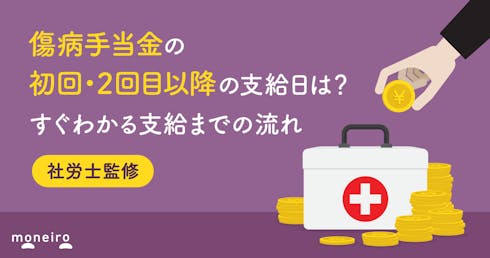
傷病手当金の基本と退職後の取り扱い
傷病手当金は、病気や怪我で仕事を休んだ際に、被保険者本人とその家族の生活を保障するために健康保険から支給される手当です。
傷病手当金は在職中だけでなく、退職後も一定の条件を満たせば引き続き受給できる場合があります。
傷病手当金の目的と概要
傷病手当金の目的は、被保険者が病気や怪我の療養のために連続して4日以上仕事を休み、その間に給与の支払いがない場合に、休業中の生活を保障することです。
支給期間は、支給が始まった日から通算して最長1年6ヶ月です。
在職中と退職後で異なる支給条件
傷病手当金は、在職中に受給を開始した場合は比較的スムーズに受け取ることができます。
しかし、退職後に受け取る場合は、「継続給付」という特別な扱いとなり、在職中とは異なる厳格な要件をすべて満たす必要があります。
「継続給付」の仕組みと健康保険法の規定
「継続給付」とは、退職日までに一定の要件を満たしている被保険者が、退職後も引き続き同一の傷病で働けない状態にある場合に、傷病手当金の支給が継続される仕組みです。
退職後にもらえる条件(継続給付の要件)
退職後も傷病手当金を受け取るには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
①退職日までに1年以上健康保険に加入している
退職日(資格喪失日の前日)までに、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あることが条件です。
転職などで保険者が変わっていても、1日も間が空くことなく連続していれば通算することができます。
なお、任意継続や国民健康保険の加入期間は通算できません。
②退職日の前日までに連続3日以上休業し、退職日も労務不能である
傷病手当金の支給には、まず3日間の待機期間が必要です。
退職後も支給を継続するには、退職日の前日までにこの待機期間を満たし、かつ退職日も仕事を休んでいる状態である必要があります。
③退職後も労務不能状態が継続している
退職後も在職中と同一の傷病の療養のために、引き続き労務不能(仕事ができない)な状態が続いていることが条件です。
この状態は、医師の診断書で証明する必要があります。
④支給開始日から通算1年6ヶ月以内である
傷病手当金の支給期間は、支給が始まった日(支給開始日)から通算して1年6ヶ月が上限です。退職後もこの期間内であれば、支給が継続されます。
将来資金が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
退職後にもらえない主な理由
退職後も傷病手当金が受け取れると思っていても、実際にはもらえないケースがあります。
受給開始前に退職した(要件未充足)
退職日までに、健康保険加入期間が1年未満だったり、待機期間を満たしていなかったりすると、退職後も受給する資格を得られません。
退職日に出勤していた(労務不能要件未達)
「退職日に短時間でも出勤した」というケースでは、労務不能要件を満たせないため、継続給付の対象になりません。
傷病が退職日以降に発症した
退職後に初めて発症した傷病では、原則として傷病手当金の支給対象にはなりません。あくまで在職中に発症した傷病と同一の傷病で療養していることが条件です。
申請期限切れや書類不備による不支給
傷病手当金の申請期限は、療養のために仕事を休んだ日から2年以内です。また、申請書に記入漏れなどの不備があると、手続きが遅れたり、支給が却下されたりすることがあります。
条件別フローチャート:退職後にもらえるかどうか
退職後も傷病手当金がもらえるかどうか、以下のフローチャートで簡単にチェックしてみましょう。
受給可否の判断例(事例シミュレーション)
・事例2:退職日に出勤 → 受給不可
・事例3:退職後に別傷病発症 → 受給不可
傷病手当金がもらえない場合の代替制度
もし退職後に傷病手当金がもらえない場合でも、他の制度で生活を支援してもらえる可能性があります。
雇用保険の傷病手当(失業給付の延長制度)
雇用保険の被保険者が失業給付を受給中に連続して15日以上病気や怪我で働けない場合に、「本来の失業給付の受給期間中の生活を安定させる」という主旨で、傷病手当を受けられる制度があります。
ただし、失業給付は「働くことができる人」に対する給付であるため、傷病手当金の支給要件とは相反し、併給はできません。
傷病手当金のかわりに受けられる民間保険給付
個人で加入している就業不能保険や所得補償保険、あるいは医療保険の特約などで、病気やケガで働けない期間の収入を保障する給付金を受け取れる場合があります。
自治体や福祉制度の生活支援金
生活に困窮した場合、住んでいる自治体の福祉制度や、社会福祉協議会が提供する生活支援金を活用できる場合があります。
退職前に確認すべきポイントと準備
退職後も傷病手当金を受け取るためには、退職前の準備が大切です。
健康保険資格期間と加入状況の確認
退職日(資格喪失日の前日)までに、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あるか、まずは確認しましょう。
申請書の入手と記入欄(事業主欄)の対応方法
傷病手当金の申請書は、会社から受け取るのが一般的です。退職前に申請書を入手し、会社には事業主欄の記入を依頼しておきましょう。
退職日と有給消化・休職期間の調整
退職日に出勤してしまうと、退職後の受給資格を失います。退職日は有給休暇や休職期間を考慮して、労務不能な状態が継続している状態で退職日を迎えることが大切です。
退職後の申請手順と必要書類
退職後の傷病手当金は、退職した会社を経由せずに、直接健康保険組合に申請します。
申請先(協会けんぽ・健康保険組合)の確認
加入していた健康保険が「協会けんぽ」か「健康保険組合」かによって、申請先が異なります。
退職前に、在職時のご加入の支部を確認しておきましょう。
資格喪失後の継続給付申請方法
退職後の傷病手当金の請求は、在職期間からの継続給付となります。
そのため、在職時に使用していた被保険者証の記号番号を控えておく必要があります。申請書に加えて、被保険者資格喪失証明書など、退職したことを証明する書類を添付します。
医師記入欄の取得と郵送手続きの流れ
退職後も療養が必要な場合、退職後も定期的に医師に診てもらい、申請書の医師記入欄を書いてもらう必要があります。
その後、必要書類をすべて揃えて、直接健康保険組合に郵送します。
まとめ
退職後も傷病手当金が受け取れるのは、退職日までに「継続給付」の要件をすべて満たしている場合に限られます。
「退職日前日までに1年以上健康保険に加入している」「退職日に労務不能である」などの要件が必須になります。
退職後に傷病手当金がもらえない場合でも、雇用保険の傷病手当や、民間の保険、自治体の制度などが利用できる可能性があります。
代替制度や自治体支援も含め、自身の状況に合った制度活用を検討しましょう。
»万が一の備えはいくら必要?3分無料診断
将来資金が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
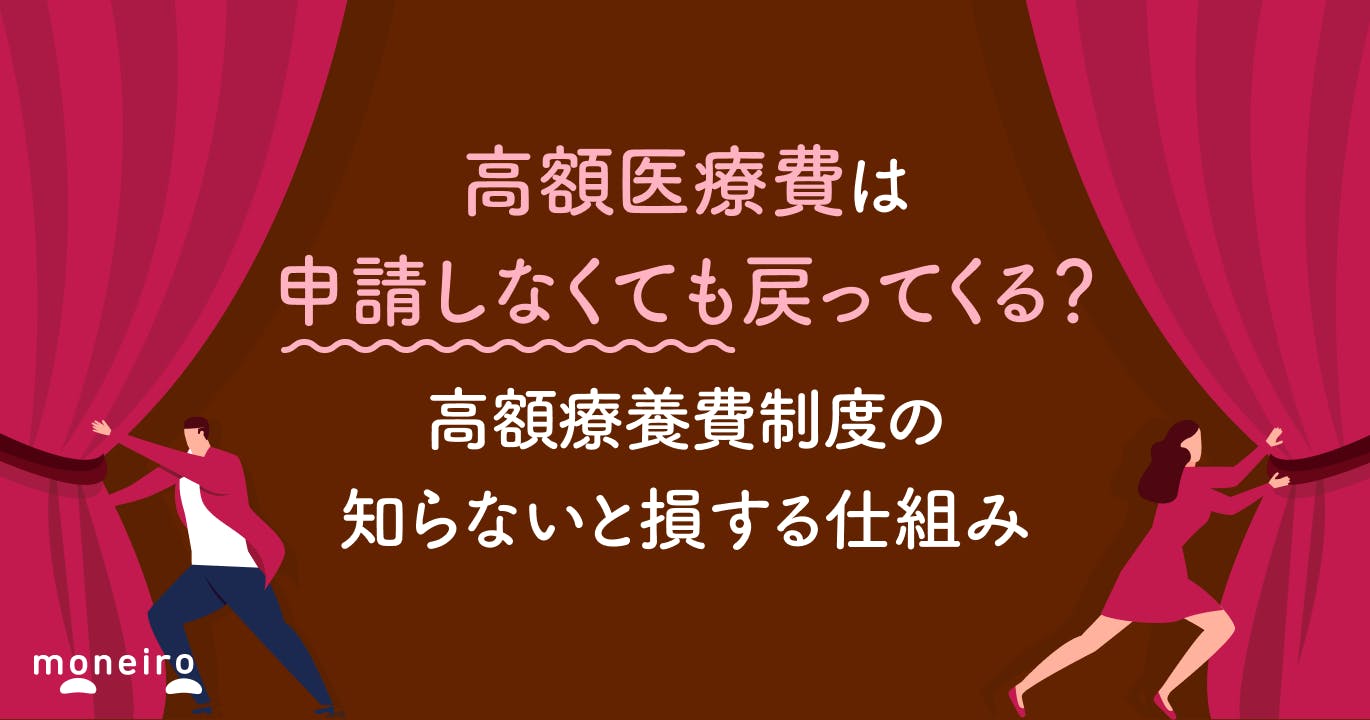
高額医療費は申請しなくても戻ってくる?高額療養費制度の知らないと損する仕組みを解説
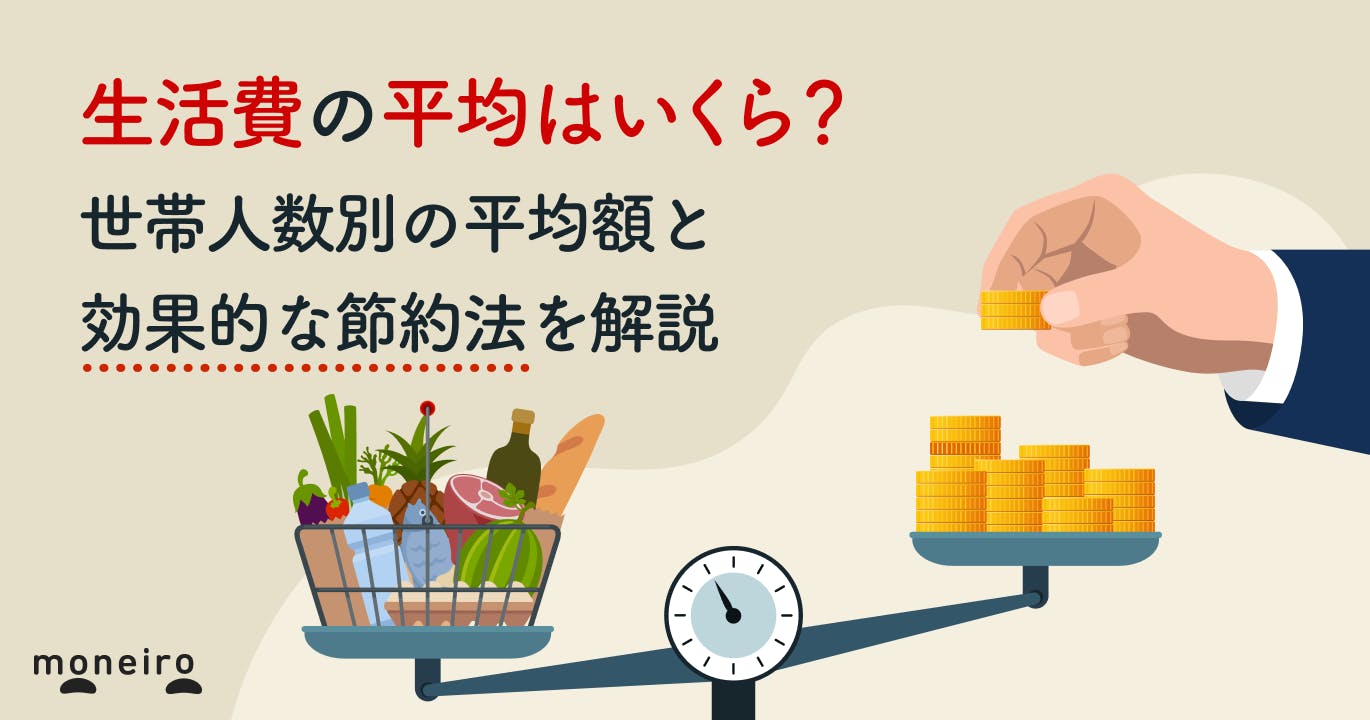
生活費の平均はいくら?世帯人数別の平均額と効果的な節約法を解説

正直みんな貯金はどのくらいある?年代別・年収別に平均額・中央値を解説
監修
山本 務
- 特定社会保険労務士/AFP/第一種衛生管理者
東京都練馬区で、やまもと社会保険労務士事務所を開業。企業の情報システム、人事部門において通算28年の会社員経験があるのが強みであり、情報システム部門と人事部門の苦労がわかる社会保険労務士。労務相談、人事労務管理、就業規則、給与計算、電子申請が得意であり、労働相談は労働局での総合労働相談員の経験を生かした対応ができる。各種手続きは電子申請で全国対応が可能。また、各種サイトで人事労務関係の記事執筆や監修も行っている。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。