
出産手当金がもらえないケースとは?退職後でもらうための条件と対処法を解説
≫将来のお金は足りる?年収や資産額から3分で診断
出産という人生の一大イベントを控え、大きな幸福感がある反面、経済的な意味で不安を抱える方も少なくないようです。
そんな経済的な不安を軽減できる「出産手当金」は、産休中の生活を支える大切な制度ですが、残念ながら誰もが受け取れるわけではありません。
そこでこの記事では、出産手当金がもらえないケースと、それぞれの対処法、さらには代替の公的支援制度までを詳しく解説します。自身の状況に当てはめて手当金がもらえるかを確認し、安心して出産を迎えられるように準備を進めましょう。
- 出産手当金が支給されない具体的なケースとその理由
- 退職後も出産手当金を受け取るための継続給付の条件と事前にできる対策
- 出産手当金がもらえなかった場合に利用できる、その他の公的支援制度
出産手当金が気になるあなたへ
子育て、教育資金、さらに先の老後のお金の不安をなくすために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、将来の資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額を3分で診断
▶夫婦で考えるお金の基本セミナー:ライフステージごとのお金の管理がわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
そもそも出産手当金とは?
出産手当金とは、会社員や公務員が加入する健康保険から支給される給付金です。出産のために会社を休み、給与の支払いがない期間に、被保険者とその家族の生活を保障する目的で設けられています。
支給対象となる期間は、出産日(出産予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの間で、会社を休み給与の支払いがなかった期間です。
出産育児一時金・育児休業給付金との違い
出産に関する公的支援には、出産手当金の他にも「出産育児一時金」や「育児休業給付金」があります。これらの制度は、目的や支給元が異なります。
出産育児一時金
健康保険から支給され、出産にかかる費用を補助する目的があります。出産という事実に対して支給されるため、被保険者本人だけでなく、被扶養者(例えば配偶者)が出産した場合も対象となります。
原則として健康保険に加入していれば、会社員・公務員、自営業・フリーランスなど、加入している健康保険の種類にかかわらず受給できます。
育児休業給付金
雇用保険から支給され、育児休業中の生活費を補填する目的があります。育児休業を取得し、雇用保険の加入条件を満たしている場合に支給されます。
これらの制度はそれぞれ異なる目的と支給要件を持つため、状況に合わせて利用できるものを確認することが重要です。
出産手当金がもらえない5つのケース
出産手当金は、加入している健康保険の種類や、産休中の給与状況、退職の有無など、さまざまな条件によって支給されない場合があります。ここでは、出産手当金がもらえない代表的なケースを解説します。
ケース1.国民健康保険に加入している(自営業・フリーランス等)
出産手当金は、会社員や公務員が加入する健康保険(協会けんぽ、組合健保など)の被保険者を対象とした制度です。
そのため、自営業者やフリーランスの方など、国民健康保険に加入している場合は、出産手当金の支給対象外となります。国民健康保険には、出産手当金に相当する制度はありません。
ケース2.会社の健康保険の「被扶養者」になっている
出産する本人が健康保険の被保険者ではなく、夫や親などの被扶養者になっている場合も、出産手当金の支給対象外です。
出産手当金は、働いている本人が健康保険に加入し、保険料を納めている場合に、休業中の所得補償として支給されるものです。被扶養者は、被保険者の収入によって生活しているとみなされるため、自身の休業に対する所得補償の対象とはなりません。
ケース3.産休中も会社から給与が支払われている
産休中に会社から給与が支払われている場合、原則として出産手当金は支給されません。出産手当金は、休業中の所得補償が目的であるため、給与が支払われているのであれば、その必要がないとみなされます。
ただし、支払われている給与の額が、出産手当金の日額を下回る場合は、その差額が支給されることがあります。例えば、出産手当金の日額が1万円であるのに対し、会社からの給与が1日5千円であれば、差額の5千円が支給される可能性があります。
ケース4.健康保険の任意継続制度を利用している
健康保険の任意継続とは、退職後に健康保険を継続して加入している状態を指します。任意継続被保険者の場合は、出産手当金の支給対象外となります。
これは、出産手当金が「被保険者本人が働いていて、かつ出産のために休業し、給与が支払われない(または減額される)場合」に支給される所得補償であるためです。任意継続被保険者は退職後の制度であり、雇用関係がないため、休業による所得補償の必要がないとみなされます。
なお、特定の条件を満たすことで「資格喪失後の継続給付」として退職後でも出産手当金の支給を受けられることがあります。継続給付の条件は以下の2点です。
- 被保険者の資格を喪失した日(退職日)の前日までに、継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
- 資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
参照:全国健康保険協会「資格喪失後の継続給付について」
ケース5.申請期限を過ぎてしまった
出産手当金には申請期限があり、この期限を過ぎてしまうと手当金を受け取ることができません。
出産手当金の申請期限は、出産のために休業していた日ごとに、その翌日から2年と定められています。この2年間を過ぎてしまうと、時効となり申請ができなくなります。
申請忘れを防ぐためにも、休業に入ったら速やかに準備を進め、申請を済ませることが重要です。
出産手当金をもらうために事前にできること
出産手当金を確実に受け取るためには、事前の準備と確認が非常に重要です。特に退職を考えている場合は 、出産手当金制度をよく理解しておくことが必要です。
退職日や産休期間などを会社と相談・調整する
出産手当金の支給期間は、出産日以前42日から出産日の翌日以降56日までと決まっています。この期間中に会社を休み、給与の支払いがない期間が対象となります。
そのため、退職を検討している場合は、この産休期間と退職日の関係が非常に重要です。会社の人事担当者や上司と綿密に相談し、退職日の調整を行うことで、出産手当金の受給資格を維持できる可能性があります。
退職予定がある場合、継続給付の条件を確認する
前述の通り、退職後も出産手当金を継続して受け取るには、一定の条件を満たす必要があります。特に重要なのは、退職日時点で健康保険の被保険者であり、かつ出産手当金の支給要件を満たしていることです。
具体的には、出産日または出産予定日が退職日を含む42日以内である必要があります。もし退職日が産前42日よりも前である場合、退職後の出産手当金は支給されません。
そのため、退職を検討している場合は、退職日が出産予定日から42日以内に収まるよう計画することが極めて重要です。
また、退職日に出勤した場合、「出産手当金の支給要件を満たしている」とはいえなくなるため注意が必要です。引き継ぎなどで出勤が必要となる場合は退職日前日より前に済ませましょう。
出産手当金が気になるあなたへ
子育て、教育資金、さらに先の老後のお金の不安をなくすために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、将来の資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額を3分で診断
▶夫婦で考えるお金の基本セミナー:ライフステージごとのお金の管理がわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
必要書類や申請手続きを事前に把握する
出産手当金の申請には、医師の証明書や会社の証明書など、複数の書類が必要です。また、申請窓口や提出期限も決まっています。
これらの必要書類や申請手続きについて、事前に会社の担当部署や加入している健康保険組合に確認し、不明な点があれば質問しておくことで、スムーズな申請が可能になります。出産間際になって慌てることがないよう、余裕をもって準備を進めましょう。
出産手当金がもらえなかった時に利用できるその他の公的支援
もし出産手当金が受給できなかった場合でも、出産や育児を支援する他の公的制度があります。これらの制度を上手に活用することで、経済的な負担を軽減できます。
出産育児一時金
出産育児一時金は、出産にかかる費用を補助する制度です。健康保険に加入していれば、会社員・公務員、自営業者、フリーランスなど、誰もが対象となります。
出産手当金とは異なり、休業の有無や給与の支払い状況にかかわらず、出産という事実に対して支給されます。
多くの場合、医療機関が健康保険に直接請求する「直接支払制度」を利用でき、これにより窓口での支払い負担を軽減できます。
育児休業給付金(雇用保険から支給)
育児休業給付金は、雇用保険から支給される制度で、育児休業中の生活を支援する目的があります。出産手当金が産前産後休業中の所得補償であるのに対し、育児休業給付金は子どもが1歳になるまでの育児休業期間(条件により延長あり)を対象とします。
雇用保険の加入期間などの条件を満たす必要がありますが、育児休業を取得する 方は忘れずに申請しましょう。
医療費控除
医療費控除は、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の合計が一定額を超えた場合に、所得税の控除を受けられる制度です。出産にかかった費用(入院費、分娩費、定期検診費用など)も医療費控除の対象となる場合があります。
ただし、受給した出産育児一時金などは医療費から控除しなければなりません。
医療費控除を申請することで、納める税金が少なくなる可能性があります。領収書などをきちんと保管し、確定申告の際に利用できるか確認しましょう。
自治体独自の助成金
国や健康保険の制度の他に、各自治体が出産や子育てに関する独自の助成金制度を設けている場合があります。
例えば、新生児誕生祝い金や、乳幼児医療費助成などがこれにあたります。お住まいの自治体のWebサイトを確認したり、役所の担当窓口に問い合わせたりして、利用できる助成金がないか情報収集することをおすすめします。
出産手当金に関するよくある質問(Q&A)
最後に、出産手当金に関するよくある質問にお答えします。
Q.出産手当金はいくらもらえる?
休業1日につき、直近12ヵ月間の標準報酬月額の平均額を30で割った額の3分の2相当額が支給されます。具体的な計算式は以下の通りです。
(直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額 ÷ 30日) × (2/3)
標準報酬月額は、健康保険料の計算に使われる給与の金額であり、勤務先に確認することができます。
Q.流産や死産の場合、出産手当金をもらえる?
妊娠4か月(85日)以上の流産や死産(人工妊娠中絶を含む)も「出産」とみなされ、出産手当金の支給対象となります。予期せぬ悲しい出来事であっても、休業を余儀なくされた場合の生活を支えるため、この制度が適用されます。
Q.会社の勤務期間が短くても出産手当金はもらえる?
会社での勤務期間が短くても、一定の条件を満たせば出産手当金を受け取れる可能性があります。
主な条件は、産休開始日(出産予定日の42日前)に健康保険の被保険者であること、そして産休中に給与の支払いがないことです。在職中に受給する場合、勤務期間の長さが直接的に受給の可否を決定するわけではありません。
ただし、退職後も出産手当金を受け取る「継続給付」を希望する場合は、退職前に継続して1年以上の被保険者期間があることが要件の1つになります。
まとめ
出産手当金は、産休中の生活を支える重要な制度ですが、受給にはいくつかの条件があります。国民健康保険加入者や健康保険組合などの被扶養者、任意継続被保険者などは原則対象外となります。
退職予定がある場合は、継続給付の条件を十分に確認し、出産手当金をもらうために退職日を会社と調整することが重要です。
出産手当金が受給できない場合でも、出産育児一時金、育児休業給付金、医療費控除など、他の公的支援制度が利用できる可能性があります。
これらの制度の活用も視野に入れ、お金の不安なく出産と育児に臨めるよう準備を進めていきましょう。
≫将来のお金は足りる?年収や資産額から3分で診断
出産手当金が気になるあなたへ
子育て、教育資金、さらに先の老後のお金の不安をなくすために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、将来の資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額を3分で診断
▶夫婦で考えるお金の基本セミナー:ライフステージごとのお金の管理がわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。

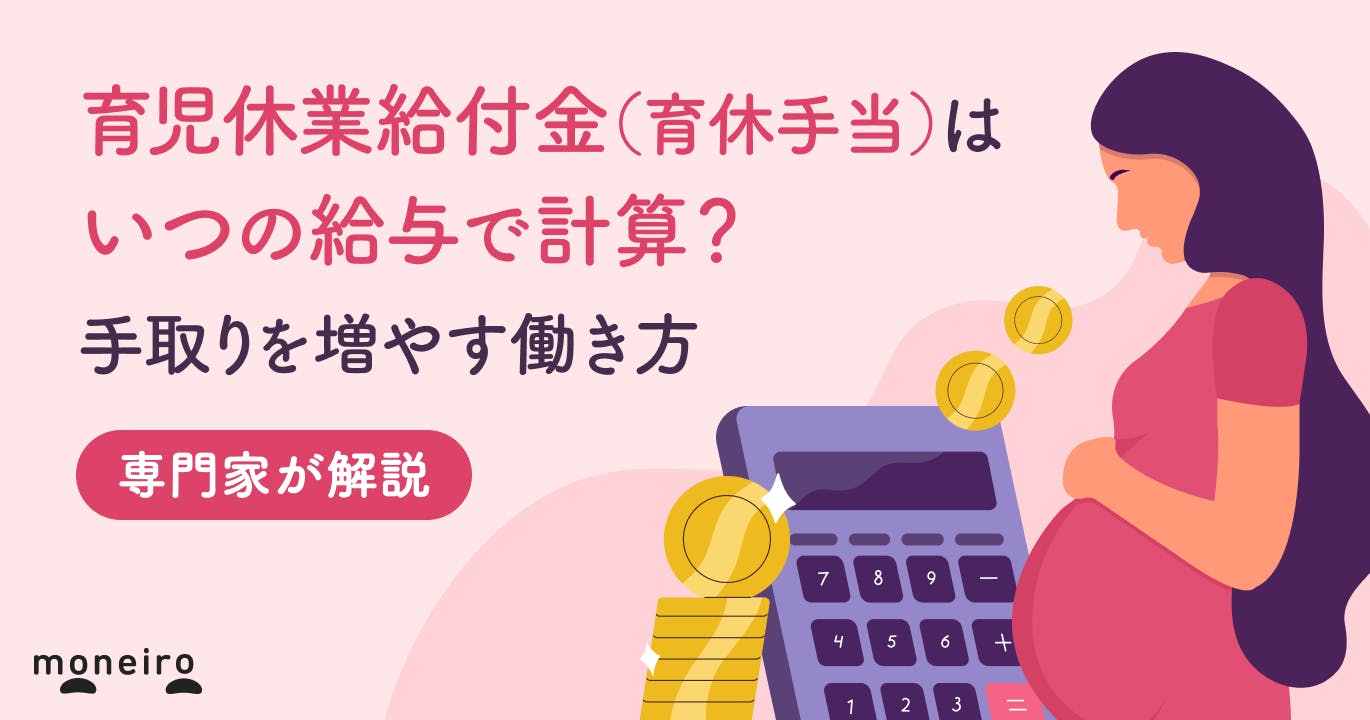
.jpg?w=1370&h=720&fit=crop&crop=faces&auto=compress,format)
