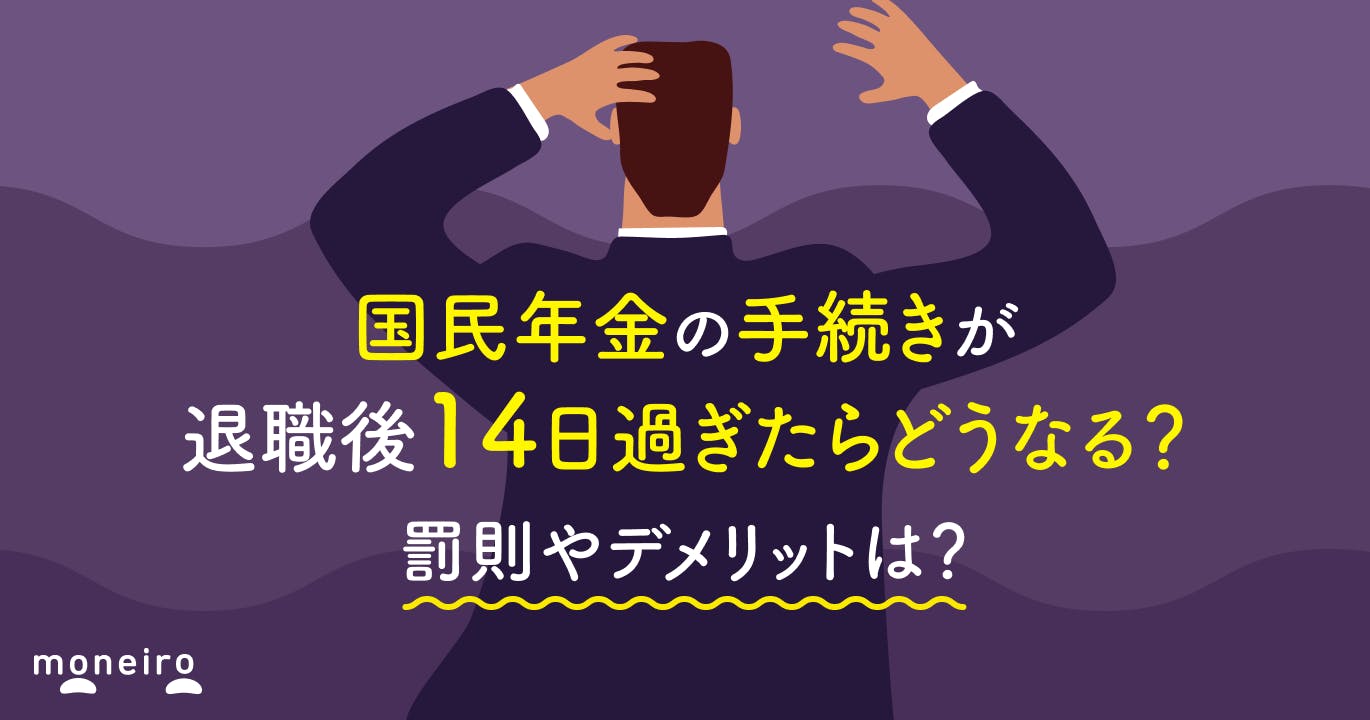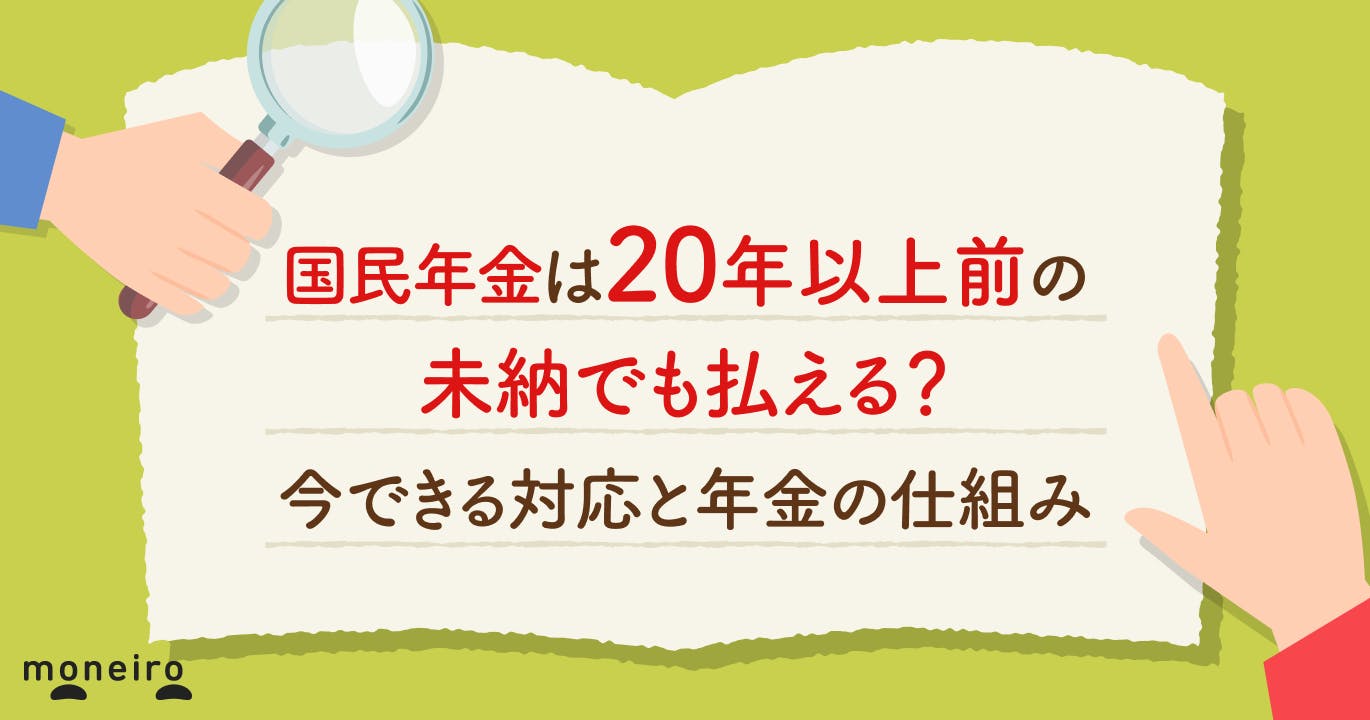
国民年金の手続きが退職後14日過ぎたらどうなる?罰則やデメリットは?
>>年金では足りないかも?老後の必要額を3分で診断
「退職後、国民年金への切り替え手続き期限の14日を過ぎてしまった」と不安に感じていませんか?
本記事では、期限を過ぎた場合の対処法を徹底解説し、手続きの遅れによる罰則や具体的なデメリット、必要な手続きや場所を詳しく解説します。この記事を読んで、国民年金に関する不安を解消しましょう。
- 退職後14日を過ぎても罰則はないこと&その代わりに生じるデメリット
- 国民年金への切り替え手続きに必要な持ち物や手続きの場所
- 保険料の支払いが困難な場合に利用できる「免除・納付猶予制度」の仕組み
老後の資金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
国民年金の手続きは退職後14日過ぎても罰則なし
国民年金の加入に関する届出期間は、法律上「退職後14日以内」と定められています。しかし、この期限である14日を過ぎてしまったとしても、それ自体に対して特に罰則があるわけではありません。そのため、手続きが遅れてしまった場合でも、過度に心配する必要はありません。
ただし、「罰則がない=問題ない」ということではありません。
手続きが遅れたり、放置したりすることによって、次に説明するような複数のデメリットが発生する可能性があります。
これらのデメリットを避けるためにも、14日を過ぎてしまったと気づいた時点で、できる限り早めに手続きを進めることが重要です。
国民年金の手続きが遅れた場合のデメリット
手続きの遅れに対する直接的な罰則はありませんが、その結果生じる「未納期間」や「無保険状態」によって、将来や万が一の際に大きな影響が生じる可能性があります。
年金の「未納期間」が発生し、将来の受給額が減る
退職した場合、会社員などが加入する「第2号被保険者」から、自営業者・学生などが加入する「第1号被保険者」へと種別を変更する手続きが必要です。この手続きをしない期間は、国民年金保険料が支払われていない「未納期間」として扱われてしまいます。
老齢基礎年金は、原則として保険料を納めた月数に応じて将来の受給額が決定されます。そのため、未納期間が長引けば長引くほど、将来受け取れる年金の総額が減ることになります。
簡易シミュレーション
令和7年度の基準に基づくと、老齢基礎年金は満額で年額83万1700円です。もし保険料の未納期間が1ヶ月発生した場合、将来受け取る年金額は年間あたり約1733円減額されます。
この減額は一生涯続くため、経済的な損失は決して小さくありません。
なお、この未納期間の保険料は、納付期限から2年以内であれば「追納」によって後から納めることができるため、将来の年金受給額を減らさないための解決策は用意されています。
万が一の際の障害年金や遺族年金がもらえないリスク
国民年金に加入することのもっとも重要な意義の一つは、「人生のセーフティネット」としての役割です。具体的には、病気や事故で障害を負った場合に受け取れる障害年金や、国民年金に加入している世帯主が亡くなった場合に遺族が受け取れる遺族年金があります。
これらの年金は、保険料を支払っている期間や免除を受けている期間が、所定の「納付要件」を満たしていないと、1円も受給できない可能性があります。
手続きを放置して未納期間が発生し、この納付要件を満たせなくなった場合、万が一のことが起きた時に、本人や家族が公的な支援を受けられなくなるという、非常に大きなリスクを負うことになります。
放置し続けると「延滞金」や財産の「差し押さえ」も
切り替え手続き自体が遅れても罰則はありませんが、手続きが完了した後、指定された納付期限までに保険料を納めない状態を放置し続けると、事態は深刻化します。
国民年金保険料を納付期限までに納めず滞納状態になると、まず年金事務所から「催告状」が届きます。それでも納付しない場合、「督促状」が送付されます。この督促状で指定された期限までに納付しないと、法律に基づき「延滞金」が課される可能性があります。
さらに滞納を続けると、以下の流れで財産の差し押さえに至るリスクがあります。
- 催告状の送付: まず、納付を促す「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)」が届きます。
- 特別催告状の送付: それでも納付がない場合、より強く納付を求める「特別催告状」さらに「最終催告状」が送付されます。
- 督促状の送付: 法律に基づく督促として「督促状」が届きます。
- 差し押さえ予告通知: 財産の差し押さえを予告する通知が送られます。
- 財産の差し押さえ: 預貯金、給与、不動産などの財産が差し押さえられます。
このような事態は保険料の未納を長期にわたって意図的に放置した場合に発生するものです。
催告状などが届いた場合は、すぐに役所や年金事務所に相談することが大切です。
老後の資金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
国民年金の退職後の手続きを解説
退職後に国民年金に加入する(第1号被保険者へ切り替える)手続きは、お住まいの市区町村の役所・役場で行います。手続きに必要な書類などを事前に確認しておきましょう。
Step1.持ち物チェックリストを確認
手続きをスムーズに進めるために、以下のものを用意しておきましょう。
- 基礎年金番号がわかるもの:基礎年金番号通知書または年金手帳
- マイナンバーがわかるもの:マイナンバーカード、通知カードなど
※マイナンバーカードがあれば、番号確認と本人確認が1枚で済みます。
- 本人確認書類:運転免許証、パスポートなど
- 退職日が確認できる書類:離職票、健康保険資格喪失証明書、退職証明書など
- 印鑑(自治体によっては不要な場合もあります)
Step2.お住まいの市区町村の役所・役場へ行く
原則として、国民年金への切り替え手続きは、お住まいの市区町村の役所・役場の国民年金担当窓口で行います。手続き自体は比較的短時間で完了します。
マイナポータルでも手続き可能
政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」を利用することで、国民年金の第1号被保険者への加入手続き(種別変更)が行えます。
スマートフォンやパソコンから24時間いつでも申請できるため、役所の開庁時間に行くことが難しい場合に大変便利です。
仕事等が多忙な場合や、手続きを急ぎたい場合は、お住まいの自治体がマイナポータル対応をしているか確認してみるとよいでしょう。
保険料が払えない時は「免除・納付猶予制度」の申請を
退職直後で収入が不安定な場合など、経済的な理由で国民年金保険料を期限までに納めることが難しい場合は、「免除・納付猶予制度」を利用できます。
これらの制度を申請し承認されると、未納期間とはならず、万が一の際のセーフティネットも維持されます。
国民年金の免除制度
国民年金の「免除制度」は、本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下である場合に、保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)の納付が免除される制度です。
この制度を利用するためには、毎年申請が必要です。
免除が承認されると、その期間は年金の受給資格期間(原則10年)に算入されるだけでなく、将来の年金額にも反映されます。
失業した場合は「特例免除」で承認されやすい
退職(失業)が理由で保険料の支払いが困難になった場合、通常の免除審査とは異なり、本人や世帯主の所得を審査する際に、本人の所得を除外して審査される「特例免除」が利用できます。特例免除が適用されると、前年の所得が高かった場合でも、失業の事実によって承認される可能性が非常に高くなります。
特例免除の申請には、通常の書類に加え、失業の事実を証明するための「離職票」や「雇用保険受給資格者証」のコピーが必要になります。
国民年金の納付猶予制度
「納付猶予制度」は、20歳から50歳未満の方を対象とした制度です。この制度を利用すると、申請者本人および配偶者の所得が一定額以下であれば、保険料の納付が猶予されます。
納付猶予が承認された期間は、将来の老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、免除制度とは異なり、猶予された期間分の保険料は将来の年金額には反映されません。
猶予された保険料は10年以内であれば追納が可能です。
免除・納付猶予を受けた場合、年金額はどうなる?
免除・納付猶予制度を利用した場合、未納として扱われるより遥かに有利になります。
- 全額免除の場合: 国庫負担により、将来の年金額に影響する期間として2分の1が算入されます。
- 納付猶予の場合: 将来の年金額には反映されませんが、受給資格期間には算入されます。猶予された保険料を後から追納することで、満額の年金額に近づけることが可能です。
いずれの制度も、万が一の際に必要な老齢年金・障害年金および遺族年金の受給資格要件を満たす期間としてカウントされるため、セーフティネットは維持されます。
国民年金の手続きに関するQ&A
国民年金の手続きに関するよくある質問と回答を以下にまとめました。
Q. 離職票がなくても国民年金の手続きはできる?
離職票や雇用保険受給資格者証は、退職の事実を証明するために必要とされる書類ですが、これらの発行が遅れている場合でも、市区町村の窓口で国民年金の加入手続き自体は可能です。
その際、代わりに会社から発行された「退職証明書」や「社会保険資格喪失証明書」など、退職日を確認できる書類があれば利用できます。
ただし、特例免除の申請を希望する場合は、離職票(コピー)などの提出が必要となります。事前に窓口で必要書類を確認しておきましょう。
Q. 転職先が決まっていて、すぐ厚生年金保険に加入する場合も手続きは必要?
原則として手続きは必要ですが、不要なケースもあります。転職先が決まっていても、退職日の翌日から再就職の前日までに1日でも空き期間があれば、原則として国民年金(第1号被保険者)への加入手続きが必要です。
ただし、退職した日の翌日と同じ月内に再就職して厚生年金保険に加入する場合は、その月の国民年金保険料を納める必要がないため、切り替え手続きが不要となるケースがあります。
判断に迷う場合は、お住まいの市区町村の窓口に「月末に退職し、翌月には新しい会社で厚生年金保険に加入する予定である」といった具体的な状況を添えて相談することをおすすめします。
Q. 手続きが遅れた場合、過去の分はいつまで払える?
納付期限から2年以内であれば納付できます。
国民年金保険料は、納付期限から2年を過ぎると時効によって納めることができなくなります。手続きが遅れた場合でも、2年以内であればさかのぼって保険料を納めることが可能です。時効になると、その期間は「未納」として確定し、将来の年金額が減ってしまうため、速やかに納付しましょう。
Q. 手続きをしないまま次の就職先が決まった場合はどうすればいい?
手続きをしないまま次の就職先が決まり、厚生年金保険に加入した場合は、国民年金への切り替え手続きは不要となるのが一般的です。
しかし、退職日から次の入社日の前日までの間に発生した「空白期間」については、国民年金保険料の未納期間として残ってしまいます。
未納期間を発生させないためには、原則通り、退職後14日以内に手続きを完了させることが重要です。
まとめ
退職後14日という国民年金の手続き期限を過ぎてしまっても、それ自体に対する罰則はありません。しかし、手続きを怠ると「未納期間」が発生し、将来受け取る老齢基礎年金が減額されるだけでなく、万が一の際の障害年金や遺族年金が受け取れなくなるという非常に大きなリスクを負うことになります。
もし保険料の支払いが難しい場合は、失業による「特例免除」をはじめとする免除・納付猶予制度を速やかに申請することで、セーフティネットを維持しつつ、将来の年金権も守ることができます。
手続きが遅れてしまったと気づいたら、不安を解消するためにも、すぐに市区町村の役所・役場へ相談し、手続きを進めるようにしましょう。
>>年金では足りる?あなたの老後に必要な金額を3分で診断
老後の資金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
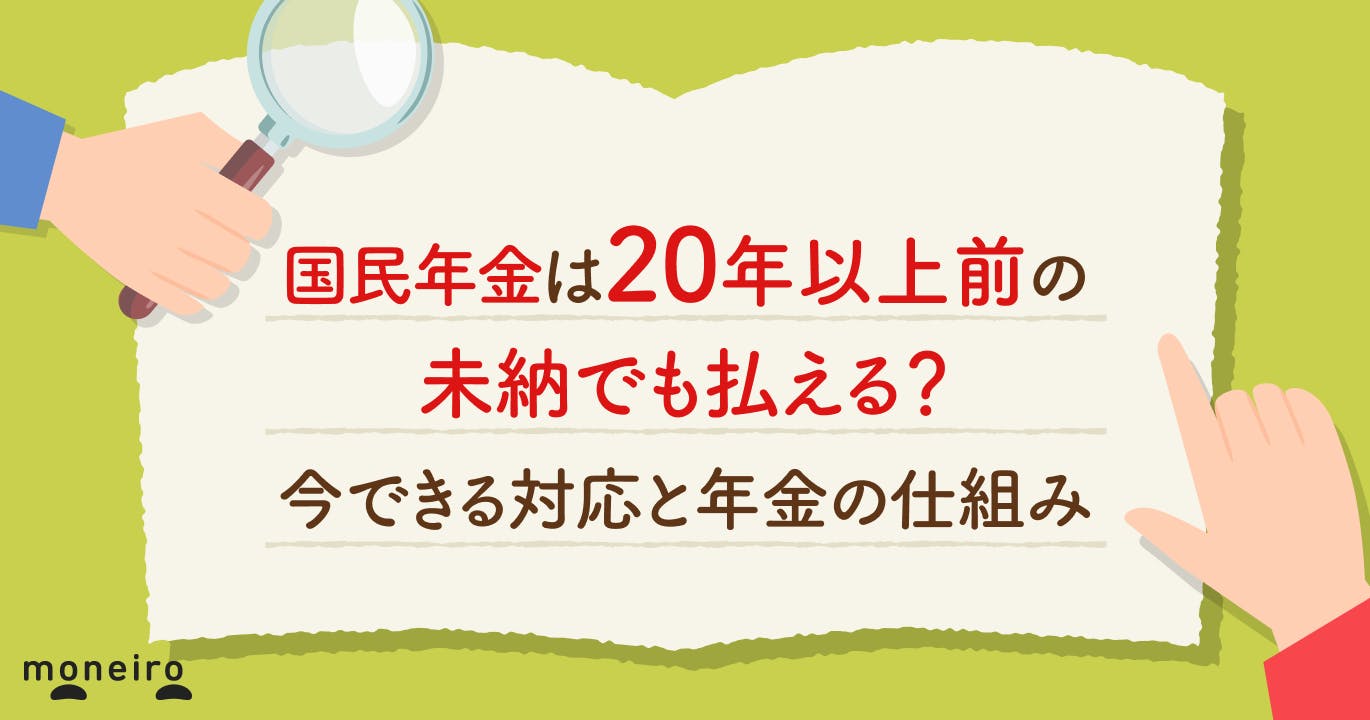
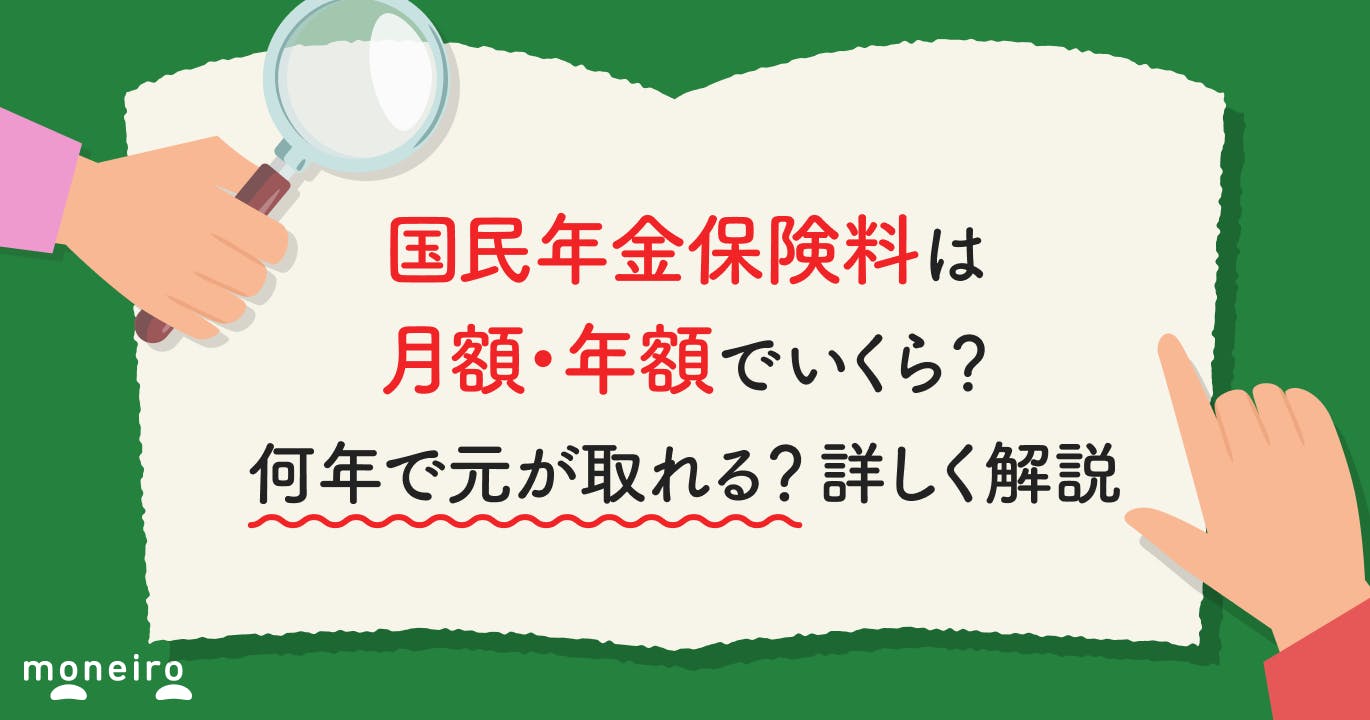
国民年金保険料は月額・年額でいくら?何年で元が取れる?詳しく解説
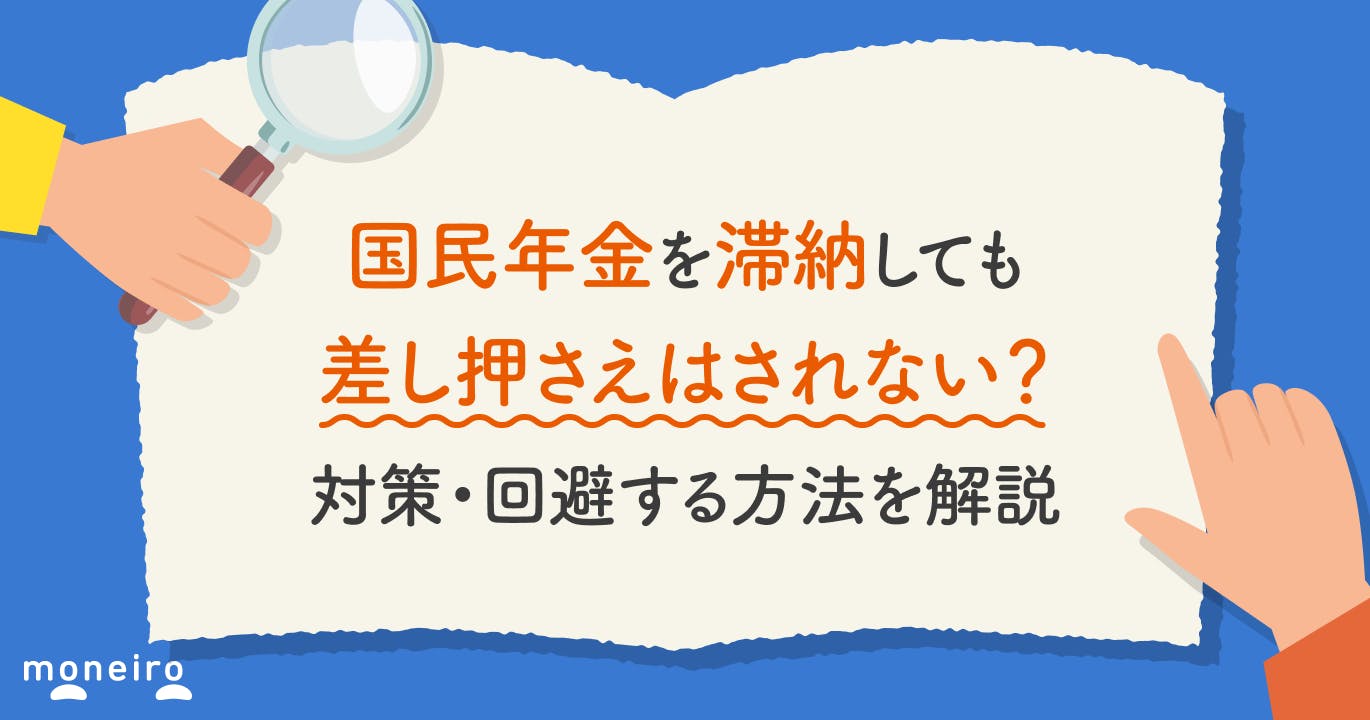
国民年金を滞納しても差し押さえはされない?対策・回避する方法を解説
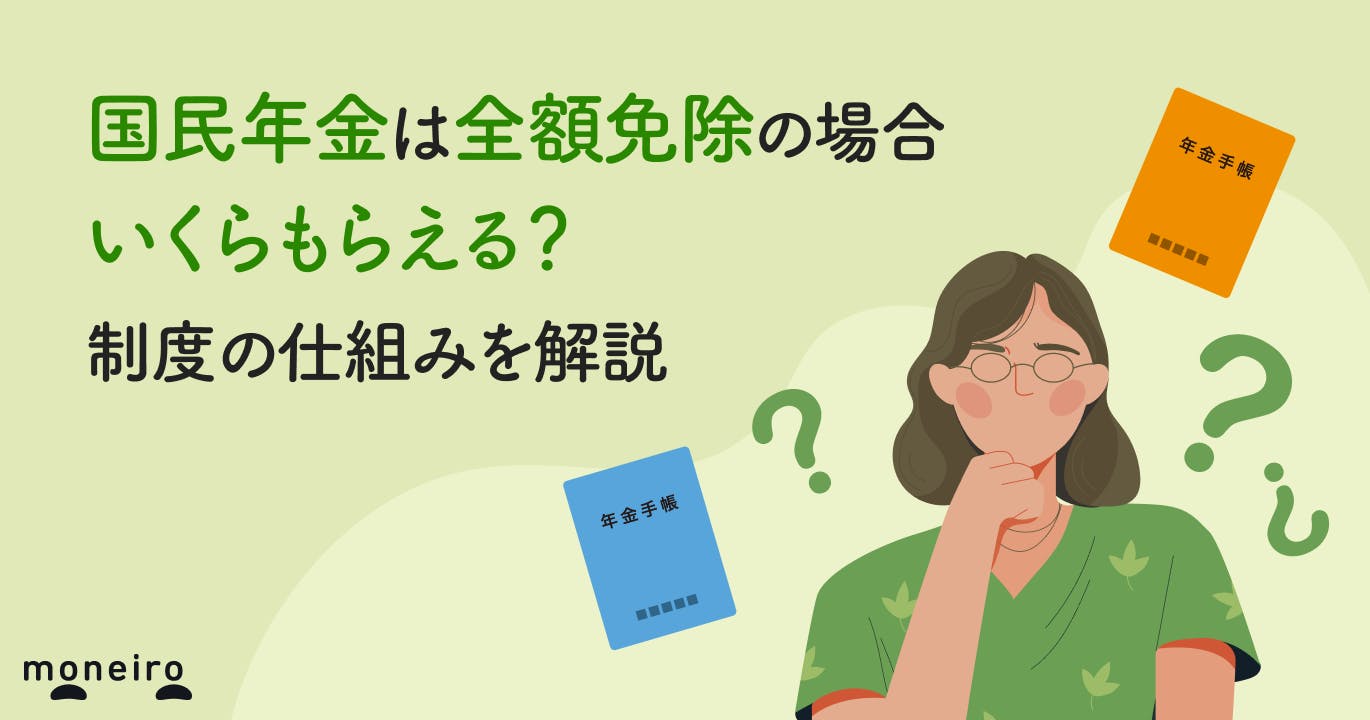
国民年金は全額免除の場合いくらもらえる?免除期間別シミュレーション
監修
山本 務
- 特定社会保険労務士/AFP/第一種衛生管理者
東京都練馬区で、やまもと社会保険労務士事務所を開業。企業の情報システム、人事部門において通算28年の会社員経験があるのが強みであり、情報システム部門と人事部門の苦労がわかる社会保険労務士。労務相談、人事労務管理、就業規則、給与計算、電子申請が得意であり、労働相談は労働局での総合労働相談員の経験を生かした対応ができる。各種手続きは電子申請で全国対応が可能。また、各種サイトで人事労務関係の記事執筆や監修も行っている。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。